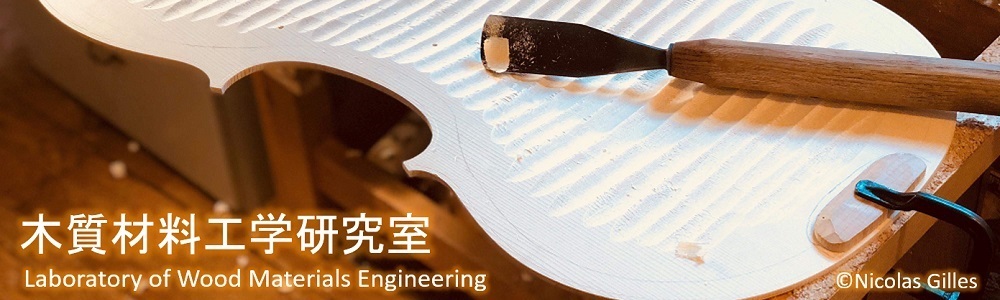研究テーマ
グラナディラに代わる木管楽器管体材の開発
木管楽器の管体に使われるグラナディラは絶滅危惧種です。そこで、グラナディラに代わる「持続可能な管体材」として、樹脂含浸圧密積層材(CLVL)の開発を行っています。詳しくは管体用材のページをご覧ください。
熱処理による木材の人工老化
古い楽器はよく鳴ります(証明済み)。適切な温度と湿度で熱処理することにより、木材の老化を自由自在に制御することを目指しています。楽器の製作だけでなく、文化財の補修にも役立つと期待されています。詳しくは響板用材のページをご覧ください。
アセチル化による葦アレルギーの抑止
木管楽器のリードに使われる葦はまれに深刻な皮膚炎を引き起こします。我々は「アセチル化」という処理により、アレルギー症状を効果的に抑止できることを発見しました。現在、奏者が自分で処理できるような、安全で簡便な処理手法を開発中です。詳しくは葦アレルギーの特設ページをご覧ください。
「枯らし」の機構解明と促進枯らし技術の開発
楽器や工芸品に使う木材は、数年間の「枯らし」を経てから加工されます。このときの材質変化やその機構についてはまだよくわかっていません。そこで、「枯らし」のしくみを解明するとともに、それを人工的に制御する手法の確立を目指しています。詳しくは響板用材のページをご覧ください。
化学処理による「割れないハープ響板」の開発
大型のハープでは木製の響板が乾燥・収縮に伴って割れる場合があります。そこで、特殊な樹脂を含浸することによって、音量を損なうことなく、響板の割れを防ぐことを目指しています。
ローズウッドに代わるマリンバ音板用材の開発
マリンバの音板には絶滅危惧種であるローズウッドが使われています。ローズウッドは減衰時間が非常に長く、普通の木材では代替できません。そこで化学処理や強化繊維複合の技術を応用し、資源量の豊富な汎用材から減衰時間の長いマリンバ音板材を作ることを目指しています。詳しくは音板用材のページをご覧ください。
CNFと天然多糖の複合による可成形性の高い樹脂材料の開発
セルロースナノファイバー(CNF)は植物から取り出される繊維で、CNFを使うと高強度の紙ができます。我々は、分厚いCNF紙を複雑な形に成型できるように、天然多糖との複合による可成形性の向上に取り組んでいます。
その他(過去の研究テーマ)
・リード用葦材の劣化機構の解明
・篳篥リード用葦材の物性解明
・木材の形状回復能の機構解明
・柔らかく傷が付かない床材の開発
・柔らかく粘り強い弾性梁の開発
・軽くて強い木質段ボールの開発
共同研究
秋田県立大学、東京医科歯科大学、利昌工業、青山ハープ、竹山木管楽器、こおろぎ、ヨーゼフ、Buffet Crampon、邦楽器製作技術保存会、三島屋楽器店ほか
当研究室は多くのみなさま(研究者、楽器製作者、楽器奏者、素材メーカー)の協力を得て研究開発を行っています。日頃のご協力に心から感謝いたします。