




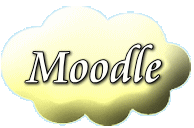



| �l���Љ�Ȋw�����ȁ@���m�ے��R�[�X �@�ٕ������ꋳ��]���_ (Testing in Second Language Education) |
�Q�O�P�P�N�x�ٕ������ꋳ��]���_�E�Q�w�����ۑ�i�������r���[�j�ł��B
��Crossley, S. A., Greenfield, J., & McNamara, D. S. (2008). Assessing
text readability using cognitively based indices. TESOL Quarterly, 42,
475-493.
��Shizuka, T., Takeuchi, O., Yashima, T., Yoshizawa, K. (2006). A comparison
of three-and four-option English tests for university entrance selection
purposes in Japan. Language Testing, 23(1), 35-57.�@�@(N. N)
��In�fnami, Y., & Koizumi, R. (in press). Factor structure of the revised
TOEIC test: A multiple-sample analysis. Language Testing.
��Yu, G. (2010). Effects of presentation mode and computer familiarity on
summarization of extended texts. Language Assessment Quarterly, 7, 119-136.
(K. S)
��Song, M. (2010). Do divisible subskills exist in second language (L2)
comprehension? A structural equation modeling approach. Language Testing,
25, 435-464. (S. N)
��Shiotsu, T., & Weir, C. (2007). The relative significance of syntactic
knowledge and vocabulary breadth in the prediction of reading comprehension
test performance. Language Testing, 24, 101-28.(K. W)
��Heilmann, J., Miller, J. F., & Nockerts, A. (2010). Sensitivity of
narrative organization measures using narrative retells produced by young
school-age children. Language Testing, 27, 603-626.
��Qian, D. D. (2009). Comparing direct and semi-direct modes for speaking
assessment: affective effects on test takers. Language Assessment Quarterly,
6, 113-125�@(M. O)
��David D. Qian (2009): Comparing Direct and Semi-Direct Modes for Speaking
Assessment: Affective Effects on Test Takers, Language Assessment: Affective
Effects on Test Takers, Language Assessment Quarterly, 6:2, 113-125
��Thi Cam Le, N., & Nation, P. (2011). A bilingual vocabulary size test
of English for Vietnamese learners. RELC journal, 42(1), 86-99. doi:10.1177/0033688210390264�i�s�D�h�j
1. Introduction
n L2�w�K�҂ɂƂ��Ẵe�L�X�g�̓ǂ݈Ղ��𐳊m�ɑ��肷�邱�Ƃ�, �w�K�҂̏n�B�x�ɍ��킹���e�L�X�g������ŏd�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���. �{�����ł�,
�e�L�X�g�̈�ѐ��E��Փx�𐔒l���ł���Coh-Metrix (e.g., Graesser, McNamara, Louwerse, &
Cai, 2004) ��p����EFL�w�K�҂ɑ���e�L�X�g�̓�Փx�̌����������݂�.
n �ǂ݈Ղ��̌�����, Flesh reading ease, Flesh-Kincaid grade level���m���Ă��邪, �e�L�X�g�̐[������,
��ѐ�, ����I���G��, ���g���b�N�Ƃ������v�����l���ł��Ă��Ȃ� (e.g., McNamara, Kintsch, Butler-Songer,
& Kintsch, 1996).
n ���̓_, ���R���ꏈ���̕���ŊJ�����ꂽCoh-Metrix (Jurafsky & Martin, 2000) ��, �e�L�X�g�������ѐ��𐔒l���ł��邽��,
�ǂݎ�̔F�m�v���Z�X (�P��F�m�E���ꏈ���E����\�z�Ȃ�) �𐳊m�ɔ��f�����ǂ݈Ղ��̌������\�z�ł���Ǝv����.
<L1
Readability>
n 1920�N�ォ��, 50�ȏ�̓ǂ݈Ղ��̌������J������Ă��邪, �����͎�� (a) ��b�E�Ӗ�����, (b) ���E����I���G����v���Ƃ��Ă���
(Chall & Dale, 1995).
n ���p�x�̒P�ꂪ�����Ɋ܂܂�Ă���, ����1���̒������Z����e�L�X�g�͓ǂ݈Ղ��Ƃ������ƂɂȂ�. ���̍l���Ɋ�Â������ƃe�L�X�g�����̑��ւ�r
= .08�ȏ�ƍ����� (Chall & Dale, 1995), ���̌����͓lj��v���Z�X�Ɋ�Â��Ȃ��Ó����̒Ⴂ�w�W���ƌ�����.
<Traditional
Readability Formulas for L2 Readers>
n ���ߐ��E�ꐔ���l��: Flesh reading ease, Flesh-Kincaid grade level, Miyazaki EFL
readability
n �N���[�Y�E�e�X�g�̓��_: Bormuth (1975), New Dale-Chall (1995) �̌���
n �����̎w�W���e�L�X�g�̕\�w�I�ȑ��ʂ������f���Ă��炸, �ǂݎ�̔F�m�v���Z�X�f�����w�W�̊m�������߂��� (Brown, 1998; Carrell,
1987).
<Coh-Metrix>
n Coh-Metrix�̓e�L�X�g�̈�ѐ��E��Փx��, �ꃌ�x��, �k�b���x��, �T�O���x���ő���ł���c�[���Ƃ��ĊJ�����ꂽ (Graesser
et al., 2004).
n �{�����̖ړI��, �ǂݎ�̔F�m�v���Z�X�f���錾��I�v����, �e�L�X�g�̓ǂ݈Ղ����ǂ̒��x���m�ɑ���ł���̂���, Coh-Metrix��p���Č����邱�Ƃɂ���.
2. Method
<Materials>
n Bormuth (1971) �̃R�[�p�X����w�p�e�L�X�g32��ނ�I��: ����w�I�v�����F�m�v���Z�X�f��, �e�L�X�g�̈�ѐ��͓ǂ݂₷����\���ł���Ƃ���������������.
n �����̃e�L�X�g��, ���l�ȕ��삩��I������, �ꐔ�̕��ς�269.28 (SD = 16.27), 100�ꒆ�̕����̕��ς�7.10 (SD
= 2.81).
n ���ꂼ��̃e�L�X�g��p����, 5�ꂨ���̃N���[�Y�E�e�X�g���쐬����.
<Variable
Selection>
n �e�L�X�g�̓ǂ݈Ղ���\�����邽�߂̓Ɨ��ϐ���, ��s�����Ɋ�Â� (a) �P��F�m: lexical recognition, (b) ������:
syntactic parsing, (c) �Ӗ��\�z: meaning construction���̗p���� (Just & Carpenter,
1987; Perfetti, 1985; Pollatsek, 1994).
(a) Lexical index:
? ���p�x�̒P��͂�葬���E�悭��������邱�Ƃ��� (�p�x����), �P��̕p�x��ǂ݈Ղ��̎w�W�Ƃ���.
�@(b) Syntactic index:
? �P���ȓ���\���������͏������₷��. Coh-Metrix�ł�, ���̗v�����Ӗ��I�ގ����Ƃ��Đ��l���ł��� (�݂��̕��̓���I��ѐ����Z�o).
�@(c) Meaning Construction Index:
�@�@�@ ? �אڂ���2���Ԃœ��e��̈Ӗ��I�֘A�����������, �e�L�X�g�����E�lj����Ԃ����シ�邱�Ƃ���, ������Coh-Metrix�ŎZ�o����.
3. Statistic Analysis
n EFL�w�K��31���̃N���[�Y�E�e�X�g�̓��_���]���ϐ��Ƃ���d��A���͂��s����.
n �l���̏��Ȃ����J�o�[���邽��, �����ς�R2�l�ɉ���, Stein�fs unbiased risk estimate (SURE), �����k-������������
(cross-validation) �̌��ʂ����.
�@? k-������������: �W�{�f�[�^����, ���̈ꕔ����͂�����, �c����ŏ��̉�͂̉�������ɗp�����@. �W�{��k�ɕ�����, k����s������ꂽ���ʂ̕��ς����Ƃɉ����̌����s��.
4. Results
<Correlation
and Multiple Regression>
n Stepwise�ł̏d��A���͂̌���, �ȉ��̕\�̒ʂ�ɂȂ���. �e�v���ƃN���[�Y���_�Ƃ̑��ւ�, sentence syntax similarity
(r = .71), content word overlap (r = .79), frequency (r = .61).
n 3�v���ł̃N���[�Y���_�̐�������86%�ƂȂ���. �܂�, �e�L�X�g�̓����86%�͂����3�v���Ő����ł��邱�ƂɂȂ�.
Descriptive Statistics
|
Variables |
Mean |
Standard deviation |
N |
|
Predicted |
|
|
|
|
Mean cloze scores |
23.854 |
12.944 |
31 |
|
Predictor |
|
|
|
|
Content word overlap |
0.1457 |
0.090 |
31 |
|
Sentence syntax similarity |
0.149 |
0.087 |
31 |
|
CELEX frequency |
2.349 |
0.243 |
31 |
Stepwise Regression Analysis
|
Dependent variable: EFL cloze
scores |
|||
|
Step
1 |
R = .793 |
R2 = .628 |
Added
content word overlap |
|
Step
2 |
R = .887 |
R2 = .786 |
Added
sentence syntax similarity |
|
Step
3 |
R = .925 |
R2 = .856 |
Added
CELEX frequency |
<Cross-Validation>
n ��������̌���, �����ς�R2 = .84, SURE = .81�ƂȂ��L�Ƃقړ��l�̌��ʂƂȂ���.
<Comparison
with Other Measures>
n �]���̓ǂ݈Ղ��̎w�W (Flesh reading ease, Flesh-Kincaid grade level, Miyazaki EFL
index) �ƍ���̌��ʂ��r��������, �ȉ��̕\�̒ʂ�ɂȂ���.
Pearson
Correlations Between Observed Scores and Scores Predicted by Various
Readability Measures
|
Readability measure |
Observed EFL |
|
�@�@�@�@Flesh reading ease |
-.845�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
�@�@�@�@Fresh-Kincaid grade level |
-.847�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
�@�@�@�@Bormuth formula |
.861�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
�@�@�@�@Dale-Chall formula |
.691�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
�@�@�@�@Miyazaki formula |
.848�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
�@�@�@�@Coh-Metrix EFL index |
.925�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
5. Discussion
n �{�����ł�Coh-Metrix��, �]���̓ǂ݈Ղ��̎w�W����EFL�w�K�҂ɂƂ��Ẵe�L�X�g�̓ǂ݈Ղ��𐳊m�ɑ���ł���̂���������.
n �e�L�X�g�̓ǂ݈Ղ��𐳊m�ɑ��肷�邱�Ƃ�, �w�K�҂ɓK��L2 input, noticing, intake��^�����ŏd�v�ɂȂ�. �{�����̌���,
�ǂ݈Ղ��̌����͈ȉ��̒ʂ�ɒ�`�ł���.
Predicted
cloze = -45.032 + (52.230 �~ Content word overlap value)
+ (61.306 �~ Sentence
syntax similarity value)
+ (22.205 �~ CELEX
frequency value)
n ������, �{�����ŗp�����e�L�X�g�͐������݂̂ł���, �܂��v����3��������Ȃ������̂�, �ǂݎ�̔F�m�v���Z�X�Ɋ�Â�������Ȃ錟�����߂���.
<�R�����g>
�@�{�����ł͏]���̓ǂ݈Ղ��̌����ɑ�, �e�L�X�g�v���Ɠǂݎ�̔F�m�v���Z�X�̊W���f���Ă��Ȃ��Ƃ������_���������邽��, Coh-Metrix
(http://cohmetrix.memphis.edu/
cohmetrixpr/index.html) �𗘗p���Ă���. Coh-Metrix�͗l�X�ȃe�L�X�g�v�� (��b�p�x�E����I���G���E�Ӗ��I�֘A���Ȃ�)
�𐔒l���ł��邽��, �\�w�I�ȓ�Փx��������ł��Ȃ��]���̌�������, �Ó����̂���ǂ݈Ղ��̎w�W���쐬�ł���ƍl������. �܂�, Coh-Metrix�̓t���[�ŗ��p�ł��邽��,
�{�����ň������v����ݒ肷���, �ǂ̃e�L�X�g�̓ǂ݈Ղ������t���g���m���߂���Ƃ����_�Ŕ��ɉ��l������.
�@������, �ǂ݈Ղ��𑪒肷�邽�߂̊�Ƃ���, �e�L�X�g�̃N���[�Y�E�e�X�g���̗p���Ă���_�Ɍ��E�_������悤�Ɏv����. �{�����ł̓N���[�Y�̍̓_�@�ɂ��ĕ���Ă��炸,
����@���K��@�̍̓_���Ńe�L�X�g�̓ǂ݈Ղ����ߏ��]���܂��͉ߑ�]�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤��. �m���ɃN���[�Y�E�e�X�g�͐�s�����œǂ݈Ղ���]�����邽�߂̑���@�Ƃ��Ċm������Ă��邪
(Chall & Dale, 1995), �lj��v���Z�X�����ɂ�����P��̕p�x���ʂⓝ��I���G��, �Ӗ��\�z�Ƃ������v���̓N���[�Y�E�e�X�g�ł͑��肳��Ă��Ȃ�.
�����̗v���͓lj����ԂȂǂő��肳��邱�Ƃ�����, �ǂ݈Ղ��e�L�X�g�ł���Γ��R�Ȃ���lj����Ԃ͒Z���Ȃ�. �lj����ԑ���@�ɉ�����, ���e�����Ɋւ��Ă��M�L�Đ��@�Ȃǂ̐S������w�I�ȑ���@���K���Ă���ƍl������.
���ɈӖ��\�z�Ɋւ���, ��������₷���e�L�X�g�ł����, ���̓��e�͋L���ɕێ�����Ă��邽��, �{�����ŗp���������̃e�L�X�g�ł����, �\���Ƀe�L�X�g�̓��e�����f�ł��邾�낤.
�@�����, ��l�̋��͎҂Ƀ��R�[���ۑ�𑱂��邱�Ƃ�, ���K���ʂ������N�����\��������̂�, �{�����ŐG����Ă���ʂ����K�͂Ȓ������K�v�ɂȂ�.
�܂�, ���͎҂̏n�B�x���l����, ����̎����œ���ꂽ�ǂ݈Ղ��̌�����, �ǂ̏n�B�x�ɂ���w�K�҂ɍł��K���Ă���̂���T��K�v�����邾�낤.
�{�����́A���{��EFL��w���w�����ɂ����Đ��_����w�I�����Ɋւ��鍀�ڂ̑I�����������炷���ʂ����������̂ł���B���{�̑�w�̓��w�����Ɏg�p���ꂽ�A4�̑I�������琬�鑽���I�����lj��e�X�g�́A�ł��I����p�x�����Ȃ��������ڂ��폜���āA3�̑I�������琬��e�X�g�ɍ��ւ���ꂽ�B�����āA�قȂ�O���[�v�Ɏ��{���ꂽ�B���̌��ʁA�I�����̐��͕��ύ��ڗe�Փx�╽�ύ��ڎ��ʗ͂ɗL�ӂɉe�����Ȃ����Ƃ����������B�s�����̑I�����͂���ƁA�͖�2.6�ɋy�сA�@�\���Ă���������̕��ϐ���2��菭�Ȃ��Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����B����āA3�̑I������4�̑I�����ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��@�\������Ƃ������Ƃ��������ꂽ�B
I.
Context of the research
�E���{�ł́A���w�����̌��ʂ��ł��d�v�Ȕ��f��ł���B
�E���N�̑�K�͂Ȏ����̍쐬�E�̓_�ɂ������鎞�Ԃɂ͌��肪���邽�߁ABrown (1995)���w�E����悤�ɁA�����I�����̖����g�p����̂���ʓI�ł���B
���{�����ł́A�e�X�g�̎��Ȃ킸�ɑI�����̐������炷���Ƃɂ���āA�W�҂̘J�͂��y�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
II.
Background
�E���ۓI�Ɋm������ESL/EFL�e�X�g�iTOEFL, TOEIC, Cambridge ESOL�Ȃǁj�́A4�̑I�������̗p����X��������B
�E3��ނ̃A�v���[�`�i�I�����̍œK�Ȑ��̓���A��_�A�œK�ȑI�������ɂ����Ď҂̔\�͂��^����e���j���œK�̑I��������3�ł���ƈ�v�B
III.
Method
1.
The four-option test
�E2003�N�ɐ����{�̎�v������w�̈�w���Ŏ��{���ꂽ���w��������A1000�l���̉𒊏o��4�̑I�������琬��A38��̍��ڂ��g�p�B
2.
The three-option test
�E��L��38���ڂ̂����A10��͂��̂܂܁A�c���28���3�̑I�������琬�鍀�ڂɕҏW�B���̍ہA�ł��I��Ȃ������I�������폜���Ă��遨�ł��I��Ȃ��I�����́A28���ڒ�19���ځi68%�j�ɂ����āA�L�ӂɕٕʗ͂��Ȃ��Ƃ��ꂽ���߁B
3.
Participants
�E��w���w���x���̓��{�l�w���B
IV.
Results
1.
Item facility
�E2�̃O���[�v����r�\�ł��邱�Ƃ��m���߂邽�߂ɁA��ʓI��10���ڂ̐������̋L�q���v�����{�B
��4�̑I���������O���[�v�́A���̔\�͂ɂ����āiin ability�j�L�ӂ�3�̑I���������O���[�v��荂�������B
��FACETS v. 3.0���g�p���āARasch����̘g�g�݂ɂ����č��ڂ̓��������{�B
��4�̍��ڂ����O���āA���z�̍œK���C����.72����.99�ɂ����B
�E�e�e�X�g�ɓ��L�ȍ��ڂ��ӂ邢�ɂ����āA���炩�ȗ�O�ƂȂ鍀�ڂ����o�B
�������̃e�X�g�ɂ����āA����36�͖�肪�������i�_�o�ւ��}�C�i�X�F-. 13, -.08�Aoutfit�̕��ϕ����̓��f���̊��Ғl���������F1.2, 1.5�j�B
���㑱���镪�͂ɂ����āA���̍��ڂ͏��O���ꂽ�B
�ESmith et al (1988)�ɂ���Ē��ꂽ����g�p���āA2�̌ŗL�ȍ��ڂ̓K�����v�ʂ́B
��3�̑I�����f�[�^�́A4�̑I�����f�[�^�Ɠ��l�ɁARasch���f���ƈ�v����B
�E4�̑I�������ڂ�3�̑I�������ڂ̕��ύ���x�́B
���Ή������t��������{�����Ƃ���A���҂̈Ⴂ�͗L�ӂł͂Ȃ����Ƃ����������it = -1.97, p =.06, df = 26�A��������j
�E�I���������炵�Ă��A���ڂ̓�Փx�͕ς��Ȃ��B
���s�A�\���̐ϗ����ւ̌��ʁA���ڂ̑��ΓI�ȓ���́A�I�����̐��Ɗւ�Ȃ����肵�Ă����B
2.
Item discrimination
�E���ۂٕ̕ʗ͂ƓK�����v�ʂ����邱�Ƃɂ���āA�ǂ��ŁA�܂��͂ǂ̂��炢���ۂ̃f�[�^������̗v���ƈ�v�����^���Ȃ�����������肷��菕���ƂȂ�B
�Estraightforward item-total computation�i�ȈՂȑS���ڂ̌v�Z�j�͕s�K�ł���B
�E���̂��߁A���̑���4�̑I�������琬�鍀�ڂ̉��ʃT���v���in =192�j�𒊏o���A��������3�̑I�������琬�鍀�ڂƔ�r�����B
�E�N�����o�b�N�̃A���t�@�W���ɑΉ�����Rasch�̒l�́A�����̑I�������œ����i= .68�j�ł������B���I�����̐������炵�Ă��A�M�����ɕ��̉e���͂Ȃ������B
�E�_�o�ւ̕��ς́A���҂̊Ԃł��܂�ς��Ȃ������i4�̑I�����F.30-.31�A3�̑I�����F.29�j�B���I�����̐������炵�Ă��A���ڕٕʗ͂͌������Ȃ������B
3.
Distractor performance
a Actual equivalent number of options
�E�m���p�����g���b�N�E�E�B���R�N�\���̕����t��������s�����Ƃ���A���҂�AENOs�̊ԂɗL�Ӎ��͂Ȃ������iz =.45, n.s.�j�B
b Endorsement rankings
�E�ł��I��Ȃ��������������폜���Ă��A�ǂ̑I��������Ԃ悭�I�Ԃ��Ƃ������ʂ́A���悻�ς��Ȃ������i�I������84%���܂����������ʒu�̂܂܂������j�B
c Distractor discrimination
�E������������{���e���ڂ̋@�\���Ă���������̐��ɁA�L�Ӎ��͂Ȃ������B
d Change in distractor discrimination
�E�����������4�̑I�������琬�鍀�ڂŕٕʗ͂��������ꍇ�A���̍�������3�̑I�������琬�鍀�ڂł��ٕʗ͂��������B
�E������������O�҂ŕٕʗ͂������Ȃ������ꍇ�ł��A��҂ł͔����ȏ�̏ꍇ�ٕʗ͂��������B
�E�ł��I��Ȃ������I�������폜���Ă��A�����̏ꍇ�c��������̐��\�ɉe�����Ȃ��B
�E�}�N�i�}�[�̑Ώ̐���������{��P�l�ɂ����āA�ٕʁ^��ٕʃX�e�[�^�X�̊Ԃœ��v�I�ɗL�ӂȕω��͂Ȃ��B
V.
Discussion
1.
Item facility
�E���ڗe�Փx�́A�ł��I��Ȃ��������������폜���ꂽ����قƂ�Ǔ����ł������B
2.
Item discrimination and distractor performance
�E�I�������k���i4����3�ɂ���j���Ă��A�ٕʗ͂͑啝�ɉ�����Ȃ������B
�����R�@�ł��I��Ȃ���������I�Ԋm���́A�ɂ߂ĒႩ�����B
�@���R�A�@�\����������̐��́A�^������������̐���3�ł�2�ł��A�L�ӂɕς��Ȃ������B
�@���R�B���ɑ����̏ꍇ�A�ł��I��Ȃ����������폜���Ă��A�c��I�����̍��ڊԂ̎x�������͕ς��Ȃ������B
�@���R�C�����̏ꍇ�A�I�����̏k�������Ă��A�������ٕ̕ʂɂ�����L�Ӑ��͎c�����B
3.
Advantages of the three-option format
�E���ڍ쐬�҂̍�Ɨʂ�����A���Ԃ̐ߖ�Ɍq����B���̏�A�e�X�g�̎��͕ς��Ȃ��B
�EAamodt and McShane (1992)�E�E�E�����鎞�Ԃ������Ȃ�A3�I�������琬�鍀�ڂȂ畽�ς���112.4�A4�̑I�������琬�鍀�ڂȂ�100�������Ƃ��o���遨��葽���̍��ڂ��������邱�Ƃɂ���āA��荂���e�X�g�̐M��������B
�E���̑��̗��_���e�X�g���q�̏k���A�����̍팸�A�҂̃v���b�V���[�̌y���A�ȂǁB
VI.
Conclusions and future directions
4�^3�̑I�����̊ԂŁE�E�E
�@���ύ��ڗe�Փx�́A�L�ӂɕς��Ȃ��B
�A�e�X�g�̐M�����Ɠ��l�ɁA���ύ��ڕٕʗ͂́A�L�ӂɌ������Ȃ��B
�B�҂̎��ۂ̑I���͖�2.6����2.7�̑I�����ɋy�Ԃ݂̂ŁA�e���ڂőI�����̑��ΓI�ȑI��Ղ��͂قƂ�Ǔ����ł���B
�C��̍��ڂɂ��@�\���Ă���������̕��ϐ���2��菭�Ȃ��A3�̋@�\������������܂ލ��ڂ́A��O�I�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�����́A3�ŏ\���ł���I
�����X3�̑I�����������ڂƁA4�̑I������3�ɂ������ڂ̊ԂɈႢ�����邩�H
�����ڍ쐬�҂́A�ǂ̒��x�����I�ɑI�����̑I��Ղ���\���o���邩�H
�ȉ��A�_����ǂݏI���Ă̊��z
�@��w�w������ɁA���鋳�E�W�̎��ƂŐ搶���e�X�g�쐬�̉ۑ���w���ɏo���������������B���̍ہA4�̑I���������悤�Ɍ���ꂽ���A���ꂪ���ɓ���������B3�ڂ܂ł͔�r�I�l��������������v�������A4�ڂ��Ȃ��Ȃ��o�Ă��Ȃ������B�܂��A�I�����͉��ł��悢�킯�ł͂Ȃ��B�I�������J�e�S���ɑ����鍀�ڂɓ��ꂵ�Ȃ���A�����ǂ��҂ɂ͎v�킸�q���g�������Ă��܂��悤�ȑI�����ɂȂ肩�˂Ȃ��B
�@�{�_���ł��Љ��Ă����悤�ɁA�����I�����̖������̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�e�X�g�̐M�����̂��߂Ƃ͂����A�e�X�g�̍쐬�҂ɑ傫�ȕ��S��^���邱�ƂɂȂ邩��ł���B��������������܂���ƁA�{�_���Ŏ����ꂽ�悤�Ȍ��ʂ����t������ƁA���ԓI�ɂ��J�͓I�ɂ��o�ϓI�ł���B�e�X�g�̎��������邱�ƂȂ��A�I�����̐������点�邩��ł���B�e�X�g���鑤�̎��_���猩�Ă��A�I�����̐�������A�X�g���X�̌y���ɂȂ�B
�@���̗��_���x�[�X�ɂ��āA����͎��̗ǂ�3�̑I�������琬�鍀�ڂ�����Ă������Ƃ��ۑ�ɂȂ�Ǝv����B���͂�ʂ��ėǂ����ڂ͕ۑ����A�ǂ��Ȃ����ڂ̓e�X�g�Ɋ܂߂邱�Ƃ���������Ȃǂ��āA�n���ɂ��悢�e�X�g������Ă����K�v������B���{�̉p��e�X�g�ł́A�����I�����̖�肪�L�����p����Ă���B���ۂɎ����������ɂȂ����Ƃ��ɁA���̗��_�����ăe�X�g�쐬�Ɋւ肽���Ǝv���B
�yAbstract�z
�@�{�����̖ړI�́A�����ł�TOEIC�ɂ����郊�[�f�B���O�Z�N�V�����ƃ��X�j���O�Z�N�V�����̈��q�\���̌����s�����Ƃł���B��s�������痝�_�I�ɂ�4��ނ̃��f��
(higher-order, correlated, uncorrelated. unitary) �����肳�ꂽ���A�m�F�I���q���͂̌��ʂ�correlated���f�����x�������B���Ȃ킿�ATOEFL���瑪�肳��郊�[�f�B���O�\�͂ƃ��X�j���O�\�͂ɂ͔�r�I�������֊W���F�߂��邪�A���ꂼ��̈��q�͓Ɨ����đ��݂��Ă���Ƃ������Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B
�yLiterature Review�z
��TOEIC�͕��L���p�����Ă���e�X�g�ł���A�����̐�s�����ɂ���Ă��̑Ó�����������Ă���
��TOEIC�Ɋւ��錤����TOEFL��IELTS���͔�r�I�������Ȃ��A�����̌����͎�Ɉȉ���3��ނɕ��ނ����F(a) �M�����Ɠ��_���z
(b) ���_�ɂ������v�� (c) ���̃e�X�g�Ƃ̊W��
��(a) �ɊY�����錤����Ƃ���Woodford (1982) ������A���[�f�B���O�Z�N�V�����A���X�j���O�Z�N�V��������ёS�̂ɂ�����.9�ȏ�̍����M�������m�F����Ă���
��(b) �ɊY�����錤����Ƃ���Boldt and Ross (1998) ������A�e�X�g�̐����Ƌ��t�̎w�����e�X�g���_�����コ��������Ƃ��傫�ȗv���ł��������Ƃ�������Ă���
��(c) �ɊY�����錤����Ƃ���Power et al. (2008) ������A����\�͂̎��Ȑf�f�A���P�[�g�̌��ʂ�TOEIC�e�X�g�̓��_�ƒ����x�̑��ւ����������Ƃ�������Ă���
���������ATOEIC�̈��q�\���ɂ��Ĉ����Ă��錤���͂قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ�
�������Ȃ�������1�Ƃ���Wilson (2000) ������A����O��TOEIC��p���Ă��̈��q�\���̌������s�������ʁA���[�f�B���O�Z�N�V�����Ƃ���2�̈��q�ƃ��X�j���O�Z�N�V�����Ƃ���1�̈��q����Ȃ���q�\��������ꂽ
���������AWilson (2000) �͉���O��TOEIC�̌��ł��邱�Ƃ���A�{�����ł͉�����TOEIC�ɂ��Ĉ��q�\������������
���{�����ł�L2�̌���\�͂̍\���Ɋւ����s�����Ɋ�Â��A���_�I��4��ނ̃��f�� (higher-order, correlated, uncorrelated.
unitary) �����肷��
��higher-order���f�����x�����錤���Ƃ��Ă�Sawaki (2007) ��������A�X�s�[�L���O�Ɋւ��5�̉��ʋZ�\�������ʋZ�\�����݂���Ƃ����悤�ȃ��f������Ă���Ă���
������ɑ��A�Z�\���K�w�W�ł͂Ȃ����݂Ɋ֘A���Ȃ����������Ƃ���correlated���f�����x�����錤���Ƃ��Ă�Bachman and Palmer
(1981) ������A�����A�X�y�����O�y�ь�b�\�͂Ȃǂ̋Z�\���������ĉp��n�B�x���\������Ƃ������f������Ă���Ă���
���������Ahigher-order model��correlated model�͑��֊W���������q�̐���3�̏ꍇ�ɂ͓��v�I�ɋ敪���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���Ă���
(see Sasaki, 1996)
�����ɁAuncorrelated���f�����x�������Ȍ����͂قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ����̂́A���[�f�B���O�\�͂ƃ��X�j���O�\�͂̊W���ɂ��Ă͂��̊֘A���̋����̓_�ŋc�_��������Ă��邱�Ƃ���
(e.g., Hirai, 1999)�A�{�����ł�uncorrelated���f�������_�I�ɉ��肷�邱�Ƃɂ���
���Ō�ɁAunitary model�ł��邪���̃��f�����x�����錤���Ƃ��Ă�Oller (1983) ������A�l�X�ȍ��ڂ�1�̓lj��n�B�x����������Ƃ������f������Ă���Ă���
���������Aunitary���f���ɂ��Ă͂��̓��v�I��@�ɖ�肪���邱�Ƃ��w�E����Ă���
���{�����ł́A������4�̃��f���̒��łǂ̃��f����TOEIC�̈��q�\���������Ƃ��K�ɐ�������̂��𖾂炩�ɂ���
���܂��A�{�����̂���1�̖ړI�Ƃ��đ���W�c�̓������͂�p���Č����Ó������m�F���邱�Ƃɂ���āA����ꂽ���f���̈�ʐ��������邱�Ƃ�����
������āA�{�����̃��T�[�`�N�G�X�`���� (RQ) �͈ȉ���2�_�ł���F
RQ1: higher-order���f���͑���3��ނ̃��f������������TOEIC�ɂ�肤�܂��K�����邩
RQ2: ������TOEIC�̈��q�\�����f���̓T���v���Ԃň�ʉ����ł��邩
�yMethod�z
(Data)
��569����L2��w���ł���A���{�l90%�A�؍�5%�y�ё��̃A�W�A�̍�5%����\�������
������W�c�̓������͂��s���ۂɂ͋��͎҂������_����2�Q�Ɋ��蓖�Ă�
��TOEIC�e�X�g�̎菇�ɂ��Ă͌����̎菇�ɏ�����
(Analyses)
��TOEIC�̌����ψ�����Ă�����ɏ]���A���[�f�B���O�X�L�����\������Z�\�Ƃ���5�� (e.g., make inferences in
written texts)�A���X�j���O�X�L�����\������Z�\�Ƃ���4�̗v�f (e.g., infer gist, purpose, and
basic context based on explicit information in short spoken texts) ���ϑ��ϐ��Ƃ���
�����ꂼ��̊ϑ��ϐ��́A�����ψ���̕��ނɂ��e�v�f���\������ݖ�̕��ϐ������Ƃ���
���Ŗޖ@��p���Ċe���f���̃p�����[�^�̐�����s���A�J�C��挟��ACFI�ANFI�ATLI�ARMSEA�ASRMR�AAIC�ACAIC�̊�ɏ]���ă��f���̓K���x�f����
����s�����ɏ]���Ĉ�ϗʋy�ё��ϗʊO��l�̌�����s�������A������̊ϓ_�ł��O��l�͂Ȃ�����
��higher-order���f���ɂ��ẮA��ꎟ���q��2�����Ȃ����߂Ƀ��f�����ʂɖ�肪���������߁A����ȏ�l�@���s��Ȃ����ƂƂ���
�yResults�z
��4�̃��f���ɂ��ēK���x�w�W�ɂ�錟�����s�����Ƃ���Ahigher-order���f����correlated���f���̓��Ă͂܂肪��r�I�悢���Ƃ������ꂽ
������ɑ��Auncorrelated���f����unitary���f���ɂ��Ă͓��Ă͂܂�ɖ�肪����ꂽ
�����̂��߁A���͂ɂ����郂�f�����ʂ̖����l������ƁAcorrelated���f����TOEIC�̃��f���Ƃ��Ă����Ƃ��悭�K�����Ă���ƍl������
�������ŁAcorrelated���f���ɂ��đ���W�c�̓������͂ɂ���Č����Ó����̌����s����
����s�����ɏ]���Č��̃��f���Ɉȉ���5��ނ̐��������������f�����쐬�����F (a) configural invariance, (b) invariance
of the factor loadings, (c) invariance for both the factor loadings and
the measurement error variables (d) invariance of the factor loadings,
measurement error variables, and factor variance, and (d) invariance of
the factor loadings, measurement error variance, factor variances, and
factor covariance
���e���f���̓K���x�w�W���m�F�����Ƃ���A������̃��f�������Ă͂܂�̗ǂ����f���ł�����
�����ɁA2�̏W�c�ɂ���č\�������e���f���Ԃō����Ȃ����Ƃ��m�F���邽�߂ɁA (a) �̃��f������Ƃ��đ��̃��f���ƃJ�C��挟��ɂ���r���s����
�����̌��ʁA (b) �̃��f���� (c) �̃��f���� (a) �̃��f���ɔ�ׂēK���x�w�W�ɍ����Ȃ��������̂́A(d) �̃��f���� (e) �̃��f���ɂ͍�������ꂽ
�����̗��R�����������Ƃ���Adivergent variance�y��divergent covariance�ɂ����̂ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ���
���ŏI�I�ȃ��f���Ƃ��ẮA�K���x�w�W�������Ƃ��D��Ă��� (e) �̃��f�����̗p���邱�ƂƂ���
�����̃��f���ɂ����Ă̓��[�f�B���O�X�L���ƃ��X�j���O�X�L���̑��ւ�.87�ƍ����l�ł��邪�ASawaki (2009) �ɏ]����.90�����͓���̗v�f�Ƃ݂Ȃ��Ȃ��Ɣ��f����
�yDiscussion and Conclusion�z
��RQ1�ɂ��āA�{�����ł͓K���x�w�W�̊ϓ_����ATOEIC�̈��q�\���Ƃ���correlated���f�����ł��K�ȃ��f���ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ���
���܂�RQ2�ɂ��āA����W�c�̓������͂ɂ����correlated���f���̓T���v���ԂɈ�ʉ��ł��郂�f���ł��������Ƃ������ꂽ
���{������������correlated���f����Wilson (2000) ����������O��TOEIC�̈��q�\���Ƃ͈قȂ邪�A���̗��R�Ƃ��Ă͈ȉ���3���l������F(a)
����ɂ����e�̕ω��A(b) ���v�I��@�̍��ًy�� (c) �ϑ��ϐ��̍���
�yImplications and Limitations�z
���{�����̋���I�����Ƃ��Ă͎�Ɉȉ���2�_����������F(a) TOEIC�X�R�A�̃��X�j���O�ƃ��[�f�B���O���ʃX�R�A�Ƃ��ĎZ�o����邱�Ƃ̑Ó������m�F���ꂽ�A(b)
����W�c�ɂ�����s�ϐ����l���������q���͂̈�ʉ��\���̌������s��������
���{�����̌��E�_�Ƃ��Ă͈ȉ���3�_�ł���F(a) �e���ڂ̕��ϓ_������ł��Ȃ��������߁A�ϑ��ϐ��Ƃ��Ċ��ɕ��ނ��ꂽ���ڂ̕��ϐ��������g�p��������
(b) �҂̃T���v�����O�����ۂ̎҂Ƃ͈قȂ��Ă��邱�ƁA(c) 1�̃t�H�[�}�b�g�����g�p���Ă��Ȃ�����
(�_����ǂ�ł̃R�����g)
�{�_���͉�����TOEIC�e�X�g�̈��q�\�������������̂ł���A���G�ȓ��v�I��@�ɂ��Ȗ��Ȍ������s���Ă���B�_���̍\���ɂ��āA2�_�قNjC�Â����_������̂ł��̓_�ɂ��Ĉȉ��ɏq�ׂ�B
�܂��́A�{�_���ɂ����Ă�4��ނ̃��f�����������Ă��邪�A4��ޑS�Ẵ��f������������K�v�������m�łȂ��悤�Ɏv���邱�Ƃł���B��̓I�ɂ́Auncorrelated���f����unitary���f���Ɋւ��Ă͐�s��������̗��_�I�Ȏx���͓����Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B���ɁAunitary���f���ɂ��Ă�Oller
(1983) �̃��f���𗝘_�I�����Ƃ��Ă��邪�A�{�_�����ɂ����āu���̃��f���͌�ɓ��v�I��@�̖�蓙�ɂ���Ĕᔻ����Ă���v�ƋL�q����Ă��邱�Ƃ���A���_�I�����͂قƂ�ǂȂ��悤�ɓǂݎ���B�܂��Auncorrelated���f���Ɋւ��Ă��A���r���[���ꂽ��s�����ł�2�̃X�L���̑��ւ̋����ɂ͈Ⴂ�͂���A�����ւ����肵�Ă��郂�f�����Ă��Ă��錤���͂Ȃ��悤�Ɏv����B���̂��߁Auncorrelated���f���Ɋւ��Ă��A���f�����������钼�ړI�ȗ��_�I�w�i�Ɍ�����悤�ɓǂݎ�ꂽ�B
������̃��f���ɂ��Ă��K���x�w�W�̓_�œ��Ă͂܂肪�����������Ƃ���A�ŏI�I�ɓK�ȃ��f���Ƃ��Ă͊��p����Ă���B���_�I�ɑz�肳���\�����c�郂�f���ɂ��Ă��������s�����Ƃ̕K�v���͊F���ł͂Ȃ����A��s�����ɂ����ė��_�I�ɂ����v�I�ɂ��x�����ア�����̃��f���̌����͗\�蒲�a�I�ł����ۂł������B
�@����2�_�ڂƂ���correlated���f����higher-order���f�������K���x�̖ʂŗD��Ă���Ƃ����������Ahigher-order���f���ɂ̓��f�����ʂɂ��htechnical
difficulties�h�����������߂Ƃ���Ă����_�ɂ��Ăł���B�Z�p�I�Ȗ��ɂ�胂�f���������Ȃ������ꍇ�ɁA���̃��f�����K�łȂ��Ɗ��p���邱�Ƃɖ��͂Ȃ��̂��낤���B���ɁA�{�����̃��T�[�`�N�G�X�`�����́u4�̃��f���̒��ōł��K�ȃ��f���͂ǂ̃��f�����v�ł͂Ȃ��A�uhigher-order���f���͑���3�̃��f���Ɣ�r���Ă��K�����Ă��邩�v�ł��邱�Ƃ���A�{�����ɂ�����higher-order���f������ƂȂ郂�f���ƈʒu�t�����Ă��邱�Ƃ���������Ă���B���̂悤�ȗ��_�I�y�ѓ��v�I�w�i�ɕx��ł���high-order���f���̓K���̋ᖡ�͂����������J�ɂȂ����ׂ��ł������ƍl����B���ɓ��v�I�ȃA�v���[�`�Ƃ��Ă͖�肪�Ȃ������Ƃ��Ă��A�htechnical
difficulties�h�ɂ�鎯�ʖ�肪�������ꍇ�ɂ͂��̃��f�������p���Ă��悢�ƌ��_�Â��Ă悢�Ƃ��������̐�����_���̌��E�_�Ƃ��Ă̋L�q���K�v�������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�ȏ�A2�_�ɂ��ďq�ׂ��B����1�_�ڂɂ��āA��s�����Ɋ�Â��ĕ����̃��f�������肵�Ă������Ƃ͏d�v�ł��邱�Ƃ͏��m���Ă��邪�A�ǂ̒��x�̃��f���܂Ŏ��ۂ̕��͑ΏۂƂ���̂��ɂ��Ă͌����҂ɔC����Ă���悤���B�������A��q�����悤�ɗ��_�I�w�i���d�v�ƂȂ�ȏ�A���ۂ́u���͑ΏۂƂȂ郂�f���v�́A���Ȃ��Ƃ��_���̓ǂݎ�ɂƂ��Ă����_�I�w�i���m�ł��郂�f���łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl����B
Abstract (p. 119)
�{�����́C���߂̉p����v��e�X�g�Ɋւ��āC�R���s���[�^�x�[�X�Ǝ��x�[�X�̂Q�̒��[�h�̈Ⴂ�C�y�ю҂̃R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�i�R���s���[�^�ɂǂ̒��x�e����ł��邩�̓x���j���ǂ̂悤�Ƀe�X�g���ʂɉe������̂����C�����l�w��157����Ώۂɂ��Ē��ׂ����̂ł���B���v���͂̌��ʁC������ŗv���������ꍇ�C���̒����ɂ����āC���[�h�̈Ⴂ�ɂ�����ʂ��m�F���ꂽ���C�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̍��́C�v�̃p�t�H�[�}���X�ɗL�ӂȉe����^���Ȃ������B�A���C�҂ւ̃C���^�r���[����́C�v�쐬�ɑ�����[�h�̕����I�C�S���I�e�����킸���ɔ`�����B
INTRODUCTION
(pp. 119-121)
�� �R���s���[�^�x�[�X�Ǝ��x�[�X�̓lj��e�X�g�̌݊����Ɋւ��錤���́C���C���A�C�f�B�A�̗���x�����C�ו��̗���x�𑪒肷�邱�Ƃ�ړI�Ƃ����I���`���̖��Ɋւ��čs���Ă����iChalhoub-Deville
& Deville, 1999�j�B
�� �܂��C���[�h�̌݊����Ɋւ����s�����ł́C�Z���e�L�X�g�̓lj�����ɂ��čs���Ă������iChalhoub-Deville &
Deville, 1999; Sawaki, 2001�j�C�㋉���x���̊w�K�҂͒������悭�ǂ�ł��邱�ƁC�y�уR���s���[�^�̉�ʂŒ�����ǂނɂ̓X�N���[�������Ԃ������邱�Ƃ��l����ƁC�����e�L�X�g����ɂ��Ē��ׂ�������K�ł���B
�� ����ɐ�s�����ł́C�Q�̒��[�h�̈Ⴂ�ɂ��e���͂قƂ�ǂȂ��Ƃ���Ă������C����͏W�c�̃e�X�g�҂ɑ��钲�����ʂł���C�X�̃e�X�g�҂ɑ���e���Ɋւ��ẮC�قƂ�ǖ��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��iDouglas
& Hegelheimer, 2007�j�B
�� �����C���[�h�̈Ⴂ�C�ҌX�̃R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�C�����ăe�X�g���ʂ̊W���C���C���邢�͊O����̃e�X�g�ɂ����Čv�ʓI�ɕ��͂��������́C�ˑR�Ƃ��ĖR��������ł���isee
Chalhoub-Deville & Deville, 1999; Sawaki, 2001�j�B
�� �����Ŗ{�e�́C�ȏ�̐�s�����̕s����₤���߁C�����e�L�X�g��ǂ�ŗv���쐬����`���̂��ƁC�R���s���[�^�x�[�X�Ǝ��x�[�X�̒��[�h�̈Ⴂ�C�҂̃R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̍��ɂ��e�����ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�C�Ƃ������T�[�`�N�G�X�`�����Ɏ��g�ނ��Ƃɂ���B
�� �Ȃ��C�{�����ł́C�W�c���x���̃e�X�g���ʂɉ����C�Ҍl���x���̐S���I���ʂɂ�����e���ׂ邽�߁C�v�쐬�̌�ɁC�҂ɑ���A���P�[�g�ƃC���^�r���[�����{����B
REVIEW OF
LITERATURE (pp. 121-123)
�� �v�쐬�^�X�N�́CTOEFL iBT�Ȃǂ̃R���s���[�^�x�[�X�̑�K�͂�high-stakes�́i�Љ�I�ɉe���̑傫���j�e�X�g�ŁC�ߔN�������i��ł���B
�� ��s�����ł́CTOEFL �̓lj��ƍ앶�̓����^�X�N�C�������͂�ǂ�ŁC���̓��e�̗v���쐬����^�X�N�Ɋւ��āC���[�h�̈Ⴂ�C�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̍��́C�҂̃e�X�g���ʂɗL�ӂɉe�����Ă��Ȃ����Ƃ�������Ă���iTaylor
et al., 1999; Trites & McGroarty, 2005�j�B
�� �A���CTOEFL iBT�ŏo�肳���p�����������e�L�X�g��ǂ�ŗv��ꍇ�̎��ؓI�����́C�M�҂̒m�����C�S�����݂��Ȃ��B
�� ���ɁC�l�ԍH�w�I�Ȋϓ_����CDillon�i1992�j�́C�R���s���[�^�̉�ʂŕ��͂�ǂޏꍇ�́C���ɏ����ꂽ���̂�ǂޏꍇ�����C20�`30%�ǂޑ��x���ቺ���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��C���̗v���Ƃ��āC��ʂɕ��͂����肫��Ȃ��ꍇ�C�X�N���[����������C��ʂ����X�Əo���K�v�����邱�Ƃ��w�E�����B�]���āC���̂悤�ȗv�������C���A�C�f�B�A�̗����C�����C�v�쐬�̑O������ivan
Dijk & Kintsch, 1983�j�ɂǂ̒��x�e������̂��́C�ǂݎ�̃R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�ɍ��E�����\��������B
�� �A���C�O�q��Taylor et al.�i1999�j�̌����ł́C�e�X�g���{�O�ɁC�v���O�����̎g������������`���[�g���A�����s���Ă���B����ɂ��C�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̒Ⴂ�҂̕s���v���y����������ʂ����邪�C�����`���[�g���A�������{���Ȃ������ꍇ�́C�e�X�g���ʂ��ς��\��������B
�� �܂��CTrites and McGroarty�i2005�j�́C���v�I���͂�ʂ��āC�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̍��ɂ��e�X�g���ʂւ̉e���͂Ȃ��Ƃ������_�������C���̌�̎��I���͂��s�Ȃ��Ă��Ȃ��_�����ł���B
�� ���̑���Shermis and Lombard�i1998�j�́C�A�����J�̑�w����ΏۂɎ������s���C�N��ƃR���s���[�^�ɑ���s�����lj��̃p�t�H�[�}���X�ɗL�ӂɉe�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ������C�앶�ɑ���e���͌��o���Ă��Ȃ��B���l�ɁCO�fSullivan,
Weir, and Jin�i2004�j�̌����ł��C���[�h�̈Ⴂ�ɂ��앶�ɑ���e���͌���ꂸ�C�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̍��ɂ��e�����قƂ�ǂȂ������B
�� ���̂悤�Ȍ��ʂɊւ��āCO�fSullivan et al.�́C���[�h���ς���Ă��앶�^�X�N���s���ۂ̔F�m�v���Z�X�͓��l�ł���Ǝ����������CRussell�i1999�j�́C���x�[�X�̃e�X�g�́C�R���s���[�^�Ɋ���Ă���w���̐��т��ߏ��]�����Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B
�� �]���Ă����̐�s�������������C�R���s���[�^�x�[�X�Ǝ��x�[�X�̓lj��e�X�g�̌݊����ɂ��āC�ˑR�Ƃ��ċc�_�̗]�n������B���ɁCEignor,
Taylor, Kirsch, and Jamieson�i1998�j���w�E����悤�ɁC�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̒�`���͂������܂��Ă��Ȃ��̂����ł���B
�� �R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�Ɋւ��ẮCETS�����āC���̎w�W��������C�����̃R���s���[�^�̋Z�p�̐i���ɂ��C�w�W���̂��̂����݂ł͓K�Ȃ��̂ƌ����Ȃ��\��������B�܂��C�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�ׂ邽�߂�ETS�̃A���P�[�g���C���R�L�q�̍��ڂ��Ȃ��Ȃǂ̐���������B
METHODS (pp.
123-125)
Participants and
Their Language Abilities
�� �{�����̎Q���҂́C�����̑�w�Ŋw��157���i�U�N���X���j��20�Α�O���̊w�����ŁC���̂����̖�80%�����q�w���ł���B
�� �Q���҂̉p��lj�͂́CTOEFL�̓lj���ŁC�X�R�A��24����48�͈̔́iFull score = 50, M = 36.3,
SD = 4.76, N = 156�j�ł������B
�� �܂��C�Q���҂ɉp��ƒ�����ŃG�b�Z�C�����������Ƃ���C�p��G�b�Z�C�̃X�R�A�́C6.5����16.5�͈̔́iFull score
= 18, M = 11.8, SD = 2.17, N = 156�j�ŁC������G�b�Z�C�̃X�R�A�́C5.0����16.5�͈̔́iFull score
= 18, M = 12.8, SD = 1.86, N = 153�j�ł������B����ɁC400��̉p���𒆍���ɖ�Ƃ��s�킹���Ƃ���C�X�R�A��4.5����15.0�͈̔́iFull
score = 18, M = 10.6, SD = 2.41, N = 154�j�ł������B�Ȃ��C���̃G�b�Z�C�Ɩ쐬�̕]���́C����̗v�̍̓_���s���R���̕]���҂̂����C�Q����I��ōs�����B
Materials and Procedures
�� �R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�ׂ邽�߂̃A���P�[�g�iCFQ�j�́C�܂��{�����Ŏg�p����O�ɁC�����̂S�̑�w�Ōv119���̊w����ΏۂɃp�C���b�g�����Ƃ��čs��ꂽ�B�����Ă��̌��ʂ́C���q���͂�ʂ���33�̎��⍀�ځC�T�̃J�e�S���iAppendix�Q�Ɓj�ɍi��ꂽ�B
�� �e�X�g���s�����O�ɁC�Q���҂ɑ��āC�v�쐬�̂��߂̈�ʓI�K���ƃX�g���e�W�[�ɂ��Ă̊ȒP�Ȑ������Ȃ��ꂽ�B
�� �v�쐬�^�X�N�ɍۂ��āC�������i�e�L�X�gA�j�C���ꕶ�i�e�L�X�gB�j�C�_�����i�e�L�X�gC�j�̂R���g�p���ꂽ�B�Ȃ��C�����̃e�L�X�g�́C���[�_�r���e�B�ƒ����i��2,200��j�����l�̂��̂ł���B
�� �e�e�L�X�g�́C�U�N���X�̂����Q�N���X�Ŏg�p����C�P���R���s���[�^�C�����P�����̃e�X�g�Ƃ��Ē��ꂽ�B�y�[�W���C�A�E�g�C�����̏��́C�傫���C�w�i�F�C�y�[�W��������������ɂ��Ă���C�R���s���[�^��̃e�L�X�g�́CMicrosoft
Word�Œ��ꂽ�B
�� �܂����ꂼ��̃N���X�ł́C�����̊w�����p��̗v�̌�C������̗v���쐬���C�c��̔������t�̎菇�ŗv���쐬�����B
�� �ŏ��̃^�X�N�ł͂Q���ԁC���̃^�X�N�͂P���Ԃ𐧌����ԂƂ��C82�����R���s���[�^�C75�������x�[�X�ŗv���쐬�����B�܂��C�e����ɂ�����v�́C300����350��ȓ��ŏ������Ƃ����߂�ꂽ�B
�� ���ɏ����ꂽ�v�́C���̂܂�Word�ɓ��͂���C�R���s���[�^��ō쐬���ꂽ�v�ƂƂ��ɁC�R���̕]���҂���I�ꂽ�Q���ɂ���āC�����I�ȕ]����Ɋ�Â��̓_���ꂽ�i��
> .84�j
�� �v�쐬�^�X�N�I����C�R���s���[�^�x�[�X�̃e�X�g������82���ɑ��C������ŃA���P�[�g�����{�����B�܂����̌�R���ȓ��ɁC�e�N���X�łS���i�p��C������̏��ɗv���쐬�����w���Q���C���̋t�ŗv���쐬�����w���Q���j��ׂɑI���25������45�����x�̃C���^�r���[���s�����B
ANALYSES AND
RESULTS (pp. 125-130)
Computer
Familiarity
�� CFQ�̉f�[�^�́C�T���I���q���́i�v���}�b�N�X��]�j�ɂ������C��P���q�̈��q���ח�.30�ȏ��15�̎��⍀�ځik = 4�j���R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̎ړx�𑪒肷�鍀�ڂƂ��Ďg�p�����B
�� ���͂̌��ʁC�҂̃R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�́C�����x���獂�߂̐��l�������ꂽ�iFull score = 60, M =
39.78, SD = 6.93, min = 21, max = 53�j�B
�� �܂�����̉ł́C�\�z�ʂ�C�e�L�X�g�̒����ɂ��L�Ӎ��͌���ꂸ�iF (1, 155) = 0.02, ns�j�C�e�L�X�g�̎�ނɂ��L�Ӎ��������Ȃ������iF
(2, 154) = 1.70, ns�j�B�܂��C�j�q�̕������q�����R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�������X��������ꂽ���iM = 39.02,
SD = 6.79�j�C���̍��ɂ��ẮC�����f�U�C���̃o�����X��C�ȍ~�̕��͂ł͍l�����Ȃ����ƂƂ����B
Summarization
Task Performance
�� �v�쐬�^�X�N�̌��ʁC������̗v�́C�p��̗v�������ς��ĒႢ�X�R�A�ł��������C���ʓI�ɂ͒������̂ƂȂ����iTable
1�Q�Ɓj�B
�� �e�L�X�g�̒��[�h�̉e���ׂ邽�߁C�����I����\�͂����ϗʁC�e�L�X�g�̒��[�h�C��ނ��Œ���q�Ƃ����P�ϗʈ�ʐ��`���f���ɂ�镪�́i�����U���́j���C�p��v�̃X�R�A�iEHS�j�C������v�̃X�R�A�iCHS�j�C�p��v�̒����iESL�j�C������v�̒����iCSL�j���]���ϐ��Ƃ��ĂS�ʂ�s�����B
�� ���ϗʂƂ��������I����\�͂́CEHS, ESL�Ɋւ��ẮCTOEFL�̓lj���̃X�R�A�Ɖp��G�b�Z�C�̃X�R�A����ɎZ�o���CCHS,
CSL�Ɋւ��ẮCTOEFL�̓lj���̃X�R�A�C������G�b�Z�C�̃X�R�A�C������̖̃X�R�A����ɎZ�o�����B
�� �e�L�X�g�̒��[�h�̈Ⴂ�Ɋւ��ẮCCSL�݂̂Ɏ���ʂ������C�R���s���[�^��Œ��ꂽ�����C���Œ��ꂽ���������v�ƂȂ����iF
= 5.81, p < .05, ��2 = 0.04, R2 = .14�j�B
�� �܂�CSL�Ɋւ��āC�e�L�X�g�̒��[�h�Ǝ�ނ̌��ݍ�p�́C�L�ӌX���i�{�[�_�[���C����j�ł���C���̌�̌���Ńe�L�X�gC�̒�����v�̒����̍��ɂ���āC���ݍ�p�����邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B
�� ���l�ɁC�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̍��ɂ��e���ׂ邽�߁C�R���s���[�^�x�[�X�̃e�X�g������82���̃f�[�^��ΏۂɁC�P�ϗʈ�ʐ��`���f���ɂ�镪�͂��s�������CEHS,
ESL, CHS, CSL�̂�����̃��f���ɂ����Ă��C�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̉e���͌����Ȃ������B
Students�f
Perceptions
�� �v�쐬��̃A���P�[�g���ʂ͂����Ƃ���C�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B���v��쐬�ɖ𗧂������Ƃ����_�Ɋւ��āC���ɖ𗧂����F5%�C�S�����ɗ����Ȃ��F9%�C�܂��܂��𗧂����F20%�C���܂���ɗ����Ȃ��F33%�C���̑��F33%�ł������B
�� �܂��C�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B���v�쐬�����e�L�X�g�̓lj��ɖ𗧂����Ƃ����������������C���v�I�ȗL�Ӎ��͌����Ȃ������i��2
= 1.90, ns�j
�� ���ɁC24���̎҂ɑ��ăC���^�r���[�����{���CwinMAX�iKuckartz, 1998�j�Ƃ����v���O������p���āC���[�h�̈Ⴂ�ɂ�镨���I�C�S���I�e���C�R���s���[�^�̑���X�L���C�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̉e���̊ϓ_���玿�I���͂��s�����B
�� �܂����[�h�̈Ⴂ�ɂ�镨���I�C�S���I�e���̍��́C���܂�傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ��������C�҂ɂƂ��Ď���邱�Ƃ��킩�����B�����[�h���D�ގ҂́C�`���Ɋ���Ă��邱�ƁC��ɂƂ��ēǂ߂���S�����������C�R���s���[�^�ł́C�v�쐬�ɂ����āC�����S�̂����邽�߂ɉ�ʂ��X�N���[�������Ԃ������邱�Ƃ��w�E���Ă���B�A���C�R���s���[�^�Ɋ���Ă���҂ɂƂ��ẮCWord���g�����v�쐬�����ɓ���^�X�N�ł͂Ȃ��Ƃ����ӌ����������B
�� �܂��C�R���s���[�^�̃X�L���Ɋւ��ẮC�Œ���̑��삪�ł���Ζ��Ȃ��Ƃ����ӌ��ł������B�]���āC�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̉e���́C�C���^�r���[�̌��ʂ���͂قƂ�nj����Ȃ������B
DISCUSSION AND
CONCLUSION (pp. 130-132)
�� ���v���͂̌��ʁC���[�h�̈Ⴂ�ɂ�����ʂ́C������v�̒����Ɋւ��Ă̂݊m�F���ꂽ�B����́C�v�̒����ɂ����ẮC�p�����������̕������[�h�̉e�������邱�Ƃ��Ӗ����邪�C������������CWord�̗v��C�R�s�[�C�y�[�X�g�@�\�̎g�p�������ł��邩������Ȃ��B�����C�p��̏ꍇ�C���ꂽ�e�L�X�g�ڃR�s�[�C�y�[�X�g���ėv���쐬���邱�Ƃ��\�ł���C���̂��ߎ҂��ꐔ�������i350�`350��j�ŏ�肭�܂Ƃ߂��ƌ����邩������Ȃ��B
�� ���������̏ꍇ�́C��ꌾ��䂦�ɁC����Ƃ͈�����X�g���e�W�[���g���Ă��邩������Ȃ����C���͂�S�ă^�C�v���Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁C�p��Ɣ�ׂ�Ζ��ƌ�����B
�� �e�L�X�gC�ɑ��钆����v�̒����̍��ɂ���āC�e�L�X�g�̒��[�h�Ǝ�ނ̌��ݍ�p������ꂽ���C���̂��Ƃ́CC�̂悤�ɗv����s���ۂ̃e�L�X�g�̓�Փx�������ꍇ�ɁC�e�L�X�g�̒��[�h�̈Ⴂ���v�쐬�ɉe��������̂Ǝv����B
�� ���v�I�ɂ́C���[�h�̈Ⴂ�ƃR���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̍��́C�v�̃p�t�H�[�}���X�ɗL�ӂȉe����^���Ȃ������B�������Ȃ���C�e�X�g�I����̃A���P�[�g�C�y�уC���^�r���[����C���[�h�ƃR���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̕��G�ȉe�������邱�Ƃ��킩�����B
�� �{�����̌��ʂ���ʉ�����̂͑��v�����C�v�쐬�^�X�N�ɂ�����e�L�X�g�̒��[�h�ƃR���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̉e��������ɒ��ׁC�R���s���[�^�x�[�X�Ǝ��x�[�X�̓lj��e�X�g�̌݊����Ɋւ��āC��藝����[�߂Ă������Ƃ��s���ł���B
���R�����g��
����̘_���́CTOEFL iBT���͂��߁C�ߔN�l�X�ȃe�X�g�œ�������Ă���v�쐬�^�X�N�Ɋւ��āC�R���s���[�^�x�[�X�Ǝ��x�[�X�̂Q�̒��[�h�̈Ⴂ�C�y�уR���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�Ƃ������̌l�����C�ǂ̂悤�Ƀe�X�g���ʂɉe������̂���ʓI�C���I�̗��ʂŒ��ׂ����̂ł���B���[�h�̈Ⴂ�ׂ������́C���̐��N�悭�ڂɂ��邪�C�{�����̂悤�ɁC�����e�L�X�g��ǂ�ŗv���܂Ƃ߂�Ƃ����^�X�N�Ɋ�Â��������́C���ɂ܂�ł���B���̈Ӗ��ŁC�{�_���̕M�҂́C�O�O�ɐ�s�����ׁC���̕s����₤�Ǝ��̃f�U�C����{�����ŗ��ĂĂ���ƕ]���ł���B�A���C�������@�C���́C���ʂ̉��߂Ŗ��_�C�^��_������悤�Ɏv����B�����ŁC�ȉ��ɂQ�_�قǎw�E�������B
�@�܂��傫�Ȗ��Ǝv����̂́C����g�p�����\�t�g�E�F�A��Microsoft Word�Ƃ�����ʓI�ȃ��[�v���\�t�g���Ƃ����_�ł���B�҂ւ̃C���^�r���[���ʂɌ�����悤�ɁC�e�L�X�g��ǂލۂ́C�ǂ�Ȃɒ����Ă��P�Ƀ}�E�X�ŃX�N���[������悢�����ł���C���̍�ƂŃR���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̍����e������Ƃ͂܂��l�����Ȃ��B�v�쐬�ɂ����Ă��Œ���̃L�[�{�[�h����Ŏ�����邱�Ƃ��l����ƁC������H�v�����Ă��悩�����悤�Ɏv����B
���ɍ���̎҂͑�w���ł���C�Œ���̃R���s���[�^�E���e���V�[������Ă���Ɛ��@�ł���B�]���āCTOEFL iBT��C�ŋ߂�e-���[�j���O�V�X�e���̂悤�ɁC�n�C�p�[�e�L�X�g�Ń����N��{�^���������Ȃ���C�^�X�N�Ɏ��g�܂���悤�Ȍ`�ł���C��������ʂɂȂ����̂�������Ȃ��B���ۂɁC�{�R�����g�̕M�҂����ƂŊw���ɑ���e-���[�j���O���ނɎ��g�܂����Ƃ���C�`���[�g���A�����s���Ă��C�L�[�{�[�h��}�E�X����C�v���O�����̗���x�̗D��ŁC�l��������悤�Ɍ���ꂽ�B���ꂪ�R���s���[�^�E�t�@�~���A���e�B�̍����ǂ����͕s�������C����̌����f�U�C����������\�t�g�E�F�A�C�V�X�e���Ŏ����Ă݂�̂��ʔ�����������Ȃ��B
���ɖ{�����̎��I���͂Ɋւ��ẮC�쐬���ꂽ�v�Ɋւ��Ă̕��͂����킹�čs���ׂ��ł������Ǝv����B�C���^�r���[��ʂ��Ď҂̐��̐����E���Ă����͍̂\��Ȃ����C���ꂾ���ł́C�R���s���[�^���[�h�̏ꍇ�ɒ�����̗v���p����������Ȃ��Ă��܂��v����T�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����v���̂����I�ɕ��͂����̂ł���C�҂��p��̃e�L�X�g�����̂܂܃R�s�[�C�y�[�X�g�����������p��̗v�Ɋ܂܂�Ă��邱�Ƃ������邱�Ƃ��ł�����������Ȃ��B���̂��ƂŁC�p��̗v��������ō쐬����ꍇ�������Ԃ̒Z�k���ł��C�����ꐔ���ł܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł����C�Ɩ��m�ɉ��߂��邱�Ƃ��\�ɂȂ�B���͂��镪�ʂ������Ƃ������Ƃł���C�����_���T���v�����O�ł��\��Ȃ��̂ŁC�v���̂̎��I���͂��~�����Ƃ���ł���B
�ȏオ�{�����ɂ�������_�ł��邪�C��������������Ă��C����̃e�[�}�́C���ۂ̃e�X�g�J���C�^�p�ɂȂ��鋻���[�����̂��ƌ�����B�R���s���[�^���g�����e�X�g�́C����܂��܂��J�����i�ނƎv����̂ŁC���̃����b�g�C�f�����b�g���C���x�[�X�̃e�X�g�Ƃ̔�r�����܂��āC����ɗl�X�Ȋp�x���猤�����Ă����K�v������B
1. Introduction
n �{�����͗��_�I�S�A���H�I�S�̗�������s��ꂽ���̂ł���B���_�I�Ȋϓ_�ł́A���[�f�B���O�A���X�j���O�͑o���Ƃ����l�ȏ�����K�v�Ƃ���Ƃ���Ă�����̂́A����炪�ǂ̂悤�ȉ��ʔ\�͂���\������Ă���̂��͂���܂ł̌����ō��ӂ������Ă��Ȃ��B�܂��A���[�f�B���O�A���X�j���O�������A�������͈قȂ鉺�ʔ\�͂���\������Ă��邩�͂���܂Ō�����Ă��Ȃ��B
n ���H�I�Ȋϓ_�ł́A���t�������̓e�X�g�J���҂́A�V���o�X�쐬��e�X�g�J���̂��߂Ɋw�K�҂̏s�ʂ��ꂽ���ʔ\�͂𗝉�����K�v������B
n �������N�AUCLA (University of California, Los Angeles) �ł͗��w����ΏۂƂ���Web-Based English as a Second Language Placement Exam (WB-ESLPE) ���J���E�g�p���Ă���B���̒��Ɋ܂܂�郊�[�f�B���O�Z�N�V�����ɂ�open-ended items, incomplete outline items���܂܂�A���X�j���O�Z�N�V�����ɂ�open-ended items�݂̂��܂܂�Ă���B
n ���[�f�B���O�E���X�j���O�Z�N�V������open-ended item�͑�w�u�`��e�L�X�g�́u���c���v�A�u�ڍו����̗����v�A�u�Î��I�ȏ��̐��_�v��3�̉��ʔ\�͂ɏœ_�ĂĂ���B���[�f�B���O��incomplete outline items�́u���c���v�A�u�ڍ��̗����v�̑����ړI�Ƃ��Ă���B
n �{�����ł�WB-ESLPE�̑��肷�郊�[�f�B���O�A���X�j���O�̉��ʋZ�\�̍\�����ASEM��p���Č�����BRQ�͈ȉ���2�ł���B
RQ1 WB-ESLPE�̃��[�f�B���O�A���X�j���O�Z�N�V�����̍��ڂ́AL2����\�͂̉��ʋZ�\���ǂ̒��x���肵�Ă��邩�B
RQ2 ���[�f�B���O�A���X�j���O��L2����\�͂̏s�ʐ��̊ϓ_����ǂ̒��x�قȂ��Ă��邩�A�������͎��ʂ��Ă��邩�B
2 Previous studies and model establishment
2.1 Divisibility of comprehension subskills
n �����̉��ʔ\�͂̑���Ɋւ���ő�̖���1�́A�����̉��ʔ\�͂����݂��A�����͉����Ƃ������Ƃł���B���̓_�ɂ��āA����܂ł̌��� (��Ƀ��[�f�B���O) �͑傫���ȉ���3�̗���ɕ��ނł���B
1. ���[�f�B���O�\�͂́A�P��̓������ꂽ�\�͂ł���A���ʋZ�\�ɂ͕��ނ���Ȃ� (e.g. Lunzer & Gardner, 1979; Rost, 1993)�B
2. ���[�f�B���O�\�͉͂��ʋZ�\�ɕ��ނ��꓾��B�������A���̋Z�\�␔�͌����ҊԂŗl�X�ł��� (e.g., Carroll, 1993; Lennon 1962)�B���X�j���O�ɂ��Ă����l�ɁA���ʋZ�\�ɕ��ނ���邪�A���̏ڍׂɂ��Ă̍��ӂ͓����Ă��Ȃ� (Buck &Tatsuoka, 1998)�B
3. ���[�f�B���O��decoding (word recognition) ��comprehension��2�̋Z�\����\�������B���X�j���O�ɂ��Ă����l��2�̍\���v�f������ƍl�����邪�A���X�j���O�ƃ��[�f�B���O�ł̓}�e���A���̒��[�h���قȂ邽�� (�����A������)�Adecoding�̃v���Z�X�͈قȂ�Acomprehension�̕��������ʂ��Ă���Ƃ���� (Larsen & Feder, 1940, p. 251)�B
2.2 Distinction between listening and reading skills
n ���X�j���O�ƃ��[�f�B���O�Z�\�̋�ʂƂ����͖̂��m�ł͂Ȃ��B���֕��͂�d��A���́A���ؓI���q���͂Ȃǂ�p��������܂ł̌����ł́A���[�f�B���O�ƃ��X�j���O�͋��ʂ��镔��������������̂́A���ꂼ��ɓ��L�̑��ʂ����˔����Ă���Ƃ������_�Ɏ����Ă��� (e.g., Bae & Bachman, 1998; Buck, 1992; Levine & Revers, 1988)�B
2.3 Establishing the models to be tested
n ����܂ł̐�s�����̗��_���l�����āA�{�����ł͈ȉ���3�̊ϓ_���烂�f��������s���B
(a) Unitary trait or separate traits
e ���X�j���O�ƃ��[�f�B���O���قȂ�����������Ă���Ƃ������f���ƁA���X�j���O�ƃ��[�f�B���O�͋��ʂ̗����v���Z�X�����Ƃ������f���̔�r�B
(b) Unitary skill or divisible subskills approaches
e L2����\�͂͒P��̔\�͂��琬��Ƃ��郂�f���ƁA�����̉��ʔ\�͂�z�肷�郂�f���̔�r�B
(c) Three- or two-subskils approaches
e L2����\�͂ɂ����Ă����̉��ʔ\�͂��s�ʉ\�ł��邩�������邽�߁A3�̉��ʔ\�� (���c���A�ڍ��̗����A���_) ��z�肷�郂�f���ƁA2�̉��ʔ\�� (�������̗��� [= ���c��+�ڍ��̗���]�A�Î����̗��� [= ���_]) ��z�肵�����f���̔�r�B
3. Method
3.1 Participants
n UCLA�ɗ��w���Ƃ��č݊w�\���110���B����A�w�K�w�i�͑��l�B
3.2 Instruments
n �{�����ł́AWB-ESLPE�̃��X�j���O�A���[�f�B���O�Z�N�V������p����B���Z�N�V�����Ƃ��A���c���A�ڍו����̗����A���_�ɏœ_�ĂĂ���B
(a) Listening test
���X�j���O�Z�N�V�����ł́A�������x���̑�w�u�`�𗝉��ł���\�͂����肳���BUCLA�̎��ۂ̍u�`��^�悵��20���̉f���Ƃ��̓��e�Ɋւ���20���ڂ�open-ended questions���p����ꂽ�B
(b) Reading test
���[�f�B���O�Z�N�V�����̓e�L�X�g�̌����߉ۑ� (incomplete outline task) 11���ڂ�10���ڂ�open-ended questions�̌v21���ڂ��p����ꂽ�B�ǂ���̉ۑ����w�������x����500����x�̓����e�L�X�g���g�p���ꂽ�B
3.3 Creating observed variables
(a) Categorizing the items
n �ʏ�A�e�L�X�g��Figure 1�̂悤�ȊK�w�\���𐬂��Ă���B
n ���̊K�w�\�����Q�l�ɁA�e�X�g�Ɋ܂܂��41���ڂ͈ȉ���3�̃J�e�S���ɕ��ނ��ꂽ�B
�E Topic (TOP)�F�e�L�X�g�̎��E�g�s�b�N�̗�����v������BFigure 1��Level 1, 2�ɂ��������₤���͂��̃J�e�S���ɕ��ނ����B
�E Details (DET)�F�����x��������A�ڍ��̗�����v������BFigure 1��Level 3, 4�ɂ��������₤���͂��̃J�e�S���ɕ��ނ����B
�E Inference (INF)�F�������ꂽ�e�L�X�g���e����̐��_��v������B
�� �����߉ۑ�͑S��TOP, DET�̂����ꂩ�ɕ��ނ��ꂽ�B
n ���ڂ̕��ނ�2����WB-ESLPE�̊J���҂ɂ���čs���A��v����93%�ł������B��v���Ȃ������́A���c�ɂ���ĉ������ꂽ�B
(b) Combining the items
n 2-3�̍��ڂ��܂Ƃ߂�1�̊ϑ��ϐ������ꂽ�B����́A41���ڂƂ�������110�Ƃ����T���v�����ɑ��Ă͑���������̂ł���A���ʂ��c�މ\�������邩��ł���B�܂��AEQS�ł�2���@�ō̓_���ꂽ�f�[�^�͂��邱�Ƃ��ł����A�W���l�Ƃ��Ĉ����K�v�����邽�߂ł���B
n ���ڂ́A�T�O�I�Ɏ��ʂ������́A�����\���T�O�𑪒肷����̂��܂Ƃ߂���K�v������B�����Ŗ{�����ł́A�������ʋZ�\�𑪒肷����̂œ����^�X�N�ł���A�������������̓p���O���t�Ɋ܂܂�����₤�A���ւ������Ȃǂ���Ƃ��č��ڂ��܂Ƃ߁ATable 1�Ɏ����悤��7�̃��X�j���O�̊ϑ��ϐ��A8�̃��[�f�B���O�̊ϑ��ϐ����쐬���ꂽ�B
3.4. Data analysis procedures
(a)
Preliminary statistical analysis
n �L�q���v�̐�x�A�c�x�̒l���炢�����̍��ڂ����K���z���Ă��Ȃ����A�Z�b�g���� (listening set, reading set, total set) ��Mardia (1970) �̑��ϗʐ�x (multivariate kurtosis) �̒l�͗L�ӂɑ傫�����̂ł͂Ȃ��A���ϗʐ��K���z���F�߂�ꂽ�B����āA�ȉ��̃��f�����͂ł͍Ŗޖ@���p����ꂽ�B
n �Z�b�g���Ƃ̃��W����.71-.79�ł���A�e�Z�b�g�Ɋ܂܂��ϑ��ϐ��̐��̏��Ȃ����l������ƁA�\���ł���Ƃ�����B
(b) Structural
equation modeling
n ��ɏq�ׂ�3�̊ϓ_���烂�f�������肳�ꂽ�B�P��\�̓��f���ł͗���\�� (COMP) ��B��̗v���Ƃ��A3�̉��ʔ\�̓��f���ł͏�q��TOP, DET, INF��v���Ƃ���B2�̉��ʔ\�̓��f���ł�TOP, DET�����킹�������I�ȏ��̗���\�� (EXP) �ƈÎ��I�ȏ��̗���\�� (INF) ��2��v���Ƃ����B
n ���f���̌����2�̒i�K�ōs��ꂽ�B�܂��͂��߂́A���X�j���O�ƃ��[�f�B���O���قȂ���������Ƃ��闧���z�肵�āA���ꂼ��ʂ̕��͂��s�����B���ɁA���X�j���O�ƃ��[�f�B���O�����ʂ̓��������Ƃ��闧���z�肵�āA���������� (�S�Ă̊ϑ��ϐ��ɑ���) ���͂��s�����B
(c)
Criteria for model evaluation
n ���f���̓K���x�̎w�W�Ƃ��āA��2�l�A��2�l�����R�x�Ŋ������l (��2/df)�ACFI, RMSEA���p����ꂽ�B
n �܂��A����l�̗L�Ӑ��̊�Ƃ��Ă͐�Βl1.96 (p = .05) �ƒ�߂��B
4. Results
4.1 Testing separate models
n 3.4�� (b) �ŏq�ׂ�3�̃��f���́A�܂����X�j���O�A���[�f�B���O�ʁX�Ɍ��肳�ꂽ�B
n ���͂̌��ʁA���X�j���O�E���[�f�B���O�����ŒP��̔\�͂����肷�郂�f���͒Ⴂ�K���x�������A���ɂ���̓��X�j���O�Ō����ł������B���X�j���O�ɂ��Ă�2�̉��ʔ\�͂����肷�郂�f���A3�̉��ʔ\�͂̃��f���̗����Ƃ��ǂ��K���x�����������̂́A��҂̂ق�����⍂�������B���[�f�B���O�ł�2�̉��ʔ\�͂̃��f����3�̉��ʔ\�͂̃��f�����������K���x���������B���ꂼ��ł������K���x�����������f���̃p�X�}�ƕW��������l�́AFigure, 2, 3���Q�ƁB
n ���[�f�B���O�̃p�X�}�Ɋւ��ẮA�ϑ��ϐ��̌땪�U�������l�������Ă���B�����open-ended task��incomplete outline task��2�̃^�X�N�̈Ⴂ�ł���\�������邽�߁A����2�̃^�X�N�̗v���݂̂��܂ރ��f�������肵�����A���̓K���x�͒Ⴉ�����B�܂�A�e�X�g�p�t�H�[�}���X�ɂ̓^�X�N�̈Ⴂ�����A2��������3�̉��ʔ\�͂��e����^���Ă���Ƃ������Ƃł���B
n ���̕��͌��ʂ���AL2�ɂ����郊�[�f�B���O�A���X�j���O�\�͂Ƃ����̂͏s�ʉ\�ȉ��ʔ\�͂���\������Ă��邱�ƁA���X�j���O�ɂ����Ă�TOP, DET, INF�Ƃ���3�̉��ʔ\�́A���[�f�B���O�ɂ����Ă�EXP, IMP�Ƃ���2�̉��ʔ\�͂����݂���Ƃ������Ƃ������ꂽ�B
4.2 Testing common subskills models
n ���ɁA���[�f�B���O�ƃ��X�j���O���\�����鋤�ʂ̔\�͂����邩�������邽�߁A15�̑S�Ă̊ϑ��ϐ��ɑ���3�̃��f���̌��肪�s��ꂽ�B���̌��ʁA3�̃��f���͑S�ĒႢ�K���x���������B
n �����ŁA���[�h�̈Ⴂ�A�܂�AUDIO, WRITTEN�Ƃ���2�̗v�����܂߂�3�̃��f�����������Ƃ���A���ꂼ��̓K���x�͌����ȉ��P���������B�������A���[�h�̗v���������܂߂����f���ł͏\���ȓK���x�ł͂Ȃ������B����́A���X�j���O�A���[�f�B���O�������f�[�^�̐����ɂ́A���ʔ\�͂ƃ��[�h�̈Ⴂ�̗������l�����邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ������Ƃł���B�������A���[�h�̗v���������܂߂����f���͒P��̗���\�͂������͉��ʔ\�݂͂̂̃��f�����������K���x�ł��邱�Ƃ���A�����f�[�^�ɂ̓��[�h�̈Ⴂ���傫�ȉe����^���Ă���ƍl������B
n ���[�h�̗v�����܂߂�3�̃��f���͂ǂ���K���x�������A1�̃��f����I������͓̂���B�P��̔\�͂����肷�郂�f����3�̒��ł��ł������K���x�������Ă�����̂́A3�̔\�͂����肷�郂�f���Ƃ̗L�Ӎ��͂Ȃ��B�܂��A�P��̔\�͂����肷�郂�f���̓��X�j���O�A���[�f�B���O�ʂ̃f�[�^�ł͒Ⴂ�K���x�������Ă��邽�߁A�����������f�[�^�̍ŏI���f���Ƃ��đI������̂͑Ó��łȂ��ƍl������B����āA�����ł͕������ʔ\�͂����肷��2�̃��f���̂����A��荂���K���x�������A��葽���̗L�ӂȕW��������l�������Ă���3�̉��ʔ\�͂����肷�郂�f�����ŏI�I�ȃ��f���Ƃ��đI������ (Figure 6)�B
5. Discussion
5.1 RQ1
n �{�����̌��ʂ���AWB-ESLPE�̃��X�j���O�A���[�f�B���O�Z�N�V������2�A��������3�̉��ʔ\�͂𑪒肵�Ă��邱�Ƃ������ꂽ�B���Ƀ��X�j���O�ł�TOP, DET, INF��3�̔\�́A���[�f�B���O�ł�EXP, IMP��2�̉��ʔ\�͂����肳��Ă����B
n ���X�j���O�A���[�f�B���O�ŏs�ʉ\�ȉ��ʔ\�͂̐����قȂ闝�R�͂������l������B
1. �҂̉p��n�B�x�̉e��
e �{�����̎҂́A��w�p�̃e�L�X�g�̎��E�ڍ����x�������邱�Ƃ͂ł��邪�A���X�j���O�ł͎��𗝉����邱�Ƃ���������B�����̌����҂́AESL�w�K�҂̓��[�f�B���O�������X�j���O�ɂ�������c���ɍ�����������Ƃ��w�E���Ă���B
2. ���[�f�B���O�Z�N�V�����ƃ��X�j���O�Z�N�V�����ɂ�����^�X�N�̈Ⴂ
e ���[�f�B���O�ɂ����ẮA�e�L�X�g��500����x�ł���Z���A�߂�ǂ݂��邱�Ƃ��\�Aopen-ended items��incomplete outline items�͓����e�L�X�g����ɍ쐬����Ă����A�Ƃ������R����҂͎��c���Əڍ��̗����̗����Ƃ��e�Ղ��������Ƃ��l������B����A���X�j���O�ł́A�u�`���e�������N���������̂̓��[�f�B���O�e�L�X�g��3�{�ȏ�̒���������A������1�x�݂̂Ƃ�����������A���[�f�B���O�e�L�X�g��lj�����悤�ɂ͎��c�����ł��Ȃ������ƍl������B���ʂƂ��āA���X�j���O�ł͎��c���Əڍ��̗������s�ʉ\�ł������B
n ��L��2�̗��R�ɂ��ẮA���ۂɁA���X�j���O�Z�N�V�����̕��ϐ�������30%�ł���̂ɑ��A���[�f�B���O�͔{��60%�ƂȂ��Ă���B�܂��AAlderson (2000) �ł͉��ʔ\�͂̕��ނ͏n�B�x�̒Ⴂ�w�K�҂ł�薾�m�ɍs�����Ƃ��ł���Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃ��l����ƁA����Փx�̍����������X�j���O�Z�N�V�����ʼn��ʔ\�͂�3�ɕ��ނł����̂͑Ó��ł���ƍl������B
n �ȏ�ɏq�ׂ����Ƃ��l������ƁA����܂ł̐�s�����ʼn��ʔ\�͂̐��ɂ��č��ӂ������Ȃ������̂́A�����ԂŎ҂̏n�B�x���l�X�ł��������߂��ƍl������B
n ���p�I�Ȋϓ_����q�ׂ�ƁA����̃��f����p���ăe�X�g���ڂ̉��P���s�����Ƃ��ł���B�Ⴆ�A���f���̒��ŕW��������l�̒Ⴂ�ϑ��ϐ��́A�\���ɉ��ʔ\�͂𑪒�ł��Ă��Ȃ��\��������B���̂悤�ȕϐ��Ɋ܂܂�鍀�ڂ��Ⴂ���חʂ��������R����肵�A���ڂ����P�����K�v������B
5.2 RQ2
n RQ2�ɂ��āA���X�j���O�ƃ��[�f�B���O���ʂɃ��f�����͂������ʂ���́A���X�j���O�̉��ʔ\�͂̓��[�f�B���O�����ׂ����s�ʉ\�ł��邱�ƁA���X�j���O�ƃ��[�f�B���O�̉��ʔ\�͂̎�ނ͎��Ă��邱�Ƃ����������B
n ����A���X�j���O�ƃ��[�f�B���O�������f�[�^�̃��f�����͂���́A���X�j���O�ƃ��[�f�B���O�ł͗���\�͂Ƃ����v�������ʂ��Ă���A2�̈Ⴂ�͒��[�h�̈Ⴂ�ł��邱�ƁA����\�͂������[�h�̂ق����e�X�g�p�t�H�[�}���X�ɑ傫���e����^���Ă��邱�Ƃ����������B�������A�����f�[�^�̃��f�����͂ł͒��[�h���܂߂�3�̃��f���S�Ăō����K���x�������Ă��邽�߁A���X�j���O�ƃ��[�f�B���O�ŋ��ʂ���v���Z�X�͒P��̂��̂Ȃ̂��A���ւ̂��鉺�ʔ\�͂̏W���Ȃ̂��͖��m�ł͂Ȃ��B
n �����̂��Ƃ��l������ƁA����̌��ʂł͓��v�I�ɍł������l���������̂͒P��̗���\�͂����肷�郂�f���ł��邪�AL2���X�j���O�A���[�f�B���O�ɂ����ĕs���ȗ����v���Z�X�����邱�Ƃ̏؋��Ƃ��Ă͉��߂ł��Ȃ��BRQ1�ɏq�ׂ��ʂ�A����ꂽ�f�[�^���҂̉p��n�B�x��^�X�N�̈Ⴂ�̉e�����Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
6. Conclusion and implications for further research
n �{�����ł́AWB-ESLPE�̃��X�j���O�Z�N�V������3�̉��ʔ\�͂𑪒肷�鍀�ڂ��琬��A���[�f�B���O�Z�N�V������2�̉��ʔ\�͂𑪒肷�鍀�ڂ���\������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B
n �܂��AL2���X�j���O�A���[�f�B���O�\�͂͋��ʂ̗����v���Z�X���܂�ł��邪�A�قȂ���[�h�ɂ��decoding process�̈Ⴂ�����邱�Ƃ������ꂽ�B
n ����ɁAL2����\�͂ɂ����鉺�ʔ\�͂̏s�ʐ��͎҂�L2�n�B�x�A�e�X�g�̓����ɂ���Ă��ω�����\�����������ꂽ�B
n ���p�I�Ȋϓ_����́A�{�����Ŏ����ꂽ���ʔ\�͂̑��݂̓e�X�g�J���҂��ǂ̂悤�ȍ��ڂ��e�X�g�Ɋ܂߂�ׂ������l����̂ɖ𗧂B���E�ڍ��̗����A���_�\�͂ȂǁA��w�ł̊w�K�ɕK�v�ȉ��ʔ\�͂Ƃ����ϓ_����AL2���X�j���O�A���[�f�B���O�e�X�g�͍\�������ׂ��ł���B
n �܂��A���݂�WB-ESLPE�ł̓Z�N�V�������Ƃɓ��_���Z�o���Ă��邪�A��������ʔ\�͂��ƂɎZ�o����ΐ��k�̃��X�j���O�A���[�f�B���O�\�͂ɂ��Ă��ڍׂȏ��邱�Ƃ��ł��A�V���o�X�f�U�C���Ȃǂɖ𗧂Ă邱�Ƃ��\�ł���B
n �{�����ł́u���ʔ\�́v�������w�W�Ƃ��āA���鍀�ڂւ̔�����p���Ă����B�������AAlderson (2000) ���w�E���Ă���悤�ɁA�K�������҂̓e�X�g�쐬�҂����҂���\�͂�v���Z�X�ɂ���č��ڂɔ�������킯�ł͂Ȃ��B���̂��߁A����́A�҂����ۂɍ��o���ꂽ���ʔ\�͂�p���č��ڂɔ������Ă��� (���������Ă���) ����������悤�Ȏ��I�ȃA�v���[�`���K�v�ł���B
�y�l�@�z
Song, M. (2010). Do divisible subskills exist in second language (L2) comprehension? A structural equation modeling approach. Language Testing, 25, 435-464.
�ȉ��ł͖{�_���Ɋ֘A���āA�@��K�̓e�X�g�ɂ����郊�[�f�B���O�E���X�j���O�Z�N�V�����ő��肳��鉺�ʋZ�\�̋L�q�ɂ��� �A SEM�ɂ�镪�͌��ʂ̕ɂ��āA�l�@���q�ׂ�B
�@ ��K�̓e�X�g�ɂ����郊�[�f�B���O�e�X�g�A���X�j���O�e�X�g�̉��ʋZ�\�̋L�q�ɂ���
�@�{�_���ł́AWB-ESLP�ɂ����đ��肳��郊�[�f�B���O�A���X�j���O�\�͂̈��q�\�������͂���Ă����BWB-ESLP�̂悤�ȓ���̎҂ɑ���e�X�g�Ɍ��炸�A�S�Ẵ��[�f�B���O�E���X�j���O�e�X�g�͕����̗v�f�𑪒肷��悤�ɍ쐬����Ă��� (Alderson, 2000)�B�����ŁA�ȉ��ł͂���ʓI�ɗp�����Ă��鐢�E�K�͂̉p��\�̓e�X�g���A�ǂ̂悤��L2�����̉��ʔ\�͂̑�����Ӑ}���Ă���̂��A�m�F���������q�ׂĂ����B
�@�܂��A���Ă̑�w�E��w�@�֗��w���邽�߂̉p��\�̓e�X�g�Ƃ��ėp�����Ă���TOEFL�ɂ��ẮA���R�A�J�f�~�b�N�ȏ�ɂ�����lj�́E����͂̑��肪���̖ړI�ł���B�������Ȃ���A�����K�C�h�u�b�N (ETS, 2009) �ɂ́A���[�f�B���O�A���X�j���O�Ƃ��ɑ��肳��鉺�ʔ\�͂ɂ��āA�X�Ɉȉ��̂悤�ȏڍׂȋL�q������B
|
�yAcademic Reading Skills�z u ���邽�߂̓lj�� e �d�v���̌����I�ȃX�L���j���O e �lj��̗������A���� u ��b�I�ȗ���� e ���A�ڍ��A�����̒��ł̌�b�A�㖼���Ɖ��̗��� e ���_�ɂ��Î��I���̗��� u �w�K�̂��߂̓lj�� e ���͍\���E�ړI�̔F�� e ����Ԃ̊W�̗��� e �}��v��ɂ�������̍\�� e ���͑S�̂�ʂ��Ė����l�����ǂ̂悤�Ɋ֘A���Ă��邩�̐��� |
|
�yAcademic Listening Skills�z u ��b�I�ȗ���� e ���₻��Ɋ֘A����ڍ��̗��� u ���p�I�ȗ���� e �b����̎p�� (attitude) ��m�M�x�̔F�� e �b����̋@�\��ړI�̔F�� u ���̌��т��E���� e ���ꂽ���̍\���̔F�� e �Î��I�ȏ��̐��_�A�y�ь��_�Â� e ��b�A�u�`�ɂ����镡���̏��̓��� e �u�`�A��b�ɂ�����g�s�b�N�̕ω��A�y�эu�`�ɂ����铱���E���_�̔F�� |
�@TOEFL�̃��[�f�B���O�Z�N�V�����ő��肳��鉺�ʔ\�͂Ƃ��āA�傫���u���邽�߂̓lj�́v�u��b�I�ȗ���́v�u�w�K�̂��߂̓lj�́v��3���q�ׂ��Ă���B���̂����A�{�_���őz�肳��Ă������ʔ\�� (TOP, DET, INF��������EXP, IMP) �ɓ�����̂��A�u��b�I�ȗ���́v�ł��낤�BTOEFL�ł͖{�_���ōו������ꂽ���ʔ\�͂��u��b�I�ȗ���́v1�ɂ܂Ƃ߂Ă���A���̑���2�̉��ʔ\�́u���邽�߂̓lj�́v�u�w�K�̂��߂̓lj�́v�̑�����Ӑ}���Ă���B�����[���̂́A�u�w�K�̂��߂̓lj�́v�ɂ��āA����𑪒肷�����̍��ڂ��ݒ肳��Ă��邱�Ƃł���B��̓I�ɂ́A�e�L�X�g�̏d�v�ȏ�����������I�������畡�������o���A�v�������������^�X�N�A�e�L�X�g�ɏq�ׂ�ꂽ����\�̌`�ɕ\���A���������������̂ɓK���镶��I�������畡�������o������^�X�N���u�w�K�̂��߂̓lj�́v�̑���ɗp�����Ă���B����A�u���邽�߂̓lj�́v�ɂ��ẮA����𑪒肷�����̍��ڂ͂Ȃ��A�����炭�e�X�g�ɗp������e�L�X�g�̒����ƃe�X�g���ԂƂ̊W�ɂ���āA�u�����ȓǂ݁v�𑪒肵�Ă���̂��ƍl������B
�@���X�j���O�Z�N�V�����ő��肳��鉺�ʔ\�͂Ƃ��ẮA�u��b�I�ȗ���́v�u���p�I�ȗ���́v�u���̌��ѕt���E�����v��3�ł���B�����͂���ɍו�������Ă��邪�A���ۂ̎��⍀�ڂ͂��̍ו����ɉ�����8��ނ��p�����Ă���B�{�����őz�肳�ꂽ���ʔ\�͂̂����ATOP, DET���u��b�I�ȗ���́v���\�����AINF�́u���̌��ѕt���E�����v�̈ꕔ�Ɋ܂܂�Ă���BWB-ESLP��ȉ��ŏq�ׂ�TOEIC�Ɣ�r���Ă݂�ƁA�b����̎p����ړI�̔F�����܂ށu���p�I�ȗ���́v��TOEFL�����肷������I�ȃ��X�j���O���ʔ\�͂ł���Ƃ�����B
���ɁA�p�����Ƃ��Ȃ��҂̉p��ɂ��R�~���j�P�[�V�����\�͂̑����ړI�Ƃ��Ă���TOEIC�ɂ��Č��Ă����BTOEIC�̃��[�f�B���O�A���X�j���O�Z�N�V�����̈��q�\����������In�fnami
& Koizumi (forthcoming) �ł́A�ȉ���5�̃��[�f�B���O���ʔ\�́A4�̃��X�j���O���ʔ\�͂��z�肳��Ă��� (TOEIC��������ꂽ�f�[�^���A���̂悤�ȍ��ڂ��Ƃɓ��_������Ă����悤�ł���)�B
|
�yReading subskills�z e (a) �e�L�X�g���琄�_������ e (b) �e�L�X�g���̓���̏��̗����A�ʒu�Â� e (c) ���ԋy�уe�L�X�g�Ԃ̏�� e (d) �������ł̌�b�̔c�� e (e) �e�L�X�g�ŗp�����镶�@�̗��� |
|
�yListening subskills�z e (a) �Z���e�L�X�g�ɂ����閾�����Ɋ�Â����A�v�_�A�ړI�A��{�I�ȕ����Ɋւ��鐄�_ e (b) �����e�L�X�g�ɂ����閾�����Ɋ�Â����A�v�_�A�ړI�A��{�I�ȕ����Ɋւ��鐄�_ e (c) �Z���e�L�X�g�ɂ�����ڍ��̗��� e (d) �����e�L�X�g�ɂ�����ڍ��̗��� |
�@���[�f�B���O�Z�N�V�����ɂ����Ă�5�̉��ʔ\�͂��z�肳��Ă��邪�A���̂���WB-ESLP�Ɛ�ɏq�ׂ�TOFFL�Ɋ܂܂�Ă��Ȃ����̂́A(c)
(���ԋy��) �e�L�X�g�Ԃ̏���A(e) �e�L�X�g�ŗp�����镶�@�̗����ł���BTOEIC�ł͖����I�E�Î��I�ȏ��̗����ɉ����A�u�e�L�X�g�P�ʂł̏���v�Ɓu�K�ȕ��@�g�p�\�́v�����[�f�B���O�̉��ʔ\�͂Ƃ��đ��肳��Ă���̂������ł���Ƃ�����B(c)
�ɂ��Ă̓_�u���p�b�Z�[�W��p�����e�X�g���ڂɂ��A(e) �ɂ��Ă͒Z���E�����̌����ߖ��Ɋ܂܂�鍀�ڂɂ���āA���肳��Ă���B
�@����A���X�j���O�Z�N�V�����́AWB-ESLP�őz�肳��Ă���TOP, DET, INF�Ƃ������ʔ\�͍\���Ɣ��ɋ߂��\���ł���B�قȂ�_�́ATOP��INF�������J�e�S���ɑ����Ă��邱�ƁA���ʔ\�͂�����ɒZ���e�L�X�g�A�����e�L�X�g��v���ɂ��ĕ��ނ��Ă���_�ł���B���ۂ̖����Z���e�L�X�g�ƒ����e�L�X�g��p�����p�[�g�ɕ�����Ă���A���ꂼ��Ɋ܂܂�鍀�ڂŎ��̔c����ڍ��̗�����₤�`���ł���B���̂��߁A���X�j���O�Z�N�V�����ɂ����ẮA���ʔ\�͂Ɩ�荀�ڂ̊֘A�����[�f�B���O�Z�N�V�����������m�ł���Ƃ�����B�������Ȃ���A�{�_���Ŏ����ꂽ�悤�ɁAL2�w�K�҂ɂ����Ă̓��X�j���O�̂ق������[�f�B���O������Փx�������A�s�ʐ����������Ƃ���A��L��4�̉��ʔ\�͂�����ɍו�������K�v�����邩������Ȃ��B�Ⴆ�A(a)
(b) �ɂ��āA���ꂼ����I�ɏq�ׂ�ꂽ���̔c���ƈÎ��I�ȏ��̗�����2���s�ʂ��邱�Ƃ��\�ł��낤�B
�@�Ō�ɁA�P���u���b�W��w�ɂ���č쐬����Ă���IELTS�ɂ��ẮAOfficial specification of IELTS (Clapham, 1996) �ɂ���đ��肳��郊�[�f�B���O�̉��ʔ\�͂��ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă��� (���X�j���O�\�͂͊m�F�ł��Ȃ�����)�B
|
�yReading subskills�z u IELTS attempts to measure e (a) �e�L�X�g�̍\���A���e�A�o�����̏����A�菇�̓��� e (b) �w���̗��� e (c) �����肪�������悤�Ƃ��Ă�����̗��� e (d) ���ݓI�ȃe�[�}�A�T�O�̓��� e (e) �e�L�X�g���̖���A�y�т����̊Ԃ̊֘A�̓��� e (f) �����A�؋��A�ӌ��A�����A��`�A�����̓���A��ʁA��r e (g) �؋��̕]���A�ًc�̒� e (h) ���ݓI�ȃe�[�}�A�T�O�A�؋��Ɋ�Â������̐��� e (i) �_���I���_�̐��� |
�@
�@TOEFL�Ɠ��l�ɁA���ʔ\�͂��ڍׂɕ��ނ���Ă���A�܂��d�Ȃ�\�͂������B����́AIELTS��Academic module��TOEFL�Ɠ��l�ɗ��w���̉p��n�B�x�̑����ړI�Ƃ��Ă��邽�߂ł��낤�B�������AIELTS�ł͂����̉��ʔ\�͂̑���̂��߂ɁATOEFL������葽�l�Ȗ��`�����p������X���ɂ���BTOEFL�Ɠ��l�̑����I����ɉ����A�p���O���t�̏����o����I�Ԗ��A�v�̃N���[�Y�e�X�g�A���X�g�̃}�b�`���O�A�e�L�X�g�\����}�������t���[�`���[�g�̌����߂��p�����Ă���B�����̖��́A(a), (c), (e) �Ȃǂ̉��ʔ\�͂𑪒肷����̂Ɛ��������B
�����܂�3�̉p��\�̓e�X�g�ɂ��āA���̑��肷�鉺�ʔ\�͂Ɋւ���L�q�̓_����T�ς��Ă����B�����̉��ʔ\�͂̋L�q�Ɋւ��ẮA�e�X�g�ԂŎ��ʂ������̂�������̂́A����e�X�g�ɓ����I�Ȃ��̂��������B���̂��߁A�e�X�g�ɂ���đ��肳��鉺�ʔ\�͂̋L�q��\���͂��̃e�X�g�̍\���T�O�m�ɔ��f������̂ł���A�{�_���̂悤�ɉ��ʔ\�͂̊ϓ_����e�X�g�̍\���T�O�v�I�ɕ��͂�����،����͔��ɈӋ`������B���̂悤�Ȍ����́A����e�X�g�̍\���T�O�Ó����Ɏx����^����ƂƂ��ɁA�e�X�g�̓Ǝ����̖����A���̃e�X�g�Ƃ̍��ʉ��̓_�ł��L�v�ł��낤�B
�܂��A�����3�̃e�X�g�ł́A�����ꏭ�Ȃ���A�L�q���ꂽ���ʔ\�͂ɂ���āA����̖��`�����p�����Ă����B���`���ɂ���đ��肳���\�͂̑��ʂ��قȂ�Ƃ����w�E (Alderson, 2000) ���l�����Ă��A���肪�Ӑ}����鉺�ʔ\�͂ɍ��킹�Ė��`����ς���̂͑Ó��ł���Ƃ�����B����������ŁAIELTS�̂悤�ɂ��̂悤�ȉ��ʔ\�͂��ו������ꂷ���Ă���ƁA�{���ɂ��ꂼ��̔\�͂��Ɨ����Ă���̂��Ƃ����^�O������B��q��9�̉��ʔ\�͂̂����A���̂������͋��ʂ��镔�����傫�� (���ւ�����) �\�͂�����̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A�����I�Ȗ��Ƃ��āA9���̉��ʔ\�͂��܂ރ��f���ɂ��āASEM�ɂ�镪�͂��s�����ꍇ�A�����K���x��������͓̂���ƍl������B���l�ɁA���͏�̖��Ƃ��āA�ϑ��ϐ����������߂ɂ��傫�ȃT���v�����K�v�ƂȂ邱�ƁA�ϑ��ϐ����\�����鍀�ڂ̐����s�����邱�Ƃ����O�����B���̂��߁A�e�X�g�쐬�ɂ�����\���T�O�Ó����̕ێ��Ƃ����ϓ_�ł͂��ڍׂȉ��ʔ\�͂̋L�q�͗��_�����邾�낤���A���ۂ̃��f�����͂�Ó������x������f�[�^��Ƃ����_�ł͕K�������]�܂����킯�ł͂Ȃ��̂�������Ȃ��B
�܂��A����1�^��Ɋ��������Ƃ́A�e�X�g�@�ւ�������Ӑ}���Ă��鉺�ʔ\�͂ƁA��s�����ŏq�ׂ��Ă��郊�[�f�B���O�E���X�j���O�̃��f���͂ǂ�قNJ֘A���Ă���̂��Ƃ������Ƃł���B����̘_����ǂތ���́A��ɉ��ʔ\�͂̍\���Ɋւ��錤���̓��[�f�B���O�̕���ő����Ȃ���Ă���悤�����A��s�����ŋc�_����Ă������f���́ATOEFL�� IELTS�̋L�q�ɂ���\�͂قǍו������ꂽ���ʔ\�͂͊܂߂Ă��Ȃ��悤�ł���B��s�����̃��f�������SEM���s���̂��A�e�X�g�@�ւ��Ӑ}���Ă��鉺�ʔ\�͂��܂ރ��f�������SEM���s���̂��͂ǂ��炪�Ó��ŁA�ǂ��炪�D�܂������ʂ邱�Ƃ��ł���̂��낤���BIn�fnami & Koizumi (2011) �ł�ETS������ꂽ�f�[�^����ɉ��ʔ\�͂����肵�Ă���悤�����A���ۂ̕��͂ɂ����Ă͐�s�����ŋc�_����Ă����u���[�f�B���O�ƃ��X�j���O�̊W�v���قȂ郂�f�����œ_�ɓ��ĂāA������s���Ă���B���̂��߁A���[�f�B���O�ƃ��X�j���O�̊W�Ƃ����ϓ_�ł�TOEFL, IELTS�ɂ����Ă����l�̕��͂��\�Ȃ̂�������Ȃ����A�����̊W�����łȂ��A�u���ۂ̃e�X�g�@�ւ��Ӑ}���Ă���悤�ȉ��ʔ\�͂��܂߂����[�f�B���O (���X�j���O) �\�͂̍\���v�ƁA�u��s�������c�_���Ă������[�f�B���O (���X�j���O) �\�͂̍\���v���ǂ̂悤�ȓ_�ŋ��ʂ��Ă���̂��A�܂��ǂ̂悤�ȓ_�ňقȂ��Ă���̂����n�l���邱�Ƃ��K�v�ł���B�������Ȃ���A�Ⴆ��TOEFL�̉��ʔ\�͂�1�ł���u���邽�߂̓lj�� (�����ȓǂ�)�v�́A����𑪒肷�邽�߂̓���̍��ڂ��������߂ɁA���̔\�͂��܂ރ��f���ɑ��ĕ��͂��s���Ƃ����̂͌����I�ɂ͓���ł��낤�B����T�ς����悤�ȑ�K�͉p��\�̓e�X�g��L2����͂̉��ʔ\�͍\���ɂ��āA����ǂ̂悤�ȃA�v���[�`�Ō����Ȃ���Ă����̂��͔��ɋ����[���Ƃ���ł���B
�A SEM�ɂ�镪�͌��ʂ̕ɂ���
����ASEM��p�������،����_����ǂ̂͏��߂Ăł��������߁A�ǂ̂悤�Ȏ菇�E���e�Ō��ʂ�����Ă����̂�������̂��߂ɊȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă����B
�܂��{�_���ł́A���f�����͂̎��O���͂Ƃ��āA���ڂ��Ƃ̋L�q���v�ƃZ�b�g (���X�j���O�A���[�f�B���O) ���Ƃ̃��W�����Z�o����Ă����B�L�q���v�ł͎�ɍ��ڂ��Ƃ̐��K���̊m�F���ړI�ƂȂ��Ă���A����ɂ̓Z�b�g���Ƃ̐��K�����m�F���邽�߂ɑ��ϗʐ�x (multivariate kurtosis) �̒l���Z�o����Ă����B
�@���f���K���̎w�W�Ƃ��ẮA��2�l�A��2�l/df�ACFI, RMSEA��4���p�����Ă����BIn�fnami & Koizumi (2011)�ŕ���������Ă��郂�f���K���̎w�W���Q�Ƃ���ƁA�{�_���ł�TLI (Tucker?Lewis index), SMSR (standardized root mean square residual) ������Ă��炸�A�\���Ƃ͌����Ȃ���������Ȃ��B
�܂��A���̂悤�ȓK���x�̎w�W�����łȂ��A�W��������l�̗L�Ӑ� (���f�����̊e�p�X���L�ӂł��邩) �ɂ��Ă��_���ł͋L�q����Ă����B����ɁA���f�����̌땪�U�̑傫���ɂ����ڂ��A�땪�U���傫�����Ƃ��烂�f���Ɋ܂܂�Ȃ��v�����e����^���Ă���\�����w�E���Ă����B���̉\����r�����邽�߂ɂ́A�l�����鑼�̗v���݂̂��܂߂����f���̓K���x���Z�o���A���ꂪ�Ⴂ���������Ƃ����菇���p������悤�ł���B
�@�������A�����̂悤�ȓ��v�I�Ȍ��ʂ݂̂���œK�ȃ��f�������肷��͕̂s�\���ł��邾�낤�B�{�_���̂悤�ɁA��s�����œ����Ă��錋�ʂ�f���Ȃǂ̗��_�I�ϓ_�A�����ŗp����ꂽ�}�e���A���̓����⋦�͎҂̓����Ȃǂ̊ϓ_���܂߂āA�œK�ȃ��f�������肷�邱�Ƃ��]�܂����ł��낤�B
���p����
Alderson, J. C. (2000). Assessing Reading. Cambridge University Press.
Clapham, C (1996). The development of IELTS: a study of the effect of background
knowledge on reading comprehension. Cambridge University Press
Educational Testing Service. (2009). The official guide to the TOEFLR (3rd
ed.). McGraw-Hill.
Educational Testing Service. (2009). �uTOEICR�e�X�g�V�������W Vol.4�v. �����F���c�@�l���ۃr�W�l�X�R�~���j�P�[�V��������.
In�fnami, Y., & Koizumi, R. (2011). Structural equation modeling in language testing and learning research: A review. Language Assessment Quarterly, 8, 250?276.
In�fnami, Y., & Koizumi, R. (forthcoming). Factor structure of the renewed TOEICR test: A multiple-sample analysis. Language Testing.
0.�@Overview
���lj�\�͂Ɋ�^����v���Ɋւ��ẮA�����̌������Ȃ���Ă���A���̗v���̑Ó�����������Ă���B�������Ȃ���AL2�lj��ɂ�����test performance�ɂ��Ă͌����Ă���B
������ɁA��b�m���̊�^�Ɋւ��錤���ɔ�ׁA����I�m���̊�^�ɂ��Ă͂��܂茤�����Ȃ���Ă��Ȃ��B
���{�����ɂ����ẮA3�̎������ʂ�SEM��p���āAL2�lj��ɑ��铝��I�m���ƌ�b�̍L���̊�^�Ɋւ��Ė��炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
1.�@Background
�����[�f�B���O�����ɂ����ẮA(1)���[�f�B���O�̉ߒ��Ɋւ��錤����(2)���[�f�B���O�Ɋ�^����v���Ɋւ��錤���̑傫��������2�̃A�v���[�`������B�{�������œ_�ĂĂ���̂͌�҂ł���B
��L1�ɂ����ẮA��b�m���A��̔F���\�́A���C�I�C�t���A�����č�ƋL���̂悤�ȗv�������[�f�B���O�ɉe�������Ă���Ƃ���Ă��� (Baddeley
et al., 1985; Cunningham et al., 1990; Jackson and McClelland, 1979; Palmer
et al., 1985)�B�������AL2�ɂ����Ă������悤�ɍl�������ł͂Ȃ��B
��L2�ɂ����ẮAL2�̒m���A�\�͂ɉ����AL1�lj�\�͂��e�����y�ڂ����Ƃ��l������B�������A����臒l�܂ł́A�O�҂̉e���̕����傫���Ƃ������Ƃ������Ă���B
������ɁA����I�m���̂悤�ɏœ_�Ă��Ă��Ȃ������v�����l�����Ă����K�v������B���ۂɁA����I�m����L2���[�f�B���O�ɂ����đ傫�ȉe�����y�ڂ��Ă���Ƃ��錤��������B
���������A����I�m���Ɋւ��ẮA��b�m���ɔ�ׂ�ƁA���[�f�B���O�ɋy�ڂ��e���͏������Ƃ���邱�Ƃ�����A����I�Ȍ����͓����Ă��Ȃ��B
2.�@General method of analysis
������I�m���ƌ�b�m���̃e�L�X�g�lj��ɂ�����d�v���ɂ��Ē������邽�߂ɁA3�̎������s�Ȃ��A���̌��ʂ��ASEM�ɂ���ĕ��͂����B�g�p�����\�t�g�E�F�A��AMOS�ŁA�Ŗޖ@��p�����B
�����f�����ȉ��Ɏ����B
<��>
3.�@Study 1
3.1�@Participants
���C�M���X�̑�w�ɂ�����pre-sessional EAP�v���O�����̊w��107���iL1�ƍ��Ђ͑��l�j�B
���R�[�X���̔F�莎���Ƃ��čs��ꂽ�B
3.2�@Instruments
���e�L�X�g�lj�20�� (Mean=11.65, SD=4.19, alpha=.79)
����b�e�X�g10�� (Mean=4.12, SD=2.31, alpha=.64)
������e�X�g30�� (Mean=20.90, SD=5.30, alpha=.83)
3.3�@Results
����2=4.821, df=6, ��2/df=.803, GFI=.985, NNFI=1.011, CFI=1.000, RMSEA=.000
��Reading�~Syntax: Beta=.47, r=.62
�@Reading�~Vocabulary: Beta=.42, r=.60
�@Syntax�~Vocabulary: r=.37
4.�@Study 2
4.1�@Participants
�����{�ɂ���3�̑�w�ɂ�������{�l�p��w�K��182���B
4.2�@Instruments
���e�L�X�g�lj�20�� (Mean=10.07, SD=4.38, alpha=.80)
��Study 1�̃}�e���A���Ƃ͈قȂ�A2���CET (Yang and Weir, 1998)�A����2���Lee and Schallert (1997)���g�p�����B
����b�e�X�g60�� (Mean=24.14, SD=11.50, alpha=.94)
��Study 1�̃}�e���A���Ƃ͈قȂ�AVLT���g�p�����B
������e�X�g32�� (Mean=15.41, SD=5.69, alpha=.82)
4.3�@Results
����2=7.521, df=6, ��2/df=1.254, GFI=.987, NNFI=.996, CFI=.998, RMSEA=.037
��Reading�~Syntax: Beta=.61, r=.89
�@Reading�~Vocabulary: Beta=.34, r=.85
�@Syntax�~Vocabulary: r=.84
5.�@Study 3
5.1�@Participants and instruments
�����{�ɂ���5�̑�w�ɂ܂�������{�l�p��w�K��624���B
���e�L�X�g�lj�20�� (Mean=10.49, SD=4.11, alpha=.74)
����b�e�X�g10�� (Mean=24.12, SD=12.81, alpha=.95)
������e�X�g30�� (Mean=15.89, SD=5.60, alpha=.79)
���S��Study 2�Ɠ����}�e���A�����g�p���ꂽ�B
5.2�@Results of single group analysis
����2=16.887, df=6, ��2/df=2.814, GFI=.990, NNFI=.989, CFI=.999, RMSEA=.055
��Reading�~Syntax: Beta=.64, r=.85
�@Reading�~Vocabulary: Beta=.25, r=.79
�@Syntax�~Vocabulary: r=.84
5.3�@Results of subgroup analysis
����2=25.917, df=15, ��2/df=1.728, GFI=.985, NNFI=.983, CFI=.992, RMSEA=.035
��High achievers
Reading�~Syntax: Beta=.50, r=.62
�@Reading�~Vocabulary: Beta=.19, r=.52
�@Syntax�~Vocabulary: r=.67
Low achievers
Reading�~Syntax: Beta=.62, r=.78
�@Reading�~Vocabulary: Beta=.26, r=.67
�@Syntax�~Vocabulary: r=.67
6.�@Discussion
������1�̌��ʂ���A���l�ȕ���L2�̊w�K�o����L����C�M���X��EAP�̊w���ɂ����āA����I�m���̕�����b�m�������A�킸���ł͂��邪�A�e�L�X�g�lj��������\������ϐ��ł���Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����B���̂��Ƃ́A�{�����̈�ʉ��ɂ����ďd�v�ȈӋ`�����B
������2�̌��ʂ���A���{�l�p��w�K�҂ɂ����ẮA����I�m���̕�����b�̍L�������A�e�L�X�g�lj��������\������ϐ��ł���Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����B����1�ɔ�ׂāA���炩�ȍ����o�����A����ɂ́A�팱�҂̈Ⴂ�ɉ����āA�}�e���A���̕ύX�̌��ʂ��l������B
���\�������ɔ�ׂėL�ӂɑ����̔팱�҂ɑ��čs��������3�̌��ʂ���A����I�m���̕�����b�̍L�������A�e�L�X�g�lj������\������ϐ��ł���Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�����̌��ʂ́A�ߋ��̎��I���� (Bernhardt, 1991)�Ƃ͈�v���邪�A�ʓI�Ȍ��� (Bossers, 1992; Brisbois, 1995; Yamashita, 1991)�Ƃ͖�������B
���������Ȃ���ABossers (1992)�ɂ����闼�҂̍��͌�b��r=.41�Ȃ̂ɑ��āA���@��r=.36�Ƒ傫�ȍ��ł͂Ȃ��������Ƃɉ����A�팱�҂��I�����_����w�ԃg���R�l�w�K�҂ƌ����Ă����B
��Brisbois (1995)�ɂ����Ă��A�}�e���A���̓���̂ɁA���ʂɏ��ʌ��ʂ������A���̈�ʉ��ɂ͋^�₪�c��B
��Yamashita (1991)�ɂ����ẮA�팱�҂̐���}�e���A���ɖ��͌����Ȃ����A�d��A���͂�p���Ă��邱�Ƃ���A���ʂ̉��߂ɂ͐T�d�ɂȂ�K�v������B�܂��A�lj�\�͂̑�����@���A�{�����Ƃ͈قȂ邽�߂Ɍ��ʂ���v���Ȃ��̂ł��낤�B
���܂��A����I�m���̕����A��b�m�������e�L�X�g�lj��������\������Ƃ������ʂ�����ꂽ���A���̂��Ƃ͌�b���d�v�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃɒ��ӂ������B���ۂɁA��b�m���Ɠ���I�m���̑��ւ́A��b�m���ƃe�L�X�g�lj��̑��ւ������� (r=.84 vs. r=.79)�B
�����ۂɁA��s�����ɂ�������q���͂ɂ����Ă��A�glexico-grammatical ability�h�Ƃ���鋤�ʈ��q������Ă��� (Purpura, 1999)�B
7.�@Conclusion
���{�����́A����I�m���ɑ��Č�b�m���̕������ΓI�ɏd�v�ł���Ǝ咣�����s�����ɂ�������_�̒ƁASEM��p�����挒�Ȏ�@����邱�Ƃ��o�����B
�����̌��ʁA�]���̌������ʂ��A����I�m���̕�����b�m���ɔ�ׁA���ΓI�Ƀe�L�X�g�lj��ɉe�����y�ڂ��Ƃ������_������ꂽ�B
������̌����ɂ����ẮAL2�̕ϐ��Ƃ��āA���X�j���O�E�^�X�N�ɂ���đ��肳�ꂽ��ʗ���\�͂��ƋL���̒����A��̔F�����x�Ȃǂ��܂߂Ă������Ƃ��]�܂��B�܂��AL1�̕���ɂ����Ă�SEM��p������@�Ō������Ȃ����Ə]���̌������ʂ���薾�炩�ɂȂ��Ă����̂�������Ȃ��B
���{�����ɂ����ẮAL2���[�f�B���O�\�͂̐����A�e�X�g�_���̗\�����A�M���W���̑���A�e�X�g���e�̑Ó����ɂ��ẮA����Ȃ�c�_�����߂��邾�낤�B
��Comment to the study��
�@����̕����́ASEM��p���āA�e�L�X�g�lj���\������ϐ��Ƃ��Ă̓���I�m���ƌ�b�m�����r�������̂ł������B�]���̐�s�����Ƃ͈قȂ��@�ŃA�v���[�`���A��������_���o�����{�����͊v�V�I�ł��邪�A���f���K���x�A�n�B�x�A�}�e���A���A����I�m���ƌ�b�m���̊W��4�_�ɂ��čl�@���Ă݂����B
�@�܂��A1�_�ڂ̃��f���K���x�ł��邪�A����1�`3�̂�����ɂ����Ă����ɍ����K���x��������Ă���B�����ŁA���ڂ��ׂ��Ȃ̂��A�J�C���l�ł���BGFI�ANNFI�ACFI�ARMSEA��4�̎w�W�͎����Ԃł���قǂ̍��͂Ȃ��ɂ�������炸�A�J�C���l�݂̂͌�̎����ɂȂ�قǍ����l�������Ă���A����3�ɂ����Ă͗L�ӂƂȂ��Ă���B����́A�_�����ł����y����Ă���ʂ�A�팱�҂̐������������߂ɁA�J�C���l�����܂�A�L�ӂɂȂ�₷���Ȃ������߂ł��낤�BSEM�̃��f���K���x�f����ۂɁA�J�C���l�݂̂Ŕ��f���Ȃ����Ƃ���������Ă��邪�A���߂Ċm�����_�̈��Ղɉ��߂��邱�Ƃ̋��낵���������ꂽ�Ƃ����悤�B
�@���ɁA�n�B�x�ɂ��Ăł��邪�A����3�ɂ����āA��ʌQ�Ɖ��ʌQ���ĕ��͂��s��ꂽ���A��ʌQ�̕����A���ʌQ�ɔ�ׂĕW�����W�������ւ̒l���Ⴍ�A�e�L�X�g�lj��ɑ��铝��I�m������ь�b�̍L���̐��������Ⴍ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ͎��ɋ����[�����ʂł���B���_�I�ɁAL2���[�f�B���O�ɂ����ẮA����臒l�����L2�̒m���A�\�͂ɉ����AL1�lj�\�͂��e�����y�ڂ��ƌ����Ă���B���̂悤�Ȏ��_���������ނ��Ƃ́A�{�����̎�|����͊O���\�������邪�A����̌��ʂ��A���̗��_�����߂Ďx��������̂ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�������Ȃ���A�{�����ɂ����ẮATOEIC��TOEFL�Ƃ������q�ϓI�w�W�ɂ��팱�҂̏n�B�x��������Ă��Ȃ���A������������臒l���ǂ̂�����ɑ��݂���̂�������̌������҂���邽�߁A����̂Ƃ���͂���ȏ�̌��y�͔��������B
�@�Ō�̋c�_�Ɉڂ�O�ɁA����1�̌��ʂ����̌�̎����Ǝ�قȂ邱�ƂɊւ��āA�����l�@���Ă��������B����1�ɂ����ẮA��̎����ɔ�ׂĕW�����W�������ւ��Ⴂ���A����̓}�e���A���̉e���ł���Ǝv����B���Ɍ�b�m���𑪂���̓��I��ѐ����������Ⴂ (alpha=.64)�B�܂�A��b�m���𑪂�͂��̖��ŁA��b�m���ȊO�i�Ⴆ�A����I�m���Ȃǁj�𑪂��Ă���\��������̂ł���B����ł́A���Ƃ���b�m�����e�L�X�g�lj��������\������ϐ��ł������Ƃ��Ă��A�W���͏������o�Ă��܂��B�s���ȃ}�e���A���ɂ���āA���������Ⴍ�Ȃ��Ă���̂ł���Ƃ�����A���̌��ʂ̉��߂ɂ͐T�d�ɂȂ�˂Ȃ�Ȃ��B
�Ō�́A����I�m���ƌ�b�m���̊W�ɂ��Ăł��邪�A����2��3�ɂ����āA����I�m���ƌ�b�̍L���̑��ւ����ɍ��� (r=.84)�B�����Ŏ��グ�����̂��A��b�m���̐[���ł���B��b�m���ɂ͒i�K�I������A�ŏ��͈Ӗ��������������̂ɁA�R���P�[�V������A���I�����i�R���Q�[�V�����j�̒m���Ȃǂ��������Ă����ƌ����Ă���B�R���P�[�V������A���I�����̒m�����l�����邽�߂ɂ͓���I�m�����K�{�ł���B�܂��A�t�ɁA������x�̃R���P�[�V������A���I�����̒m��������ƁA����I�ɕ��͂��Ȃ��Ƃ��A���@���ɓ������邱�Ƃ����낤�B���̂悤�ɁA������x�܂Ō�b�m�����[�܂�ƁA����I�m���Ɛ��Ă��藣�����Ƃ̂ł��Ȃ���̓I�Ȓm�����`�������BPupura (1999)�ȂǂŌ����Ă���glexico-grammatical ability�h�Ƃ͂��̂悤�Ȓm���̂��Ƃ��w���Ă���̂ł��낤�B����ŁA����I�m������b�m�����R������Ԃɂ����ẮA���݂̃����N�͊��҂ł��Ȃ��BWAT�Ȃǂ�p���Ȃ���A���ڍׂȕ��͂��s���Ă����ƁA���̂�����̖����������Ă�����\���������B
�Q�l����
Hudson, T. (2007). Teaching
second language reading. Oxford: Oxford University Press.
Nation, I. S. P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.
Purpura, J. E. (1999). Learner strategy use and performance on language tests: a structural equation modeling approach. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
�� Abstract
�����ł̕���� (oral narrative) �ɂ���Ďq����oral language skill�𑪒肷�邱�Ƃ��ł��邪�A�����̕]���͂��̕]���@�̉e����傫����B�{�����͎q����organization
skill (�ҏW�X�L��) ��]��������@�����r���[���A����Ɋe����@�ɂ���Ďq���̕���Z�p��]���E��r�����B���̌���Narrative Scoring
Scheme (NSS) ���ł��q���ȑ���@�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B
�� Introduction
�� Oral narrative skills
in children
�E �����ŕ�������\�� (oral narrative skills) �͎��Ƃ̒��ŕ]������邱�Ƃ͏��Ȃ����A���̔\�͎͂����̍l����`������A�N���X�����ɎQ�����邽�߂ɕK�v�ȋZ�p�ł���B
�E �q����narrative skill�͏����̓lj�\�� (e.g., Bishop & Edmudson, 1987) ��A�L���Ӗ��ł̊w�p�I����
(e.g., Fazio, Naremore, & Connell, 1996)�A���w�\�� (O�fNeill, Pearce, &
Pick, 2004) �Ȃǂ�\������A�ƌ����Ă���B
�E narrative skill�ɂ��Ă͌��ꑹ���̕���ł��������Ȃ���Ă����B���ꑹ���̂���q���͈�ѐ��̂��镨�ꂪ�ł��Ȃ��B���������āAoral
narrative�̊ώ@�͌��ꑹ���̗L���ׂ�1�̕��@�ł�����B
�� Oral narratives in
bilingual children
�E �o�C�����K����ESL�w�K�҂�Ώۂɂ��������ɂ����Ă��A�q����narrative skill�͓lj�\�͂�L�ӂɗ\������ƌ����Ă��� (e.g.,
August & Shanahan, 2006; Miller et al., 2006)�B
�E story telling�͑��̃e�X�g�`���ɔ�ׂāA��莩�R�œ���݂̐[�����̂ł���B
�E story telling�͌���\�͂𑪒肷��w�W�ɂȂ�B
�� Criterion referenced
assessment
�E oral narrative�͖ڕW������]�� (criterion referenced assessment: CR assessment)
�ɂ���ĕ]������邱�Ƃ������B�ڕW������]���ł͖ڕW (e.g., ����̕ҏW) �ɑ��āA�p�t�H�[�}���X���ǂ̒��x�B������Ă��邩���]����ƂȂ�B
�E ������CR oral language assessment�ł́A�����̃R�~���j�P�[�V������ʂ�z�肵���]�������Ă���A�������痣�ꂽ����\�͂�]�����Ă͂��Ȃ��B
�E �q���̌���\�͂̒����A�Z���ׂ邽�߂ɂ͂��ڍׂȖڕW������]�����K�v�ɂȂ�B(e.g., ���G�Ȍ�b�E���@�A�o��l���ւ̐��������y�A��v�ȏo�����̐����A�o�����̕ҏW�A�b����ɂƂ��ċ����[�����̂ɂ��Ă��邩)
�� Difficulties
associated with developing CR assessments
�E CR�̕]���@��Ó��Ȃ��̂ɂ��邽�߂ɂ́A�]�����q���̌��ꔭ�B��q���ɑ���ł��Ă��邩�ǂ�����]������K�v������B
�E ����Y�o�ɉe����^����v���͑������݂��邽�߁A�]���͕ς��₷���B
?�q���̕���Y�o�ɉe����^����v��: ���̘b�������Ƃ����邩�ǂ����A���̘b�����������Ƃ����邩�A�X�g�[���[�̒��̏o�����ւ̐e���x�A�X�g�[���[�̕��G���A�w���̎d��
�� Measuring children�fs
narrative organization skills
�E ��ѐ��̂��镨����Y�o���邽�߂ɂ́A�K�Ȍ�b�A���@�A�����p���ăX�g�[���[�̃v���b�g���C�����쐬���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�E ���ꕶ�@: �S�Ă̕���͐ݒ� (setting) �Əo���� (episode) ���琬��A�o��������̎n�܂�A���ւ̔����A���̉����A�����Ȃǂ��܂܂�Ă���
(Stein & Glenn, 1979)�B
�E narrative skill�̔��B�v���Z�X�͒x���A���l�ł����S�ɏn�B��������ɂȂ�Ȃ��ꍇ�������B
�E plot and theme analysis: �q����narrative organization skill�𑪒肷�邽�߂̎w�W��1�Ƃ��āA�q���̂��Y�o��������̒��Ƀv���b�g�ƃe�[�}���܂܂�Ă��邩�ǂ����ׂ镪�́B
?�X�g�[���[�̌��ƂȂ镨�ꕶ�@�̗v�f (�v���b�g�A�e�[�}) �������܂܂�Ă���قǁA�n�B����narrative skill�������Ă���ƌ��Ȃ����
(e.g., Berman, 1988; Botting, 2002; Bourderau & Hedberg, 1999)�B
�E holistic judgements (�S�̘_�I�]��): �q�����Y�o��������Ɋ܂܂��X�̍\���v�f��]������̂ł͂Ȃ��A����S�̂̎��┭�B���x����]��������@�B
?Manhardt and Rdscorla�fs (2002) Applebee�fs categorical level: ���ꕶ�@�Ɋ�Â��ēǂݎ�̕���Y�o��5�i�K
(heap, sequence, primitive narrative, focused chain, true narrative) �ŕ]��
?Pearce, McCormack, and James�fs (2003) Stein�fs scoring scheme: ���ꕶ�@�Ɋ�Â��ēǂݎ�̕���Y�o��11�i�K
(isolated description, descriptive sequence, action sequence, reactive
sequence, abbreviated episode, incomplete episode, complete episode, complex
episode, multiple episode, embedded episodes, interactive episodes) �ŕ]��
�� The narrative scoring
scheme: A comprehensive measure of narrative organization skills
?Narrative scoring scheme (NSS) �̓E�B�X�R���V����w��language analysis lab�ŊJ�����ꂽ�A�q����narrative
skill�𑪒肷����@�B�]���̕��ꕶ�@�Ɋ�Â����ϓ_�ɂ���Ɋϓ_�������A�ȉ���7�̊ϓ_����]�������B
�@introduction: �X�g�[���[���̐ݒ�Ɋւ��ڍ�q�ׂ��Ă��邩
�Aconflict resolution: �X�g�[���[���̖��Ɖ����q�ׂ��Ă��邩
�Bconclusion: �X�g�[���[�̌������q�ׂ��Ă��邩
�Cmental states: �X�g�[���[�̓o��l���̐S��q�ׂ��Ă��邩
�Dcharacter development: �o��l���̓W�J���q�ׂ��Ă��邩
�Ereferencing: �㖼����w����𐳂����g�p���ďq�ׂ��Ă��邩
�Fcohesion: �o�������_���I�ɁA�Ȃ���������ďq�ׂ��Ă��邩
�� Method
�� 129����5~9�̎q���̌���f�[�^�����W���ꂽ�B
�� �����҂��G�{ (Frog, Where are You?; Mayer, 1969) �����ǂ��A���͎҂�������Ęb (retelling) ����B�Ęb�͑S�Ę^������Asystematic
analysis of language transcripts (SALT) ��p���ĕ\���ꂽ�B
�� �Ęb�̃g�����X�N���v�g��NSS scoring, plot and theme approach, Applbee�fs narrative levels,
Stein�fs narrative level��p���č̓_���A���ʂ��r�����B
(NSS�ł͊e�ϓ_�ɂ���0~5�_�ō̓_�B7�̑��ʂ�����̂ŁA�����_��0~35�_�ɂȂ�B)
�� �̓_�҂̓g���[�j���O���\���ɍs���Ă���̓_�������B�S�f�[�^��20%���̕]���҂��ʂɍ̓_���A�c��̃f�[�^����1�����̓_�����B
�� Results
�� �e�̓_�@�̌��ʂɂ��āA�c�x�Ɛ�x�A�V����ʂ��番�z�̐��K�����r
�E �c�x: |0.8|���Ă���ꍇ�A���z���c��ł���Ɣ��f�ł���B�܂��A�c�x�����̒l���Ƃ鎞�A���_���S�̓I�ɍ������邱�Ƃ��Ӗ����A�̓_����Ⴗ����Ɣ��f�ł���B
�E ��x: ���_�̕��z���ǂꂾ���t�߂ɂ����܂��Ă��邩�B
�E 90%�ȏ�̓��_�f�[�^��V����ʂƌ��Ȃ����B
�� �c�x
�E �S�Ă̓��_�@�ɂ����āA�c�x�͕��̒l���Ƃ��� (Skewness for Plot & Theme = -1.0, Applebee =
-1.1, Stein = -1.0, NSS = -0.5)�B
?���_�̕��z���S�̓I�ɍ������ɏW�����Ă���B
�E NSS���ł��Ⴂ�l���Ƃ��Ă���B
�E Plot & Theme, Applebee, Stein��|0.8|��荂���l�������Ă��邽�߁A���z���c��ł���Ɣ��f�ł���B
�� ��x
�E �S�Ă̍̓_�@�� >.00�@?���ϒl�t�߂ɑ����̃f�[�^���W�����Ă���B
�E NSS���ł��Ⴂ�l���Ƃ��Ă���B����3�̍̓_�@�ł͓��_�̕��������B
�� �V�����: 90%�ȏ�_���Ă���f�[�^�̐�
�E NSS�ł͓V����ʂ͌����Ȃ������B
�E ����3�̍̓_�@�ł�30~35%�̃f�[�^�ɓV����ʂ�����ꂽ�B
�� Sample Narratives: �̓_��@�̈Ⴂ����薾�m�ɂ��邽�߂ɁA3�̃T���v�� (Sample1,2,3) �����I�Ɋώ@����
�E Sample3�͑���2�ɔ�ׂĖ��炩�ɒZ���A��������̂�����B
�E Sample1��Sample2�ɔ�ׂĂ��n�B�������̂ŁA�ڍׂȏ����܂�ł���1��1�̏o�������悭�\���Ă���B�܂����G�Ȍ�����p���ăX�g�[���[����ɂƂ��Ėʔ������Ă���B
�E ���ۂ�4�̍̓_�@��p���č̓_���Ă݂�ƁASample3�͑���2�����Ⴍ�̓_���ꂽ���APlot & Theme, Applebee,
Stein�ł�Sample1��2�̊Ԃɍ��������Ȃ������B�������ANSS������Sample2���Sample1�̕��������̓_�ł����B
�� Discussion
�� Sensitivity Analysis
�E Krippendorff alpha (�M�����W��) �ׂ��Ƃ���ANSS��Plot & Theme�̓� = .79, Stein�̓�
= .61, Applebee�̓� = .69�ł������B
?Plot & Theme�͓���̗v�f���̓_������@�ł���A�M�������ł������Ɨ\������Ă������ANSS�ɂ��̓_���ʂ�Plot &
Theme�Ɠ����x�̐M������L���Ă����B
�E NSS�ɂ��̓_�@�́A�c�x�E��x������3�̍̓_�@��菬�����A�f�[�^�̓V����ʂ������Ȃ������B
?NSS�ō̓_����ƁA���̍̓_�@�����f�[�^�̐��K���z�����肳��₷���Anarrative skill�̒Ⴂ���k���獂�����k�܂ł𑪒肷�邱�Ƃ��\�B
�E �q����narrative skill�͔N��Ƌ��Ɍ��シ��̂ŁA�\�͂�q���ɑ���ł��鑪��@���K�v�ł���B
?�{������NSS�ł́Amaximum possible score��35�_���������A���͎҂̍ō��_��26�_�ł��������Ƃ�����A��������͎҂̂���Ȃ�X�L���̌��オ�\�������B
�E ����͗l�X�ȃ}�e���A����p���āANSS�ɂ�鑽���̍̓_�f�[�^�����W���邱�Ƃ��K�v�B
�� Use of the NSS in research,
educational, and clinical contexts
�E oral language skill�͋���J���L�������ɂ����Ă��d�v�Boral language skill�ƃ��[�f�B���O�\�́A�w�p�I�Ȑ����Ƃ̊W������ɒT��K�v������B
�E NSS�̂悤�ȑ���@��p���邱�Ƃɂ���āA����w�K�ɂ����鍢��x��A�q���̌��ꔭ�B��q���ɒ������邱�Ƃ��ł���B
�� Conclusion
�� �{�����ł�4�̈قȂ�̓_�@��p���Ďq���̍Ęb��]���������ʁANSS���ł��q���Ȋ�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B
�� �{�����͖ڕW������]���̐�����]������1�̎���Ƃ��Ă��ʒu�t������B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comments
�� �̓_��̑Ó���
�{�����͎q���̕���Y�o�f�[�^��4�̕]���@�Ɋ�Â��ĕ]�����A�c�x�A��x�A�V����ʂɊ�Â������K���̊ϓ_����e�]����̑Ó����������Ă���B�e�X�g���̂̐M�����E�Ó����ɂ��Ę_���錤���͐��������݂��邪�A�{�����̌��ʂ�����킩��悤�ɓ����^�X�N��e�X�g���s���Ă��]���@�̈Ⴂ�ɂ���ĕ]�����قȂ��Ă���Ƃ����_�͔��ɏd�v�Ȏw�E�ł���B���ɁA�{�_���ŗp���Ă��镨��Y�o�̂悤�ȃ^�X�N�ł͎Y�o�����f�[�^�̎��R�x���������ߕ]���͓���A�X�̃f�[�^��q���ɕ]���ł���̓_�@�̓��肪�K�v�ł���B�e�X�g�̑Ó��������łȂ��A���̍̓_����]���������ϓ_��Ó��ɕ]���ł��Ă��邩�Ƃ����u�̓_��̑Ó����v���^�X�N�̕]���ɂ����Ĕ��ɏd�v�ł���B�{�����̂悤�ɕ����̍̓_��ɂ�錋�ʂ��r����Ƃ������@�́A�̓_��̑Ó�����]������1�̕��@�Ƃ��ėL���ȕ��@�ł���ƍl������B
�@����ŁA�{�_���Ŕ�r����Ă���4�̊�͂��ꂼ��]���̒i�K�����قȂ��Ă��� (possible range for Plot &
Theme = 0-12; Applebee = 0-5; Stein = 0-11; NSS = 0-35)�B���������āA�i�K���̑���NSS�ł̕]�������̊�����q���Ƀf�[�^��]���ł���A�Ƃ������ʂ͂���Ӗ����R�Ƃ��l������B�܂����H�I�ȑ��ʂ���́A�]������ׂ����ݒ肷�邱�Ƃɂ��A�]���҂̕��S���傫���Ȃ�Ƃ����_���l������K�v������B(�{�_���ł�oral
narrative skill�����Ɠ��ŕ]�������ʂ͏��Ȃ��A�Ƃ����L�q����������) ���H�I�Ȍ���w�K�ɂ�����oral narrative�Ƃ����^�X�N�����p����ꍇ�A���̕]���@�ɂ��Ă͕]���@�̑Ó����Ƌ��ɕ]���҂̕��S�ɂ��Ă��l������K�v�����邾�낤�B
�� �{�_���̕��͕��@�ɂ���
�@�{�_���ł͑O�q�����ʂ�f�[�^�̐��K�����ώ@���邱�Ƃɂ���č̓_�@�̑Ó�����]�����Ă���̂ɉ����āASample Narratives�Ƃ���3�̃f�[�^�����I�Ɋώ@���Ă���_�����ɋ����[�������Bsample�ϓI�ɕ]���������ɖ��炩��Sample1>2>3�̏��ɕ]���ł��Ă��APlot
& Theme, Applebee, Stein�̊�ł�Sample1��2�̊Ԃɍ��������Ȃ������A�Ƃ����_�͂����̕]���@�̌��E�m�Ɏ������ʂƂȂ��Ă����B�^�X�N�̕]���ɂ����ẮA��x��Ɋ�Â��č̓_������ƁA���Ƃ̃f�[�^�̓��e�����I�ɍĊώ@����Ƃ����菇�ނ��Ƃ͋H�ł��邪�A���̕��@�͊�̑Ó������������Ƃ����Ӗ��ł����ɗL���ł���ƍl������B
�� NSS�ɂ���
�@NSS�͏]���̕��ꕶ�@�Ɋ�Â��ϓ_���炾���ł͂Ȃ��A���x��narrative skills (e.g., cohesion, referencing)
���܂ނ��L���ϓ_����̕]���@�ɂȂ��Ă���B�{�_���̃^�X�N�Ƃ��ėp�����Ă���Ęb (retelling) �Ƃ����^�X�N�́A�P�ɃX�g�[���[�̓��e�𗝉����邾���łȂ��A�X�̏o������ǂݎ�̐S���ōč\�z���ĎY�o����Ƃ����v���Z�X���Ƃ��Ȃ����̂ł���A�Ƃ������Ƃ��l�����Ă�cohesion,
referencing�̂悤�Ȕ\�͂͏d�v�ł���A������]���̊ϓ_�ɓ���邱�Ƃ͑Ó��ł���ƍl������B�^�X�N�̕]�����ݒ肷�鎞�ɂ́A�]���̊�����肷�邾���łȂ��A�^�X�N�̐������l��������ŕ]�����lj�����Ƃ����菇���d�v�ł���B
INTRODUCTION
���R���s���[�^�Z�p�����B�������Ƃɂ��A�V������̃e�X�g���@����������B(a)face-to-face�܂���direct�e�X�g�A(b)person-to-machine�܂���semi-direct�e�X�g�Ƃ���2�̃e�X�g�̓K�ؐ����V�����c�_�ɂȂ��Ă���B
�����̘_���ł́A2�̃e�X�g�ւ̍��`�̎҂̔����⊴�������r�������̂ł���B���ʂƂ��ẮA�����̎҂̓e�X�g���@�Ɋւ��ē���̗D��X���͎����Ȃ���������ǂ��Adirect�e�X�g�������D�ގ҂̐��́Asemi-direct�e�X�g���D�ގ҂̐������Ȃ�����Ă����B���R�Ƃ��āAsemi-direct�ł́A�e�X�g���҂Ǝ����҂̌𗬂��Ȃ����Ƃ��������A����͎҂̐S���I��ǂ�����Ă��܂��悤�ł���B
|
BACKGROUND
��Chapelle & Douglas (2006)
Jones & Maycock (2007)
�����݁ACambridge ESOL��TOEFL iBT�ȂǁA�����̍��ۓI�Ȍ���e�X�g�ɂ����āA�R���s���[�^���g�����e�X�g�`�����̗p����Ă���B
���܂��ATOEFL iBT�ł́A�R���s���[�^��ʂ̑O�Ńe�X�g�҂��p��̃X�s�[�L���O�͂������e�X�g���g�ݍ��܂�A�A�����J�ł́A���w�Z�⒆���̃e�X�g�v���O�����ŁA�R���s���[�^���g�����e�X�g�̎��s�\�����T������Ă���B
���R���s���[�^��ʂ�����������n�B�x�]�����l�C�̌X���ɂ���B
�@���������A���̃R���s���[�^��ʂ�����������]���̃����b�g�Ɩ��_�f����K�@�v������
Formats for Oral
Proficiency Assessment
�������n�B�x�𑪂�3�̌`����indirect testing, direct testing, semi-direct testing (Clark, 1979; O�fLoughlin, 1995, 1997, 2001)
��indirect testing
�E�I�[�����X�L����ړI�ɕ]�����鍀�ڂ����܂܂�Ȃ�
�@�@���b�����ƂȂ��ɁA�����A�A�N�Z���g�Ȃǂ��y�[�p�[�e�X�g�ŕ]������
�@�E�e�X�g�쐬�҂��{���ɒm�肽���e�X�g�҂̃I�[�����X�L���𐳊m�ɁA�m���ɕ]�����Ă���Ƃ����_�Ŗ�肪����
�@�����݂ł́Aindirect testing�͊�{�I�ɃX�s�[�L���O�]���Ɋւ��Ē��~����Ă���
��direct testing (or live testing)
�@�E�e�X�g�쐬�ҁA�����҂��m�肽���҂̃I�[�����X�L���𑪂�Ó����A���m���̂���e�X�g��indirect�ƈ���āA���ۂɎ����҂Ɩʂƌ������Ęb���K�v�����邽��
�@�Edirect oral testing��1950�N��ɃA�����J�ł͂��߂ē������ꂽ��the Oral Proficiency Interview (OPI)�������ł��������悤�ɂȂ�
��semi-direct testing
�@�E�e�[�v�ACD�A�R���s���[�^�A�C���^�[�l�b�g�Ȃǂ̔}���ʂ��āA�I�[�����X�L����]��������@���҂̓^�X�N�����s���A�����̓e�[�v�A�f�B�X�N�A�f�W�^���t�@�C���Ȃǂɘ^������A�̂��ɕ]�������
�@�E1980�N��ɃA�����J�Ō���]����i�Ƃ��ē�������遨 Simulated Oral Proficiency Interview (SOPI)
�@�����E�{�݂��������A�Z�����Ԃő����̎҂Ƀe�X�g�����{���邱�Ƃ��ł���
�@�@�@�E����ł̎����҂�K�v�Ƃ����A���o�ϓI�A�����I�Ƀe�X�g�����{�ł���
�@�@�@�EOPI�����M���������遨�����҂̉e���œ��_���ς�����肵�Ȃ�
�@�Z���EOPI�̕����A���I�[�Z���e�B�b�N�ɋ߂���ԂŃR�~���j�P�[�V�����͂�]�����邱�Ƃ��ł���
��SOPI, semi-direct testing�̕����A�����I�A�o�ϓI�A�����ŁA�M����������
Previous Research
Findings
��Stanfield (1991) Stanfield & Kenyon (1992)
�@�Edirect��semi-direct testing�̃X�s�[�L���O�]���ɂ����āA���̃e�X�g���ʂ���2�̃e�X�g���@�͈�v�����Ó����̂��鑪��@���Ƃ��Ă���B
�@��2�̃e�X�g���@�͓����̂��̂ł���
��Shohamy (1994)
�@�E���H�I�k�b�̃p�^�[���ƌ���̃A�E�g�v�b�g�Ƀe�X�g���@���ǂ̂悤�ɉe�����Ă��邩������߂邽�߂ɁA�����҂Ɣ팱�҂̌��ݍ�p�ƃ^�X�N�̓�����\���͂����B
��Luoma (1997), O�fLoughlin (1997, 2001)
�@�E2�̃e�X�g���@�̕\�ʓI�Ó��������邽�߂Ɏ҂̃t�B�[�h�o�b�N�����W�����B
�ˎ҂̃A�E�g�v�b�g��]���҂̕]���ɂ�����A�e�X�g�\���A�f�U�C���A�k�b�����A���ݍ�p�A��b���x���܂e�X�g�ƕ]���̉ߒ�����2�̕��@�ɍ���������
��Brown (1993), James (1988), McNamara (1987), Shohamy, Donista-Schmidt & Waizer (1993), Stanfield (1991), Stanfield et al. (1990)
�@�E�҂̃t�B�[�h�o�b�N�ɂ�钲���͓��荬���������ʂ��o�Ă���B
�@�@�������̌����ł́A�҂�direct testing�̌`���̕����D�ނƂ������ʂ������Ă��邪�Asemi-direct testing���D�ގ҂̊����̕����傫���Ƃ������ʂ̌���������
Research Issues
�����`�̒n���̐l�X�ɂƂ��āAsemi-direct testing�̂悤�Ȍ`�����ǂ̂悤�ɉe�����邩�̌����͂قƂ�ǂ���Ă��Ă��Ȃ�����������K�v������
RQ1: direct testing��semi-direct testing��2�̕��@�́A�ǂ��炪�҂ɂ��������̂��B
RQ2: �ǂ��炩�̃e�X�g���@���҂��D�ނƂ��A�ǂ̂悤�ȗ��R���\���Ƃ��Ă������邩�B
RQ3: �e�X�g�҂�2�̃e�X�g���@�ɑ��Ăǂ̂悤�Ȋ���I�������������B
������I�������e�X�g���@�ɂ�����\��A�A�C�R���^�N�g�A�̂悤�Ȕ����R�~���j�P�[�V�������܂A�l�Ƃ̌𗬁A�܂�����̌��@�Ȃǂ̗v�f�Ɋւ��
��RQ1���A���P�[�g����
RQ2��RQ3������ɑ��Ă̎Q���҂��������R�����g�̎��I�ȃf�[�^
METHOD
Participants
and Procedures
��17�̕��삩��W�߂�ꂽ���`�̍ŏI�w�N�̑�w��186�l�B
��direct��semi-direct testing�̗���������A2�̃e�X�g�ɑ��锽�������⎆�A�A���P�[�g�ɂ���Ē�������B
Tests Used for
the Comparative Study
��direct testing �� the International English Language Testing System (IELTS)
�@�E11�`14���ԂŁA�����҂Ǝ�1��1�ōs����B
�@�E3�̃p�[�g�ɂ���č\�������B
�@�@�@�Ȃ��݂̂�����e�ɂ��Ď҂Ɏ����҂����₷��(1�`2��)
�@�@�A�҂��A�^����ꂽ�g�s�b�N�ɂ���1�`2���ŒZ���v���[�������A����Ɋւ��
�����҂����1�`2�̎���ɓ�����
�@�@�B�����҂ƎҊԂŁA�A�̃g�s�b�N�ɂ��ăf�B�X�J�b�V�������s��
��semi-direct testing�� the Graduating Students�f Language Proficiency Assessment-English (GSLPA)
�@�E�}���`���f�B�A���ꃉ�{���g���[��40���ԍs���A5�̃^�X�N�ō\������Ă���
�@�@�@���W�I�C���^�r���[�̏���v����
�@�@�A�A�E�ʐڂł�����A�̎���ɓ�����
�@�@�B�d���̉�c�Ɍ������āA���������ƂɃv���[��������
�@�@�C�d���ɊW����d�b�̗���d���b�Z�[�W���c��
�@�@�D���`�ł̐����Ɋւ�������A�V�������w���Ɍ������Đ�������
Questionnaire
���ґS����2�̃e�X�g�ɑ��锽�����A���P�[�g�ɂ���Ē������ꂽ�B
�@�ȉ���2�̎���ɑ��āAstrongly agree, agree, not sure, disagree, strongly disagree�@�ʼn����Ă�������B
�@�@GSLPA�X�s�[�L���O�e�X�g(semi-direct)�́A�����Ɏ����̉p��̃X�s�[�L���O���x����]�����邱�Ƃ��ł��Ă���B
�@�AIELTS�X�s�[�L���O�e�X�g(direct)�́A�����Ɏ����̉p��̃X�s�[�L���O���x����]�����邱�Ƃ��ł��Ă���B
��2�̎���̐M�����́A���W����0.75�ł������B
RESULTS
���A���P�[�g�̏W�v����
�E73.1���̎҂�IELTS���x�����Ă������AGSLPA���x������҂�49.5���ɗ��܂����B
���Ή������t����̌���
�E2�̃e�X�g�ɑ��锽���A�D�݂ɗL�Ӎ����������B
�����⎆����ɂ����V����5�̃J�e�S���[�̏W�v
�E(a)IELTS�����D�ށA(b)GSLPA�����D�ށA(c)�����̃e�X�g�ɍm��I�A(d)�����̃e�X�g�ɔے�I�A(e)�ǂ���̃e�X�g�ɂ��ӌ����Ȃ�
�EIELTS�������D�ސl�̕����AGSLPA�������D�ސl�������������B
�E40.9���̐l�������̃e�X�g�ɍm��I�ł������B
�E16.7���̎҂��ǂ���̃e�X�g�ɂ��m��I�ł͂Ȃ������B
�E(c)(d)(e)3�̃J�e�S���[�����킹��ƁA��58���̎҂�����̍D�݂������Ȃ������B
���҂̎��⎆�ɏ����ꂽ�R�����g�ɂ́AIELTS���D�ޗ��R��������������Ă����B
�@�EIELTS�̕����A�l�Ɖ�b������̂ŁA��莩���̃X�s�[�L���O�͂�I�m�ɕ]���ł���
�@�E�l�C�e�B�u�X�s�[�J�[�Ƃ̉�b�̕����A�R���s���[�^�ɘ^��������悢
�@�E�W�F�X�`���[��A�C�R���^�N�g�̓X�s�[�L���O�͂�]������̂ɏd�v�ł��邩��AGSLPA�͂��܂�𗧂��Ȃ��@�Ȃ�
��GSLPA���D�ރR�����g�����Ȃ�����ǂ�������Ă����B
�@�E�����҂̕\��┽���ɂ���Ă��т₩����邱�Ƃ��Ȃ��̂ŁAGSLPA�̕����悭�ł����Ɗ�����
�@�E�����̓V���C�ł��邩��A�]���҂̑O�Řb�����������b�N�X���Ăł����@�Ȃ�
DISCUSSION
Testing Mode
Preference
���Q���҂̑���(57.6��)���A�e�X�g�`���ɑ��ē���̍D�݂������Ȃ������B
�@������̍D�݂������Ȃ��������傫���Ƃ������ʂ��o����s�����́A���܂łɂȂ�����
������A�命�����Asemi-direct testing����direct testing���D�ތX���ɂ������B
�@����s�����ɂ���ė��t����ꂽ���ʂł���
���ǂ���̃e�X�g���҂ɂƂ��Ď�����邩�Ƃ������_���o���ɂ́A�T�d�ɂȂ�ׂ������ʂɂ́A���낢��ȗv��(�e�X�g�̎��A���@�A�����I�w�i�Ȃ�)���ւ�邩��
���҂��ǂ���̃e�X�g�����ꂽ�Ƃ�������
�@��semi-direct test�̔��W�ɗL�]�ȏ����̑O���ƂȂ�
Testing Mode and
Test Performance
����葽���̎����I�؋����K�v�ł͂��邯��ǂ��A�����̎҂�direct testing�ɍD�ӓI�Ȕ������������B
����Ӄt�B���^�[�́A�҂̃p�t�H�[�}���X�ɉe�����邽�߁A�����ł��Ȃ����ʂł���
Predictive
Validity
��direct testing�́A�������ɉ������R�~���j�P�[�V������K�v�Ƃ���̂ŁAsemi-direct�����\���I�Ó���������Ƃ�����
���R���s���[�^�ɘb���A�^�����邱�Ƃ́A�\�ʓI�Ó����A�\���I�Ó������Ⴂ
��2�̃e�X�g��]�������ŁA�d�v�ȗv�f�ƍl������ׂ�
CONCLUDING
REMARKS
��semi-direct�ɕK�v�Ȃ̂́A�l�Ɛl�Ƃ̌������E�̃R�~���j�P�[�V�����͂𑪂邱��
���Z�p�̔��W���i�߂A�������̐l�Ԃ̌𗬂ɋ߂�semi-direct test���s�����Ƃ��ł��邩������Ȃ�����ʂɌ������Ď҂̔��b�ɑ��Ă��̏�ł���肪�ł���e�X�g��
�y�l�@�z
����Adirect��semi-direct test�ɑ���e�X�g�҂̊���I���ʂ��e�[�}�Ƃ����_����I�������B�ŋ߁A�X�s�[�L���O�͂��R���s���[�^���̋@���ʂ��ĕ]������e�X�g�����ۓI�ɂ������Ă��Ă���B���ۂ̂Ƃ���Adirect��semi-direct�̂ǂ��炪�҂ɂƂ��Ă͎���₷�����Ƃ������Ƃɋ������������BDirect test�́A���ۂ̃R�~���j�P�[�V�����͂�]������̂ɁAsemi-direct�����Ó����������Ǝv���邪�A�������A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�̓_�����ƁAsemi-direct�̕����D��Ă���ƍl������B
�@���̎����ł́A�����҂Ǝ҂�1��1�Ŗʂƌ������ăe�X�g������direct test�ƁA�R���s���[�^�Ɍ������Ē��ꂽ�^�X�N�ɂ��Ęb��semi-direct test��2�̌`���ɑ���҂̊���I���ʂ��A���P�[�g�ƃR�����g�̋L���ɂ���Ē������Ă���B���ʂƂ��ẮAdirect test���D�ގ҂��������߁A�܂��A�e�X�g�ɑ���R�����g��direct test�̕����A�l�Ɛl�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����������œK���Ă���Ƃ����L�q�����������B����������ŁA�ǂ���̃e�X�g�ɑ��Ă��m��I�ӌ��������́A�ǂ���̃e�X�g�ɑ��Ă�����̍D�݂������Ȃ����̂��A�傫�Ȋ������߂Ă����B���̌��ʂ́Asemi-direct test���A����̉��ǂɂ���Ă͎��H�I�Ȗʂł�direct test�Ǝ���đ���\�������邱�Ƃ��������Ă���ƍl������B
�@�������A���̘_���ł́A���~�e�[�V�����Ɋւ���L�q���قƂ�ǂȂ������B���̘_����ǂ�ŋC�ɂȂ������Ƃ�2�_���������Ǝv���B�܂��A1�_�ڂ́A�e�X�g���Ԃ̒����Ɠ��e�ł���BDirect test��11�`14���ԁAsemi-direct test��40���ԂƂ������Ȃ�̊J����������B�����܂ł̊J��������ƁA�����P���Ƀe�X�g����������A�Z������Ƃ������R�ł��̃e�X�g�ɑ���ԓx���ς���Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������B�܂��A�e�X�g���e��2�̃e�X�g�ł͂��Ȃ�قȂ��Ă���BDirect-test�̓f�B�X�J�b�V�����⎿��ɑ��鉞������ł���̂ɑ��āAsemi-direct test�͓��e�̗v���v���[���e�[�V��������ł���B�����̗v�f�́A�A���P�[�g�⎿�⎆�̌��ʂɑ傫�ȉe���������炷�̂ł͂Ȃ��̂��낤���B�����ԃe�X�g���A�����Ԙb�����Ƃ͎҂ɐS���I���S�������Ă��܂��Ǝv����B����āAdirect test���҂ɍD�܂ꂽ���R�ɂ́A���H�I�ȃR�~���j�P�[�V������I�m�ɑ����Ă���Ƃ������Ƃ������N�����Ă���Ƃ́A���̎����ł͍l���ɂ����B
�@2�_�ڂ́A�e�X�g�̃p�t�H�[�}���X�̌��ʂɊւ��ċL�q���Ȃ����Ƃł���BDirect test�̕����A��Ӄt�B���^�[��������\��������ƍl�����邱�Ƃ��w�E����Ă������A���ہA���̃p�t�H�[�}���X�̌��ʂ��ǂ��������̂����킩��Ȃ��܂܂ł���B��Ӄt�B���^�[�������������ƂŁAdirect test�̕����Asemi-direct test�����e�X�g�X�R�A���ǂ������̂ł���A���̓_�Ɋւ���semi-direct test�͉��P����l���Ă����K�v������B�����āA���̂悤�Ƀe�X�g�X�R�A���ׂ�ɂ́A�O�q�����悤�Ƀe�X�g���e�������������ꂷ��K�v������悤�Ɏv����B
�@�ȏ�̂��Ƃ���Adirect test���������I�ł���semi-direct test�����L�߂�K�v��������Ȃ�A���̎���������ɉ��ǂ��Asemi-direct test�̔��W�ɂȂ���ׂ��ł���B
1. �w�i
�������P�O�N�قǂ̊ԂɃR���s���[�^�[�e�N�m���W�[�̔��B�ɂ�茾��\�͂̂����鑤�ʂ𑪒肷��ہA�R���s���[�^�[���p������悤�ɂȂ����B�e�X�g��Ђ̂悤�ȂƂ���ł��R���s���[�^�[�^�C�v�̃e�X�g�����삳��Ă���BJones
and Maycock(2007)�̓�l�́u�R���s���[�^�[�e�X�g���g�p���闝�R�́A���ׂĂ��v���ɁA�����悭�֗��ɍs���邩��ł���A���܂łƈႤ���ǂ��e�X�g���\�ɂ���v�ƃR���s���[�^�[�g�p�̕K�v����M��Ɏx�����Ă���B
�������̍��ۓI�ȉp��\�͂̏n�B�x�e�X�g���R���s���[�^�[������Ă���B�Ⴆ�A�C�M���X�̃P���u���b�W��w�ɂ���ď�������J������Ă���r�W�l�X�p�ꑪ���Cambridge
ESOL�̓R���s���[�^�[�ƃy�[�p�[�e�X�g�̗����ɑΏ����Ă���B�܂��A�����J�̐��E���̃e�X�g��Ђ�the Educational Testing
Service�͐������̍��ۓI��v�ȃe�X�g���R���s���[�^�[�x�[�X�̃e�X�g���J�����Ă���A2005�N�X���ɃC���^�[�l�b�g���x�[�X�ɂ����V����̃e�X�g�Ƃ��ďЉ�ꂽTOEFL
iBT�����̈�ł���B����ɂ��X�s�[�L���O�v�f�̂Ȃ������]���̃e�X�g�ƈႢ�R���s���[�^�X�N���[���̑O�Ŏ҂̉p��X�s�[�L���O�̗͂������悤�ɂȂ����B���A�����J���O���͂ǂ�ǂ�R���s���[�^�[�x�[�X�̃e�X�g���J�����Ă���A���E���w�Z�����̃e�X�g�����łɊJ������Ă���A�R���s���[�^�[���g�����C���^�[�l�b�g��}���`���f�B�A�A�𗘗p������w�̌��q�e�X�g�\�͎����̕]�����A�ŋ߂̌�w�e�X�g����̃g�����h�ƂȂ��Ă���B���̂悤�ɁA�V�����@��̐l�C�ɂ��A�R���s���[�^�[�x�[�X�̃I�[�����̌���e�X�g�Ɋ֘A������Ƃ��̗��_��]������K�v���������Ă����B
2. �I�[���������̌`��
����s�����ɂ����ẮA���̃X�s�[�L���O�͂𑪂�e�X�g�`���Ƃ��āASOPI( semi-direct testing )��OPI (direct
testing ) �������_������Ǝ������ꂽ�B
(1) SOPI�͐ݔ�������A�Z���Ԃɑ����̎҂ɑ��Ď��{�ł���B
(2) SOPI�̂悤�ȃe�X�g�ɂ���āA�����ǂ��ꂩ���ɏW�܂�K�v�����Ȃ��Ȃ�A�����悭�o�ϓI�Ɏ��{�ł���悤�ɂȂ����B
(3) SOPI��OPI���M���������������ł���Ƃ݂Ȃ���Ă��邪�AOPI�������ǂƎҊԂŖ{���ɋ߂��I�[�����R�~���j�P�[�V������ʂ��Ă��Ȃ�̐M������������Ƃ������_������B
�@Indirect testing
���҂̔��b�Ȃ��ł�paper-and-pencil�ɂ���Ĕ�����]���ł���Ƃ���Lado(1961)�̌���e�X�g�̏����̎���(Shohamy,1998�̌���discrete-point
era:���U�I�i�K����)�̃A�v���[�`�́A���͂�`�B�͏d���ȑO�̂��̂Ƃ��āA����x��Ƃ݂Ȃ���Ă���B
�@���e�X�g�쐬�҂����肽���Ǝv���Ă���҂̃X�L����Ó��ɐ��m�ɑ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A���̌��ʂɂ���Ď҂�������邱�Ƃ��ł��Ȃ����̃e�X�g�����͐M�����ɖ�肪����B
�ADirect testing ( Live testing )
��Hughes(2003)�u��X�����m�ɑ��肵�����X�L�����҂���������Ƃ��A�e�X�g�͒��ړI�łȂ���Ȃ�Ȃ��v
�����̗l���̃^�X�N�́A�e�X�g���{�҂��S�̂���X�L���̎�ނ�x���𐳊m�ɔ��f����e�X�g���ʂ������o�����Ƃ��ł��邽�ߐM�����������B�쐬�҂́A�҂��I�[�����̔\�͂���������e�X�g�ł���A�ł��邾���I�[�Z���e�B�b�N�ȃ^�X�N�荞�ނ��Ƃ��ł��A�҂͈�l�܂��͂���ȏ�̎������Ɗ�Ɗ�����킹���Ƃ���s���B
�@�@��Direct oral testing (face-to-face oral proficiency)�́A1950�N��Proficiency
Interview ( OPI )�e�X�g�Ƃ���ɔ����]�����A�A�����J���O���œ�������A��ɑ��̍��X�ł����l�ɍL���������悤�ɂȂ����B
�BSemi-direct testing
�����̕]���@�́A���Ă̓e�[�v��}�̂Ƃ��Ă������A���݂̓R���s���[�^�[��C���^�[�l�b�g�Ƃ������e�N�m���W�[����ɂ��Ă���A���݂̓R���p�N�g�f�B�X�N��}�̂Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ������Ă���B�҂͎��o�A���o�ɂ��l�X�ȃ}���`���f�B�A���瑦���Ƀ��b�Z�[�W�����A������C���v�b�g�Ɋ�Â������X�̃^�X�N���s���B�����Ă��̎������e�[�v�A�f�B�X�N�A�f�W�^���R���s���[�^�[�t�@�C����ɘ^������A�P��������l�ȏ�̕]���҂��]�����s���B
�@���n���x�̍����]�����Ƃ��ȒP�ɏW�߂��Ȃ��ꍇ�A���Ȃ�̔�p�������܂��ꍇ�Ɍ��������悭�A�R�X�g�̐ߖł�����@�ł���B�����ɒZ���Ԃő����̎҂ɓ���e�X�g���s���邽�߁A��̃e�X�g��p�ӂ��邾���Ńe�X�g�����{�ł���_�Ŕ�p�̑傫�Ȑߖ�ɂȂ�B
�@�����̃e�X�g�����ł͕]���҂ɂ��C���v�b�g�Ƀo���G�[�V�����͂Ȃ��A�҂͕W�������ꂽ�w������͂𑣂����b�Z�[�W����邱�Ƃ��ł��邽�߁A�M�p���ƌ������������B
�@��1980�N��A���V���g���c�b�ɂ��郏�V���g������@�ւ̕]���ҒB�ɂ��J������A���SOPI ( Simulated Oral Proficiency
Interview )�@�Ɩ��t����ꂽ(Stansfield & Kenyon,1988)�BSOPI���������ꂽ�����A���O���ŔF�m�x�̒Ⴂ����̏n�B�x��]������̂���ł������B
3. ��s�����ł̔���
��direct testing��semi-direct testing�̃e�X�g���ʂɊ�Â��Ó����̑���A�U���I�^�X�N�̍\��������̕��́A�قȂ�e�X�g�`���̃A�E�g�v�b�g����ۓI�ȉ�b�p�^�[���ւ̉e���A���ꂼ��̗��_������Â���҂̃t�B�[�h�o�b�N�̎��W�̔�r�������������s���Ă����B
���Q�̃e�X�g�̓��v�w�I�Ó����́A����0.89-0.95�ł���A�����̐��l������ꂽ�B�����҂͂��̓_�ł͂Q�̃e�X�g�͊T�˓����ł���ƔF�����Ă���B
���҂̃A�E�g�v�b�g��]���҂̐f�f����݂��e�X�g�\���E�^�X�N�f�U�C���E�k�b�̓����E���݂��Ƃ�E��b���x���܂ގƕ]���v���Z�X�̒�������A���̂Q�̃e�X�g�ɂ͔��ɑ傫�ȈႢ�����邱�Ƃ����m�ɂȂ����B
���҂���̃t�B�[�h�o�b�N�̌����ł͕��G�Ȍ��ʂ��o���B�قƂ�ǂ̕ł͐��́A������킹���e�X�g���D�ގ҂��D�܂ꂽ���Asemi-direct��܂��͂ǂ�����D�ނƂ����҂����Ȃ肢���B
�@
4. ��������
����s�����Ŏ����ꂽ�悤�ɁA�҂�direct testing���D�ނƌ����҂��l���Ă��邪�A�n�C�e�N�̋}���Ȕ��B�ɂ��semi-direct
testing�̎g�p�����܂�A����TOEFL iBT�����ڂ���Ă���B���̂悤�ȏ���A�e�X�g�J���҂͗l�X�Ȑ��Ɏ����X����ׂ��ł���
�����`�ł̃R���s���[�^�x�[�X�I�[�����e�X�g�̔����ƂQ�̃e�X�g�̊��z�͒m���Ă��Ȃ��B����ăe�X�g�����{����K�v�����o�Ă����B
���q�p�P�Fdirect��semi-direct testing�@�ł͂ǂ��炪�҂Ɏ�����邩�B
�@
�q�p�Q�F���̃e�X�g��I���R�͉����B
�@�@�q�p�R�F�Q�������҂́A��I�Ȕ����Ɋ�Â��ĂQ�̃e�X�g���ǂ̂悤�ɔF�����Ă���̂��B
��affective effect(��I����)�͎҂��e�X�g���Ă��鎞�̊���̔����ƒ�`���Ă���B
�����̂悤�Ȍ��ʂ͎�ɁA�e�X�g�`���Ɋւ��v���ɂ���Ĉ����N�������B
��Krashen(1985)Affective Filter Hypothesis�F��t�B���^�[�̑��݂⏜���́A���܂��͊O����w�K�҂ɒ��ډe����^���Ă���
����w�e�X�g�ɂ����ď�t�B���^�[���쓮���A�҂̊���I�������e�X�g���ʂɉe�����y�ڂ��Ƃ���A�قȂ�`���̃I�[�����e�X�g�͎҂ɂǂ̂悤�Ȋ�����������N�����̂��낤���B
5. ���@
�팱�҂Ǝ菇
��Hon Kong Polytechnic University 17�̊w������243�l�̂S�N���̃{�����e�B�A
�e�X�g��ɃA���P�[�g�����{���Q�̃e�X�g�̔����Ɗ��z�ɂ��Đq�˂��B�ґS��%�ɂ�����186���������B
��r�����Ɏg�p�����e�X�g
��direct testing�E�E�EIELTS(International English Language Testing System)Speaking
subtest
�@British Council, IDP:IELTS�I�[�X�g�����A, Cambridge ESOL���J���B11�`14����
�������Ǝ҂ɂ��P�P�̃C���^�r���[�`���B�R�Z�N�V�������琬��B
�Z�N�V�����P�@���������q�˂��悭�m���Ă��鐫���ɂ��āA�I��������I��
�Z�N�V�����Q�@�^����ꂽ�g�s�b�N�ɂ��ăv���[���e�[�V�������s������A1�`2��̎���ɓ�����
�Z�N�V����3�@�Z�N�V�����Q�̃g�s�b�N�Ɋ֘A�����������Ǝ҂Ƃ̃f�B�X�J�b�V�����@�@
��semi-direct testing�E�E�EGLSPA(Gracuating Students�f Language Proficiency
Assesment-English)
Hon Kong Polytechnic University ��the GSLPA Testing Team���J���B 40����
Task 1 ���W�I�̃C���^�r���[����̏������|�[�g���v��
Task2�@�d���̖ʐڂ̈�A�̎���ɑ��铚��
Task3�@�r�W�l�X��c�̏��ނ���̏��̓ǂݎ��ƃv���[��
Task4�@�d���Ɋւ���d�b���b�Z�[�W�̐�������
Task5���`�����߂ĖK�ꂽ�O���l�ɍ��`�̐����ɂ��Ă̏���^����
6. �A���P�[�g
���A���P�[�g�̓I�����C���ƃn�[�h�R�s�[�̗������҂ɑ����A�Q�̃e�X�g�ɂ��Ď҂̖����I�Ȋ��z�����f����B
���e�X�g��r�̊ϓ_���@���e�֘A���A�e�X�g�f�U�C���B�e�X�g�`���C�e�X�g�̗L�����D�҂̍D��
���A���P�[�g�̑Ó�����Expert Panel�ɂ���ĕۏႳ�ꂽ�B�A���t�@�Ó���0.75.
���A���P�[�g�̗\���������A�Q���҂ɂƂ��Ă��ׂĂ̍��ڂ����A�Ӗ��ɂ����ēK���ƕۏႷ�邽�߂ɁA�����x���̊w�͂̊w��30�l�ɑ��čs�����B
���S�̂̎������コ���邽�߂ɁA�Q��ڂ̗\�������ł͍��ڂ̎��I���͂��s���AA-5 point Likert scale��p�����Q�̍��ڂ��I�ꂽ�B
���A���P�[�g�L�����͔��Έӌ��̋L�����l�����ď\���ȃX�y�[�X��������B
�@
7. ����
�����͂̓e�X�g�`���̔�r�ɏœ_�āAstrongly agree, agree, not sure, disagree, strongly
disagree�̂T�i�K�̃J�e�S���[�ł̉����߁A�҂��Q�̃e�X�g�̂ǂ�����x������Ȃ�Η����x�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����B
��73.1%��IELTS�̕���49.5%�ɂ���Ďx������Ă���GSLPA���������ɃI�[�����̗͂𑪒�ł���Ǝx�������B
��a paired-samples t test�̒l�Ft= 5.377, two-tailed
Wilcoxon Signed Rank Test�̒l�FZ=-5.066, p= .000, two-tailed
���̒����ł̂Q�̃A���P�[�g���ڂɑ���Q���҂̉ɂ͗L�ӂȍ����������B
�@�@��New categories
(a) In
favor of the testing mode of IELTS ( direct testing)
(b) In
favor of the testing mode of GSLPA ( semi-direct testing)
(c)
Positive to both testing modes
(d)
Negative to both testing modes
(e) No
opinion about either testing mode
����186�l��76�l(40.9%)�͗����̃e�X�g���x���B31�l(16.7%)��������s�x���B
8. �f�B�X�J�b�V����
������(57.6%)�̎҂��e�X�g�`���ɕs�x���ł��������A�c��̎҂̂قƂ�ǂ��Asemi-direct testing����direct
testing���D�B���̌��ʂ͑����̌����҂炪�֗^���w���|�I�����̎҂�semi-direct testing����direct testing���D�ނ��낤�x�ƌ��_�Â������ʂ𗠕t������̂ƂȂ����ƒ��������f�[�^���瓾��ꂽ���v�I���ʂɊ�Â��Č�����B
�����Ȃ�̊����̎҂��e�X�g�`���ɑ��ē��ʂ̍D�݂��Ȃ����Ƃ�����s�����͍��܂łɂȂ������B
������̒������ʂ́A�����̎҂�direct���semi-direct���D�ނƂ���Brown�fs(1987)�̔�����ے肷����̂ƂȂ���
���҂̍D�݂́A�e�X�g�����̂�҂̕����E�`���E���Ȃǂ̉e���ɂ����̂�������Ȃ��̂ŁA�e�X�g�`�����҂Ɏ���₷���Ƃ����_����̂��_�������o�����ƂɐT�d�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�����̒����̉҂̑����������̃e�X�g�`�������ꂽ���ƂɁA�e�X�g�f�U�C���҂͈��g���Ă���B���̌������ʂɂ����semi-direct testing�̂���Ȃ锭�B��������A�V�����e�X�g�̊J�����Ɍ��ݓI�ȗv�����t������邾�낤�B
�@
9. �e�X�g�`���ƃe�X�g�̎��{
���e�X�g�`���ɂ���ď�v���͎҂ɉe������������B�҂��������S�n�悢�Ɗ������e�X�g�ɂ����ĕ]�������Ƃ��A���̃e�X�g�Ŕ\�͂�����B���̂��Ƃ́A�����ŗ����ꂽ�؋����ďؖ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��Krashen(1985)�F�V��������̏K�����A�{��A�ْ�����A�S�z����Ȃǂ̊���N����ƃC���v�b�g�̃t�B���^�[�͂͂����B
�܂�A�����҂������ے�I�ȋC���ɉe������Ă���Ƃ���A��t�B���^�[�̓e�X�g�ŗ͂����邱�Ƃ�W���Ă��܂��B
10. ����̑Ó���
��semi-direct testing�ɂ͏\���ȑÓ����������Ă���BDirect testing�ƈႢ�l�H�I�v�f���e�X�g�Ɏ������܂�邩��ł��邪�A����Q�̃e�X�g���r����ۂɑ厖�ȗv���Ƃ��Ă��̑���_���l�������ׂ��ł���B
11. �I����
�I�[�����e�X�g�̔��W�ɂ����ăR���s���[�^�[�e�N�m���W�[�̏o���͉���I�ł��肩�K�v�ł��邪�A����̎������ʂ͎������ɍ��܂Ŗ������Ă����������v���o�����Ă����B���̋Z�p�v�V�͎������̐l�Ԃ̂��Ƃ���]���ɂ��Ă���B���i�K�ł͉����͓�����A�����K������e�X�g�̒��S���Ȃ��ۑ�ƂȂ�ɈႢ�Ȃ��B
�l�@
�E�A���P�[�g�̍��ڂ����Ă�ꍇ���̎��̌��v�I�ɍs�����ƂɁA�������͂̌������������܂����B
�E�X�s�[�L���O�̕]���̊��L�����ɂ��ẮA����g���Ċo����p��̎��Ƃ�����ɐ��i�����ƁA�������O�ł��S���������g�s�b�N�ł͂Ȃ����Ǝv���B�R���s���[�^�[���g�p����e�X�g�����A���ۂɎ������ƌ��������Ă����Ȃ��e�X�g���x������l�����������Ƃ���A�q�ׂ��Ă����Ӄt�B���^�[�Ƃ̊֘A�ɂ��Ď������R�~���j�P�[�V�����𑪒肷����悢�c�[���̊J�������Ȃ������Ǝv����B
�E����̎����͂ق�ESL���̍��`�ōs��ꂽ���Ƃ���AEFL���̓��{�ōs�����ꍇ�ǂ̂悤�Ȍ��ʂ��o�邩�����[���B
�y�[�W�g�b�v�֖߂�
Thi Cam Le, N., & Nation, P. (2011). A bilingual vocabulary size test
of English for Vietnamese learners. RELC journal, 42(1), 86-99. doi:10.1177/0033688210390264
(T. I)
Abstract
���{�_���ł́A�M�L�ɂ������e�I��b�T�C�Y�𑪒肷�邽�߂�Vocabulary Size Test�i�ȉ��AVST�j�̃x�g�i����Ɖp��̓�ł̊J���ƑÓ����ɂ��Ę_����B
���w�K�҂̍��v��b�T�C�Y��VST�̌��ʂ�100���|���ĎY�o���A�{�����̌��ʂ͈ȉ���3�_�Ō�b�T�C�Y�e�X�g�Ɋւ���m���Ɋ�^�����B
1. ���VST�͈ꌾ���VST�Ɠ����悤�ɏ�肭�@�\���A�قȂ�n�B�x�̊w�K�҂ٕ̕ʁE�p�x���x���ɔ����_���̒ቺ���m�F�ł����B
2. �S�p�x���x���̃e�X�g���ڂ������Ȃ���A�w�K�҂̌�b�T�C�Y���ߏ�ɒႭ���ς����Ă��܂��������������B���̔����́A�w�K�҂̌�b�̐�������̕p�x�ƍ����֘A����L���Ă���Ƃ��������̉���̌��E���������̂ł���B
3. ���VST�́A�w�K�҂ɂƂ��Ă���Փx���������Ԃ��v����ꌾ���VST�̑���ɗp���鎖�̂ł���K�ȑ�փe�X�g�Ƃ��ċ@�\�����B
Introduction
���w�K�҂̌�b�T�C�Y�́A����^�p�ɂƂ��ĕK�v�s���Ȍ���m���̏d�v�ȑ��ʂƍl�����Ă���A���̑���͒������j��L���Ă���B�����āA��b�T�C�Y�e�X�g�́A�傫�������Ĉȉ���4�_����d�v�ł���B
��1�_�ڂɁA��b�T�C�Y�e�X�g�̌��ʂ́A�w�K�҂ɓK�����p��w�K�v���O�����i��b�����łȂ����[�f�B���O�����j�����肷���ƂȂ�BHu & Nation (2000)��Paul Nation (2006)�̐�s�����ł́A�w���҂̃T�|�[�g�Ȃ��Ńe�L�X�g�̓��e�𗝉����邽�߂ɁA�w�K�҂̓e�L�X�g����98%�̌��m���Ă���K�v������Ƙ_�����Ă���iTable 1�Q�Ɓj�A���L���P��������Ă��Ȃ�����E�M�L�e�L�X�g�̉^�p�ɂ́A��8,000���[�h�E�t�@�~���[�̊l�����d�v�ł���B
���x�g�i�������̃x�g�i���lEFL�w�K�҂́AYear 3����12�N�ԉp����w�K���邪�A���w�Z���n�܂�Year 6�܂ł͉p��̊w�K�͕K�C�ł͂Ȃ��B�܂��A��������J�n�܂ł͊w�K�v���O�����⋳�ނ�Ministry of Education and Training�ɂ���Ē�߂��Ă��邪�A���̌�͊w�K�҂̕K�v���ɉ������p�ꋳ�炪�\�ł���B
�E���A��������J�n�܂ł̔��ɐ������ꂽ�J���L�������̒��ł��A�X�̊w�K�҂̌�b�𑣐i���邽�߂̏_��ȏ��u�i�P��J�[�h�C���[�f�B���O�̃e�L�X�g�̑I���C���ЁE�E�F�u�T�C�g�`���̕⏕���ނ̎g�p�j������Ă���B
��2�_�ڂɁA��b�T�C�Y�e�X�g�́AESL/EFL�w�K�҂ƕ��b�҂̌�b�̐����Ɋւ���䗦�������邽�߂̗ǂ��c�[���ł���B
��3�_�ڂɁA�w�K�҂��p��Ɋւ���X�L���i�Ⴆ�A��b�m���Ɩ��ڂƊ֘A����L���郊�[�f�B���O��C�e�B���O���j�ɖ�������Ă���ꍇ�ɁA��b�T�C�Y�e�X�g�͗L�v�Ȑf�f�̊�ƂȂ�B
��4�_�ڂɁA���q���͂Ɋ�Â�������n�B�x�ɉ������w�K�҂̕��ނ������ŁA��b�T�C�Y�e�X�g�͗L�v�Ȍ����c�[���ƂȂ�B
���{�����̖ړI�́A���ʓI�ȃx�g�i����Ɖp��̓��VST�̍쐬�y�ы@�\�̗L�������������ł���B�܂��A�k���ł̃e�X�g�����ʓI���ǂ����������Ē�������B
Measuring Vocabulary Size
���ꌾ���VST�y�єh���̓�ł́ABritish National Corpus (Nation & Webb, 2011)����J�����ꂽ��b�p�x���X�g�iword frequency lists�j����ɍ쐬����Ă���A��b�p�x���X�g��Bauer & Nation (1993)�ɂ����ꂽ��̍\�z��iword-building criteria�j����Ƀ��X�g���̊e��̃��[�h�t�@�~���[���܂�ł���B
�����[�h�t�@�~���[�́A���o����C���܌`�C���ڂȊ֘A����L����h���`�ō\������Ă���A���o����͎��R�`���i���P�ƂŌ�Ƃ��Đ����j�ŁA���̌��o����ɐڎ���t�^���鎖�ŋ��܌`�E�h���`�������B
�E���Ƃ���Access�Ƃ����P��́A���[�h�t�@�~���[�S�̂�Bauer & Nation (1993)��Level 6�̊����8�̒P��iAccess, Accessed, Accesses, Accessibility, Inaccessibility, Accessible, Accessing, Inaccessible�j��L���Ă���B
����e�I�m���̑���ɂ����āA�w�K�҂����Ɍ��o�����m���Ă��āA�p��̋��܁E�p�x�Ɛ��Y���̍����h���ڎ��̒m��������A���܌`��h���`�̈Ӗ��𐄑����鎖�͓���Ȃ��B
�˂���āA���[�h�t�@�~���[�Ɋ�Â��e�X�g�͎�e�I�m���̑���ɂ͓K���Ă���i�A���A���Y�I�m���̑���ɂ͓K���Ă��Ȃ��j�B
The Vocabulary Size Test
��VST (Nation & Beglar, 2007)�́AESL/EFL�w�K�҂̑����I�Ȍ�b�T�C�Y�̑����ړI�Ƃ��Đv����ABritish National Corpus�̃��[�h�t�@�~���[�̕p�x�ɂ�鐔�����Ɋ�Â���14�i�K��1000�ꃌ�x�����A�e10�P��i���v140�P��j�ō\������Ă���B
���e�X�g��4�̑I��������Ȃ�M�L�I�����ŁA�I�����ŗp�����Ă����̓e�X�g���ڂ̌�������p�x�ł���B�܂��A�e�e�X�g���ڂ̌�͓���̕������������ɔz�u�����B
���e�e�X�g���ڂ̌��100���[�h�t�@�~���[���\���Ă���̂ŁA�w�K�҂̓_����100�{����A�����I�Ȍ�b�T�C�Y���Z�o�����B
Validating the Test
��Belgar (2010)�́ARasch���f����p���Ĉꌾ���VST�̑Ó����̌����s���A�ȉ�7�_�̓����������B
1. �ꌾ���VST�́A���L���n�B�x�̊w�K�҂ɑ��ėp���鎖���ł���B
2. �ꌾ���VST�́A���肪�\���������q�𑪒肷��Ɠ����ɁA���̈��q�͑��肵�Ȃ��B
��Beglar�̌��ł́A�P��̑��ʁi�M�L�ɂ������e�I��b�m����\�����Ă����j�m�ɑ���ł��A����ȊO�̑��ʂ̓e�X�g�Ɋւ��錾��^�p�ɂقƂ�lje����^���Ȃ������B
3.�ꌾ���VST�́i��L2�̒ʂ�j�\���������ʂ��Y�o�ł��邾���łȂ��A�قȂ�n�B�x�̊w�K�҂�ٕʂł��A�e�X�g���ڂ̌�̕p�x�Ɋ֘A�������L����Փx��L���A�قȂ郌�x���̌�b�m���m�ɕ��ނł��鎖����A�����I�Ȍ�b�̐����𑪒肷�鎖���\�ł���B
4. �ꌾ���VST �́A���Ƃ��e�X�g�Ɋւ���v�����ω����Ă��A��ѐ��ƐM������L���錋�ʂ��Y�o���鎖���ł���BBeglar�̎����ł́A�e�X�g���̕ω��Ƃ��Ď҂̐��ʂɂ�錾��^�p140���ڂ̃e�X�g��70���ڂ̃e�X�g�C�قȂ�n�B�x�̊w�K�҂̔�r���s�������ʁARasch���f���ł̐M������.96�ł������B
5. �ꌾ���VST�ɂ����āA�_���t���Ɠ_���̉��߂͗e�Ղł���B
6. �ꌾ���VST�̃e�X�g���ڂ͖��Ăł���A�B������L���Ă��Ȃ��B
7. �ꌾ���VST�����ʓI�Ɏ��{���鎖���\�ł���A�i��L4�̌��ʂ���j�K������140���ڂ̃e�X�g�ł͂Ȃ�70���ڂ̃e�X�g�����{���Ă��ǂ��B
���܂Ƃ߂�ƁA�ꌾ���VST�́A���L���p�x���x�����J�o�[���A���Ӑ[���I�ꌟ���ꂽ�����̃e�X�g���ځi���̔����ł���肭�@�\���鎖���m�F�ρj�ō\���A�X�Ɍ�b�m���̒��̈�̑��ʂ𑪒�ł��鎖����A���ɗǂ��@�\�����B
���d�v�Ȃ̂́A�e�X�g�g�p�҂��ꌾ���VST�ɂ���đ��肳�����q�Ƒ��肳��Ȃ����q��c�����Ă��鎖�ł���B�ꌾ���VST�́A�M�L�ɂ������e�I��b�m���𑪒肷�����ŁA���X�j���O�̌�b�T�C�Y��X�s�[�L���O��C�e�B���O�ɂ������b�m���͑���ł��Ȃ��B
�˕M�L�ɂ������e�I��b�m���̓��[�f�B���O�ɕK�v�s���Ȍ�b�m���̑��ʂł͂��邪�A���[�f�B���O�̃X�L���̈�v�f�ł����Ȃ��̂ŁA�ꌾ���VST�ł̓��[�f�B���O�̃X�L���𑪒肷�鎖�͕s�\�ł���B
The Value of Bilingual Versions of the Test
���ꌾ���VST�ł́A�w�K�҂͕��G�ȕ��@�Ɋւ�����̒m���E�K�x�ȃ��[�f�B���O�̃X�L����L���Ă���K�v������B
�ˈ��Ƃ��āA�ꌾ���VST�ł́A�W�߂�O�u���哙��p���đI������������������B
�Emarsupial: It is a marsupial.
a. an animal with hard feet
b. a plant that grows for several years
c. a plant with flowers that turn to face the sun
d. an animal with a pocket for babies
�����z�I�ɂ́A��b�T�C�Y�e�X�g�͉\�Ȍ����b�m���݂̂ɏœ_�Ă�ׂ��ł���A���̎�̖������������̕��@���w�K�҂�L1��p���鎖�ł���B
�E3. marsupial: It is a marsupial.
a. loai ??ng v?t co chan r?t kh?e
b. cay lau nien
c. hoa h??ng d??ng
d. loai thu co tui
���܂�A���VST�́A�e�X�g�̌��ʂɉe�����y�ڂ����b�I�ȗv�f�����炵���A��萳�m�Ȍ�b�T�C�Y�e�X�g�ƌ��������ł��A����̂Ɂi���ɏn�B�x�̒Ⴂ�j�w�K�҂̓_�����͂��ɏ㏸���邾���łȂ��A���@�m����[�f�B���O�̃X�L������������b�m������萳�������f����B
�E�ꌾ���VST�y�ѓ��VST�Ɋւ��ẮA�ȉ��̃E�F�u�T�C�g�i http://www.victoria.ac.nz/lals/staff/paul-nation.aspx �j�ɂĎg�p�\�ł���B
The Development of the Bilingual Test
�����VST�̊J���ł́A�e�e�X�g���ڂɑ���4�̉p��̑I�������w�K�҂�L1�ɖ|��K�v�����邪�A�����ł͂Ȃ��A�I�����ɍ�����L1��p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�˒�����p���Ă��܂��ƁA�w�K�҂ɖ����̂���b�m���i�e�X�g���ڂɊւ����`�j�ł͂Ȃ��A�|��\�͂ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A��{�I�ɁAL1�őΏۂ̑I�����ɑΉ����铙���̌�͑��݂��Ȃ��B
�����VST�i���̏ꍇ�A�x�g�i����Ɖp��̓��VST�j�쐬�ɂ����āA�܂�L1�̕��b�ҁi�p��ƃx�g�i����̓�b�ҁj�ɂ���Ė|�ꂽ��A������l��L1�̕��b�҂ɍZ�����ꂽ�B�|��҂́A���ɉp��̃x�e���������ł���B
���Z���̌�A��l�̖|��҂͋��ɁA�|�����ڂ̐��m���C���Ă��C���R�������������B�܂��A�|��ɍۂ��āA�\�Ȍ����`�̖|������e�X�g���ڂ������\���悤�ȒP��̌�Ă͂߂�悤�Ɏ��݂��B
���e�X�g�̖ړI�Ɠ_���̉��߂Ɋւ�����������l�ɖ|��E�e�X�g�ɓY�t���ꂽ�B�X�ɁA�e�X�g�J�n�O�Ɋw�K�҂ւ̐������s�����B
Trialling the Bilingual Test
�����VST�́A�x�g�i������2�̑�w�ŁA�p���U�̃x�g�i���l3�N��62����ΏۂɎ��{�����B���A�e�X�g�J�n�O�Ƀe�X�g�̐����ƃe�X�g�Ɋւ��鎿�^�������s�����B
���w�K�ҒB�̓e�X�g���I����܂Ŗ]�ތ��莞�Ԃ��|���ėǂ��A�ŏ��̖|��҂������ē߂ăe�X�g�Ɋւ��鎿��ɉ����B
���e�X�g�̌��ʂ́A�܂��|���VST�̑Ó����������邽�߂ɕ��͂��ꂽ��A�ȉ���2�_���m�F���邽�߂ɗp����ꂽ�B
1. Does the test distinguish learners of different proficiency levels?
����b�m���͌���\�͂̏d�v�ȗv�f�ł��邽�߁AVST�ɂ����āA���n�B�x�̊w�K�҂͒�n�B�x�̊w�K�҂��������_�����l������B
��4�N�w�m�R�[�X��2�N��2�w���̃��[�f�B���O�C���C�e�B���O�C���X�j���O�|��C�|�_�̃e�X�g�̕��ϓ_�Ɋ�Â��A�w�K�҂͓�����3�̏n�B�x�̃O���[�v�i���E���E��j�ɕ��ނ��ꂽ�iTable 2�Q�Ɓj�B��b�T�C�Y���W�v���ꂽ���_�ŁA�w�K�҂�3�N�ł������B
�E���n�B�x�O���[�v21�l�i10�_��8�_�ȏ�j
�E���n�B�x�O���[�v21�l�i10�_��7�_�ȏ�8�_�����j
�E��n�B�x�O���[�v20�l�i10�_��5�_����6�_�̊ԁj
���ȏ�̓_���Ɋ�Â��n�B�x���ނɂ����āA�ގ������_���̏ꍇ�̓��[�f�B���O�̓_���ōŏI�I�ȏn�B�x�̕]�����s�����B
��Table 3�̒ʂ�A100�{�����e�O���[�v�̕��ϓ_�́A6060.00�i���n�B�x�j�C6509.52�i���n�B�x�j�C7385.71�i��n�B�x�j�ł������B
��2���7�i�K��VST�ɂ����āA���n�B�x�O���[�v�́A���n�B�x�E��n�B�x�̃O���[�v���������_�����l�����Ă����̂ŁA�{�e�X�g�͈قȂ�n�B�x�̊w�K�҂�ٕʂł��Ă���ƍl������B
���������A3�̃O���[�v�Ԃ̕W�����i���_���̃o�����j�͍��n�B�x�O���[�v�ōł��傫�������̂ŁA���l�̎�����n�B�x�O���[�v�ɂ�������\��������B3�O���[�v�Ԃ̍��ق����v�I�ɗD�ʂł��鎖�������邽�߁A�ꌳ�z�u�̕��U���͂��s�����iTable 4�Q�Ɓj�B
���̌��ʁA3�O���[�v�̍��ق́AVST�̑����I�ȓ_�� F (2, 61) = (3.081, p < .05)�E�ŏ���7�i�K��VST�̓_�� F (2, 61) = (3.220, p < .05)�Ō݂��ɗL�ӂł������B
��2��ڂ�VST�ŗL�Ӎ����o�Ȃ��������R�Ƃ��ẮA2��ڂ�VST ��7�i�K�̃��x�����S�w�K�҂̌�b�T�C�Y��啝�ɒ����Ă����\�������������B
��3�O���[�v�̍��ق��m�F���邽�߁A����e�X�g�����{�������A�����_�� (p < .05)�C1��ڂ�VST (p < .05)�C2��ڂ�VST (p = .052)�S�ĂŁA���n�B�x�O���[�v�ƒ�n�B�x�O���[�v�Ԃ̕��ϓ_�ŗL�Ӎ�������ꂽ����A���n�B�x�O���[�v�ƒ��n�B�x�O���[�v�Ԃ̕��ϓ_�ł͗L�Ӎ��͌����Ȃ������iTable 5�Q�Ɓj�B
����b�m���͊O����̏n�B�x�̒��S�I�v�f�̈�ł���A�{�e�X�g�̌��ʂ����̎咣���x��������̂ł������B�A���A��b�m���͏n�B�x���\�������v�f�Ȃ̂ŁA���ٕ̕ʌ��ʂ͊��S�ł͂Ȃ��_�ɂ����ӂ��K�v�ł���B
2. Do scores drop from one frequency level to the next?
��Read (1988)�̐�s�����ł��q�ׂ��Ă���ʂ�A�w�K�҂́i���p�x����悭���������邽�߁j��p�x��������p�x���m���Ă���\���������B �]���āA���VST����肭�@�\���Ă���A���l�̌��ʁi���p�x���x�����オ��ɘA��āA�_�����ቺ����j���������͂��ł���B
��Table 6�̒ʂ�A�p�x���x���ɔ����_���̒ቺ�͊T�ˈ�т��Ă���A1��ڂ�7�i�K�ł�荂���_���E 2��ڂ�7�i�K�ł��Ⴂ�_���ƂȂ����B
��Table 6�ɂ����镽�ϓ_���ŏ�����ő�܂ŕ��ׂ����̂�Table 7�ł���A�ő啽�ϓ_�̓��x��2 (8.69)�ƃ��x��1 (8.63)�ŁA���x��4 (6.63)�C���x�� 3 (5.92)�C���x��5 (5.06)�C���x��6 (5.03)�C���x��8 (4.56)�C���x��7 (3.85)�C���x��10 (3.76)�C���x��11 (3.48)�C���x��14 (3.13)�C���x��9 (2.76)�C���x��12 (2.68)�C���x��13 (2.42)�ƌ㑱�i�ቺ�j�����B
���p�x���x���Ɛ������̊Ԃɂ͑�܂��Ȋ֘A���������A�{�e�X�g����Ƃ��ď�肭�@�\���Ă��鎖�������ꂽ�B���A�p�x���x���ɔ����_���̒ቺ�����S�ɂ͈�т��Ȃ��������R�͎��߂ōl�@����B
Using the Test
Is it necessary to sit all fourteen levels of the test?
���w�K�҂��S14���x���̃e�X�g����K�v�����邩�ۂ��́A�����I��VST�̓_���Ŕ��f�����������ł���B�{�����ł́A�����I��VST�̓_���i�\�ȍō����_��14,000�_�j��p���āA���T�C�Y��4�̃O���[�v�Ɋw�K�҂ނ����B
��Table 8�̒ʂ�A�S�w�K�҂�2��ڂ�7�i�K�̕p�x���x���̃e�X�g���ڂɂ��i70���ڒ�3���ڂ���46���ڂ̕��Łj�������Ă��邽�߁A�S14�i�K�̕p�x���x���̎��K�v�ł��鎖�����������B
��140�̃e�X�g���ڂ���������ꍇ�́A1��ڂ̕p�x���x���݂̂Ńe�X�g���\������i7�̃��x���~�e10���ځ��v70���ځj�����A14�̃��x������5���ڂ����ڂ�I��Ńe�X�g���\����������ǂ��Ƃ���Ă���ABeglar (2010)�̎����ł͈ꌾ���VST�ł́A����70���ڂ̏k���ł�140���ڂ̊��S�łƓ����ɏ�肭�@�\����ƕ���Ă���B
���{�����ɂ����āA�S�w�K�ҁi��n�B�x�O���[�v���܂ށj��2��ڂ̕p�x���x���̍��ڂɂ������ł����E�p�x���x���ɔ����_���̒ቺ�����S�ɂ͈�т��Ȃ��������R�́A�ȉ���4�_���l������B
1. �w�K�҂̈Ӗ��̐���
�E�A���AVST�͑����I�Ȍ�b�T�C�Y�𑪒肷�邽�߂̕��Ȃ̂ŁA�����ɂ��_���͏C�������ׂ��ł͂Ȃ��B
2. �p�ꂩ��̎ؗp��y�ѓ��n��̉e��
�E�x�g�i����Ɖp��̓��VST�ł́A�x�g�i����ɂ�����p�ꂩ��̎ؗp�ꂪ�e���x���Ō���ꂽ�B
Level 1: 9. standard
Level 2: 9. microphone; 10. pro
Level 5: 7. miniature
Level 7: 1. olives; 10. yoghurt
Level 8: 5. eclipse
Level 11: 3. yoga
Level 12: 7. caffeine
Level 13: 3. rouble
�E�����̊O����͊w�K�҂̌�b�̏d�v�ȑ��ʂł���A�Ӗ��̓�������w�K�̕��ׂ̒Ⴓ�̔��f�ł�����̂ŁAVST�ňێ������ׂ��ł���B
�E�ؗp��̑��ɁA�w�K�҂��m���Ă��鑼�̊O����Ƃ̓��n��̉\�����l�������ׂ��ł���B�A���A���VST�ɂ����āA���n��̌�`��I�����ɗp���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3. British National Corpus�̑�\���̌��E
�E�e�X�g���ڂ̃����W�ƕp�x�̊�ƂȂ��Ă���British National Corpus�́A�x�g�i���lEFL�w�K�҂̕K�v���ƌo�����\���Ă���Ƃ͌������A�K�������x�g�i���lEFL�w�K�҂ɂƂ��Ă̕p�x���x����\���Ă���Ƃ͌����Ȃ��B
�ˎ�����̌�b�T�C�Y�e�X�g�̑���ɁA�p�x���x������Ƃ����b�T�C�Y�e�X�g���I�ꂽ�̂́A�K�ȑ�\����L���Ă��邽�߂ł���B
4. �s�K�ȃe�X�g����
�E�ɉ��炩�̉e����^����悤�ȕs�K�ȃe�X�g���ڂ����݂����\�������݂���B
�ˈꌾ���VST�́A�����������ڂ���菜�����߂ɉ��x�������d�˂��Ă���ABeglar (2010)�ł̓e�X�g���ڂ̓K��������Ă���B
�E���VST�Ɋւ��鏫���I�Ȍ����ł́A�O�ꂵ���e�X�g���ڂ̕��͂��s���A�K�v�ɉ��������������E�e�X�g�̐M�����̌����L�����ƍl������B
�������I�Ȍ����ł́A�����̊w�K�҂Ɂi�e�X�g��Ɂj�ʂ̖ʒk���s�Ȃ��āA�ǂ����Ē�p�x��ɐ����ł����������₷�鎖���L�v�ł���B�܂��A�ꌾ���VST�Ɠ��VST���i�팱�ғ��v���E�팱�Ҋԗv���Łj��r���āA��VST�̓_���Ɗw�K�҂̏n�B�x�̑����������ׂ��ł���B�X�ɁA70�̃e�X�g���ڂ̏k���ł��쐬���āA140�̃e�X�g���ڂ̊��S�łƓ������ʂ��Y�o�ł��邩�̊m�F���d�v�ł��낤�B
���x�g�i����Ɖp��̓��VST�͔��ɏ�肭�@�\���鎖�������ꂽ�̂ŁA�����I�Ȏ��p�����]�܂��B
Links
���{�����ŗp�����ꌾ���VST�́A�ȉ��̃E�F�u�T�C�g�ŗ��p�\�ł���B�܂��A�x�g�i����⑼�̌���ł̓��VST�́A��Ԗڂ̃E�F�u�T�C�g�ŗ��p���鎖���ł���B
�Ehttp://www.victoria.ac.nz/lals/staff/paul-nation.aspx
�Ehttp://jalt-publications.org/tlt/resources/2007/0707a.pdf
�Ehttp://www.lextutor.ca/
Comments
�{�_���́A11��2���ٕ̈������ꋳ��]���_�Ŕ��\�����ȉ��̘_���i�̌��ʋy�є����j�����p�����_���ł���B
Beglar, D. (2010). A Rasch-based validation of the Vocabulary Size Test. Language testing, 27(1), 101-118. doi:10.1177/0265532209340194
�܂��A���̈��p�����Ɋւ��ăR�����g���Ă����B���p����Belgar (2010)�ł́ARasch���f����p���āA���e�I���ʁi��\�����j�C�{���I���ʁC�\���I���ʁC��ʉ��\���C�������C���߉\����6�̊ϓ_����ꌾ���VST�̑Ó��������Ă���B
Belgar�̐�s�������T�ς����{�_����Validating the Test�̂܂Ƃ߁i2�_�ځE3�_�ڂ́������j�́A��s������ǂ��܂Ƃ߂Ă���ƌ�����B�������A1�_�ڂ́��Ŏ������X�̍��ڂ̕��͂ł́A�^��̗]�n�i�����̊g����߂̉\���j��1�_���݂���BBelgar�̐�s�����̔���3�_�ڂŒ��҂́u�����I�Ȍ�b�̐����𑪒肷�鎖���\�ł���ilearners�f vocabulary growth over time could be measured�j�v�ƒf�����Ă���B���̓_��Belgar��
�{�����ł͏œ_���̑��݁i���X�̋��͎҂̐��ݓI�\���T�O�̕ω����@�j�̑���ɓ��Ă��̂ŁA�����I��VST�����ł͒����Ԃł̓���̋��͎҂ɂ��̑��݂̕ω�������ׂ����ƍl������B�����āA�{�����́A�w�K�҂̒����Ԃɓn���b�w�K�̐i���̑���Ƃ����e�X�g�̖{���I���l�Ɍq���镨�ł���iIn this study . . . the focus was on interindividual measurement, that is, the way in which the latent construct varied over different persons. In future studies of the Vocabulary Size Test, intraindividual change should be investigated by measuring variation in person measures over time with the same persons. Indeed, the greatest value of the test will likely be in measuring learners�f progress in vocabulary learning over time�j (Belgar, 2010, p. 116)
�Ƃ������_�ɔ����Ă���A���ʂ��g����߂����\�����l������B
�@�܂��ABelgar�̐�s�����Ɋւ�����_����A���̔����Ɋ�Â����҂̈ꌾ���VST�Ɋւ���O��͊���̐Ǝ㐫��L�������B���ɁA�قȂ�n�B�x���x���ٕ̕ʂɊւ��āABelgar�̐�s�����ł͓��{�lEFL�w�K�҂̏n�B�x�ʕ��ނ���s�N���E���b�҂̃O���[�v���ٕʌ��ʂɑ��ĕ��̉e�����y�ڂ��Ă���\�����l����ꂽ�B�]���āA�n�B�x���x���ɉ������ٕʂɊւ���O��͒f��ł͂Ȃ��A�u�`�ƍl������v���x�̐������K��������Ȃ��B
�@���ɁA�{�_���̓��e�Ɋւ��āA5�_�R�����g���Ă����B1�_�ڂɁi����͖{�_���̌��ʂɒ��ڂ͊W�Ȃ���������Ȃ����j���҂̓x�g�i��������EFL����ɂ�����_��ɂ��ďq�ׂĂ���AMinistry of Education and Training�ɃJ���L���������w�肳��Ă��鍂������ȑO�̉p�ꋳ��ł��A�X�̊w�K�҂̕K�v���E��b���i�̂��߂̏_��ȏ��u�Ƃ��ĒP��J�[�h�C���[�f�B���O�̃e�L�X�g�̑I���C���ЁE�E�F�u�T�C�g�`���̕⏕���ނ̎g�p������Ă��鎖�������Ă���B�������A�N���X�ł̎��Ƃ̒��ŁA�����̌X�̊w�K�҂ɉ��������u���ǂ̒��x����Ă���̂��B�܂��A����ꂽ���Ǝ��Ԃ̒��ŁA���C���̊w�K���e�Ƃ̌��ˍ����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B��肭�J���L�������ɑg�ݍ��ގ��A�܂��Ă��ʓI�����Ƃ��ďq�ׂ鎖�͔��ɓ���ƍl����B
�@2�_�ڂɁA�{�����̏n�B�x�Ɋ�Â����ނł́A2�N��2�w���̃��[�f�B���O�C���C�e�B���O�C���X�j���O�|��C�|�_�̃e�X�g�̌��ʂ�p���Ă��邪�A�������ɂ͋��͎҂�3�N���ɂȂ��Ă���B���Ȃ����ς����Ă�4�����O��i�ꍇ�ɂ���Ă͔��N���j�̊��Ԃ��Ă���A��Ƃ����ߋ��̓_���Ƌ��͎҂̎������_�ł̒m���E�X�L���i���ɁA��b�T�C�Y�⒘�҂��q�ׂĂ���u�����v�Ɋւ���\�́j�ɘ����������Ă��Ȃ����ǂ������C�ɂȂ�_�ł���B�Ⴆ�A�]���C�㑺�C�}���C���V�i2011�j�ł́A�n�B�x�̕��ނ̎Q�l�ɂ���e�X�g�ƌ�b�T�C�Y���𑪒肷��e�X�g���E�Z���Ԃōs�Ȃ��Ă����͂��ł���i���j�B
3�_�ڂɁA�{������VST�ɂ����āu�w�K�ҒB�̓e�X�g���I����܂Ŗ]�ތ��莞�Ԃ��|���ėǂ��iThe learners were told to spend as much time on the test as they wished until they finished it�j�v�ƂȂ��Ă��邪�A�����I�Ȍ����ł́A���Ԑ�����݂��Ȃ��������ɂ��e�����i�Ⴆ�A���Ԑ�����݂��ē��l�̎菇�œ��VST�̎��{�Ɣ�r������Łj�������ׂ����ƍl����B���Ԑ�����݂��Ȃ��������ŁA�e�X�g���ڂ̈Ӗ��̐����𑣐i�����\�������\�z�����B
�@�l�_�ڂɁA�ꌾ���VST�ƈقȂ�_��������Ȃ����A�ؗp��⓯�n��A�Ӗ��̐��������i���w�K�҂̌�b�m���̏d�v�Ȉꑤ�ʂƂ��āA�����I�Ȍ�b�T�C�Y�Ɋ܂ށj�Ƃ���l������VST�̓_���ɉ��炩�̃o�C�A�X��^���Ă��Ȃ����̒������K�v���ƍl����B�Ӗ��̐����͈ꌾ���VST�ł��s���Ă���\�������邪�A�Ⴆ�Ζ{�_���ň��p���Ă���Belgar (2010)�̐�s�����ł́A�ؗp��̉e���͏����I�Ȍ����ł͍l�����ׂ��_�Ƃ��Ă���B�x�g�i����ɂ����Ă����L���p�x���x���Ɏؗp�ꂪ���U���Ă���ƕ���Ă������A�p�ꂩ��̎ؗp�ꂪ�������{��Ɖp��̓��VST�ł͍X�ɕ��U����\�����l�����A�����������Ƃ�����A���{�lEFL�w�K�҂̈ꌾ���VST�Ɠ��VST�̌��ʂ͑傫���قȂ邩������Ȃ��B
�@�Ō�ɁA�ꌾ���VST�ł�British National Corpus�̑�\���͊��S�ł͂Ȃ��Ƃ���Ă���̂ŁA���VST�Ɋւ��Ă͍X�ɂ��̌X���͋����Ǝv����B�܂��A�s�K�ȃe�X�g���ڂɊւ��Ă��AVST���܂ވꌾ��ł̌�b�T�C�Y�e�X�g�����ǂ��d�˂ė������j���l������ƁA�쐬���ꂽ����̓��VST�ɑ��݂���\���͍����B�]���āA���҂��q�ׂĂ���ʂ�A���̓�_�͍���̓��VST�ɂ��Ă̌����ʼn��ǂ���Ă����ׂ��d�v�ȓ_���ƍl����B
�����L�̎Q�l�����̒ʂ�A�]���C�㑺�C�}���C���V�i2011�j�̏ڍׂ́A�����_�ł͕����̐����w�ŊJ�Â��ꂽJACET�S�����ł̌������\�݂̂ŏq�ׂ��Ă���A4�̃e�X�g���S�Ă����������Ɩ������鎖�͂ł��Ȃ��B�������A���Ȃ��Ƃ��]���E�}����2���Ɋւ��ẮA�n�B�x�̕��ނ̎Q�l�ɂ���e�X�g�ƌ�b�T�C�Y���𑪒肷��e�X�g���E�Z���Ԃōs�Ȃ��Ă����ƋL�����Ă���B
�Q�l����
Beglar, D. (2010). A Rasch-based validation of the Vocabulary Size Test. Language testing, 27(1), 101-118. doi:10.1177/0265532209340194
�]�������C�㑺�r�F�C�}�����C���V����i2011�j�D�w�������I��b�e�X�g�̐V���Ȏ��݁x[PowerPoint Slides]
�y�[�W�g�b�v�֖߂�