




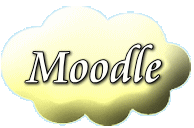



| �l���Љ�Ȋw�����ȁ@���m�ے��R�[�X �@�ٕ������ꋳ��]���_ (Testing in Second Language Education) |
�ٕ������ꋳ��]���_�Ŕ��\���ꂽ�������r���[�̃��W�����ł��B
Wigglesworth, G., & Elder, C. (2010). An investigation of the effectiveness
and validity of planning time in speaking test tasks. Language Assessment Quarterly,
7, 1?24.
�@�{�����̖ړI�́CIELTS1�̃X�s�[�L���O���W���[���ɂ����āC�v�����j���O�C�n�B�x�C�^�X�N�̂R�̕ϐ��Ԃ̊W���ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩�ׁC�v�����j���O�^�C���̏������P���C�Q���ƈ�����ꍇ�C�҂̃p�t�H�[�}���X�ɍ���������̂��ǂ������m���߂邱�Ƃł���B�܂��v�����j���O�̍ہC�ǂ̃X�g���e�W�[���ł����ʓI������肷�邱�Ƃ��{�����̂˂炢�ł���B�����ׂ邽�߂ɁC90����ΏۂƂ����e�X�g�����{���C�҂̃X�R�A�C�y�юY�o���ꂽ����͂����Ƃ���C�v�����j���O�^�C���̈Ⴂ�Ńp�t�H�[�}���X�ɗL�ӂȍ��͐��܂�Ȃ������B�A�����͌��ʂ���C�P�������̕����e�X�g�Ƃ��Ă̌������C�Ó����ɂȂ���Ƃ�������������ꂽ�B
BACKGROUND TO
THE RESEARCH (pp. 1?3)
�� �^�X�N���s���O�̃v�����j���O�́C�w�K�҂̔��b���e�C�y�юY�o����錾��̎��ɉe����^���C�w�K�҂�L2�m���ւ̃A�N�Z�X�𑣂��Ƃ����_�ŏd�v�Ȗ������ʂ����ƍl�����Ă���B
�� ����܂ł̐�s�����ł́C�v�����j���O���C�������C���G���̊ϓ_�ŁCL2�w�K�҂̃p�t�H�[�}���X���T�ˌ��コ���邱�Ƃ�������Ă���iEllis,
2005�j�B�A�����m���Ɋւ��ẮC�w�K�҂̌�肪�y���������ꕔ�Ȃ���Ă��邪�C�^�X�N�̓����̈Ⴂ�Ȃǂ̕ϐ����������Ƃ���C��v���������ɂ͎����Ă��Ȃ��B
�� �v�����j���O��SLA�̌����҂ɋ����S��������Ă��闝�R�Ƃ��āC�v�����j���O�������A�E�g�v�b�g�ipushed
output�j�𑣂��C����K������������ƍl�����Ă���_����������B
�� �������Ȃ���CSkehan�i1998�j���w�E����悤�ɁC�v�����j���O�^�C�����e�X�g�Ɋ܂߂邱�Ƃ��C�w�K�҂̌���\�͂𑪂��őÓ��Ȃ̂��Ƃ�����肪����B����Ɋւ��āCElder,
Iwashita, and McNamara�i2002�j�́C�A�J�f�~�b�N�Ȋ��ɂ�����X�s�[�`�ł́C���O�Ƀv�����j���O�����邱�Ƃ̕��������C�I�[�Z���e�B�V�e�B�[�̖ʂ����IELTS�̂悤�ȃe�X�g�ł̓v�����j���O�^�C�����܂߂�ׂ��C�Ǝ咣���Ă���B
�� ���������炭�C�v�����j���O���e�X�g�Ɋ܂߂�̂́C�e�҂ɑ��āC�s�����ł������y�������C���i�̃p�t�H�[�}���X���ő���ɔ����ł���@���^����Ƃ�������������ɏd�����邽�߂Ǝv����B
�� ���̂悤�ȗ��R����C�X�s�[�L���O�e�X�g�ɂ�����v�����j���O���x������Ă��邪�C�ǂ̒��x�̎��Ԃ��҂ɗ^����ׂ��Ȃ̂��C�܂��v�����j���O�ɂ��e�X�g���ʂւ̉e���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��C�Ƃ������ƂɊւ��ẮC���炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B
�� �������ƈ���āC�e�X�g���ɂ�����v�����j���O�̉e���Ɋւ��錤���͐������Ȃ��C���̌��ʂ���v���Ă��Ȃ��BWigglesworth�i1997�j�̌����ł́C�v�����j���O�ɂ��C�n�B�x�̍����҂ɕ��@�̐��m���̌��オ����ꂽ���C�e�X�g�X�R�A�ɍ��������Ȃ������B�܂�Tavakolian
and Skehan�i2005�j�́C�e�X�g�X�R�A�ւ̉e���͕��Ă��Ȃ����̂́C�҂��v�����j���O���s�����ƂŃ^�X�N���s���e�ՂɂȂ�C���m���C���G���C�����������シ�邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�����Xi�i2005�j�́C�O���t�`�ʃ^�X�N��p�����e�X�g�ŁC�v�����j���O���S�̓I�ȃX�R�A�̌���Ɋ�^�������Ƃ��������B
�� �������Ȃ���CWigglesworth�i2000�j��Iwashita,
McNamara, and Elder�i2001�j�̌����ł́C�v�����j���O�ɂ��҂̃p�t�H�[�}���X�̌���͂قƂ�nj����Ă��Ȃ��B
�� �ȏ�̂悤�ɁC�e�X�g���ɂ�����v�����j���O�̉e���́C�������̂��̂ƈႤ���ʂ�������Ă��邪�C���̗��R�Ƃ��āC�҂��e�X�g�ɕs���������C�v�����j���O�̗��_����肭�����ł��Ȃ��\�����l������B���̈Ӗ��ŁC�e�X�g���ɂ�����v�����j���O�̉e���ׂ邱�Ƃ͏d�v�ł���ƌ�����B
THE CURRENT
STUDY (pp. 3?5)
�� �{�����ł́C�n�B�x�ʂɕ�����ꂽ�҂ɑ��āC�������Ƃ̂P�P�̖ʐڌ`���ŃC���^�r���[�e�X�g�����{�����B���̍ہC�v�����j���O�^�C���̏����C�n�B�x�̈Ⴂ�ɂ��e���̑��C�҂̃v�����j���O�̃v���Z�X��C�v�����j���O�^�C���Ɋւ���F���Ɋւ��Ă��������s�����B
Context for the Research
�� �{�����ł́CIELTS�̃X�s�[�L���O���W���[����Part 2�ɂ�����v�����j���O�^�C���̉e���������BIELTS�̖{�����ł́C�^�X�N�O�ɂP�����^�����C��������邱�Ƃ�������Ă��邪�C�^�X�N�O�̃��n�[�T���Ƌ�ʂ��邽�߂ɁC���̃v�����j���O�s�ׂ��u�����I�v�����j���O�istrategic
planning�j�v�iEllis,
2005, pp. 3?5�j�ƌĂԂ��Ƃɂ���B�{�����̃��T�[�`�N�G�X�`�����iRQ�j�́C�ȉ��̂T�ł���B
RQ1. �����I�v�����j���O�^�C���̏����̈Ⴂ�ɂ��C�҂̃X�R�A�ɍ���������̂��B
RQ2. �����I�v�����j���O�^�C���̏����̈Ⴂ�ɂ��C�҂̔��b�̎��ɍ���������̂��B
RQ3. �҂́C�����I�v�����j���O�^�C���̌��ʂƑÓ����Ɋւ��āC�ǂ̂悤�ɔF�����Ă���̂��B
RQ4. �҂́C�����I�v�����j���O�^�C�����ǂ̂悤�Ɋ��p���Ă���̂��B
RQ5. �����I�v�����j���O�^�C���̊��p�ɂ����āC�ł����ʓI�ȃX�g���e�W�[�͉����B
Variables
�� �{�����̃f�U�C���ɂ�����ϐ��͈ȉ��̂R�ł���B
1. �n�B�x�F�҂��O���[�vA�i�������x���j�C�O���[�vB�i�㋉���x���j�̂Q�ɕ������B�O���[�v�����́C�҂�IELTS�̃X�R�A�������̓v���[�X�����g�p�̃e�X�g���ʂɊ�Â����C�Ó�����ێ����邽�߂ɁCNation�̃A�J�f�~�b�N��b���X�g3,000�`5,000�ꃌ�x���̌�b��p�����e�X�g���s�����B
2. �v�����j���O�^�C���̗ʁF�ia�j�v�����j���O�^�C���Ȃ��C�ib�j�P���C�ic�j�Q���̂R�̏�����p�����B
3. �^�X�N�FIELTS�̖{�����ɏ������R�̃^�X�N��p�����iAppendix A�Q�Ɓj�B
METHODOLOGY (pp.
5?9)
Participants
�� �A�J�f�~�b�N�p����w�Ԃ��Ƃ��ł���R�̋���@�ւ���C��������͂��ߗl�X�Ȍ������Ƃ���19����36�܂ł̊w�K��90���i�j����͂قڂP�F�P�j���Q���҂Ƃ��ďW�߂��B�Q���҂̂قƂ�ǂ́C����IELTS�������o��������C�w���C��w�@�ւ̐i�w�̂��߁C����IELTS���Ăю���\��ł���B
Study Design
�� ����C�҂́C���ꂼ��R�̃^�X�N���s�����B90���̎҂́C�n�B�x�ɉ�����45�����O���[�vA��B�ɔz�u����C�J�E���^�[�o�����X���Ƃ��Ċe�R�̃T�u�O���[�v�ii,
ii, iii�j�ɕ�����ꂽ�B�܂��C�v�����j���O�����̈Ⴂ�����邽�߂ɁC�e�T�u�O���[�v�͂���ɂT�l���ɕ�����ꂽ�iTable
1, 2�Q�Ɓj�B
Data Collection Procedures
�� �C���^�r���A�[�͌o���L�x��IELTS�̎������W���ŁC���O�ɌP�����{�����iAppendix B�Q�Ɓj�B
�� �҂��v�����j���O������ۂɂ́C���ƃy�����n����C��������邱�Ƃ������ꂽ�B�܂��C�^�X�N���s���Ă���Ԃ��������Q�Ƃ��邱�Ƃ��ł����B
�� �S�ẴC���^�r���[�͘^������C�e�^�X�N�I����ɁCIELTS�̕��͓I�]����Ɋ�Â��āC�҂̔��b�̗������C���e�̈�ѐ��C��b�C���@�C���������ꂼ��]�����ꂽ�B�A���C�������ɂƂ��ă^�X�N���̕]����������ƂȂǂ��킩�������߁C����̕��͂ł́C���̕]�����̗p���Ȃ������B
�� �҂́C�C���^�r���[�̌�C�A���P�[�g�ɉ����iAppendix C�Q�Ɓj�B�Ȃ��C�A���P�[�g���ڂɊ܂܂�Ă���v�����j���O�̃X�g���e�W�[�́CRutherford�i2001�j�œ��肳�ꂽ���̂Ɋ�Â��Ă���B
�� �A���P�[�g�I����C�O�q�̌�b�e�X�g���s�����B
�� ����Ɏ҂̈ꕔ�ɂ́C�O���[�v�C���^�r���[�ɎQ�����Ă��炢�C�v�����j���O�����̈Ⴂ�Ɋ�Â��^�X�N�̍���C�������C�܂��v�����j���O�^�C���̊��p�̎d���Ȃǂ�q�˂��B
Data Compilation and Analysis
�� 90�����̃C���^�r���[��^�������e�[�v�́C�S�ĕ����ɋN������C���͂̂��߂̃R�[�h�����Ȃ��ꂽ�B
�� �C���^�r���[�̂R�̃^�X�N�́CIETLS�̕��͓I�]����Ɋ�Â��C�Q���̌P�����ꂽ�]���҂ɂ���ĕ]�����s��ꂽ�B
�� �e�T�u�O���[�v���烉���_���ɑI�ꂽ�v36�����̔��b�Ɋւ��āC�k�b���͂��s�����B���͂̊ϓ_�́C�������C���m���C���G���̂R�_�ł���B
�� �������́C�����������łȂ����C���̓������|�[�Y�ifilled pauses�j�C�����|�[�Y�iunfilled pauses�j�C���������Ɋւ��āC���m���́C���Ȃ���AS���j�b�g2�Ɛ߂̊����Ɋւ��ĕ��͂������B�܂����G���́CAS���j�b�g���̏]���߁ibecause, before, after�Ȃǂ̒k�b�W�����܂��̂Ƃ���ȊO�̂��̂ɋ�ʁj�̊����Ɋւ��ĕ��͂��s�����B
�� �҂ւ̃A���P�[�g�́C�����l������C�v�����j���O�����̈Ⴂ��t����C�X�g���e�W�[�̈Ⴂ�imicroplanning,
macroplanning�j����2����ŁC�L�Ӎ������邩�ǂ��������肵���B�܂��C�X�g���e�W�[�ƃe�X�g�X�R�A�̑��W�����Z�o�����B
�� �O���[�v�C���^�r���[�Ɋւ��Ă��C�e�X�g���l�C���������ꂽ��ɃL�[���[�h���g���ăR�[�h�����ꂽ�B
RESULTS (pp. 9?18)
�� ��b�e�X�g�̌��ʁC�҂̂Q�̃O���[�v�̓��_�ɗL�Ӎ�������ꂽ�it
(87)
= 4.243, p < .0001�j�B�܂��C�Q���̕]���ҊԐM�����́C.51�`.73�ł������B�ȉ��CRQ�ɑ�����܂Ƃ߂�B
�� RQ1�̉F�e�X�g�S�̂̃X�R�A�iTable 3�Q�Ɓj�C�y�ѕ��͓I�]���iTable 4, 5�Q�Ɓj�ɑ��āCFacets��p�������́CF������s�����Ƃ���CA�CB�ǂ���̃O���[�v���C�^�X�N�C�v�����j���O�^�C�������̈Ⴂ�ɂ��L�ӂȉe���������Ȃ������B
�� RQ2�̉F�Q�̃O���[�v�̒k�b���͂̌��ʂ𗬒����C���m���C���G���̊ϓ_���琔�l�����ĕ��͂����Ƃ���C���ׂĂ̊ϓ_�ɂ����āC�^�X�N�C�v�����j���O�^�C�������̈Ⴂ�ɂ��L�ӂȍ��������Ȃ������B�A���CAS���j�b�g���̒k�b�W�����܂]���߂̊����isubordinate
clauses per AS unit�j�Ɋւ��āC�����̃O���[�v�łP�������̐��l���������ʂ������ꂽ�iTable
8, 9�Q�Ɓj�B
�� RQ3�̉F�A���P�[�g���ʂ��C�҂�89�p�[�Z���g���v�����j���O�^�C�����m��I�ɑ����Ă����B�O���[�v�C���^�r���[�̌��ʂ����l�ł���C�ނ�́C�����̍l�����܂Ƃ߂���C�X�g���X�̂�����e�X�g���ŗ����������߂ɂ́C�v�����j���O�^�C�����K�v�ł���Əq�ׂĂ���B
�� �܂��C�^�X�N�p�t�H�[�}���X���ǂ��Ȃ��������R�Ƃ��āC�������鎞�Ԃ�����Ȃ������Ƃ����ӌ������������B�A���C�v�����j���O�^�C���̑��ɁC�҂ɂƂ��Ẵg�s�b�N�̓�Փx�C�e���x���C�^�X�N�̏o���C�s�o���Ɋւ��傫�ȗv���ł��邱�Ƃ��C�A���P�[�g���ʂ̕��͂��疾�炩�ƂȂ����B���ɁC�^�X�N�p�t�H�[�}���X���ǂ������ꍇ�̗��R�Ƃ��āC62.9�p�[�Z���g�̎҂��g�s�b�N��v���Ƃ��Ă����C�t�Ƀv�����j���O�^�C���Ɠ������҂�23.5�p�[�Z���g�ł������B
�� RQ4�̉F�A���P�[�g�̕��͌��ʂ��C�҂��v�����j���O���ɗl�X�ȃX�g���e�W�[���g�p���Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����iTable
13�Q�Ɓj�B�܂��C�҂͂Q�������̎��ɁC��葽���̃X�g���e�W�[���g�p���Ă���C�P�������Ɣ�r���ėL�Ӎ�������ꂽ�it (88) = 2.575, p = .012�j�iFigure 1, 2�Q�Ɓj
�� RQ5�̉F�X�g���e�W�[�̎g�p���ƕ]���҂ɂ��S�̓I�C���͓I�X�R�A�̑��ւ́C��������L�ӂł͂Ȃ��������Cmacrostrategies�i�g�s�b�N�C���e�C�\���Ɋւ��X�g���e�W�[�j�Cmicrostrategies�i���@�C�\���C��b�Ȃnj���I�Ȃ��̂Ɋւ��X�g���e�W�[�j�̒��ŁC�ǂ̃X�g���e�W�[�������g�p���ꂽ���́CFigure
3�̃��X�g�̍��ڂƂ��ē���ł����B
�� �܂��C�v�����j���O�^�C�����P�������̏ꍇ�Cmacrostrategies�̕��������g�p���ꂽ���C�Q�������̏ꍇ�́C�t��microstrategies�̕��������g�p���ꂽ�B�A����2����̌��ʁCA, B�̂ǂ���̃O���[�v�ɂ����Ă��Q�̃X�g���e�W�[�̎g�p�p�x�ɗL�ӂȍ��͌����Ȃ������B
�� ����ɁCmacrostrategies����葽���g�p�����҂�microstrategies����葽���g�p�����҂̃p�t�H�[�}���X�̍���t����ŕ��͂����Ƃ���C�L�Ӎ��͌����Ȃ������B
DISCUSSION AND
CONCLUSION (pp. 18?19)
�� �{�����́CIwashita et al.�i2001�j�CWigglesworth�i2000�j���l�C�����I�v�����j���O�^�C���ɂ��҂̃p�t�H�[�}���X�̌���𗠕t���錋�ʂ����o���Ȃ������B
�� �A���C���b�̕��G���Ɋւ��ẮCA, B�����̃O���[�v�ɂ����āC�P�������̕����L�Ӎ��͂Ȃ����̂́C�������l���������B�]���āCIELTS�̃X�s�[�L���O���W���[��Part 2�̃v�����j���O�^�C���i�P���ԁj�́C��L�p��������ƌ��_�t������ł��낤�B
�� �܂��C�҂ւ̃A���P�[�g�C�O���[�v�C���^�r���[�ł́C�҂��v�����j���O�^�C�����m��I�ɑ����Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B�]���āC�X�s�[�L���O�e�X�g�Ƀv�����j���O�^�C����݂��邱�Ƃ́C���Ӗ��ł͂Ȃ��ƌ�����B�A�����̎��Ԃɂ��ẮC�P�������C�Q�������Ńp�t�H�[�}���X�̍��������Ȃ����߁C�P��������������K�v�͂Ȃ��ł��낤�B
�� �v�����j���O���̃X�g���e�W�[�̎g�p�Ɋւ��ẮC�҂��p�t�H�[�}���X�̌���ɂȂ��Ă���Ƃ������ʂ͌��o���Ȃ������B����ɂ��ẮC�e�X�g��̎���������̕C�y�уO���[�v�C���^�r���[�̃R�����g�ɂ��ƁC�����̎҂��������ɋN������s���̂��߁C�����v�����j���O����悢�̂��킩��Ȃ��ɂȂ��Ă������Ƃ��������ꂽ�B�Ȃ��C����̎Q���Ғ�������45�����C���O�Ƀv�����j���O�̎w�������o�������邱�Ƃ��A���P�[�g���ʂɎ�����Ă��邪�C���̂悤�Ȏw���̗L�����X�g���e�W�[�̎g�p�ɂǂ̂悤�ɉe�����邩�ׂ�K�v�����邩������Ȃ��B
�� �܂��v�����j���O�́C�҂̋L���ɍ��E�����ʂ�����C���b�̍ŏ��̂����������̌��ʂ͎������Ȃ��\��������B����ɁC�ɓx�̃v���b�V���[�̒��C�����̃p�t�H�[�}���X�����܂����j�^�����O�ł��Ȃ��\�����l������B
�� �҂��v�����j���O�������ƂƁC�]���҂̕]�����ڂƂ̃~�X�}�b�`����������������Ȃ��B�����C�҂͓��e�ʂ̃v�����j���O�ɂ��d�_��u���Ă��邪�C�]���҂͋t�Ɍ���`���ɂ��œ_�Ăĕ]�����Ă��������B�]���āC�k�b�̖���I���G���𑪂邽�߂̕��@���H�v����K�v�����邩������Ȃ��B
�� �X�g���e�W�[�Ɋւ��ẮC�v�����j���O�Ō��ʂ̌���ꂽ�Ҍl�����ڍׂɒ��ׂ�K�v������B�Ȃ����̍ۂɂ́C���������ꂽ�X�g���e�W�[�̕��ނ��s���C�҂�think-aloud�f�[�^�����K�v�����邩������Ȃ��B
���\�Ғ�
1. IELTS�ithe International English Language Testing System�j�́C�p���C�I�[�X�g�����A�C�j���[�W�[�����h�Ȃǂ̋���@�ցC��ƁC���{�@�ւŔF�肳��Ă���C�A�J�f�~�b�N�ƈ�ʂ̂Q�̌`���ŁC�S�Z�\���ׂĂ̗̈���O�`�X�̃X�R�A�ő���p��\�͑���e�X�g�ł���B���̒��ŃX�s�[�L���O�̃��W���[���́C�R�̃p�[�g�ō\������CPart
1�����ȏЉ�Ɗ֘A����i�S�`�T���j�CPart
2���J�[�h�ɏ����ꂽ�^�X�N�Ɋ�Â��V���[�g�X�s�[�`�Ɗ֘A����i�v�����j���O�^�C���P�����܂߂R�`�S���j�CPart
3��Part
2�Ɋ֘A�����g�s�b�N�Ɋ�Â��f�B�X�J�b�V�����i�S�`�T���j�ƂȂ�iUniversity
of Cambridge Examination Syndicate, 2007�j�B
2. Analysis of Speech Unit�̗���ŁC��ɘb�����t�͂���ۂɎg�p�����P�ʁBFoster,
Tonkyn, and Wigglesworth�i2000�j�̒�`�ɂ��ƁC��̃��j�b�g�́u�P��̔��b�҂��������Ɨ��߁C���߂ł���C�]���߂����Ƃ�����v�ip.
365�j�B�ގ������P�ʂ�T���j�b�g�iHunt, 1970�j�����邪�C�ȉ��̗�B�̂悤�ɁC���X�߂ł��������̂��ȗ����ꂽ���߂̏ꍇ��C������̌�ɏ㏸�C���~�̃C���g�l�[�V����������C0.5�b�ȏ�̃|�[�Y������ꍇ����̃��j�b�g�Ƃ��ċ��i�ȉ��̗�ł́C�c�̐������j�b�g�̐�ڂ������j�Ƃ����_���CT���j�b�g�ƈႤAS���j�b�g�̍ő�̓����ł���B
A: ��how long you
stay here��
B:
��three
month.�� �iFoster, Tonkyn,
& Wigglesworth, 2000, p. 366�j
���p����
Foster,
P., Tonkyn, A., & Wigglesworth, G. (2000). Measuring spoken language: A
unit for reasons. Applied Linguistics,
21, 354?375.
Hunt,
K. (1970). Syntactic maturity in school children and adults. Monograph of the Society for Research into
Child Development, 35, 1?67.
University
of Cambridge Examination Syndicate (2007). IELTS
handbook 2007. Retrieved from http://www.ielts.org/pdf/IELTS_Handbook_2007.pdf
���R�����g��
�{�����́C�v�����j���O�^�C�����X�s�[�L���O�e�X�g�Ɋ܂߂�ꍇ�̉e���C�y�т��̑Ó����ׂ����̂ł���C������グ��IELTS�Ɍ��炸�C�����̉p��\�͑���e�X�g���������ŁC���ɋ����[�����e�ł���B���ɁC�X�R�A�ւ̉e�������łȂ��C�҂̔��b�̎��C�e�X�g�ɑ��鑨�����ȂǁC�����I�ɒ��������Ă���_�́C�����f�U�C���Ƃ��čH�v���ꂽ���̂ƌ�����B
�@�A���C�����̌��ʂƂ��āC�v�����j���O�^�C���̉e�����҂̃X�R�A�C�y�є��b�̎��ɂقƂ�nj����Ȃ������_�́C���̌������l�@����K�v������B�_���̒��҂����y���Ă������C���̎�Ȍ����Ƃ��čl������̂́C�]����̖��ł��낤�B�{�����ɂ�����҂̃p�t�H�[�}���X�̕]���Ɋւ��ẮC����������`���̖ʂɏœ_�����Ă�ꂽ���C�҂��v�����j���O�̍ۂɒ��ӂ��Ă������e�ʂɊւ��ẮC�ǂ��炩�Ƃ����Əd�_���u����Ă��Ȃ��B����̔��\��̃f�B�X�J�b�V�����ł��w�E���Ȃ��ꂽ���C���e�ʂ�]�������������������荞�܂�Ă�����C��������ʂɂȂ����\��������B
�܂��C�҂̔��b�̕��͂Ɋւ��Ă��C�������C���m���C���G���̎w�W������I���̂őÓ��Ȃ̂��Ƃ�����������B�Ⴆ�Ε��G���̎w�W�Ƃ��āCAS���j�b�g���̏]���߂̊������g�p����Ă��邪�C����͓���I���G���݂̂����������̂ł��邽�߁C���͌��ʂ̑Ó��������߂邽�߂ɂ́C��b�̕��G���̎w�W�ł���M���[�w���iGuiraud
index�j�ȂǁC�������������̎w�W���g�p���Ă݂�K�v�����邩������Ȃ��B�A���CAS���j�b�g���̒k�b�W�����܂]���߂̊������P�������̍ۂɐ��l���������Ƃ́C�{�����Œ��ڂɒl����_�ł���C�҂��P�������̃v�����j���O�Ɋ���Ă������Ƃ��\�z�����B���̓_���f�B�X�J�b�V�����Ŏw�E���Ȃ��ꂽ���C�҂ւ̃v�����j���O�w���̗L�������b�ɂǂ̂悤�ɉe������̂��Ƃ������Ƃ́C���ɋ����[���g�s�b�N�ƌ�����B
�]���č���́C�҂ւ̎w���̌��ʂ��������Ȃ���C���o�����X�̎�ꂽ�]����C���͍��ڂŁC�X�s�[�L���O�e�X�g���̃v�����j���O������ɒ�������K�v�����낤�B
�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�
![]() 2011�N4��27���iA.H.)
2011�N4��27���iA.H.)
Crossley, S. A., Salsbury, T., McNamara, D. S., & Jarvis, S. (in press). Predicting lexical proficiency in language learner texts using computational indices. Language Testing.
�� �͍\���͒S���҂����҂���
1. Introduction
�� ��b�n�B�x (lexical
proficiency) �̖��m�Ȓ�`�������ɂ��ւ�炸�AL2�����ł� (a) ��b�m���̍L��, (b) ��b�m���̐[��, (c) ��b���ڂւ̃A�N�Z�X����b�n�B�x�Ƃ��Ĉ����Ă���
(Meara, 2005)
�E�L��: �ǂꂾ�������̒P���m���Ă��邩
�E�[��: 1�̌���ǂꂾ���悭�m���Ă��邩
�E�A�N�Z�X: �ǂꂾ�������P������� / �����ł��邩 (�Ӗ����v���o���邩)
�� L2�w�K�҂̌�b�n�B�x�̒�`�͈ȉ���2�_����K�v�Ƃ����
(1) ��b���x���̌��̓R�~���j�P�[�V�����̖W���ƂȂ��Ȍ����ł��� (Ellis, 1995)
(2) ��b�n�B�x�͊w�� (�w��) �Ƌ������֊W�ɂ��� (Daller et al., 2003)
�� �{�����́A��b�m���̓��� (�L���E�[���E��b���ڂւ̃A�N�Z�X) �Ɋ�Â���b�n�B�x�̕]����\���ł��郂�f���ɂ��Č�����
2. Measures of lexical
proficiency
(1)
Lexical diversity
�� ��b�̑��l���ɂ��Ă�type-token ratio
(TTR: �قȂ�ꐔ�����ꐔ) ���p�����Ă���
�� ���̑���Corrected TTR
(Carrol, 1964), Log TTR (Herdan, 1960), D (Malvern et al., 2004), Advanced TTR
(Daller et al., 2003), Guiraud Advanced (Daller et al., 2003), Measure of
Textual Lexical Diversity (McCarthy & Jarvis, in press) ������
�� �w�K�҂����l�Ȍ�b���g����̂ł���A���̊w�K�҂̏n�B�x�͍����A��b�����L�x�ł��邱�Ƃ�������B�������A���l�Ȍ���g����Ƃ����Ă��ȒP�Ȍ�݂̂����g���Ȃ��̂ł���Ώn�B�x�𐳊m�ɑ���ł���Ƃ͌����Ȃ�
(Vermeer, 2000; Daller et al., 2003)
(2)
Lexical frequency
�� ��p�x����g����w�K�҂̏n�B�x�͍����Ƃ��������Ɋ�Â��w�W
(Meara & Bell, 2001)
�� �w�K�ߒ��ŒP��ɐG��邽�тɌ`���|�Ӗ��̌q���肪�����Ȃ邽�߁A���p�x��قǏ������x�������Ȃ�B�t�ɒ�p�x��̌`���|�Ӗ��̏K���͓�����߁A��b�n�B�x�̎w�W�ƂȂ肤��
�� �������A���w�҂̃X�s�[�L���O�ŎY�o���ꂽ��b���ώ@����ƁA�g�p�p�x�̒Ⴂ�P��ł���ې��̍������̂ł���Εp�ɂɎY�o����邱�Ƃ����������B���������Č�b�p�x�̎w�W���ڂ���������K�v������
(3)
Word meaningfulness
�� ����ꂩ��A�z�ł���ꂪ�����قǁA���̌�͗L�Ӗ�
(meaningfulness) �ƂȂ�
(e.g., food, music vs. acumen, cowl)
�� ��A�z�ƌ�b�l���̊W�ɂ��āAZaewva
(2007) �ł͏n�B�x�̍����w�K�҂قǂ�葽���̘A�z����Y�o�ł��邱�Ƃ��������Ă���
�� �����Salsbury et al.
(in press) �ł́A�n�B�x�������قǁA�w�K�҂͗L�Ӗ��Ȍ���g�p���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����������B����͘A�z��̏��Ȃ��������g���o�����炾�ƍl������
(4)
Word concreteness
�� ��ی�͒��ی�ɔ�ׁA���R�[���E�ĔF�E��b�����f�ۑ�E�����Ȃǂ��e�ՂɂȂ�
�� ���������Ċw�K�҂̏n�B�x���Ⴍ�Ă���ی�͊l������₷��
(5)
Word familiarity
�� ��̐e���x�͕p�x�Ƃ��W���Ă��邪
(Schmitt & Meara, 1997)�A�e���x�̍�����̓e�L�X�g�̒��ł��ڗ��ꂾ�Ƃ���Ă��� (e.g., the vs.
dog)
�� �e���x�������Ɣ��f������́A�Ӗ��̃��R�[����A�z�̑�������ƂȂ�
(6)
Word Imagability
�� �S�I�C���[�W�������N������́A�f�����ȒP�ɈӖ����v���o�����Ƃ��o����
�� ���������č����S����������͊w�K�҂̐S�������̒��S�����ɂȂ��Ă���
(7)
Hypernymy
�� ��ۊW�Ƃ͏�ʌ� (e.g., vehicle:
���鉺�ʌ�̏�ʂɂ����ň�ʓI�ȑ��̂ɂ�����) �Ɖ��ʌ� (e.g., bus,
taxi: ������I�Ȍ�) �Ƃ̊K�w�I�W�̂��Ƃ��w��
�� ���n�B�����w�K�҂̕�����ƌ�̕�ۊW���l�����Ă���
(e.g., Anglin, 1993; Snow, 1990)
(8)
Polysemy
�� 1�ȏ�̊֘A����Ӗ�������𑽋`��Ƃ����B���`��ɂ͊j�ƂȂ�T�O������A���ꂼ��̈Ӗ����d�Ȃ��Ă���
�� ���`��̂��ꂼ��̈Ӗ��Ɋւ���m���͊w�K�҂̏n�B�x���オ��ɂ�Ċl�������
(Schmitt, 1998)�BCrossley
et al. (2010b) �ł́A�w�K�҂̏n�B�x���オ��Ƒ��`��̕����̈Ӗ����Y�o�����悤�ɂȂ邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���
�� �ȏ�̐�s�����ɂ��A��b�m���̍L���E�[���E�Ӗ��ւ̃A�N�Z�X�͌�b���B�x�Ən�B�x�Ɋւ���d�v�Ȏw�W�ł��邱�Ƃ�������
�� �܂��A��ۊW���̗L�Ӗ����͌�b�l�b�g���[�N�̍\�z�Ɋւ��v���ł���A��ې��E�S�����E�e���x�͐S������w�I�Ȍ�̓����𑪒肷��w�W�ƂȂ�
3. Method
���{�����̖ړI��
�� �P�����ꂽ�]���҂ɂ���b�n�B�x�̕]����\���ł��郂�f���̍\�z���A��b�m���̍L���E�[���E�A�N�Z�X�Ƃ����v�����l�����čs��
�� �]���҂ɂ���b�n�B�x�̕]���́ATOEFL��writing section�̎��I���͂�ʂ��čs����
��Corpus
collection��
�E�p���w�̒Z���v���O�����ɎQ�����Ă���L2�w�K��10�� (18-27��) ��Ώۂɂ���
�ETOEFL�ɂ��n�B�x���㒆���Q�ɃO���[�v��������
�E���ꂼ��̏n�B�x�Q����60���p�앶�̃T���v�� (�e�[�}��^�����ɖ���������������) �����W�����B���b�҂Ɣ�r���邽�߁AStream
of Consciousness Data Set������b�҂��������p�앶��60��ޏW�߂� (�S����240 sample)
��Survey
instrument��
�E���ꂼ��̉p�앶��American
Council on the Teaching of Foreign Languages�f proficiency guideline
�@��American
College Testing�ACollege
Board�Ɋ�Â��S�̓I�ȕ]�����s����
�E�e�p�앶�̌�b�n�B�x�������̎w�W�����ƂɎZ�o���Ă���
�E3�l�̉p����b�҂�240�̉p�앶���̓_���A���ꂼ��̌�b�n�B�x��5
point scale�ō̓_���� (�]���ҊԐM����r =
.921)
��Variable
selection��
�E��s�����ŋ�������b�n�B�x�Ɋւ���v����Coh-Metrix�ɂ���ĕ��͂���
|
��b�n�B�x |
Coh-Metrix�Ō�����v�� |
������@ |
|
��b�m���̍L�� |
(1)
��b�̑��l�� |
MTLD |
|
|
(2)
��b�̑��l�� |
D |
|
��b�m���̐[�� |
(3)
��ۊW |
Hypernymy |
|
|
(4)
���`�� |
Polysemy |
|
|
(5)
�Ӗ��I�֘A�� |
Latent
Semantic Analysis |
|
|
(6)
�p�x |
CELEX
content word frequency |
|
��b�m���ւ̃A�N�Z�X |
(7)
��ې� |
MRC
database |
|
|
(8)
�e���x |
MRC
database |
|
|
(9)
�S���� |
MRC
database |
|
|
(10)
�L�Ӗ��� |
MRC
database |
Note. �����ɉ����ĒP��̒��� (���ߐ�) ���v���ɉ�����
�ECoh-Metrix�Ɋ܂܂��ǂ̗v�������ʂ�L�ӂɗ\������̂����肷�邽�߁A240����p�앶�̃f�[�^��Training set
(180) ��Test
set (80) �ɕ������B
�ETraining
set�Ō�b�n�B�x��L�ӂɐ�������v������肵�ATest
set�Ń��f���̑Ó�����������
4. Results
�� ���͂ł͕]���҂��p�앶�̎�����w�K�҂̌�b�n�B�x��]���������̂ƁA10�̗v���Ƃ̑��ւ�������
�� ���`��ƒP��̒����̗v���ȊO�ŁA�]���҂̕]���Ƃ̗L�ӂȑ��ւ�����ꂽ (see
Table 2)
�� �܂��A��ې��ƕ]���҂̕]���̑��ւ��Ⴉ�������߁A�ȍ~�̕��͂ł� (a) ���`�� (b) �P��̒��� (c) ��ې��̗v�������O����
��Training
set��
�� 7�̗v�����]���҂̕]�����ǂꂾ�������ł���̂��𖾂炩�ɂ��邽�ߏd��A���͂��s�������ʁA(a) D
(��b�̑��l��),
(b) ��ۊW, (c)
�p�x
(CELEX) �̗v�����L�ӂɌ��ʂ�\���ł��Ă��� (see
Tables 3 and 4)
��Test
set��
�� Training set�ŎZ�o������A�������Ƃ�Test set�̌��ʂ�\�������B���̌��ʂƎ��ۂ̓��_�Ƃ̑��ւ��Z�o�������ʁAr2 =
.421�ŗL�ӂɌ��ʂ�\���ł��邱�Ƃ���������
��Total
set��
�� �Ō��240�̉p�앶����]�����ꂽ��b�n�B�x�̓��_�ƃ��f���ɂ��\�����ꂽ���ʂƂ̑��ւ͂����B
�� ���ʁATraining set��Test set���ʂɌ����ꍇ�Ɠ����x�̐�����������ꂽ (r2 = .444)
5. Discussion & Conclusion
��
Coh-Metrix�ŕ��͂Ɋ܂߂�3�̗v�� (��b�̑��l���E��ۊW�E�p�x) ���]���҂ɂ���b�n�B�x�]����44%��\�����邱�Ƃ��ł���
�� �����̗v���͌�b�m���̍L���E�[���Ɋւ����̂ł���A��b�̈Ӗ��ւ̃A�N�Z�X�Ɋւ���\�͍͂���̎����œ���ꂽ���f���ɓ��Ă͂܂�Ȃ����Ƃ���������
Predicted
lexical proficiency = 4.701 + (.022 �~ lexical diversity: D value)
+ (-1.130 �~ average of word hypernymy value)
+ (-.736 �~ content word
frequency value)
�� ��L�̉�A���ɂ��ꂼ��̒l������Ɗw�K�҂̌�b�n�B�x��5�i�K�ŕ]�������
�� �������A����l�X�ȗv�����܂߂Ă��l�Ԃ̕]���ɋ߂����f�����Ă��ׂ��ł���
���R�����g��
�@�]���̌�b�m������@
(e.g., ��b�T�C�Y�e�X�g�EWAT)
�ł͌�b�m���̍L���E�[���E�A�N�Z�X�ɂ��Čʂ̔\�͂����]�����邱�Ƃ����ł��Ȃ������B�������{�����ł́A��b�n�B�x�Ɋւ��l�X�ȗv����Coh-Metrix�Ōv�Z���A���C�e�B���O�̃p�t�H�[�}���X����w�K�҂̌�b�n�B�x��]���ł���悤�ɂȂ����Ǝ咣����Ă���B�d��A���͂ɂ�蓾��ꂽ��A���ɂ����āA��b�m���̍L���E�[���̗����ʂ����ʂ�L�ӂɐ����ł���Ƃ����̂́AQian
(2002) �̌����Ƃ�������������Ă���B
�@����̓��C�e�B���O�̃p�t�H�[�}���X����w�K�҂̌�b�n�B�x��\�����Ă������A�Ⴆ�X�s�[�L���O�̃p�t�H�[�}���X�����b�n�B�x��\�����悤�Ƃ���ꍇ�A�܂���������ʂ�������\��������B���ɁA����̌����Łu��b�m���ւ̃A�N�Z�X�v�����f�����������v���ƂȂ�Ȃ������̂́A���C�e�B���O�ł͎��g�̌�b�m���֑f�����A�N�Z�X����K�v�����܂�Ȃ���������ł͂Ȃ����ƍl������B���C�e�B���O�ƈ���āA���e�𐄝Ȃ��鎞�Ԃ����܂�^�����Ȃ��X�s�[�L���O�ł���A��b�n�B�x���������v���͕ω����邾�낤�B
�@����ɁA���C�e�B���O��X�s�[�L���O�̃p�t�H�[�}���X�����b�n�B�x��\������̂ł���A���̏n�B�x�͌���̎Y�o�ʂ̔\�͂�������Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B��s�����ł͌�b�̔��\�m��������e�m���̕����͂邩�ɍ����ƌ����Ă���
(Webb, 2008)�B���������āA����̃��f�����K�������w�K�ҌŗL�̌�b�n�B�x�𐳊m�ɕ]�����邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B
Qian, D. D. (2002).
Investigating the relationship between vocabulary knowledge and academic
reading performance: An assessment perspective. Language Learning, 52, 513-536.
Webb, S. (2008).
Receptive and productive vocabulary size of L2 learners, Studies in Second Language
Acquisition, 30, 79-95.
Schmitt, N., Wun Ching Ng, J., & Garras, J. (2011). The
Word Associates Format: Validation evidence. Language Testing, 28, 105-26.
0.�@Overview
��the Word
Associates Format (WAF)�͌�b�m���̐[���̑���ɂ����Ďg�����邪�A���̊��ɑÓ����Ɋւ��Ă͂قƂ�nj�����Ă͂��Ȃ��B�{�����́A2�̎�����ʂ��āA���̖��ɒ��ނ��̂ł���B
������1�ł́AWAF�Ƃ��̌�̃C���^�r���[��ʂ��āAWAF�̓��_�̑Ó������������B
������2�ł́A����1�P�������ɉ����A�̓_���@�Ȃǂ̂��ڍׂȕ��͂����݂��B
��2�̎�������AWAF�͋ɒl�ɂ����Ă͌�b�m���𐳂������f���邪�A���ԑw�ɂ����Ă͐M���ł�����߂ɂ͂���Ȃ����Ƃ��킩�����B����ɁAWAF�͌�b�m�����ߏ��]���������͉ߑ�]�����邩������Ȃ��X��������Ƃ������Ƃ��킩�����B
1.�@Introduction
����b�w�K�͑Q�i�I�ȉߒ��ł���
(Paribakht and Wesche, 1997; Schmitt, 2000)�B
��Nation (2001)�ɂ��A�ȉ��̂悤�Ȓi�K������ƍl������B
�@�@��`�i�����A�Ԃ�A�`�ԑf�j
�@�A�Ӗ��i�Ӗ��A�T�O�A�A�z�j
�@�B�g�p�i���@�A�R���P�[�V�����A���W�X�^�[�j
����b�m���ɂ͑傫�������āA�L��
(size)�Ɛ[��
(depth/quality)��2�̑��ʂ�����B
����b�m���̍L���𑪂�e�X�g�Ƃ��Ă͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����B
�@�@the Peabody
Picture Vocabulary Test (Dunn and Dunn, 2009)�FL1�p
�@�Athe Vocabulary
Levels Test (Schmitt, Schmitt, and Clapham, 2001)�FL2�p
�@�����̑��ɂ��A�]����b�T�C�Y�e�X�g�Ȃǂ̗l�X�ȃe�X�g�����݂���B
����b�m���̐[���́A���\�m���Ƃ��Ďg����̂��ǂ�����ǂꂾ�����m�Ɏg����̂��Ƃ��������Ƃɑ傫�ȉe����^����B�������Ȃ���A�m�����ꂽ�e�X�g�͍L���𑪂�e�X�g�قǂ͑����Ȃ��B��b�m���̐[���𑪂�e�X�g�Ƃ��Ă͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����B
�@�@the Vocabulary
Knowledge Scale (Paribakht and Wesche, 1997)
�@�@developmental
approach�i�e��b���ڂ��Ƃ�0 = no
knowledge�`5 = full
mastery�j
�@�Athe Word
Associates Format (Read,1993; 1995)
�@�@dimensions approach
2.�@Study 1
2.1�@Methodology
���팱�҂͓��{�l�p��w�K�ҁi���l�j18��
��VLT�ɂ�����2000�ꃌ�x����90%�̏K���x�����3000��`�A�J�f�~�b�N�E���x���͂���ɋ߂��K���x�ł������B
���}�e���A����Read�ɂ��1998�N�ł�WAF���g�p�����B
���A�J�f�~�b�N�E���[�h�E���X�g����Ƃ�ꂽ�`�e��50�ɑ��Ă��̗ދ`��
(paradigmatic association)�Ƌ��N�� (syntagmatic association)��I�ԂƂ������̂ł���iFigure 1�Q�Ɓj�B
���菇�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@�@WAF�̑S50���ڒ�40���ڂ�팱�҂ɓ���������B
�@�A���̌�A�e�팱�҂ɃC���^�r���[���s�����B
�E���̍ۂɁA�c���10���ځi�S�팱�ҋ��ʁj�ɓ��������Ȃ���Athink-aloud�v���g�R�����Ƃ������A�����ňȉ���6�̕������m�F���ꂽ�B
Strategy 1�F�Ώیꂨ��ъ֘A��̒m���������Ă���
Strategy 2�F�Ώیꂨ��ъ֘A��ɑ��ĈӖ��I�Ȓm�����I�Ɏ����Ă��Đ��_���s��
Strategy 3�F�Ώیꂨ��їދ`��̌`�ԑf�̒m���������Ă��Đ��_���s��
Strategy 4�F�Ώیꂨ��їދ`��ɑ��Č�������_���s��
Strategy 5�F�̌`�����琄�_���s��
Strategy 6�F�s��
�@�E�܂��A�C���^�r���[�̍ۂɁA40���ڒ�10���ځi���ꂽ���ځj�𒊏o���A���̌�b�ɑ��Ď��ۂɂ͂ǂ̒��x�̒m��������̂����₵�A4�_���_�ō̓_�����iAppendix
2�Q�Ɓj�B
2.2�@Results and discussion
��WAF (one-point method)�ƃC���^�r���[�̈�v���iTable 1�Q�Ɓj
�@�EWAF��4�_��ꂽ�҂Ƌt��1�_�ȉ��������Ȃ������҂Ɋւ��Ă̓C���^�r���[�̌��ʂƈ�v���Ă����B
�@�EWAF��2-3�_�̎҂̓C���^�r���[�ł̕]���������ꂽ�B
�@�E���������A46%�̎҂͗��҂̕]������v���邪�AWAF��49%�̎҂��ߑ�]���A25%�̎҂��ߏ��]�����Ă���Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�������g�p�̌X��
�Estrategy 1-2���g�p�����ꍇ�A�������������Astrategy 3-6���g�p�����ꍇ�A���������Ⴂ�Ƃ������ʂ����炩�ɂȂ����iTable 2�Q�Ɓj�B
��WAF�ɂ�����3-4�_�͈Ӗ��I�m���f���Ă��邪�A0-2�_�͂���f���Ă��Ȃ��\�������� (cancelling meaning / no meaning)�B
3.�@Study 2
3.1�@Methodology
���팱�҂͍��یn�̊w��28���i����15���͒�������b�ҁj
���}�e���A����Read�ɂ��1998�N�ł�WAF��Â��쐬�����iAppendix
3�Q�Ɓj�B
���菇�͎���1�Ƃقړ��l�ł���B
�@�@���K���s���A�Ɋ��ꂳ����B
�@�A20���ڂ�WAF�i�I������6�̂��̂�8�̂��̂�10���ڂ��j��팱�҂ɓ���������B
�@�B14���ځi�I������6�̂��̂�8�̂��̂�7���ڂ��j��팱�҂ɓ��������A�������̃^�C�v�ɂ��e���𑪒肵���B
�C���̌�A�e�팱�҂ɃC���^�r���[���s�����B
�@�E��e�m���ɂ��œ_�āA����ɂ�no-partial-full��3�i�K�ŋ�ʂ��邱�Ƃɂ����B
3.2�@Results and Discussion
��WAF (one-point method)�ƃC���^�r���[�̈�v���iTable 3,4�Q�Ɓj
�@�E����1�Ƃقړ��l�ł������B
��WAF�̍̓_���@
�@�@All-or-nothing�F�S�����1�_�i1��ɂ�1�_���_�j
�@�ACorrect-wrong�F����O�����������ɂ�1�_��^����i1��ɂ�8�_���_�j
�@�BOne-point�F1�̉ɂ�1�_��^����i1��ɂ�4�_���_�j
�@�˃C���^�r���[�ɂ��]���Ƃ̑��W���͂��ׂėL�ӂł����� (p < .01) �iTable 6�Q�Ɓj�B
�@�@�������A�̓_���@����ANOVA�i�Ɨ��ϐ��F�C���^�r���[�Ɋ�Â��n�B�x�A�]���ϐ��FWAF���_�j���s���A���ʗʂ��݂�ƁA6���ڂł�All-or-Nothing�A8���ڂł�One-Point���ł��傫�����Ƃ��킩��iTable 7�Q�Ɓj�B
��WAF�̍��ڂɂ����������
�@�@No relationship
�@�AMeaning
�@�BForm
�@�˃C���^�r���[�ɂ��]���Ƃ̑��W���͂��ׂėL�ӂł����� (p < .01) �iTable 6�Q�Ɓj�B
�@�@�������A�̓_���@����ANOVA�i�Ɨ��ϐ��F�C���^�r���[�Ɋ�Â��n�B�x�A�]���ϐ��FWAF���_�j���s���ƁAForm�͕ٕʗ͂��Ⴂ���Ƃ��킩��iTable 9�Q�Ɓj�B
��WAF�̐����̕��z
�@�@�ދ`��1���ڂƋ��N��3����
�@�A�ދ`��2���ڂƋ��N��2����
�@�B�ދ`��3���ڂƋ��N��1����
�˃C���^�r���[�ɂ��]���Ƃ̑��W���͂��ׂėL�ӂł����� (p < .01) �iTable 10�Q�Ɓj�B
�@�@�������A�@�͑��ΓI�ɓ���\�����݂���B
4.�@General discussion
���Ó��ȍ��ڐ� (6 vs. 8)
�@�����̌��ʁA8���ڂ̕����Ó��ł���Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@�������A�Ώی�ɂ���Ă�6���ڂ̕����悭�@�\����Ƃ������������� (Greidanus et al., 2004)�B
���Ó��ȍ̓_���@
�@6���ځFAll-or-Nothing
�A8���ځFOne-Point
���������A�����A�����I�m����]������K�v��������ꍇ�AOne-Point��Correct-Wrong�̕����D�܂����ꍇ������B
���Ó��ȍ�����
�@Form-based�F������ׂ��ł���
�AMeaning-based�F
�E���ӌ�͔�����ׂ��ł���
�E�Ώی�̈Ӗ��Ɋ֘A������ipositive��������negative�ȒP��j
�E���������m��collocation�������������
�BNo Relation�F���������
��Limitation
�E�팱�҂̏n�B�x������I�ł������B
5.�@Conclusion
��WAF�̋��݂ƌ��E�_�����炩�ɂȂ����B
�����݁�
�E��b�����⋳���ň�����
�E�����I�ɂ͐�������b�m���������Ă���
�����E�_��
�E�w�K�҂̒m�����ߑ�]�����Ă��܂�
�E���ԑw�̓��_���߂����
�Q�l����
�]������, ���V���, & ����R�I�v (2003). �w�p���b�̎w���}�j���A���x. �����F��C�ُ��X.
��Discussion��
�@WAF�ɂ�����������̃^�C�v�ɂ���ĕٕʗ͂��قȂ�Ƃ������ʂ�����ꂽ���A���ʂ̉��߂ɂ͌�����������邾�낤�B�S���֘A�̂Ȃ���̕����A���ڂ������e�X�g�ɂ����Ă͗L���ł��邪�A�Ӗ��I�֘A�̂����̕����A���ڂ����Ȃ��e�X�g�ɂ����Ă͗L���ł���Ƃ������ʂ�����ꂽ���߂ł���B���҂̌����l�ɁA�����I�Ɍ��đS���֘A�̂Ȃ��I�����̕����Ó��ł���Ɣ��f���邱�Ƃ��ł��邪�A�������v�ł���悤�ȋC������B�܂��܂����炩�ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ������A����Ȃ钲�����K�v�ł��낤�B
�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�
![]() 2011�N6��8��(S.N.)
2011�N6��8��(S.N.)
Sydorenko, T. (2010). Item writer judgments of item
difficulty versus actual item difficulty. Language
Assessment Quarterly, 8, 34-52.
1. Introduction (���͐ߔԍ��͔��\�҂��t�^��������)
������܂ł̌����ł́A���ړ�Փx�ɉe����^����l�X�ȗv���𖾂炩�ɂ��Ă����B
���e�X�g�J���ɂ����ẮA���ڍ쐬�� (item writer) �ɂ��̂悤�Ȍ����Ɋ�Â��u���ڂ̃��x���Ɋւ���L�q�v��^���邱�Ƃɂ��A���ڂ̓�Փx�̒������s���Ƃ������@���L���p�����Ă���B
���쐬���ꂽ���ڂ�pilot
study�ɂ���Ă��̓�Փx��ٕʗ͂Ƃ������ϓ_���番�͂����ׂ��ł��邪�A���ԂƘJ�͂�v���邽�߁AHambleton and Jirka (2006) �͍��ڂ̓�Փx��\�����鑼�̕��@�Ƃ��č��ڍ쐬�҂̔��f����Ă���B
1.1 Judgment of item difficulty
�����ڍ쐬�҂ɂ�鍀�ړ�Փx�̗\���́AL1, L2�̗����̌���e�X�g�ɂ����ĕK���������m�łȂ����Ƃ�������Ă��� (e.g., Alderson, 1993; Elder et al., 2002)�B
���������Ȃ���AL1, L2�̗����ɂ����āA�쐬�҂ɑ����ړ�Փx�̗\���Ɋւ���P�� (e.g., ���ڂ̓�Փx�ɉe����^����v�����w��) ���s�����Ƃ͂��̗\���̐��m�������P���邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��� (Hambleton& Jirka, 2006; Fortus et al., 1998)�B
��Bejar (1983) �͍��ڍ쐬�҂ɂ���Փx�̗\���͉��P���\�ł�����̂́A���ۂ̍��ڂ�p�����p�C���b�g�̑���Ƃ��ėp����ɂ͕s�\���ł���ƌ��_�Â��Ă���B�������A���̌��_��high-stakes test���������������瓱���ꂽ���_�ł���Alow-stakes test�ł͍��ڍ쐬�҂ɂ���Փx�\���͗L�p�ł���\�����c��B
������܂ō��ڍ쐬�҂ɂ���Փx�̗\�����ǂ̂悤�ɉ��P����邩�͑����̌����Ȃ���Ă�����̂́A���ڍ쐬�҂�����e�X�g�^�C�v�̍��ڂɂ��āA���̃e�X�g�^�C�v�̍��ڂ������m�ȗ\�����ł��邩�͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B
�� ���ڍ쐬�҂ɂ���Փx�̗\�����Ac-test, cloze test�����lj��e�X�g�ɂ����Đ��m�ł��������Ƃ�������Alderson (1993) ���͂��߁ABachman et al. (1996), Fortus et al. (1998) �ł��e�X�g�^�C�v�ɂ���ē�Փx�\���̐��m�����قȂ邱�Ƃ�����Ă���B�������A���̗��R��v���͕s���ĂȂ܂܂ł���A���ڍ쐬�҂̓�Փx�\���Ɋւ�����ڍׂȌ������K�v�ł���B�����āA���̌��ʂ͕]���ҌP���ւƉ��p���邱�Ƃ��ł���B
1.2 Factors influencing item difficulty
�y�C���v�b�g (���X�j���O) �z
�E speech rate, �]�萫 (redundancy), type-token ratio, ���̒���, ����I���G��, �g�s�b�N�̐e���x�ȂǁB
�y���ځE�I�����z
�E ���C���A�C�f�A or �ڍ���₤���̂�, �C���v�b�g�ƑI�����̌�̏d��,
�e�L�X�g�̍ŏI�����̏���₤���̂�, �I���� (���) �̔ے�\��, ������肩���_��肩�ȂǁB
�y�e�X�g�`���z
�E True-False (T / F), Multiple Choice (MC), Multiple Select (MS),
Cloze�ȂǁB
�E ���̑��A�������ёւ����
(a sequencing format), DIALANG project�Ȃǂ̌`�������邪�A�p�ɂɎg�p�������̂ł͂Ȃ��A�����̌`���Ɋւ��Ă͂��܂茟���s���Ă��Ȃ��B
�y�ڕW�ƂȂ錾��m���E�\�́z
�EPurpura (2004) �ł͂��錾��m���E�\�� (���@�A��b�Ȃ�) �͑��̒m���E�\�͂Ƃ͈قȂ锭�B��������Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃ���A�ڕW�ƂȂ錾��m���E�\�͂����ڂ̓�Փx�ɉe����^����v���ƂȂ�B
1.3 Context of the study
���{�����ł̓~�V�K����w�ɂ���ĊJ�����ꂽMultimedia Interactive Modules for Education and Assessment (MIMEA) ��p�����]�����s���BMIMEA�ł́A�w�K�҂��������̃r�f�I�N���b�v���������A�e�N���b�v�̌�MC��Cloze�Ȃǂ̈قȂ���`���ɂ��A���X�j���O�\�͂Ȃǂ̈قȂ錾��\�͂����肳���B
��MIMEA�ł́A�҂����̃��x���������A�����A�㋉����I���ł���BMIMEA�͖{���A�҂̕]���ł͂Ȃ��w�K�𑣂��v���O�����ł��邽�߁A�����̃��x�������͍��ڍ쐬�҂��C�ӂɍs���Ă���A���̑Ó����ɖ�肪�c��B�܂��A�e�X�g�`���ɂ��Ă��l�X�Ȃ��̂�p���邱�ƈȊO�́A���Ɍ��y�͂Ȃ��B
�������̖�����������MIMEA�̐����𖾂炩�ɂ���Ƌ��ɁA���ړ�Փx�̗\���ɂ��Ă��V���ȓ��@�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�{�����ł͈ȉ���2��RQ��T������B
RQ1 : ���ڍ쐬�҂́A�ǂ̒��x���m�Ɏ��ۂ̍��ړ�Փx��\�����邩�B
RQ2 : ���ڍ쐬�҂̓�Փx�\���ɉe����^����v���Ǝ��ۂ̍��ړ�Փx�ɉe����^����v���͓������B
2 Method
2.1 Participants
�����V�A�����Ƃ���p��w�K��10�l�Ɖp�����Ƃ��郍�V�A��w�K��35�l�B���V�A��̊w�K����2�N��14�l�A3�N��11�l�A4�N��10�l�ł������B
�����ڍ쐬�҂�1�l�ł���A�p���L2�Ƃ��郍�V�A����b�҂ł������B
2.2 Procedure
[Part1]
�� �w���̖��Ă��A�e�X�g���ڂ̑Ó������m�F���邽�߂Ƀ��V�A����b�҂ɂ��e�X�g���s���A�R�����g�����߂��B���b�҂̐�����80%�ɒB���Ȃ��������ڂ�R�����g�ɂ���ĕs�K�Ɣ��f���ꂽ���ڂ͍폜�E���P���ꂽ�B
[Part2]
���܂��A���V�A��w�K�҂ɑ��A���V�A��w�K�Ɋւ���A���P�[�g���s�����B���̌�A1���Ԕ�~2���Ԓ��x��MIMEA�̎��s���A�e�X�g��ɂ͕s�K�ȍ��ڂ�������������q�˂��B
���e�X�g����ɂ�24���̊w�K�҂ɂ���10���Ԃ̌l�ʐڂ��s�����B
2.3 Materials
[Videos]
���e�X�g��12�̃r�f�I�N���b�v�ō\�����ꂽ�B���ۂ�s����`����Ƃ�����6�̉�b�@�\�ɂ��A���ꂼ��2���̃r�f�I�N���b�v���������B
���r�f�I�N���b�v�̒�����13~63�b�A40~168��ł���A������117~189
wpm �ł������B
�����͎҂͊e�N���b�v��2�������B
[Items]
���e�N���b�v�ɂ��A7~17�̖�荀�ڂ��������B�����͎����O�ɍ��ڍ쐬�҂ɂ���āA�����E�����E�㋉�ɕ��ނ���Ă���B�㋉���ڂł͎w���̓��V�A��ł��������A�����E�������ڂł͉p��ł������B
���e���ڂ̓��X�j���O�A��p�_�I�m���A��b�A���@�A��ѐ��̒m����5�̂����ǂꂩ��]��������̂ł���A�l�X�Ȗ��`���Œ��ꂽ�B�]�������\�́E�m���Ɩ��`���̓����Table 1���Q�Ƃ��ꂽ���B
�� �]�������\�͂Ɩ��`���̏ڍׂɂ��Ă͊����B�{��p.41���Q�ƁB
3. Analysis
����A���� (RQ�ɑΉ�����2��)�AANOVA, �L�q���v�ɂ�镪�͂��s�����B
����A���͂̓Ɨ��ϐ��́ARQ1�̕��͂ł͍��ڍ쐬�҂��\���������ړ�Փx�ARQ2�̕��͂ł͐�s�����Ŗ��炩�ɂ��ꂽ���ړ�Փx�ɉe����^����v���ƁA���͎҂ւ̖ʐڂɂ����Ĕނ炪��Փx��^����Ɖ����v������I�o���ꂽ8�̗v���ł��� (Table
2)�B
��128�Ƃ������ڐ��́A1�E8�̓Ɨ��ϐ�������A���͂ɂ͏\���ȃT���v�����ł��� (Green, 1991)�B
��2�̉�A���͗����ŏ]���ϐ��͍��ړ�Փx�ł������B�҂̏��Ȃ�����A���ړ�Փx�̓��b�V�����͂ł͂Ȃ��A�ÓT�I�e�X�g���_�Ɋ�Â����@ (�����҂̊���) �ŎY�o���ꂽ�B
���S�Ă̍��ڂ�1, 0�ō̓_����AMIMEA�ɂ���Ď����I�ɍ̓_���s��ꂽ�B
4. Results
4.1 RQ1
����A���͂��s�������ʁA���l�͏����E�����ԂƏ����E�㋉�Ԃ̗����ŗL�ӂł���A���̂��Ƃ͍��ڍ쐬�҂̓�Փx�\�������ۂ̓�Փx�ɂ��ėL�ӂȗ\���ϐ��ł��������Ƃ������B�������A���̐������͒Ⴉ���� (�����ς�R2 =
.07)�B
�������A�����A�㋉���x���̍��ڊԂō������������������邽�߂ɁA�ꌳ�z�u���U���͂��s�����Ƃ���A����ʂ��L�ӂł������BFisher��post hoc test���s�����Ƃ���A�����ƒ����A�����Ə㋉�̊Ԃ̍��͗L�ӂł��������A�����Ə㋉�̊Ԃ̍��͗L�ӂł͂Ȃ������B�܂�A���ڍ쐬�҂͒����Ə㋉���x���̍��ڂ�K�ɏs�ʂ��č쐬�ł��Ă��Ȃ��������Ƃ������B
4.2 RQ2
����A���͂̌��ʁAFormat,
topic, linguistic focus, negative stem��4���L�ӂȗ\���ϐ��ł���A�����4�̐�������53%�ł������B���̂����ł��傫�����������������̂�Format�ł���A�P�Ƃł̐�������39%�ł������B�e�v�����̓�Փx�̊W��Table 6, 7���Q�ƁB
�����ɁA���ڍ쐬�҂̓�Փx�\�����ǂ̂悤�ȗv���Ɋ�Â��Ă��邩�������邽�߁A3�̗\�����ꂽ��Փx�ԂŁA��A���͂ŗL�ӂł������v���̕��z���Y�o���� (Table 8�Q��)�B�����Ȍ��ʂ́A�������x���ł̓��X�j���O���ڂ����ɑ����A�����E�㋉�̌�b���ڂ�������2�{���x�̐��ƂȂ��Ă��邱�Ƃł���B
���e�X�g�t�H�[�}�b�g�ɂ��ẮA������MC�������A���E�㋉�ł�MS��ordering,
dialog reconstruction�Ȃǂ̊����������Ă��邪�ATF, Cloze�Ɋւ��Ă͓�Փx�ԂŊ��������܂�ς���Ă��Ȃ��B����́ATable 9�Ɏ�����Ă���悤�ɍ��ڍ쐬�҂������2�̃e�X�g�`���̃��x���������ƒ��㋉�̊Ԃł��܂��s�ʂł��Ă������߂ł��낤�B
���܂��A����ɂ�����ے�\���ɂ�鍀�ڍ쐬�҂̓�Փx�\���ɂ��Ă����m�ł������B
5. Discussion
5.1 RQ1
������̌��ʂ��獀�ڍ쐬�҂͎��ۂ̍��ړ�Փx��L�ӂɗ\��������̂́A���̗\���͂͏��������Ƃ������ꂽ�B���̌��ʂ́A����܂ō��ڍ쐬�҂̓�Փx�\�������m�łȂ����Ƃ������������ƈ�v����B
�����ڍ쐬�҂̓�Փx�\�������m�łȂ����R�Ƃ��āA���ڂւ͍̉쐬�ҊԂƎҊԂ̗����ňقȂ�v���Z�X�A�����A�\�͂��o�邱�� (Fortus et al., 1998) ����������B�܂��A����̍��ڍ쐬�҂����b�҂ł��������Ƃ����̗��R��1�ƍl������ (Stansfield
& Kenyon, 1996)�B
���܂��A�{�����ł͍��ڍ쐬�҂͒����E�㋉���x���̍��ڂ����܂��s�ʂł��Ă��Ȃ������B����́A���X�j���O�̃C���v�b�g���Ղ����������߂ɁA�����̃��x���̍��ڂɍ�������̂�����������߂ł��낤�B
5.2 RQ2
�����ۂ̍��ړ�Փx�ɂ́AFormat,
topic, linguistic focus, negative stem�̗v�������̏��ŗL�ӂɉe����^���Ă����BTF, MC������Փx���Ⴂ�̂́A���Đ��ʂ̉\������l���Ă����R�̌��ʂł���B
���{�����ł́A�����̌����œ�Փx��L�ӂɗ\������Ƃ���Ă���speed of delivery ���L�ӂł͂Ȃ������B����́A1�̃N���b�v����speed
of delivery���l�X�ɕω����Ă��邽�߂ł���Ɛ��@�����B
���S�̂Ƃ��āA���ڍ쐬�҂�Format,
linguistic focus, negative stem�Ƃ������v���ɕq���ł���A��Փx�ɍ��킹�Ă������g�p�E��ʂ��Ă����B���̂��Ƃ���A���ړ�Փx�ɉe����^����v���ɂ��ĕ]���҂��P�����邱�Ƃ́A���̗\���̐��m�������P���邱�ƂɌq����Ǝ��������
6. Conclusions
�� �w�K�҂͉��鍀�ڂ�������Ă��ȒP�����Ă��A���e�B�x�[�V�����������Ă��܂��̂ŁA�{�����̌��ʂɊ�Â��ēK�ȓ�Փx�̍��ڂ��w�K�҂ɗ^���邱�Ƃ��d�v�ł���B
���܂��A�{�����̌��ʂł͒����E�㋉���x���̍��ڂł͓�Փx�ɍ��������Ȃ���������AMIMEA�Ɋ܂܂�鍀�ڂ͏����I�ɂ͏����ƒ����{��2�i�K�Ƃ��邱�Ƃ��\�ł���B
���{��������́A���ڍ쐬�҂̓g�s�b�N�e���x�̂悤�ȃC���v�b�g�Ɋ֘A�����v���ɕq���ł��邱�Ƃ����������B�܂��A�e�X�g�`���⌾��̈قȂ鑤�ʂɊւ���m���Ȃǂ����ړ�Փx�ɉe�����邱�Ƃ������ꂽ���߁A���ڍ쐬�҂ɑ���P���̒��ł����̗v���Ɍ��y���邱�Ƃ��K�v�ł��낤�B
���{�����̌��E�_��1�ɁA���ڊԂŃe�X�g�`���ƌ���\�͂̓��������Ă��Ȃ����Ƃ����� (e.g., cloze- grammar)�B�܂��A�����̍��ڂ����܂܂�Ă��Ȃ��`�� (e.g., ordering, matching) �̈�ʉ��ɂ͒��ӂ��K�v�ł���B
�� ���ڍ쐬�҂̓�Փx�\���͗L�p�ł��邪�A���P�����K�v�����邽�߁A���̌��͍X�ɍs����ׂ��ł���B����̌����ł́A�����̍��ڍ쐬�҂ɂ���Փx�\������b�҂Ɣ���b�҂ɂ���Փx�\���̌��A���b�v���g�R���ɂ���Փx�\���̔F�m�ߒ��̌��A�V�����e�X�g�`����p�������Ȃǂ��s����ׂ��ł���B
�y���Ɠ��R�����g�z
���_�~�[�ϐ��𓊓�����`���̉�A���͂ŁA�{���Ɍ��������̂����ł��Ă���̂��B
��Table 6 (p.45) �ł́AFormat�ł����MC�̔�r�ATopic�ł����Sympathizing�Ƒ��̔�r�ALinguistic
focus�ł����Listening�Ƒ��̔�r�݂̂��s���Ă���B�m���ɁA����ł͊e�v�����̓�Փx�̊W���ڍׂɂ͕�����Ȃ��B�������Ȃ���A���ɂǂ̂悤�ȕ��͎�@���K���܂ł͕�����Ȃ������B
�� ����̌��ʂ͂����܂�MIMEA�ɂ����Ă̂ݓK�p�������̂ł���A��ʉ��͓���̂ł͂Ȃ����B
�� �_�����ɏq�ׂ��Ă��邪�A�{�����ł͍��ڍ쐬�ҌP���ɗL�Ӌ`�Ȏ�����^����ƂƂ��ɁAMIMEA�Ƃ�������̃e�X�g�̉��P�����̖ړI��1�ƂȂ��Ă���B����̌����͍��ڍ쐬�҂�1�l�Ƃ����P�[�X�X�^�f�B�I�ȗv�f���������Ƃ�����A���ʂ͍L���e�X�g��ʂɍv������Ƃ�����������̃e�X�g�̉��P�ɑ��čv��������̂ł��낤�B
�� ����̓��V�A���L2�Ƃ���w�K�҂�ΏۂƂ��Ă���̂ŁA�p���L2�Ƃ���w�K�҂�ΏۂƂ����ꍇ�A�������ʂ�������̂��낤���B
�� L2�Ƃ��Ċw�K���Ă���Ƃ����_�͓����ł��邪�A�u�ڕW�Ƃ��錾��\�́E�m���v�����ړ�Փx�ɉe������悤�ɁA�u�ڕW�Ƃ��錾��v�ɂ���Ă����R���ʂ͈قȂ��Ă��邾�낤�B����͉p��w�K�҂�ΏۂƂ��������҂����B
�� ���ڍ쐬�҂�1�l�ł��邽�߁A���̓�Փx�̗\�����肪����̂ł͂Ȃ����B
�� ���̓_�͕����̕����瓯���ӌ������B���҂��_�����Ɍ��y���Ă��邪�A����̂悤�ȃP�[�X�X�^�f�B���瓾���錋�ʂ́A���ڍ쐬�ґS�ʂ̌X���Ƃ��Ĉ�ʉ��ł��Ȃ��Ƃ������E�_��������̂́A�O���[�v��ΏۂƂ�����������͓����Ȃ��A�l�̍��ړ�Փx�\���ɂ��Đ[�����@��^���邱�Ƃ��\�ł���B�������Ȃ���A���R�O���[�v��ΏۂƂ�������������]�܂�邾�낤�B
�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�
![]() 2011�N11��2���iT.I.)
2011�N11��2���iT.I.)
Beglar,
D. (2010). A Rasch-based validation of the Vocabulary Size Test. Language testing, 27(1), 101-118. doi:10.1177/0265532209340194
Abstract
���{�����ő�̖ړI�́A14,000��̉p�P��̎�e�I�m������̂��߂ɊJ�����ꂽ140��b���ڂ�Vocabulary Size Test�i�ȉ��AVST�j�̏����i�K�ł̑Ó����̏ؖ��ł���B
���{������19�l�̉p����b�҂�178�l�̓��{�l���b�҂̋��͂̉��AMessick�̒����\���T�O�Ó����̕����̗v�f�ɏœ_�āARasch���f���ŕ��͂��s�����B
���{�����̔����́A�ȉ���5�_�ł���B
1.
�e�X�g���ڂƋ��͎҂́A�T���āA�挩�I�����ɂ���ė\�����ꂽ�ʂ�̌��ʁE�s�����������B
2.
�命���̃e�X�g���ڂ��ARasch���f���ւ̓K�����������B
3.
Rasch���f����p�������A�e�X�g���ڂ́A�ϐ���85.6%���߂鍂���ꎟ�������������B
4.
�e�X�g���ڂ́A0.91��0.96�̈قȂ�e�X�g���ڂ̏W������\�����ꂽ�팱�ґ���ɑ�����C�������s�A�\���̑��W���Ƃ̊Ԃɋ�������s�ϐ����������B
5.
Rasch���f���̐M���w���i>0.96�j�������ʂ�A�l�X�ȃe�X�g���ڂ̑g�ݍ��킹�ŁA�{�W�{�̋��͎ҒB�ɑ��Đ��m�ȑ�����s�������ł����B
���ȏ�̔������AVST�͕M�L�ł̎�e�I��b�T�C�Y�̑��肪�����炷������@�̕���傫���g�債�A�V���ȑ�����@�����t�ƌ����҂ɒ���ƌ����̂��A�{�����̌��_�ł���B
Introduction
�����b�ҁE�w�K�ҋ��Ɍ�b�̊g���͑����̔N����v������̂ŁA��b�̃��[�f�B���O��X�j���O�ւ̍v���x����A����҂ɂƂ��Ă��w�K�Ҏ��g�ɂƂ��Ă���e�I��b�T�C�Y�̊T�Z�͏d�v�ł���B
�����N���ڂ��W�߁A�l�X�ȗp�r�E����Ŏg�p����Ă����b�T�C�Y�e�X�g�ɂ́AEurocentres Vocabulary
Size Test (Meara & Buxton, 1987; Meara & Jones, 1990; �ڍׂ�]����Read, 2000, pp. 126-132�Q��)��Vocabulary Levels Test
(Nation, 1983, 1990)������B�A���A��҂ɑ���Nation (2001)�́u�f�f�I�e�X�g�v�Əq�ׂĂ���ANation���g�͕�I������@�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��Ǝv����B
���O���ꋳ��ɂ����đ��푽�l�Ȗ��������Ƃ����������炩�ɂ��ւ�炸�A���݁A�p��̔���b�ҁi�n�B�x�̒Ⴂ���S�҂���n�B�x�̍����w�K�҂܂Łj�ɑ��Ă̕M�L�ł̎�e�I��b�T�C�Y�𑪒肷�邽�߂̍L���e�F����Ă���e�X�g�͑��݂��Ȃ��B
���{�_���́A�M�L�ł̎�e�I��b�����ړI�ɊJ�����ꂽVST�̑Ó�������������̂ł���B�{�����̌��ł́AMessick (1989, 1995)�̍\���T�O�Ó�����6�v�f�i���e�I�A�{���I�A�\���I�A��ʉ��\���A�O�I�A���ʓI�j�̍ŏ���4�v�f�ƁA�X��Medical Outcomes Trust
Scientific Advisory Committee (1995)����Ă�����\���E���ߐ���2�v�f������B�܂��AWolfe & Smith (2007a, 2007b)����������I�Ó�������̂��߂�Rasch���f����K�p����B
���{�_���ɂ�����Ó����̏ؖ��́AMessick (1989)�́u�e�X�g�ł͂Ȃ��A�e�X�g�̉��M�����ƑÓ�����L���Ă���c�i�����j�c�e�X�g�̉́A���ځA�^�X�N�A�h����݂̂����łȂ��҂⑪��������킹�Ă̑��֓I�v�f�ł���v(p. 14)�Ƃ����ϓ_�Ɋ�Â��Ă���B���̂��߁A�{�����ő�̖ړI�́A����̊��ɂ�����҂̈�Q�ɑ���VST�̖��������鎖�ł���B
Method
Paticipants
���{�����́A�ȉ���4�Q�iN = 197�j���͂̉��ōs��ꂽ�B
1.
NSE group�F�A�����J�̑�w�̏C�m�ے��E���m�ے��ŋ�����U���Ă��鐬�l�̉p����b�ҁin = 19�j
2.
High group�F����U�ō��n�B�x�iTOEFL 560-617�j�̓��{����b�ҁin = 19�j
3.
Mid group�F���A�����J�̑�w�̊O����W���v���O�����E���{�̈ꗬ������w�̒��n�B�x�̓��{����b�ҁin = 53�j
4.
Low group�F���{�̑�w�̒�n�B�x�̓��{����b�ҁin = 96�j
�����͎҂̓e�X�g�̖ړI��ʒm����Ă���A���{�l�̋��͎҂����TOEFL�̃X�R�A�𗘗p���鋖�����Ă���B
The Instrument
��VST�́A���Ƃ��ĉp����w��ł���w�K�҂�ΏۂɁA1�ԍ��p�x��1000���[�h�t�@�~���[����14�Ԗڂɍ��p�x��1000���[�h�t�@�~���[�܂ł̕M�L�ɂ������e�I��b�m���������M�����ŁA���m����I�ɑ��肷�邽�߂̃e�X�g�ł���B���ꂼ��140�̍��ڂ�L����3��Form�̓��A�{�����ł�Form 1�ɏœ_�Ă��B
���{�����ł́A�ȉ���5�̗��R�ɂ��A�����I�������̗p�����B
1.
���L�����e�����ʓI�Ƀe�X�g�\�B
2.
���푽�l�Ȍ���I�w�i�����w�K�҂ɑΉ��\�i���ɁA�����I�����́A�����̊w�K�҂����ʂ��Ă���`���ł���j�B
3.
�e���ڂ̉̍ہA���̍��ڂƓ����x���̒m�����v������邽�߁A���ږ��̓�Փx���\�i�e�I�����́A��Փx����������I�Ȍ�b�E�ł��p�x�̍����p�@�őΏۍ��ڂƌ������\�Ȃ悤�ɋL�q�j�B
4.
���ʓI���M�����̍����̓_���\�B
5.
�w�K���e���ڂɊւ���m����p���ĉ\�i�I�����̒��̐����ƌ듚�́A�Ӗ��v�f�����ʂ��Ă���̂ŁA�w�K�҂͒m���◝����v�������j�B
Procedures
���n�B�x�̍������2�O���[�v�ɂ�1�ԍ����p�x����14�Ԗڂɍ����p�x�܂ł̊e1000���[�h�t�@�~���[���10���ڂ��I������140���ڂ�Form 1�A���ʃO���[�v�ɂ�1�ԍ����p�x����8�Ԗڂɍ����p�x�܂ł̊e1000���[�h�t�@�~���[���80���ڂ�Form 1�A���ʃO���[�v�ɂ�1�ԍ����p�x����4�Ԗڂɍ����p�x�܂ł̊e1000���[�h�t�@�~���[���40���ڂ�Form 1���A�ʏ�̎��Ɠ��Ŏ��{�����B
�����W�����f�[�^��Excel 11.3.5 spreadsheet�ɓ��͂��āAWINSTEPS 3.64.2 (Linacre,
2007a)�ɃG�N�X�|�[�g�̌�ARasch�̍��ڔ������_��ꐔ���f�� (Rasch, 1960: Pn = exp(Bn - Di) / [1 + exp(Bn - Di)])��p���Čv�Z���ꂽ�B
��Rasch�̍��ڔ������_��ꐔ���f����p�������R�́A�ȉ���4�_�ł���B
1. �����i�ꎟ���j�ō��ڂƔ팟�҂̑���̕\�L���\�B
2. �����ł̍��ڂƔ팟�҂̕��ނ��A���ݓI�ϐ��Ƃ��̕ϐ��ɑ��鋦�͎҂̔����Ɋւ���挩�I�����Ɗ֘A�����鎖���\�B
3. �ϑ����ꂽ�����ƃ��f���Ɋ�Â��ė\������锽���Ƃ̍��ق������鎖���\�B
4. ���ڂ̗]�蕪�U�Ƃ��̗]�蕪�U���Ӗ��̂���I���ݐ���L���Ă���Ǝv����x�����̕��͂�ʂ��āA���W�����f�[�^�̑������������肷�鎖���\�B
���S���͎҂ɋ��ʂ���40��ȊO�ł́Ainternal anchor (Wolfe, 2004)�𗘗p�������ʍ��ڂ̐v�𑪒�ɗp�����B0.90-1.10�Ԃ�infit���ϕ������v�w�W������23���ڂ�anchor�Ƃ��ėp�����A������͒ʏ��10�{�̌������Őݒ肳�ꂽ�BLink quality�́Aanchor set��p����ꍇ�Ɨp���Ȃ��ꍇ�ł�displacement values�̃`�F�b�N�ƍ��ړ�Փx�y�ы��͎҂̔\�͂̃N���X�E�v���b�g�̎��{�Ɋ�Â��]������A���͌����Ȃ������B
Content
aspect of construct validity�i���e�I���ʁj
Representativeness
��Representativeness�́A����3�_�ɊW���Ă���B
1.
������@���ɏ\���Ȑ��̍��ڂ��܂܂�Ă��邩�ۂ�
2.
�����ł̍��ڕ��ނ��\���ȕ��z�������Ă��邩�ۂ�
3.
�����ł̍��ڕ��ނɂ����č������݂��邩�ۂ�
��197�l�̋��͎҂�140���ڂɑ���Rasch���f���ł̖ڐ�����Ō���Figure 1���A�{������VST�ɂ͏\���Ȑ��̍��ڂ��܂܂�Ă��鎖��������A�e���x����10���ڂ��S���͎҂̕M�L�ł̎�e�I��b�m���𑪒�\�ł������B
���{������140���ڂɑ���(4Gitem + 1) / 3�ŎZ�o����鍀�ڂ̕��ނ�7.29�ł���A�{������VST�����푽�l�ȕM�L�ł̎�e�I��b�m����L����w�K�҂Ɏg���鎖�E�����Ԃɓn��w�K�҂̌�b�K���̑���ɑ���\���Ȑ��̕��ނ�ł��鎖�������ꂽ�B
�������ł̍��ڕ��ނɂ����č��͑��݂����A�ނ��뒍�ڂɒl����̂͗]�萫�ł������B�]���āA����̐������������鎖�Ȃ��A�e��p�x���x���̍��ڐ������炷�����\���ƌ�����B
Technical quality
��Technical quality�́A178�l�̓��{�l���͎҂���\������A���ϕ����K���x�𑀍삵��Rasch���f���ŕW�������ꂽ�e�X�g���ځE�K���x���z���Ă��܂������ڂ����鎖�ŁA���؉\�ł���B
��1000-10�̍��ڂ�����������A�c��4�̓K�����Ȃ����ځi3000-9, 2000-1, 2000-5, 5000-3�j���{�����̌`���ŏ����I�Ɋώ@�����K�v�����邪�A�S�ʓI�ȓK�����Ă��Ȃ����ڂ̐���140���ڂ̃e�X�g�Ŏx��𗈂������A��K������3.6%��z���z�Ɋ�Â�5%����������B
The
substantive aspect of construct validity�i�{���I���ʁj
���{���I���ʂɊւ��āABNC���X�g�ɂ�����p�x�Ɋ�Â��AVST�̃e�X�g���ڂ͓�Փx�̘A���̂��`������Ɖ��肳���B
���{����́A�e�X�g���\������14�i�K��1000��̕p�x�ɑ��镽�ς̏W�����v�Z���鎖�Ō��ł���BFigure 2�̒ʂ�A14�i�K��1000��̕p�x���x���̓�Փx�̕��ς̏W���́A��{�I�ɉ����ŗ\�����ꂽ�ʂ�̐���`�����B
���X�ɁA�e�X�g���͎҂̔\�͗\�������肳�ꂽ�����ɂ��邩�ۂ��̎ړx�́AVST�ő��肳�ꂽ�\���T�O�����_�Ɛ�s��������\�������p�^�[���ɏ����Ă��邩���ׂ鎖�ŁA�����鎖���\�ł���BTable 3�̒ʂ�A�e�X�g���͎҂�4�O���[�v�͗\�����ꂽ�������`�����Ă���A���̏����Ԃ̍����\�����ꂽ�ʂ�i�����ʃO���[�v�ƒ��ʃO���[�v�Ԃ̍��́A����ȊO�������ɏ������j�ł������B
The
structural aspect of construct validity�i�\���I���ʁj
���\���I���ʂɊւ��āABeglar & Hunt (1999)��Vocabulary Levels Teat
(Nation, 1990)�Ɋւ����s�����Ɋ�Â��AVST�͍������_����I�ꎟ�����������Ɖ��肳���B
���{������VST�Ɋւ��āARsch���f���i85.6%�j�E�ŏ���4�̗]��v�f�i���ꂼ�ꂪ0.4����0.6�̊ԁj���ɁALinacre (2007b)�̊�����Ă���B�܂��ASteven (2002)�̃K�C�h���C�����A�Ӗ���L��������͊m�F�m�F����Ȃ������B
���]���āA���肪�x�����ꂽ���ɉ����āA�e�X�g���͎҂̉^�p�\�͂ɂ�����ϐ���Rasch�̃e�X�g���͎҃��f���Ő����\�Ȏ��������ꂽ�B
The
generalizability aspect of construct validity�i��ʉ��\�����ʁj
����ʉ��\�����ʂ͕s�ϐ��Ɋ֘A���Ă���A������ɂ����鋦�͎҂ƍ��ڂ̑���Ɋւ�����ł���B
��DIF (differential item functioning;
Wright & Stone, 1979)�C140���ڂ̒�����̖���ׂȊe��p�x���x���ł�5��̒��o�CWinsteps�œ����鐳�ƕ��̍��ڗ]�蕉�חʂɊ�Â�2�̉��ʏW�c�ւ̍��ڂ̕��� (Linacre, 2007a)��3�̌��ؕ��@�ɂ��AVST�̍��ڂ̗l�X�ȑg�ݍ��킹�������s�ϐ���L���Ă���A�ގ��������͎҂̔\�͗\���l���Y�o�ł��鎖�������ꂽ�B
���X�Ȃ��ʉ��\�����ʂ̌��Ƃ��āA������VST�i�k���œ��j���쐬���A�{�����̏������łǂ�VST�������̃G���[���N�����Ȃ������������B���̌��ʁATable 1�̒ʂ�A�S�Ă�VST���قړ����M������L���Ă����B
Responsiveness�i�������j
�������� (Medical Outcomes Trust Scientific
Advisory Committee, 1995)�́A�����i���ǂꂾ�����m�ɕω��𑪒�ł��邩�Ƃ����ړx�ł���B
��VST�̔������́A�e�X�g���͎҂̕��ނ����肷�鎖�ő��肳��A�Z�o�̎���Gp = (4Gp + 1) / 3�ł���B
��197�l�̃e�X�g���͎҂ɑ��镪�ނ̒l��7.15�ł���A�{�����ł�VST�͕W�{�̃e�X�g���͎҂̕M�L�ł̎�e�I��b�m�����A���v�I�ɕٕʉ\�Ȗ�7���x���ɕ��ނł��鎖�������ꂽ�B
�����̒l�́A�{���������łȂ��A���푽�l�ȕM�L�ł̎�e�I��b�m���E���̎�e�I��b�m���̒����Ԃł̕ω��̑���ɑ�����ݐ��̊ϓ_����������������ł���B�܂��A14000��̕p�x���x���Ɋg��������b�e�X�g�œV����ʂ������p��̑��w�K�҂͖w�Ǒ��݂��Ȃ��̂ŁAVST�͂قڑS�Ă�ESL/EFL���ŗp���鎖���ł���B
Interpretability�i���߉\���j
�����߉\�� (Medical Outcomes Trust Scientific
Advisory Committee, 1995)�́A�ʓI���肩��l�����鎿�I�Ӗ��������ړx�ł���B
��VST�̌��ʂ̉��߉\�����l������ɂ������āAVST��3�̌��E�_�܂��Ă����K�v������B
1.
VST�͕M�L�ɂ������e�I�Ȍ�b�T�C�Y�𑪒肷�邽�߂̃e�X�g�Ȃ̂ŁA���X�j���O�ɂ������b�T�C�Y��VST��p���鎖�͍D�܂����Ȃ��B
2.
VST�ł̎҂̉́A�X�s�[�L���O��C�e�B���O�̃^�X�N�ɂ����āA�e�X�g���ڂ��ǂꂾ����肭�g�p����邩�Ƃ�������w�ǎ����Ȃ��B
3.
��b�m���̓e�N�X�g�̉ǐ��ɍł��e����^����v���Ƃ���Ă��� (Klare, 1974)���AVST�ł̎҂̉͑�܂��Ȗڈ��ɉ߂��Ȃ��̂ŁA���[�f�B���O�̃e�X�g�Ƃ��ėp���鎖�͂ł��Ȃ��B
��VST�̌��ʂ����߂���ɂ������āA�e���ڂ�100���[�h�t�@�~���[�̑�\�i��10���ڂ��A�e1000���[�h�t�@�~���[�̕p�x���x����\���Ă���j�Ɖ��肷����@�����݂��邪�A���D�܂����͍̂��ډ��_�Ɋ�Â������@�ł���B��҂̕��@�ł́A�e�X�g���ڂ��K�����������p�x���x���ɑ�����K�v���Ȃ��A�������Ȃ��A���͎҂ƍ��ڂ̓K���w�W�ɂ���ċ��͎ҌX�̉p�^�[���⍀�ډ^�p�����߂ł��Aanchor���ڂɂ���ċ��͎҂��ꂶ��̕M�L�ł̎�e�I��b�T�C�Y��P��̘A���̂ő��鎖���ł���B
���{���@��p���Ẳ��߂̌��ʂ�Table 2�̒ʂ�ł���A55.2��Rasch�\�͑���l��L����e�X�g���͎҂͖�7000���[�h�t�@�~���[�̌�b�T�C�Y�������Ă����B
Conclusion
���{�_���ő�̖ړI�́A���ݓI�ϐ��Ɋւ���挩�I�����C���ݓI�ϐ��̑���\�Ȓ�`�C�팱�҂̑���̎��I���قݏo�����胂�f������������@��p���āAVST��1�̃p�^�[���ɑ���ŏ��̑Ó����̘_�����������i��1�ԍ��p�x��14,000���[�h�t�@�~���[�̕M�L�ł̎�e�I�m���𑪒肷�邽�߂̃e�X�g���ڂ̓��A�\���T�O�̐��m�ȑ���Ɋ�^���Ȃ��������邩�ۂ��̌��j�ł������B
���f�[�^���͂̑O�ɒ����e�X�g���ڂ̋@�\�iFigure 2�Q�Ɓj�C�e�X�g���͎҂̉^�p�\�́iFigure 3�Q�Ɓj�C�e�X�g�̎������Ɋւ���3�̉����́A�S�Ďx�����ꂽ�B���|�I�命���̃e�X�g���ڂ��ARasch���f���Ƃ̐��m�ɓK�����A�]�荀�ڕ��̕��͂ɂ���Ď�����鋭�����_����I�ꎟ�����Ɨl�X�Ȍ`���̃e�X�g�ł̗ގ������Ώێ҂̑���l�ɂ���Ď�����鋭������s�ϐ��������A�ǂ�����̊�����Ă����B�܂��A�e�X�g���͎҂͑����I�����e�X�g�ւ̍������x�������A�G���[�͏��Ȃ�����ō����M������L���Ă����B
���{�����ł͏œ_���̑��݁i���X�̋��͎҂̐��ݓI�\���T�O�̕ω����@�j�̑���ɓ��Ă��̂ŁA�����I��VST�����ł͒����Ԃł̓���̋��͎҂ɂ��̑��݂̕ω�������ׂ����ƍl������B�����āA���̒����́A�w�K�҂̒����Ԃɓn���b�w�K�̐i���̑���Ƃ����e�X�g�̖{���I���l�Ɍq���镨�ł���B
Comments
�{�����̌��ʂ́A���e�I���ʂ�����߉\���܂ŁA���ɗǍD�Ȃ��̂ł������B���̗ǍD�Ȍ��ʂ́A�e�߂�Table��Figure������m�F���鎖���ł��A���ɖ{���I���ʂɊւ���Figure 2 (p. 109)�ł́i8000��p�x���x���ȊO�́j�S�Ă̕p�x���x���̌�b���ڂŁA�\�z�Ɋ�Â����ʂ�����ꂽ�B�A���A���̕��ς̓�Փx�̏W���𑪒肷�邽�߂ɗp������b���ڂ͖���ׂɒ��o���Ă���A���̓_�ɂ͗��ӂ��Ă����K�v������ƍl������B
�܂��A���\���ɏq�ׂ��ʂ�A����̔��\�ł͎��ʂ̓s���ɂ��A���[�h�E�t�@�~���[�Ƃ����P�ʂ�p���鎖�̓K�ؐ��ɂ��Ă͊������Ă����B�{�R�����g�ŗv�_�݂̂܂Ƃ߂Ă����ƁA��e�I��b�m���̑���ɂ����āA���[�h�E�t�@�~���[�͓K�ȒP�ʂł���ƌ�����B���̂Ȃ�A��n�B�x�ȏ�̊w�K�҂́A���̌�`���̒m����L���Ă���A�`����Ӗ��Ɋ�Â��֘A������K���I�Ȑڎ��ɂ���`���i�Ⴆ�Aproduce�Ƃ����P�ꂩ��� producing, producer, product, production, productive���j�𗝉��E�g�p�ł��邩��ł���B�X�ɁA���[�h�E�t�@�~���[�͐S������w�I�Ɍ����I�P�ʂƂ��������x�����鑽���̐�s���� (�Ⴆ�ABertram et al., 2000;
Bertram et al., 2000; Nagy et al., 1989)�����݂���B�����āA�{�����ŗp����14�i�K��1000��̃��[�h�E�t�@�~���[�̒P�ꃊ�X�g�́ABauer & Nation (1993)�̎ړx�ł�level 6�ɑ������A�K�����C�p�x�C���Y���C�\�����̊�����Ă���Ƃ�������The Instrument�̐߂ʼn������Ă���B
�ȏ�̂悤�ɕ��@�E���ʋ��ɗǍD�Ȗ{�����ł͂��邪�A����̋^��_�E���P�_��������B��_�ڂɁA��ɖ{�_���̍\����̖��Ƃ��āAParticipants�̐߂ɂ����ē��{�l���͎҂�TOEFL�̓_������ʃO���[�v�݂̂���������Ă��炸�A�{���I���ʂ�Figure 3 (p. 110)�Œ��ʁE���ʃO���[�v�̑�܂��ȓ_���͈̔͂�������Ă���݂̂ł���B�u���{�l�̋��͎҂����TOEFL�̃X�R�A�𗘗p���鋖�����Ă���v�Ƃ����|�L���Ă����ɁA��ʃO���[�v�͏ڍׂ��q�ׂĂ���̂ŁA���ʁE���ʂɂ����l�̏ڍׂ��K�v���ƍl����B
��_�ڂɁA�{������19���̉p����b�҂���Ȃ�NSE�O���[�v��p�����Ӌ`�͔�r���Ǝv���邪�A���b�҂̎�e�I��b�m���ƌ����Γ��R�Ȃ���i�{�������͎҂�90%�ȏ���߂����b�҂Ɣ�r���āj���ɍ����A�������̐߂ł̖{�������͎҂�7�i�K�̕��ނɕ��̉e���≽�炩�̃m�C�Y�i��ʂ̕��ނ̎�e�I��b�m���̃T�C�Y������b�҂ɂƂ��Ĕ��ɍ������ɂȂ��Ă���\�����j���y�ڂ��Ă���\�����l������B
�O�_�ڂɁA1000��p�x���x������14000��p�x���x���̌�b�T�C�Y�́i���ɔ���b�҂ɂƂ��āj���ɑ傫���̂ŁA���̉��ɂ��ďڂ������y����߂����݂��Ă���ƁA���D�܂����Ǝv����B�܂��A����̓��{�lEFL�w�K�҂̉ł́A���m�ȉp��ؗp��̉e���i�Ⴆ�Abeagle��caffeine���X�j������Ă���A���̓_������̌����łǂ������Ă��������d�v�Ȃ͂��ł���B
O�f
Toole, J. M., & King, B. (2011). The deceptive mean: Conceptual scoring of
cloze entries differentially advantages more able readers. Language Testing, 28, 127-144.
�� Abstract
�@�N���[�Y�e�X�g�̍̓_�@�Ƃ���conceptual coding (�K��@) ��exact
coding (����@) �����Ó����������ƌ����Ă������A���̗��R�Ƃ��Ă͓K��@��poor reader�ɂƂ��Č����ł��邩��ƍl�����Ă����B�{�����ł�447���̒��w����3�̃N���[�Y�e�X�g�ɉ��A���ꂼ���2��ނ̍̓_�@�ō̓_�����B����ꂽ���ʂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B(a) �K��@�̓N���[�Y�e�X�g���_��L�ӂɑ���������A(b) �K��@�ɂ��_���̑����́A�n�B�x�̍����ǂݎ�̕����傫���A(c) �K��@�͏n�B�x�̍����ǂݎ肪��Փx�̒Ⴂ�e�L�X�g��ǂނƂ��ɈقȂ�e����^����B
�� Introduction
�� �N���[�Y�e�X�g: �p�b�Z�[�W���畡���̌ꂪ�폜����A�e�X�g�҂͋ɓK�Ȍ�߂�悤�Ɏw�������B
�� �̓_���@
�E �hstrictly�h: �폜���ꂽ��Ƃ܂�����������łȂ��Ɖ��_���Ȃ��B�̓_���e�ՁA�q�ϓI�B
�E �hconceptually�h: �T�O�I�E���@�I�ɓK�ł���Ή��_����B�n�B�x�̒Ⴂ�ǂݎ�ɗL���B
�� A short history of
cloze
�E
���݂̃N���[�Y�e�X�g�́A�e�L�X�g�̈�ʓI�ȓǂ݂₷���A�������₷���𑪂�w�W�Ƃ��ĊJ�����ꂽ���̂ł���B�܂��A�w�K�҂̏n�B�x�𑪒肷�邽�߂ɗp�����邱�Ƃ�����B
�E
Spolsky
(2000): �N���[�Y�e�X�g�͗��p���₷�����A�hfad (�C�܂����)�h �ł���B�Ó��������߂邽�߂ɂ́A�K��@�̕����K�ł���B
�E
Oller
and Jonz (1994): ����@�́A���̂�荢��ŐM�������Ⴍ���Ԃ̂�������@�Ɠ������x�ɁA�e�L�X�g��ٕʂ��邱�Ƃ��ł���B
�E
Kobayashi
(2002a): ����@�͓K��@�ł͔��f�����悤�ȓǂݎ�̗����������Ȃ����Ă��܂��B
�E
�N���[�Y�e�X�g�̌`�����l�X�ł���A����̕i�����폜������� (Bachman, 1985)�A�Ƌ̊Ԃ��L���Ƃ���� (Kobayashi, 2002a)�A�폜���ꂽ��̃��X�g�����I�Ԃ��� (St-Germain, 2000) �Ȃǂ�����B
�� Scoring reader entries
in cloze deletions: An enduring quandary
�E
�K��@�͎��Ԃ�������̓_�@�ł��邾���łȂ��A��ς������Ă��܂��Ƃ������Ƃ͔F�߂��Ă�����̂́A�lj������ȓǂݎ�ɂƂ��Ă͌���@�����L���ɂȂ�B
?��s�����̑������P���ɕ��σX�R�A���r���Ă���B
�E
Taylor
(1953): �T�O�I�ɍ����Ă�����̂ɔ����̓_����^����Ƃ����̓_�@��p����ƁA�̓_�̔\���͏オ�邪�e�X�g�ٕ̕ʗ͂͏オ��Ȃ������B
?��ɑ�������������@���x�����錋�ʁB���̍̓_�@���瓾���錋�ʂƂ̑��ւ������B
�������A���ւ͑Ó�����ۏ�����̂ł͂Ȃ��A���ۂɂ͓K��@�̕������ڕٕʗ͂������A�ǂݎ�̏n�B�x��L�ӂɗ\���ł��� (Oller, 1972)�B
�E
�ߔN�̑����̌����œK��@�̕����D��Ă���Ƃ������ʂ������Ă�����̂́A�K��@���lj������ȓǂݎ�ɂƂ��ėL���ɂȂ闝�R�ɂ��Ă͖��炩�łȂ��B
�� Objectives of the
present investigation
�̓_�@�̈Ⴂ���N���[�Y�e�X�g�ɂ�����ǂݎ�̃p�t�H�[�}���X�ɗ^����e���ɂ��Č�����B�܂��A��s�����̕��͂ł̓e�X�g���_�̕��ς��r����ɂƂǂ܂��Ă������A�{�����ł���ʉ����@���f�� (����`��A���f���̈��) ��p����2�̍̓_�@�̊W����������B
RQ1: ��ʉ����@���f���́A�P���ȕ��ς̔�r�����A2�̍̓_�@�̈Ⴂ����薾�炩�ɂł��邩�B
RQ2: 2�̍̓_�@��p����ƁA�ǂݎ�̓��_�p�^�[����parallel�Ȍ��ʂɂȂ�̂��B
RQ3: ���_�̃p�^�[���̓e�L�X�g�̈Ⴂ�A�w�N�A���ʁA����I�w�i�A���Ȃɑ��鎩�M�x�̉e�����邩�B
�� Method
�� Student sample
�E ���Ȃ̎��Ƃʼnp����g���Ă���I�[�X�g�����A�̒����w�Z�̐��k447�� (7�N��125���A8�N��109���A9�N��124���A10�N��89��)
�E 150���͉p��݂̂�b���ƒ�A297���͑��̌����b���B
�� Test generation
���͎҂͖�300��̃p�b�Z�[�W��3�lj�����B3�̃p�b�Z�[�W�͓��e�͓��������A���ꂼ��قȂ�e�L�X�g�ł���B5�ꂨ���Ɍ���폜�����B
?cloze�̊Ԋu���L�����Ă��\���������߂Ȃ� (Aborn et al., 1959)�B�܂��Acloze�̊Ԋu��3��ȓ����ƁA���݂ɉe����^���Ă��܂� (MacGinitie, 1960)�B
�� Study design
�@ ���e�������ŁA�ǂ݂₷�����قȂ�3�̃e�L�X�g��p�����B
�A �n�߂�1�����c����5�ꂨ���Ɍ���폜�B
�B 7~10�N����Ώۂɂ����������s�����B
�C �e�e�X�g�͌���@�ƓK��@�̗����ō̓_���ꂽ�B
�D �e���͎҂�improvement
score (2�̍̓_�@�ɂ�錋�ʂ̍�) �́B2�̍̓_�@�̊W���̓O���t������A��ʉ����@���f���ɂ���ĕ��͂��ꂽ�B
�� Test scoring
�E �{�����̓K��@�́A���e�L�X�g�̈Ӗ���ۂ��Ă�����X�y���̌���@�I�Ȍ��͍l�����Ȃ��A�Ƃ������@���Ƃ����B
�E 1��ȏ�̌�����Ă����e���K�ł���Ή��_�����B
�E ��ϐ��ɂ��e���̈Ⴂ���ŏ����ɂ��邽�߁A�S�Ă̋��͎҂̉��l���̓_�����B
�� Test reliability: Cronbach�fs
�� �͂ǂ���̍̓_�@�ł��\���Ȓl�ł����� (�� = .73~.89)�B�M�����W���͌���@ < �K��@
�� Statistical techniques
�E �e447�����̃f�[�^���O���t�����A2�̍̓_�@�̌��ʂ��r�����B
�E �K��@�ł̓��_���]���ϐ��A����@�ł̓��_��Ɨ��ϐ��Ƃ��āA�K��@�ł̓��_����ʉ����@���f�� (GAMs: Generalized
additive models) �ɂ���ă��f���������B
�� Results
�E Figure 1 (��): 3�S�Ẵe�L�X�g�ŁA2�̍̓_�@���r�������ʁB
�E Figure2 (�E): �e�e�L�X�g���Ƃ̌��ʁB
<�O���t�ȗ���
�E 2�̍̓_�@�̍��͓��_�������Ȃ�ɂ�đ傫���Ȃ�B
�E �Ȑ����W�����`���f���Ɣ�r���Ă��A���v�I�ɗL�ӂł����B
?����@�̓��_�͓K��@�̓��_��L�ӂɗ\���ł���B
�� Figure 1��GAM�̌��ʂ���A�n�B�x�̍����ǂݎ�͓K��@�̕����L���ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B
�� �K��@�̓��_�̌��ʂ́A�P�ɕ��ς̔�r�����Ō���ƌ��ʂ��c�߂��Ă��܂����Ƃ����� (���ς̔�r�����Ō���ƁA�K��@�͋��͎҂�ٕʂł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂�)�B
�� ���ʂ���ʌQ�E���ʌQ�ŕ�����t������s���Ă݂Ă��A��ʌQ�̕����K��@�ŗL���Ȍ��ʂɂȂ��Ă���B
�� Figure2: text2���ł��K��@�ɂ��̓_�̉e�����Ă���Btext1��text3�ł͂��܂�ς��Ȃ�
?�̓_�@�̈Ⴂ�̓e�L�X�g�̓ǂ݂₷���̉e������߂�B
�� ���̑��̗v��
�Ƃʼnp���b���w�K�� > ���̌��b���w�K�ҁA���q > �j�q�A���w�N > ��w�N�A�e�L�X�g���e�̒m���Ɋւ��Ď��M�����鐶�k > ���g�̂Ȃ����k
�� Interpretation
��
�̓_�@�ɂ�鍷�́A�lj��n�B�x�̍����ǂݎ�̕����傫��
?�n�B�x�̍����ǂݎ�́A��b���L�x�ł��邽�߃N���[�Y�e�X�g�̑I�����ƂȂ�ꂪ�n�B�x�̒Ⴂ�ǂݎ���������B
��
���ɁA�n�B�x�̍����ǂݎ肪��Փx�̒Ⴂ�e�L�X�g��lj����鎞�A�̓_�@�ɂ�鍷���傫���Ȃ�B
��
�����̐�s�����ł́A����@�ƓK��@�͕��s�̊W�ɂȂ��Ă���ƍl�����Ă������A�{�����ł͓_�����オ��ɂ�Ă��̍����傫���Ȃ邱�� (Figure 1)�A���_�������w�K�҂̓e�L�X�g�̈Ⴂ�ɂ���č̓_�@�̉e�����₷������ (Figure2) �����炩�ɂȂ����B
�� Implications for
scoring cloze tests for different purposes
��
�K�ȍ̓_�@�́A�e�X�g���ǂ̂悤�ȖړI�ōs�����ɂ���ĕς���Ă���B
��
�ǂݎ�̉��ʂɕ��͂�����A�ǂ̂悤�Ȍ������Ă��邩������ꍇ�́A�K��@���K�ł���B
��
���͎҂������N�t�������������K��@���K���Ă���B
?�K��@���ƌ���@�������U���傫���Ȃ�̂ŁA�e�X�g�쐬�҂��ǂ̊�_�Ń����N�t�����邩�����߂₷���B
��
�������̃e�L�X�g�̗������₷�����N���[�Y�e�X�g�ő��鎞�͌���@���K���Ă���B
�� Conclusion
�� �O���t�ƈ�ʉ����@���f���̌��ʂ́A�]���̕��ς̔�r�Ƃ����悻��v���錋�ʂ��o�����A�]���̃A�v���[�`�ł͖��炩�ɂȂ�Ȃ������_���𖾂��ꂽ�B
�� �{�����ł́A�K��@���N���[�Y�e�X�g�̍̓_�@�Ƃ��đÓ��ȗ��R�ɂ��Đ������邱�Ƃ��ł����B
Comments
�@�{�_���̍Ō�ɁA�N���[�Y�e�X�g�̍̓_�@�̓e�X�g���ǂ̂悤�ȖړI�ōs�����ɂ���ĕς��Ǝ�������Ă����B���������āA�̓_�@�̓e�X�g�̑Ó����ɂ��ւ���Ă���\�����l������B�w�K������b�m���E���@�m���𑪒肷�邽�߂ɍ쐬�����e�X�g�ł���A�e�L�X�g�̒P������̂܂ܐ����Ƃ��錴��@���K�ł��낤�B����ŁA�ǂݎ肪�e�L�X�g�́u���e�v���ǂꂾ���[���������Ă��邩�𑪂邽�߂̃e�X�g�ł���A�K�������{���Ɠ����P����o���Ă���K�v�͂Ȃ��A�e�L�X�g�̓��e�ɍ��v���Ă���Ή��_����K��@���K���Ă���ƌ�����B�e�X�g�̑Ó������m�ۂ��邽�߂ɁA�e�X�g�̍쐬�������łȂ��A�̓_�̕��@���l������K�v������B
�܂��A�{�����̈Ӌ`�͒P�ɃN���[�Y�e�X�g�̍̓_�@�Ƃ��Ă̌���@�ƓK��@�̑Ó������������Ƃ����_�����ł͂Ȃ��B�{�����ł̓e�X�g���_�͂�����@�Ƃ��āA�P�ɂ��ꂼ��̕��ϓ_�E���U���猋�ʂ����邾���łȂ��X�̃f�[�^�f������悤�ȕ��͕��@ (e.g., ��ʉ����@���f��) �ɂ���ĕ��ϓ_�̔�r�����ł͌����Ă��Ȃ��f�[�^�̓������ώ@���邱�Ƃ��ł��A�X�̃f�[�^���L����Ӗ����傫���Ȃ�ƍl������B�{�_���̃^�C�g���� �hthe deceptive
mean�h �Ƃ���悤�ɁA�e�X�g�f�[�^���������͒P�ɕ��ς̌��ʂ����邾���łȂ��l�X�ȓ��v�@����̃A�v���[�`���d�v�ɂȂ�Ɗ������B
���{�����⑫�� ��ʉ����@���f��
(GAM: Generalized Additive Model)�@
�E ���v�\�t�gR (R-Deveropment-Core-Team, 2004)
�ɂ���Čv�Z�\�B
�E 2�v���̊W����g�` (wiggly) �̃O���t�ŕ\���B
�E ���`���f�����ƌ��ʂ�overfitting���Ă��܂����Ƃ����邪�AGAM��p���邱�Ƃɂ���Ă����h�����Ƃ��ł��A�X�̃f�[�^�̊W������萸�k�Ƀ��f���ɔ��f���邱�Ƃ��ł���B