




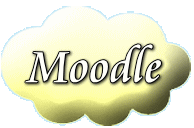


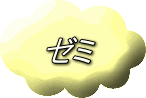
     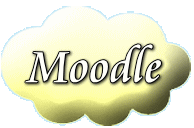   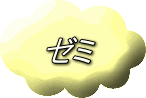 |
Wei, L. & Moyer, M. G. (2008)
PART
I: Researching Bilingualism and Multilingualism (pp. 3-31)
1.
Research Perspectives on Bilingualism and Multilingualism (pp. 3-17)
n bilingualism/multilingualism�i�ȉ�BM-L�j�͍��␢�E�̓���ł���A�����̋^���S�������݂���i��F1�ȏ�̌�����Ɋw�Ԃ��Ƃ͎q���̒m���̔��B�ɍv�����邩�H�j�B�����͉Ȋw�I��@�ɂ��𖾂��邱�Ƃ��ł���B
n BM-L�ɂ͎Љ�I�ȑ��ʂƌl�I�ȑ��ʂ����邪�A����͕�������̂ł���B�܂�A���I�ɂ�BM-L�ȍ��ł��i�Љ�I�j�A�����ɂ���l�̓��m�����K���ȏꍇ������i�l�I�j�A�t�̏ꍇ���܂����݂���B
n BM-L�ɂ��Ă̌����̗��j�͌Â��A17���I�ɂ܂ők�邪�A��v�Ȍ�������Ƃ��Ēn�ʂ�z�����̂�1970�N��ɓ����Ă���ł���B��ɁA����3�̊ϓ_���猤�������B
(1) ����w�I�ϓ_�ilinguistic perspective�j�F
�l�ɂ����āA��������̌���m���i��b�╶�@�Ȃǁj���ǂ̂悤�ɑ��݂��A�p�����A�܂��l�������̂�����Ƃ��Ē����Bcode-switching�̌�����one-system-or-two�̋c�_�i���@���b�͊e���B�i�K�ɂ�����1�̃V�X�e���Ȃ̂��A2�Ȃ̂��j�ȂǁB
(2) �S������w�I�ϓ_�ipsycholinguistic perspective�j�F
�L�q�I�ȁi1�j�Ƃ͈Ⴂ�A�����I�E�Ȋw�I��@�Ńo�C�����K���̍s����������悤�Ƃ���B�o�C�����K���̌�b-�T�O�W��������Concept Mediation
Model��Lexical Association Model�ADifferential Access Hypothesis?�Ȃǂ��J�����ꂽ�̂����̕���B
(3) �Љ��w�I�ϓ_�isociolinguistic perspective�j�F
������g�p�ƃo�C�����K���̃A�C�f���e�B�e�B�[�̊ւ����B�o�ϊK���E���ʁE�o���ȂǗl�X�ȎЉ�v�����l���ɓ���邪�A���m�����K���I�Ȑ���ρithem��us�j���e����^���₷���̂������ł���B
n �����̌�������̘g���āA��I��BM-L�𑨂���ꍇ�̖��͈ȉ���4�_�ł���B�@�u����v�̒�`�����삲�ƂɈقȂ�\��������A�A������@�̈Ⴂ�ɂ��A���w�╪��̒������ʂ������ɂ͉��p�ł��Ȃ��\�������邱�ƁA�B���w��I�ȁimultidisciplinary�j�������K�����������l�ς̍��V�iinnovation�j�ɂ͂Ȃ�Ȃ����ƁA�C���p�I�ȁu���p�����iapplied
research�j�v�ɌX�|���A�u��b�����ibasic research�j�v���Ȃ�������ɂ���X�����݂��邱�ƁB
2.
Research as Practice: Linking Theory, Method, and Data (pp. 18-31)
2.1 Introduction
n �{�߂ł͌����̎�@�ɂ��ďq�ׂ邪�A2.2�ł̓o�C�����K���f�[�^�̓����ɂ��āA2.3�ł͔ᔻ�I�E���͓I�v�l�̂��߂̎���ɁA2.4�ł͌����ߒ����\�������{�I�v�f�⊈���ɂ��Ă��ꂼ�ꌾ�y����B
2.2 Data and Knowledge on
Bilingualism and Multilingualism
n BM-L�̌���m���f�[�^�̓��F�͈ȉ���4�_�œ����Â�����B
(1) �`����\���Ƃ��Ă̌���F����ώ@�����A����̕��@���ۂɒ��ځB���ʉ������ĕ��́B
(2) Competence�Ƃ��Ă̌���F�ώ@�s�\�Ȍ���m���𑪒�B�팱�҂̒����┻�f�Ɋ�Â��A���@���ۂ��f�[�^�ɗp����B
(3) �Y�o�ƔF�m�Ƃ��Ă̌���F�]���̌��ꏈ���̎d�g�݂����ꂽ�����ɂ���Ė��炩�ɂ���B
(4) �Љ�I�s���Ƃ��Ă̌���F�Љ�I�W��z����i�Ƃ��Ă̌���ɒ��ځB�Љ�I�E�����I�E�����I�����ɂ����錾��I�f�[�^����ȑΏہB
2.3 Questions for Critical
Thinking
n ���T�[�`�͏n���̕K�v�Ȋ����ŁA�ȉ���5�̎���͌����v��𗧂Ă�ۂɖ𗧂��̂ł���B
(1) ���Ȃ�������������BM-L�̌��ۂ͍L��������Ɖ��ł����H
(2) �ǂ��������f�[�^���C�ӂ�BM-L���ۂ��������̂ɂӂ��킵���ł����H
(3) ����̓I�ȃe�[�}�i��intellectual puzzle�j�͉��ł����H
(4) ���̌����̖ړI�i���������ʂ̎��H�ւ̉��p�\���j�͉��ł����H
(5) �ǂ̂悤�ȗϗ��I�z�����K�v�ł����H
2.4 Linking Research
Questions, Theory, Method, and Data
n ���T�[�`�͕K���������̎菇�Ŏ��{�������̂łȂ��A�_�C�i�~�b�N�ȃv���Z�X�Ȃ̂ŁA�����҂͕K�v�ɉ����ėՋ@���ςɁA��������E���_�E�������@�E�f�[�^�E���͂Ȃǂ̈�A�̌����ߒ��ip.26��Figure
2.1�Q�Ɓj�̍ĕ]�����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
n �g�s�b�N��I�����邱�Ƃ͏d�v�ł���B����ɂ��u��������/�ł���Ώۂ͈̔́i�lor�O���[�v�j�v��u�����̎�ށi�ʓIor���I�j�v�����܂��Ă��邩��ł���B
n �����ihypotheses�j�⌤������iresearch questions�j�𗧂Ă�ɂ́A�g�s�b�N�����߂邱�Ƃ��̗v�ł���B�����ɂ����邱�Ɠ������̕��@��1�ł��邪�A���ۂɒ������s�����Ƃʼnۑ肪������ꍇ������B�����̏����i�K�ɂ����ẮA�����ł������⌤����������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
n BM-L�̌����ł͗l�X�Ȍ������@����������̂��]�܂����B���_����ɂ����������@�ɂ�2��ނ���B1�́u������㈖@�ihypothetico-deductive
way�j�v�ƌĂ����̂ŁA�X�̎��ۂ�������邽�߂̉��������O�ɗ��Č�������́B����1�́u���_�\�z�itheory building�j�v�ƌĂ����̂ŁA�ώ@���ꂽ�X�̎��ۂ��畁�ՓI�������ꍇ�ł���B��҂͋A�[�I���@�ł���B
n �f�[�^���W�ɂ����ďd�v�Ȃ̂͂��̃f�[�^���A�i1�j��ʉ��ł��邩�igeneralizable?�j�A�i2�j�M���ł��邩�ireliable?�j�A�i3�j�Ó����ivalid?�j��3�_�ł���B
n �f�[�^���W�����ꂽ��A��ɑ������͂̂��߂Ƀf�[�^�����ď�������K�v������B���̉ߒ��ł�coding�␔�ʉ��Ȃǂ��s����B
n ���ʂ̒��@�͌����̖ړI�ɂ���ĕς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ړI�����ɃA�J�f�~�b�N�ł���Ύ�@�ׂ̍�����v������邵�A���ԓ��ł̃��r���[�ł���Ηv�_�̔����ł��������낤�B
2.5 A Summary of Research as
an Ongoing Process
n ���̂悤�Ƀ��T�[�`�ɂ͊��K������B�䂦�ɂ��̎菇�ɂ��Ă͓���ݐ[���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
PART
II: Procedures, Methods, and Tools (pp. 35-72)
3.
Types and Sources of Bilingual Data (pp. 35-52)
n
bilingualism/multilingualism�i�ȉ�BM-L�j�̌����ŕK�v�ɂȂ�f�[�^�͖ړI�ɂ��قȂ�B���̏͂ł̓f�[�^�̍̏W���@��f�[�^�̏W���ɍl�����ׂ������ɂ��Č��y����B
(1)
Census
and Sample Surveys�imacro-level�j�F
��Ē����icensus�j�͑ΏۂƂ���W�c�S���ɁA�T���v�������isample surveys�j�͑ΏۂƂ���W�c���C�ӂɒ��o������\�̂ɑ��Ē������s�����Ƃ������B�����I�����EYes/No����E5/7���@�E�Z���t���|�[�g�����p�����邪�Acode-switching�Ȃǂ̍s���ibehavior�j�̒����ɂ͌������A��ɘb�҂̑ԓx�iattitudes�j�ׂ邱�Ƃ��ړI�B
(2)
Questionnaires�imeso-level�j�F
�팱�҂̎Љ��I���isociolinguistic profile�j���̎悵�A��̕��͂�s���̗\���ɖ𗧂Ă邱�Ƃ��ł���B�ȉ���4�̏�܂܂��B������j�i��F���w�K���n�߂����j�A����I���i��F�Љ�I�����ɂ��ǂ���̌����I�����邩�j�A����x�z�i��F���퐶���łǂ���̌��ꂪ�D�����j�A����ԓx�i�ǂ���̌�����Y�킾�Ɗ����D��ŗp���邩�j�B
(3)
Observations�imicro-level�j�F
�ώ@�ɂ���Ăǂ̂悤�ȏW�c���ʂ������ړI�ɍ����������ɂ߂邱�Ƃ��ł���B���R�ȉ�b���ώ@����ɂ͌����Ҏ��g�����̉�b�ɎQ�����邱�Ƃł���iparticipant observation�j�B����ɂ��code-switching�̎�ށiintra-,
inter-, extrasentential�j���킩��Blanguage diary���������A�ώ@����̂�1�̕��@�ł���B
(4)
Matched-Guise Tests�F
(5)
Spontaneous
and Semi-Spontaneous Conversations�F
�����I��b�͎��R�Ȃ��̂ŁABM-L�̌����ɂ͍œK�ł���B��b���r�ꂪ����������A���܂��i�܂Ȃ��Ƃ��ɂ́A�G��e�[�}��^�����肵�ĉ�b��U�����邱�Ƃ��\�ł���B���̏ꍇ���J�n����10-20��������Ύ��R�ȉ�b�ƂȂ�B�����N�����itranscription�j�Ȃǂ̎�Ԃ��������ρA�ړI�̌���\�����ώ@�ł���ۏ��Ȃ��Ȃǂ̒Z��������B
(6)
Elicited
Information in Experimental Settings�F
�����I��b�͑���ȘJ�͂�v����̂ŁA���_�≼���Ȃǂ����m�ł���ꍇ�ɂ́A�����ɂ���ĈӐ}�������b�������悭�����o���ielicit�j���Ƃ��\�ł���B����1��sentence
repetition task�ł��邪�A����͕��@�I�Ɍ����܂ޕ��������A�팱�҂����̌��ɋC�Â��C�����邩�ǂ������ώ@����Ƃ������̂ł���B
(7)
Written
Sources: Books, Song Lyrics, and the Internet�F
�o�C�����K���̌���f�[�^�͒����ō̎悵�����̈ȊO�ɂ����݂���B�{�A�̎��A�V���A�L���A�C���^�[�l�b�g�ȂǂɌ����錾������p�ł���B
4. Bilingual
Speech Data: Criteria for Classification (pp. 53-72)
n
�o�C�����K���f�[�^�ƈ���Ɍ����Ă��`���E����i�S������w�E���@�ESLA���X�j�Ƃ��ɗl�X�ŁA��X�͒��Ӑ[�����ނ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
n
���m�����K���f�[�^���l�A�o�C�����K���f�[�^���l�X�ȃ��x���i��b�I�E����I�E���C�I�E�`�ԓI�j�ŕ��͂��ł���B�Ⴆ�A���C���x���ł͂Ȃ܂�Ȃǂ����̑ΏۂƂȂ�B
n
���삲�Ƃň����f�[�^���ω��B���̗��ɒ[�ɂ���u�S������w�v�Ɓu�Љ��w�v�̕���ł́A�O�҂ł͌��ꏈ���ߒ��̑��ʂ��ł��邾���������A��҂ł͂ł��邾������̂܂܂̃f�[�^�悤�Ƃ���B
n
���ۂ̃o�C�����K���f�[�^�͕��G�ŁAcode-switching�iCS�j��borrowing���ǂ���ʂ��邩�ACS��code-mixing�̈�`�Ԃɉ߂��Ȃ��ȂǁA�p��ɂ��Ă̗l�X�Ȓ�`������Ă����i�ڍׂ�Milroy & Muysken, 1995; Li Wei, 2000���Q�Ɓj�B
n
�p��̏ڂ����c�_�͂Ƃ������ACS�͒ʏ�single-word,
multi-word, inter-/intrasentential, turn-switching �ɂ��������ςɕ��ނ���邪�A���̋�ʂ�����ꍇ������B
n
CS���͂́u���@�I�ȃA�v���[�`�v�ł́A����iconstraints�j���͂��ߗl�X�Ȋϓ_�ŕ��͂��s�Ȃ��A�������@���_��~�j�}���X�g�̗�����Ƃ�҂�����BMyers-Scotton�i1997,
2002�j��Matrix Language Frame�͊v�V�I�ȍl�������������A�S�Ă�CS�ɒP��̕��@�����݂���Ƃ����咣�ɂ͖������������B
n
CS���͂́u�Љ��I�A�v���[�`�v�ł́A�̈�i�����@���Ȃǂ̎Љ�I��ʂ�CS���N�邩�j��CS�̗L�W���i�L�W�ł��遁���ʂȂ瑽���h����ɃX�C�b�`�����ʂŏ����h�����p����j�̌����Ȃǂ��s���BCS�̔\�͂ƎЉ�ɂ�����l�b�g���[�N�\�z�̊W���q�ׂ����҂�ɂ��Social Network Theory�����̕���ɂ�����CS������1�B
n
CS���͂́u��p�_�I�A�v���[�`�v�ł́A���t�̎��Ӗ��ȏ�̖����ɂ��Č�������BCS��preference
organization�̖��������i��CS�ɂ�茾����X�C�b�`���Ăق����Ƃ����M���𑗂�j�Ƃ����̂����̕���̍l�����B
n
�ȏ�̓o�C�����K���f�[�^�̕��G���������Ă���B�]���Ď��̂悤�ȕ��͎菇���Ó��ł���B
1.
����I�Ȋϓ_���甭�b�̕��ނ�L�q���s��
2.
���b�����ꂪ�N�����A�ł��邾�������̕����i�n��⌾��n�ʁj�Ɋ֘A�t����B
3.
���G�ȎY�o�f�[�^��b�҂̌���\�͂�ԓx�A��b�̓����Ɋ֘A�t����B
�����ėl�X�ȕ���̃f�[�^��v�����l���ɓ���邱�Ƃ͑厖�ł���B