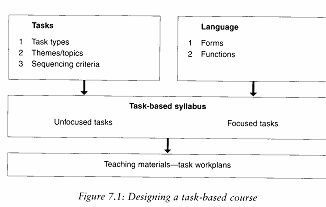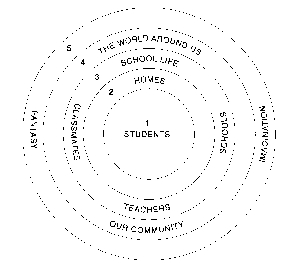研究会トップに戻る
5/9 5/23 6/20 7/11 7/25 8/21 9/5 9/26 10/10 10/31 11/14 11/21
12/5 12/19 1/16 1/30 2/6 2/20 3/16 4/9前 4/9後
Ellis, R. (2003).Task-Based Language Learning and Teaching.
Oxford: Oxford University Press.
2008/05/09
Chapter 1, pp. 1-17.
1 Tasks in SLA and language pedagogy
■Introduction
第二言語習得の研究者や言語教育者は、学習者の言語使用のサンプルを引き出し、研究者にとっては、どのように習得が生じているのか、教育者にとっては、どのような学習が言語習得に適しているのかを調査しようとしている。また、サンプルには、その抽出を促す材料によりサンプル自体の質が変わり、コミュニケーション活動により引き出されたサンプルの場合、L2学習者のメッセージ運用の仕方を反映する傾向にある。そこから、学習者が中間言語をどのように構築・再構築するかが明らかになる。また教育者は、L2学習者がそのような状況を経験しない限り流暢かつ効果的なコミュニケーションは生じないことを認識している。そこでタスクが用いられる。第二言語習得研究及び教育においてタスクが中心に位置づけられ、そのような研究から様々な問題提起が生じている。
本章では、タスクの定義、また焦点化されたタスク・焦点化されていないタスクの重要な区別に関して議論する。タスクに関する記述の概要を発展させ、実際のタスクについての記述で応用する。後半では、第二言語習得の研究者・言語教育者の視点からタスクを観察し、重要な問題点を総覧する。
■Defining a 'task'
Figure 1.1では、様々な論文におけるタスクの定義を紹介している。
□Scope
タスクはメッセージ運用を重視、エクササイズは、型に焦点を当てた言語使用である。しかし目的は、両者とも言語教育であり共通している。
□Perspective
Perspectiveとは、タスクの捉え方がタスク制作者の視点からか、もしくは協力者の視点からかということである。例えば、タスク制作者が意味に重点を置いたタスクをつくったとしても、学習者はコミュニカティブな言語使用というよりもむしろ「見せかけ」の言語使用を行っているかもしれない。そうした意味で、タスクに対する捉え方が両者で異なる。しかし、今回はタスク制作者という視点でここでは記述する。
□Authenticity
タスクが現実世界の言語使用と一致しているかどうか。
□Language skill
タスクを行うことで、どのような言語能力が測られているのか。ここでは、タスクは4つの技能を含むものであるとしているが、本書の主要目的はtaskに基づく研究及び教育であるため、内容はオーラルタスクが特に強調されている。
□Cognitive processes
タスクを行う上で関係するプロセスの性質。特に認知的に行われる処理を取り上げている。選択、理由付け、分類、情報処理、情報の転換などがそれに当たる。
□Outcomes
タスクの素性の1つには、単に言語使用なだけでなく、明確な成果があるとしている。つまり、現れた言語使用の意味がタスクの指示通りに進行しているかという点である。outcomeとaimのちがいは、前者が学習者がタスク達成時にできていることであり、後者がタスクの教育目的、つまり意味に焦点を当てた言語使用を引き出すということである。それゆえ、outcomeが達成できても、aimが達成できていないということがある。
(例:spot-the difference task→違いは見つけられても、言語運用していないという場合)
■Criterial features of a task
【タスクの基準となる素性】
1 A task is a workplan.
2 A task involves a primary focus on meaning.
3 A task involves real-world processes of language use.
4 A task can involve any of the four language skills.
5 A task engages cognitive processes.
6 A task has a clearly defined communicative outcome.
→最も重要な素性は、2であり、続いて3・6である。1・4・5はエクササイズのような活動にも含まれている。
Figure 1.2は言語教育活動の例
[Activity1, 'A dangerous moment']
過去の経験を順序だてて説明するときに、学習者はより自発的に話そうとする。この活動では、タスクの全ての特徴が観察できる。ただインプットがないため、学習者が持つ既存のストーリーを考えなければならない。
[Activity2, 'The same or different']
言語教育下では多く使われているタイプのものである。これもまた、全てのタスクの特徴を網羅している。
[Activity3, 'New students']
これには、3つの活動が含まれている。まず、学習者が4人の異なる人々の情報を聞き、空欄部分に情報を埋めていく。次に、表の下にあるパッセージの空欄を情報を元に埋めていく。そして最後に、クラスメイト自身に質問を行うというものである。ここでは、一番初めに行う活動が、タスクの特徴を全て含んでいる。しかし、2つ目の活動部分がエクササイズに近いタスクになっている。
[Activity4, 'Asking for help']
これは、cue-cardを用いた活動であり、タスクの特徴のいくつかが含まれている。特に、発言の意味が前もって決められている点で、メッセージ性に重点が置かれていない。それゆえ、このような活動はタスクとして成り立たない。
[Activity5, 'Going shopping']
この活動はさらにエクササイズ的なものである。提示された道具のみを用いて行われるため、Authenticityや、認知的処理という点でも、タスクとしての特徴に欠けている。しかし、この活動も、情報を分割し、インフォメーションギャップを生じさせることで、よりタスクに近い活動になることを示唆している。
【タスクの定義】
タスクとは、命題に対し、適切で正確な内容を運用できるかに関しての評価をもたらせるために、学習者に実用的な言語処理を行わせる作業計画である。このために、タスクは意味に最も注意がいくようにし、またタスクのデザイン上、特定の形を学習者に選ばせるかもしれないが、学習者に彼らが持つ言語資源を使わせる。タスクは現実世界でみられる言語使用に直接的もしくは間接的に類似した活動を意図している。そしてタスクは、生産的または受信的であり、書きことばや口頭での言語使用や認知処理も用いられる。
■Unfocused and focused tasks
Figure1.2にある焦点化されていないタスク(タスクを通して観察したい点を明示していない活動のこと)は、学習者に言葉の形式を選びやすくするが、特定の型の使用をもくろんでいるわけではない。
一方で焦点化されたタスク(観察したい点を明示しているもの)は、学習者を誘導し、特定の言語素性の処理を行わせようとしている。(特定の文法構造など)
焦点化されたタスクは2つの目標を持つ:
① コミュニカティブな言語使用を刺激する
② 特定の素性の使用を目標にしている
・焦点を達成するための2つの主な方法
①タスクをつくる際、学習者が特定の言語素性を用いることで、唯一それが達成できるもの(Activity1 in Figure 1.3 → 焦点:位置を表わす前置詞)
②言葉それ自体をタスクの内容にしてしまう
(Activity2 in Figure 1.3 → 焦点:時間を表わす前置詞→表題自体がPrepositions of timeになっている)
ディスカッション&コメント
・workplanとは? → 学習者の作業計画のようなもの。
・exerciseはform重視 ⇔ taskはmeaning重視。
・Ellisのタスクの定義では、communicativeであっても、活動自体が形式を問うものであるとexerciseに分類されるようである。
・taskを実施する前にexerciseを実施するというコンビネーションもある。
・活動の中で形式に焦点を当てていく流れがfocus on form。 (鳴海, 平井)
ページトップに戻る
2008/05/23
Chapter 1, pp. 17-27.
・ The design features of tasks(タスクの構造的な特徴を検討するための枠組み)
1. Goal
タスクがCommunicative competence のどの側面に寄与するとされるものなのかを決定する、タスクの目的。
2. Input & 3. Conditions
タスクは「インプットデータ」と「指示的な質問」の二つの要素から成る(Wright,1987)
タスクは「インプット」、「アクティビティ」、「ゴール」の3つの構成要素から成る(Nunan,1989: 48)
「インプット」⇒「インプット」「状態(conditions)」の2要素に分けるべき。
⇒インプットされるデータと、そのデータの提示の仕方を考慮する必要があるから。
4. Procedures
方法論的選択肢(=どの方法を選ぶか)に関わってくる。
⇒「指示的な質問」や「アクティビティ」に含まれるかどうかはわからない。
タスクで期待された活動が、指示に含まれず、生徒が他の方法を選んでしまう場合もある。
5. Predicted outcomes:
a) Product
タスクを完成することで得られるもの。Open、closedに分けられる。
b) Process
協力者が実際にタスクを実行した場合に得られるもの。個別の協力者に依存しているため、推測は難しい。しかし、Input,
conditions, proceduresから推測することはできる。
以上が、タスクを説明するための枠組み(⇒Table 1.1参照)
枠組みの意義:①異なる様々なタスクを体系的に説明できる、②タスクを計画する上で様々なオプションを特定できる、③異なるタスクの分類と特定が出来る の3つ。
特定のタスクの構成を知らなければ、研究や指導はうまくいかない。
・ Tasks in SLA research
① 初期の記述的研究(対象:学習者がL2を自然に習得する場面)
分析的、実験的に収集されたデータは自然に発生するデータと似ているか、異なるかという問題があった。⇒変項(variability)に関する研究
② 近年の理論的基盤を持った研究
(Unfocused Tasks)
・Input Hypothesis(Krashen)…
言語習得はInputに依っている。学習者のレベルまたは習熟度に合わせたInputが望ましい。
・Interaction Hypothesis(Long)…
学習者が対話によって意味を理解するときが最も良いInputである。(⇒pg.23)
・言語学習の理論(Vygostky)…全ての学習は社会的に構築されているものである。
・言語能力やスピーチの能力の理論
・Speech Productionのモデル(Levelt)
(Focused Tasks)
Focused tasksの研究では、一部のタスクのproceduresを特定の特徴を使用するよう操作することが出来ることが実証されている。
また、最新の研究では、タスクの協力者が形式に集中するために意味に意識を向けることについての研究などがなされている。
この他にタスクそのものを対象とした研究も多くなされており、②で挙げた理論に基づいた研究も多くある。
タスクは教授法における一単位であり、またタスクを行う上では個別のタスクを計画することや、指導計画への配列などが必要となる。
⇒Tasks in language teaching(次項)へ
(伊藤)
ディスカッション&コメント
・condition と procedure について、細かく微妙な定義分けをしている。研究者によっては、両者の用語を重ね合わせて使っている可能性もある。授業研究などでのタスク・デザインについて議論する場合は、特に注意されたい。 (長橋)
ページトップに戻る
2008/06/20
Chapter 1, pp. 27-35
Tasks in language teaching
・言語教育者、教材作成者、コース製作者も研究者同様、タスクの価値を早い段階で認識していたが、使用法という点でそれぞれ異なる
手法1:単に伝統的な言語に基づいたアプローチを教育に用いた
手法2:より根本的に、タスクを教育それ自体の1ユニットとして扱い、それにまつわる全コースを構成
・2つのタスクの用法は「タスクによって支えられる言語教育」と「タスクに基づく言語教育」だといえる。
・両者の場合も、タスクは言語教育をよりコミュニカティブにするために用いられている。⇒タスクはCommunicative language teaching(CLT)の重要な素性
Communicative language teaching
・Communicative Language Teaching (CLT):実際のコミュニケーションの中での言語運用の学習者の能力を開発を目指す
・Brown and Yule(1983):コミュニケーションに2つの一般的な目的があると特徴付けている(①コンタクトを取る、または維持するための言語使用the interaction functionと、②情報交換・処理のための言語使用the transaction function)
⇒CLTは直接、学習者に第二言語での相互行為や情報処理を機能させている
・しかし、CLTの目標は、コミュニカティブな言語使用の能力開発を主張している聴覚言語的なものや、口頭での状況的なものなどの初期の方法とあまり変わらないが、言語モデルが異なる
⇒初期の方法は言語体系の集合(音韻、語彙、文法)としての言語観に基づいているが、CLTは言語の機能的モデル(Halliday’s)そして、コミュニケーション能力の理論(Hymes’)を描いている。
Widdowson’s(1978)の言葉を借りれば、語法、すなわち正しく言葉を使う能力に焦点を当てた教育に対する構造的なアプローチに対し、CLTは言語使用、すなわち、言語を意味的に、そして適切に談話構造の中で用いる能力へと方向付けされている。
だが実際には、CLTは一体的ではなく、1つの形式のアプローチではない。Howatt(1984)は強いバージョン、弱いバージョンに分け、弱いバージョンは、コミュニケーション能力の構成要素は識別可能で、体系的に教えられうるという仮定にもとづいている。この点で、弱いバージョンはWhite(1988)が言及するタイプAの言語教育のアプローチを反映している。つまり干渉的かつ分析的アプローチであることから、初期の方法から根本的には離れていないものである。
このように、学習者に言語の構造的な領域を教える代わりに、弱いバージョンのCLTでは、継続時間や可能性のような特有の一般的な概念や、招待や謝罪といった言語機能を分からせる方法を教えるべきだと提案している。弱いバージョンでは、Wilkins(1976),Van Ek(1976)により開発された、概念的・機能的なシラバスの提案が明らかにされている。
対照的に、強いバージョンでは言語はコミュニケーションを通して習得される(Howatt1984: 279)と主張している。すなわち、学習者は言語の構造的側面を第一に習得し、それからコミュニケーションの中でこのシステムをどう使うかを学ぶのではなく、実際にコミュニケーションの仕方を学ぶプロセスの中でそのシステム自体を発見するということ。強いバージョンでは、学習者に実際に言語がコミュニケーションの中でどのように使用されるかを経験する機会をを含む。このアプローチはWhite(1988)でタイプBのアプローチと呼ばれ、すなわち干渉がなく、全体論的なアプローチを反映している。それはKrashen&Terrell(1983)の自然アプローチやタスク使用中心の教育に対しての提案(Candlin 1987)の中で明示されている。
CLTの弱・強バージョンの区別は、タスク支援型言語教育とタスクに基づく言語教育の区別と平行し、弱の観点は、伝統的な方法で紹介された言語アイテムに対するコミュニケーションの実践を供給する方法をタスクとして用いている。それらは、必要であるが言語のカリキュラムとしては十分ではない基盤を構築している。一方、強バージョンは、タスクを学習者にコミュニケーションの中でどのように使うかを経験させることで言語を学ばせようとする手段で、タスクは学習にとって必要かつ十分なものである。
Task-supported language teaching
・weak version of CLT
・Present-Practice-Produce(PPP)により構成
・従来型の言語教育に近い(言語の形式と運用を区別して教育する)
・PPPでは第二言語習得に必要なプロセスが達成されにくい。
Task-based language teaching
・TBLTはCLTの強バージョンを示す
・しかしTBLだけがCLTの強いバージョンを達成するわけではなく、その他多くのコミュニケーション活動によっても達成される。(タスクだけではない)
・TBLTは従来型のシラバスと方法論を分けることなく、曖昧にしている。(弱いバージョンには残っている)
・しかし弱いバージョンも、PPPの順序を、produceの部分を先に持ってくることで、改善されうる。
・初期の段階では、humanistic language teachingに関連。学習においても、認知においても感情的な次元の重要性という考えが発生 →コミュニカティブなタスクへ。
・これを用いる上でタスクを教育のどこに位置づけるかが重要。
Conclusion: on the relationship between researching and teaching tasks
SLAの研究領域と言語教育学の研究領域の関係性は複雑であり、研究により言語教育の様々な方法が明らかになる。研究と教育の関係は、両者の施行者により強められ、Pica(1997)では、2つの両立により、最も強められるとしている。また、言語教育に最適なタスクとは、特に言語の形式、構造、流暢さに注意を向けうるタスクである。よって、SLAと教育学は相互依存をなすと考えられ、本書では、相互依存の本質を証明することを目的としている。
考察:
日本の英語教育は、まさにTask-supported language teachingに当てはまる。そして現在では、コミュニカティブな言語教育への推進が図られている点で、Taskに基づく言語教育が求められているといえる。Task-basedの場合、学習者の動機付けに関しても、authenticityを含むタスクの実施など、より現実的な場面を想定して行われるため、言語の実用的な側面が養成されると考えられ、アウトプットに弱いとされる日本の英語教育にとっては有効な教育法であるように思う。
(山下)
ページトップに戻る
2008/07/11
Chapter 2, pp.37-49.
2. Tasks, listening comprehension, and SLA
本章ではリスニングのタスクに焦点を当てる。リスニングタスクとは、研究者にとっては、ある特定の言語特徴について学習者の能力を測定することが可能となる。また教師にとっては、習熟度の低い学習者にもtask-basedのスタート地点を与えることができるものである。
研究上の課題:
(1)タスクが持つ学習者の理解への影響は?…Listening to comprehend(理解するためのリスニング)
(2)L2習得にタスクが持つ影響は?…Listening to learn(学習するためのリスニング)
・Two types of listening
ここからリスニングの種類を2つ挙げるが、実際行われている多くのリスニングタスクでは同時に複数のリスニングを行うことが求められている。
① Listening to comprehend
聞き手の役割:聞き手には(1)overhearers (2)addresses (3)hearers の3つの役割のパターンが存在する。この役割は聞き手の理解に影響を及ぼすため、学習者がこのうち(2)addresses と(3)hearerのどちらの役割をタスクによって要求されているのかを考慮する必要がある。
リスニングの目的:リスニングタスクは、その目的が明らかに、またはそれとなく学習者が理解できるようなものであるべきである。しかしタスクの目的がはっきりと明示されているにも関わらず、個々の学習者がそれぞれに目的を作り上げてしまう可能性もある。よって、タスクに対してどう学習者が反応するのかといった研究も今後必要である。ただしこれまでの研究では、タスクに対するパフォーマンスを評価する際、そのタスクが意図された目的に関してのみ評価する研究が典型的である。
スキーマ知識の活用:聞き手は本文を理解するために、スキーマを(1)解釈 (2)推測 (3)仮説検証 の3つの主要な方法を取る。このようにスキーマを活用してリスニングを行う場合、聞き手はトップダウン方式のリスニングを行っていると言える。(これに対してボトムアップ方式のリスニングとは、言語的要素の特定に焦点が当てられたものである。)
文脈的知識の活用:習熟度の低い学習者は、聞き手として参加しているその場面に存在する「文脈的知識」に頼ることが多い。多くのタスクはこの文脈的知識を含む。
メンタルモデルの共同的構造:相互行為が行われるリスニングタスクの場合、聞き手と話し手の間で、共通のメンタルモデルを構築することでよりよい理解が得られる。共通のメンタルモデルの構築については、社会的・文化的な要因も影響することに留意するべきである。また、講義などある意味「一方的な」リスニングを苦手とする学習者が多いが、これは相互行為がないことで共通のメンタルモデルを構築できないことが一因となっている可能性もある。
聴解の相互行為モデル:ここでは、「相互行為」=①ボトムアップ処理での相互行為②トップダウン処理での相互行為 の二つをさす。また、話者と聞き手のスキーマの合致を確認する、社会的なプロセスもまた相互行為の一つである。
② Listening to learn
インプットが理解可能であることが習得のために必須である(Krashenのインプット仮説)
…習得は、学習者が発話を理解すれば自然に起こるものである
・ Krashen, Longの"comprehension"の定義が特定されていないことへの批判
インプットの定義に関して:
・ 理解としてインテイクするインプットと学習としてインテイクするインプットを分ける必要がある。(White,1987など)
・ インプットには、理解に関わる処理と習得に関わる処理の2つがある。(Sharwood Smith,1986)
意識と注意について:
・ Krashenが習得を潜在意識的に行われるものだとする一方、Schmidt(1990,1994,2001)は、習得が意識的なものだとしている。
また、付随的処理なしではインプットから言語材料を学習することはほとんど(もしくは全く)できない。→では付随的処理は何から構成されるのか?また、それなしでの学習は可能か?
学習者の意志によるものではない気付きは起こりうる(Schmidt,2001)
…タスクを通じて学習者の注意を引くことが可能となる。
・ 意味と形式の両方に聞き手が接した場合、どうなるのか?
VanPatten(1990)のリスニングの実験:学習者が形式に注意を向けると、理解が落ちた。→学習者の注意にとって、意味と形式は競合する。
・リスニング理解のタスクを行うことによって、L2を首尾よく習得することが出来るのか?
→次項から
(伊藤)
ページトップに戻る
2008/07/25
Chapter 2, pp. 49-67
□Researching listening tasks:
2種類のリスニングタスク(①reciprocal [interactive], ②non-reciprocal [non– interactive]) の区別は二分するというよりも連続的なものであるとみなされる。この連続性においてnon-reciprocalを持つタスクについての調査研究に関して議論
・Listen-and-do tasks (L&D):L&Dが生成するものには定義づけが行われている。
①目的:
L&Dタスクは理解のためのリスニングを促進。新出の言語形式をインプットに含めることで、それを教えることも可能。
②インプット:
インプットは言語的情報(指示や陳述の形式)と非言語的情報(物理的なもの:絵、地図、図形)を成す。インプットの単純化、スピード調節も可能。
③過程:
L&Dタスクはクラス全体の活動として行える。ペアや小集団でも可。指示や説明は一度でも繰り返しも可能。
④予測される結果:
・L&Dタスクは、理解のためのリスニングと学習のためのリスニングの両者に関係した処理を行う機会を与える
・L&Dタスクは特にSLAの研究者に以下の理由で有効:
タスクにより得られたものは個々の学習者がどのくらいインプットをよく理解できたかの記録となる点、指示や説明はインプットがどう理解や習得に影響するかという特定の仮説を検証するために構築することができる点、インプットは学習者がまだ学習していない言語形式含むことも出来る点(→”focused tasks”)等
・L&Dのタスクに基づく研究は、インプット仮説及び相互行為仮説の主張を調査することに方向付けされてきた。(特に修正インプットの領域の理解と習得の面における学習者への影響)
・全ての研究で、相互行為による修正インプットは理解を促すということが示された。
・研究対象は全て青年期及び成人の協力者→小さな子供では同じような結果にならない
・相互行為による修正インプットは意味交渉において説明者として、また聞き手として直接的に関係している学習者に最も効果的に働く。
・学習者に相互行為の機会を与えることは、インプットに負荷を掛けすぎる場合、ときに理解を妨げる場合がある。
・修正インプット後の目標語彙に関する簡単な説明は、語彙習得の面で相互行為による修正インプットと同等の効果をもたらす。
・理解と習得の関係性については、習得がその研究の中でどう計測されるかで関係性の強さが異なる。(その項目を経験した文脈と近くなるほど、習得との関係は強くなる)
・個々の学習者の能力によりタスクの修正インプットからの理解や習得が変化する。(タスクに対する個々の適性、協力者の年齢など)
・L&Dタスクからの生成物はSLAの理論の仮説検証に優れた素材となる
・語彙習得以外の側面の調査の必要性
・語彙学習におけるL&Dの効果
Academic listening tasks(ALT)
・ALTのタスクは全て同一の基本フォーマット(学習者が学術的なトピックの講義を聞いている間、学習者はノートテイク課される)を持っている。
・研究の多くは講義の談話的素性の記述に焦点を当てている。
① 目的:
・学術的な講義理解のための学習者の能力開発、
・後に読み、理解できるノートテイクを実行させる
②インプット:
非言語的教材(黒板、ハンドアウト掲載の図形、地図、図表など)
③状況設定:
相互行為を聞くことによるタスク。ノートテイクは講義の概要を完全に把握するためのもの。
④過程:
生徒にノートテイク指導を行う。(Rost1990参照)
⑤予測される結果:
・このタスクにより生成されるのは学習者のノートであり、それが講義内容の記録となる。
・この方法によるALTの記述は、タスクの活動に影響を与えうる多くの変化を明確にしている
・研究はノートテイクと講義内容の理解にある関係性に焦点を当てている。
・ALT によるL2研究は2つの問題(L2学習者によるノートテイクの性質と、理解におけるノートテイクの効果)を説明
・問題の重要性はL2学習者のノートテイクの質
・L2学習者がノートテイクの際、経験する問題点
・講義を聴くのみよりノートテイクしたほうが理解は促進されるか:
ノートテイクによる理解促進は、完璧さ、正確さ、などの質的側面が求められる。
・ノートテイクの質と理解:
質がよければ理解は促進される。しかし何が質を向上または落とすのかという点はまだ証明されていない。
【2つの理由】
① ノートテイクの効果が完全に定められていない
② 個々の学習者により、どんなノートが最もよく働くかという点にちがいが生じる可能性がある
Conclusion(理論、研究方法、言語教育の観点で考察)
Theoretical considerations:
・このチャプターでの研究はリスニングの相互行為モデルを支持
・ALTでは、適切な背景知識が不足すると、ノートテイクや講義の理解に支障をきたす。
・L2学習者はネイティブに比べノートテイクという点で劣る。(オーラルインプットの処理の速さの問題)
L&Dタスクによる研究は、聞き手と話し手が共有のメンタルモデルを構築できれば理解が成功するとした。その1つの方法として意味についての交渉がある。
また理解のためのリスニングと学習のためのリスニングには異なるプロセスがあることを示した。理解と言語習得には密接な関係がない。(→理解は習得なしに起こりうる、またその反対もありうる。)
TBLの研究は、どのように具体的なインプットの領域が理解及び習得に影響するのか、また重複がどのように両者を促すか(ただし重複しすぎは習得に悪影響を及ぼす可能性あり)に関する理解を深める。しかし、談話におけるマクロ、マイクロな領域の影響に関してはまだまだ研究が必要。
Methodlogical consideration:
・リスニングタスク(L&D and ALT)は理解と学習に関するマイクロプロセスを調査が可能。(→学習者が課されるインプットの実験的に操作及びコントロールできるため。)これにより、インプットが習得にどう影響するかという具体的な仮説が検証可能。ただ人工的な会話のため、実際の状況におけるその結果をここから予測するのは困難。ALTの場合、実際のレクチャーではなくビデオレクチャーが使用されている等の批判がある。この点に関して、ALの民俗学的定義を満たす必要がある。
・発展的な方法論の問題として、学習者がタスクをどう見るかについての情報の必要性がある(ワークプランとしてのタスクが個人的なタスクとならないように)。個々の学習者がタスクにどのように反応したかを構築する試みが行われていない。
(例:ALTでは、学習者がノートテイクの際何を思い、また学習者のノートテイクが役立つ活動なのかということが調査されていない。)
Pedagogic considerations:
・listen-and-do taskに基づく研究は、タスクが聴解の道具、かつ新出の言語材料を提示するのに効果的だと示した。また、修正インプットと相互行為による修正インプットが同じくらい習得に効果があることも示した。
・academic-listening taskに基づく研究はノートの取る技術の教育を向上させる。最重要の貢献は効果的なノート取りを構成するものが何であるかについての単純な考えに注意を喚起すること。
考察:
リスニングの理論的及び教育的側面の両者を調査する効果的な方法論を提示し、理解のためのリスニングと学習のためのリスニングの重要な区別を示した。またノートテイクによる学習への効果に関する研究について概観した。ノートテイクに関しては、やはり学習者の要因が大きく、質の向上という点でも、具体的にどの部分を、どのように記せば学習により効果的であるのかは示されておらず、今後の研究が期待される。
(山下)
ページトップに戻る
2008/08/21
Chapter 3, pp. 69-102
Chapter 3 Tasks, interaction, and SLA
The study of learner interaction
本章では、学習者に相互行為を求める、相互行為的なタスクについて検討する。
タスクと学習について考える際には、タスクと言語運用、言語運用と言語習得のそれぞれの関係について考えなければならない。
まず、タスクと言語運用という点では、主に以下の3点について研究がされている。
(1) the negotiation of meaning(意味の交渉)
相互行為の中で生ずる誤解を解決するために行われる。特に次の4つ。
① Comprehension checks…話者の発話内容を理解されたかどうかを相手に確認する。
② Clarification requests…より明瞭な発話を要求する。
③ Confirmation checks…発話の直後に、理解または聞き取りを正確に行うことができたかどうかを確認する。
④ Recasts…相手の発話を、その中心的な意味は変えないままで、1つ以上の文の構成要素を変えて反復する。
ただし、理解ではなく知識の問題でもこのような会話は起こり得る。(pg.71)
が、negotiation of meaning/content を判別することは容易ではない。
・ pushed output(Swain, 1985):学習者がtarget languageを正確に、意識的に使うことを強要されたとき、学習者が作り出すことのできるアウトプット。
・ comprehensible input:学習者が理解することのできるインプットのこと。
・ その他の、より特定なinteractional strategiesの類型
Rost and Ross(1991):聞き手の返答・反応の種類(pg.73)
→理論的基盤なし・一般化できない可能性
一般化でき、言語習得に貢献できる理論にできるようなdiscourse strategies が求められる
(2) communicative strategies(コミュニケーション方略)
「相手に助けを求める必要がない、自助の形式」(Kasper and Kellerman,1997:2)
→話者中心
・ 計画の段階の一部である(Fa ch and Kasper, 1983)
・ Knowledge/control based それぞれで区別される(Bialystok,1990)
≒conceptual/ linguistic の二つのarchistrategies(談話内問題を解決するための一般的なアプローチ)(Kellerman, Bongaerts, and Poulisse 1987, Poulisse 1990; Kellerman 1991)
・ 学習者がなぜある特定のストラテジーを選ぶのか、その理由が研究で主要な問題
・ コミュニケーションの2つの原則:①the principle of clarity(明瞭性)②the principle of economy(経済性)…優先するものと、犠牲にするものが出てくる。
・ 研究手法の弱点
① 意味を伝えることが学習者にかかっているが、学習者がactional,reactional goalsに関する問題、またこの2つのゴールを調和させる必要については、語用論的な性質のものは見つけにくいために、研究者に無視されてきた。
② strategic competence(※言語的・実際的な資源を効果的に使うための能力…communitative competence はstrategic competenceの重要な構成要素)を補助的な役割とみなすあまり、重要視されてこなかった。
「全てのコミュニケーションの中心」(Bachman,1990)
(3) communicative effectiveness(伝達の有効性)
(1)(2)→全般的なcommunicative effectiveness に影響する。
Yule(1997)
①'identification-of-referent' dimension:話す対象、指示物を特定し、符号化できる必要がある。(1)the perceptual ability (2)the comparison ability (3)the linguistic abilityの3つの能力。
②'role-taking' dimension:話し相手を考慮し、intersubjectivityを達成するための能力に関わる。言語学的というよりは社会的・認知的な技能。(1)相手の視点の重要さを認識する能力 (2)相手の視点に関して推論を行う能力 (3)伝達項目を暗号化して伝える際、(1)(2)の推論を考慮する能力 (4)相手からフィードバックを受け、それによってアウトプットをモニターする能力
・communicative effectivenessはcommunicative outcomesの分析によって研究される。→タスク(それもclosedのみ)を遂行するかどうか。したがって教師は、生徒が満足のいくoutcomesを達成できるかどうかでタスクを選ぶことができる。
Interaction and language acquisition
・ 相互行為を行う機会は、どう習得に影響するのか?
→相互行為主義では、言語学習を談話(特に対面)への参加のoutcomeと見る。
The Interaction Hypothesis(相互行為仮説)
当初はインプット中心の仮説→徐々に談話を考慮するよう拡張されてきた。
Pica(1992,1995):意味の交渉を行う機会は、3つの主な方法で学習者の助けとなる。
(1)理解可能なインプットを学習者が得る機会となる
(2)交渉によって学習者自身のL2のフィードバックがされる
(3)交渉は学習者に、自身のアウトプットを調整、操作することを促す
・ 相互行為仮説は、相互行為がどのような方法で言語習得に貢献するかをいくつか提示している。一般的に言えば、意味・内容での交渉の機会があるほど習得は起こりやすい。
・ しかし、相互行為仮説は数々の点で限定的との批判を受けてきた
信頼性(交渉が実際に起こる場所の特定、またそのoutcomeの特定)、妥当性(インプットの理解は言語習得を促進するのか?)
ただしこれらの批判は理解可能なインプットを強調していた初期の仮説に対するものと考えられる。
・ 相互行為が形態的な特徴の習得にどう貢献できるかは不明
・ 全てのpushed outputがmodified outputとは限らない(pg.81)
・ 意味の交渉が文法的発達につながるかどうかの研究は少ないが、近年の研究ではその関係を示すものが現れ始めている。
・pushed outputが言語習得を促進すると思われる程度の研究結果は存在するが、Pushed outputの習得の上での有意性はまだ示されていない。
・ 相互行為によって得られる様々な側面に比べ、相互行為仮説は修復の場面を強調しており、限定的である。
・ Task-basedの研究における相互行為仮説が持つ危険性…談話を全体的、協力的、動的なものと見るのではなく、細かく分析される対象として見てしまう。
Communication strategies and language acquisition
Communication strategiesは、習得を説明するものというよりL2でのコミュニケーションを理解するためのものとして見られてきたが、習得(とくに文法)に関してストラテジーが有効であるという意見がある。
・ Skehan(1998a):ストラテジーに熟達した学習者は知識を使う必要がない
・ Communication strategiesはたとえ言語能力に貢献しなくとも、ストラテジー能力に貢献する。
Communicative effectiveness and language acquisition
Communicative effectivenessと言語習得の関係は個別に言及されていない→これまでにされてきた指示的コミュニケーション研究、伝統的なL2習得研究それぞれの焦点が違うためか。
・ 相互に強化しあうのではなく、互いに補足しあう関係、さらにはトレードオフの関係であるという考え→学習者はタスクを行う際、communicative effectivenessか言語習得かのいずれかを強調することを選ぶ可能性がある。
・ しかしCommunicative effectivenessがoutcomesで測定された場合は、言語習得に有効であるという結果が出るだろう。
学習者が言語を習得するほどコミュニケーション能力は高くなり、コミュニケーション能力が高いほど、学習者自身が言語を習得する機会は多くなるだろう。
Investigating tasks: a review of the L2 research
ここでは、相互行為にタスクが与える影響について概観する。
Task features(タスクの特徴:目標、インプットの種類、タスクの状態などに関わるもの)
→pg.96のTable3.1参照
(1) required vs. optional information exchange
インフォメーション・ギャップ・タスク(与えられた情報交換)とオピニオン・ギャップ・タスク(与えられた以上の、自分たち自身の意見の交換)の違いである。
(2) types of required information exchange
一方向と双方向のタスクがここに分類される。NNSとNSが双方向のタスクを行う場合にNSが相互行為を調整する可能性が大きいなどの研究結果が出ている。ただ、一方向と双方向、2つのタスクの違いは連続的なものであるとする説もある。
(3) expected task outcome
open tasks(あらかじめ決まっているような答えはないと、学習者がわかるようなタスク)と closed tasks(答えがあらかじめ決まっているタスク)がある。
インフォメーション・ギャップ・タスクとopen taskが組み合わされた場合、会話をする努力を行う必要がなくなるといった指摘がある。ここから、組み合わせを考慮することが必要だと考えられる。
(4) topic
トピックについては、topic familiarityとtopic importanceについて研究がされている。
(5) discourse domain
過去形、現在形などの時制などを含む。また、「会話」「指示」など談話の種類によってもタスクに及ぼす影響が異なる。
(6) cognitive complexity
広義的。内容が文脈に沿っているものかどうか、などは認知的に影響を及ぼすと考えられる。またある領域の談話が、他よりも認知的に複雑である可能性は十分に考えられる。
Task implementation(タスクの手段:タスクの手順などに関わるもの)
例えば教室で行われるものか、小さなグループで行われるものか、など。タスクの特徴に関するものに比べると、研究は少ない。以下はこれまでに研究された結果だが、これらが言語習得に影響を与えるというような結果はまだない。
(1) participant role
学習者が受動的な役割(聞き手など)の場合よりも、能動的な役割の場合の方が交渉が効果的である。
(2) task repetition
タスクを反復して行うことは相互行為とcommunicative effectivenessに効果的である。
(3) interlocutor familiarity
より親しい話し相手とタスクを行う場合、交渉の量が増える。
(4) type of feedback
フィードバックは、confirmation checkではなくclarification requestによって受ける方がmodified outputを促進させる。
Tasks, interaction, and SLA まとめ
この分野における研究は、タスクの心理言語学的要素を特定することが目的にあった(Long,1989:12)。しかし、全般的に満足のいく研究成果が出ているとはいえない。その理由は、
(1) 相互行為に関する要素が膨大であること、そのうちどの要素が独立的でどの要素が互いに関連しているかということ、が不明確であること
(2) タスクのパフォーマンスは学習者に関する様々な要素によっているが、それらの要素抜きにタスクを考えてしまう危険があること
(3) これまでの研究は意味の交渉が注目されてきたが、今後はその中でも特に理解可能なインプット、フィードバック、調整されたアウトプットに焦点を当てた研究が望まれること
(4) 言語習得までつながる研究は、本章で扱った研究ではほとんどされていないこと
などである。相互行為のoutcomeを理解する上では、本章で扱った研究は意義深いものといえるが、教師が実際に使用するタスクとしては、言語習得につながる研究が必要である。
コメント
今回は、interactionの性質について理解するよい機会となった。この分野の研究は習得との関係がはっきり現れていないものが多く、教師が教室でinteractionのタスクを行う理論的基盤の不足が指摘されている。
しかし、interactionによって得られる技能、例えばコミュニケーション方略は実際のコミュニケーションを行う際に不可欠と考えられる。教育の目的を習得だけではなくコミュニケーションの遂行に広げると、今回見てきた理論、またそれに基づくタスクの重要性は増すだろう。その際にはタスクの特徴だけでなく、学習者の役割や反復など、その手段にも注目して行いたい。
(伊藤・平井)
ページトップに戻る
2008/09/05
Chapter 4, pp. 103-115
Chapter 4 Tasks, production, and language acquisition
本章では、学習者が産出する言語の全体的な流暢さ、正確さ、複雑さへのタスクの影響を扱う。特に、unfocused tasksの結果として現れたものに焦点を当てる。
ここからは、(1)学習者の言語知識がどう表現されるのか(2)この知識は学習者による産出でどう処理されるのか(3)この知識を産出で使うことはどのように言語習得に貢献するのか の3点について述べ、さらにそれがどう学習者による産出のTask-basedの研究に役立つかを考える。
The representation of linguistic knowledge
議論の中心となっているのは
(1) 言語知識がある特定の言語的な認知器官に位置しているのか、あるいはそれよりも全般的な認知器官に位置しているのか
(2) 言語知識は暗示的なのか、明示的なのか、それとも両方なのか
(3) 言語知識は規則に基づいているのか、あるいはひな型に基づいているのか
の、3点である。
The nature of the faculty for language
symbolist(生成文法主義)vs. connectionist(認知主義)…言語の心的表象についてかなり違った見解を示している。
生成文法…言語知識は記号の普遍的なセットと考えられる。'property'(言語システムを構成する記号や規則)と 'transition'(言語システムに変化を与える機構)を別なものとして考える。
認知主義…言語知識は、同時並行の処理を可能にする、互いに関連し合った複雑なネットワークである。このネットワークが動的なもので、常にインプットの頻度に応じて動いているため、表象と学習のメカニズムの間にははっきりとした区別はない。
⇒ただし、Hulstijn(2002)によれば、ネットワーク内の関連しあうもの(associations)が常に活動していることによって、それらが比較的永続的な小ネットワークとなり、これを記号的と見ることもできる。→「関連しあうもの」が「記号」に進化することができる
→symbolist, connectionistのモデルを合体させたモデル
Implicit and explicit knowledge
生成文法、認知主義の両方の立場が、暗示的(implicit)・明示的(explicit)知識の区別を認めている。
暗示的知識…話者が言語運用において示すが、そのことに気づいていないような言語知識(→pg.105)。手順が決まっていて(proceduralized)すばやいアクセスが可能。
明示的知識…話者がそのことに気づいており、聞かれれば説明できる言語知識。操作された処理によってのみアクセスが可能で、暗示的知識のような簡単で速いアクセスは不可能。
・ 暗示的・明示的知識の区別ではなく、その2つの関連について研究がされている。
暗示的知識は、明示的知識の発達の基礎となる⇒では、明示的知識が暗示的知識に変化することは可能か?
→明示的知識は暗示的知識に変化しないという説(Non-interface)(Krashen,1981, Zobl,1995, Hulstijn,2002)/接点(interface)があるとする強力な説(Sharwood Smith,1981, DeKeyser,1998)/明示的知識が暗示的知識に変わるというよりも、明示的知識が暗示的知識の発達を促進させるという説(weak-interface)(Ellis,1994)
Rule- and exemplar-based linguistic knowledge
暗示的知識は、規則で構成されているのか、それとも個々の固定パターンで構成されているのか
→言語知識は分析されているのか、されていないのか/文法的なのか、語彙的なのか
言語学者・認知主義者:両方の表象の存在を認めている(Skehan,1998aの'a dual mode system')が、この二つの関係については議論がまだされている。
L2学習者は習得した形式的なチャンクを分析するのではなく、インプットを処理することによって規則を別に習得する(Krashen and Scarcella,1978)というように、2つのシステムは完全に独立していて、相互に作用することはないという説(言語の生得的な性質を強調する、文法学者に多い)
⇔既製のパターンを構成する個々の単位に学習者が気づくことで、それが規則の発達の基盤となる(Wong Fillmore,1976)というような説(語のつながりを記憶の中の規則のデータベースとして見る、認知心理学者に多い)
認知心理学者たちは、言語運用で言語知識がどう使用されているかを、情報処理モデルを通して明らかにしようと試みている。したがってTask-basedの研究者たちは、認知的な言語モデルにより大きな関心を持っている。
Language production
話し言葉はどのように産出されるのか?
・ Levelt(1989)のモデル:
① 概念化(Conceptualizer)→②形式化(Formulation)→③調音(Articulation)
人間が持つ処理能力は限定的であるにもかかわらず、スピーキングのような複雑な能力はいくつもの知的活動を同時並行的に行う必要があり、処理にかなりの圧力がかかる→なぜ話者はこれに耐えられるのか?
・ 形式化の段階で、模範形式(exemplar)を基盤としたシステムにアクセスすることができるので、音声計画をすばやく行うことができる(Skehan,1998a)
・ 流暢さに関する瞬間基盤(instant-based)の理論:流暢なスピーチは規則のすばやい計算に拠っているのではなく、全体としてアクセスされるために最低限の処理しか必要としない「既製の模範形式」に拠っている。
・ ただし新しい伝達内容など、既製の模範形式では対応できない場合は、規則を基盤としたシステムを使用すると考えられる。
以上の言語産出に関する見解から、2つの重要な点が導き出される。
(1) L2学習者が伝達内容を概念化、形式化、調音する際に、トレード・オフが起こる可能性が高い。産出の1つの側面に注意を向けることは、他の側面の負担となる。
※ただし、学習者の処理能力が限定的であることによって正確さと複雑さでトレード・オフが起こるということに関しては、学習者には同時並行的に注意を向ける能力がある(Robinson,1995)など異なる説もある。
(2) L2学習者の産出の問題は、話し始める前に計画する時間があれば軽減することができる。①話者がコミュニケーション行動に出る前に起こる戦略的計画('strategic planning)(Wendel,1997)②コミュニケーション行動の最中に起こり、マクロ計画・マイクロ計画を含むオンライン計画('on-line planning')(Levelt)③同じく産出の最中に起こり、話者が当初の計画に間違いを発見した場合に行われるモニタリング('monitoring')など、いくつかの計画方法がある。
タスクの言語運用で学習者のアウトプットを操作するには、これらの計画の
うち、どれか一つ以上に合った状態を作り出すとわかりやすい。Ex.戦略的計画
の時間を配分する(Mehnert,1998)、オンライン計画にたくさんの時間を与える(Hulstijn and Hulstijn,1984)、タスクの後に修正するモニタリングを奨励するような要求をする(Skehan and Foster,1997)など。これらを通して、学習者が産出する言語への効果、さらには中間言語の発達が期待されると言われる。
Production and language acquisition
スピーキングが習得に役立つということは明らかではない「スピーキングは習得の結果であり、その原因ではない」(Krashen,1985)
・ 産出(production)によっては、習得の妨げになることもあり得る(ex.ストラテジーの使用)
しかし、産出が習得に果たす役割についての理論を発展させることは可能
・ Skehan(1998a):産出が持つ6つの役割
(1) 学習者が産出を行うことで得られるフィードバックによってより良いインプットを生成することができる
(2) 統語的処理を行うことを余儀なくさせる
(3) 学習者が、目標言語の文法について仮説を検証することを可能にする
(4) 既存L2知識の自動化(automatize)を助ける
(5) 談話能力を伸ばす
(6) 学習者が興味を持つトピックの会話に参加することで'personal voice'を発達させる
(7) ※学習者自身の産出による「自動インプット」('auto-input')(Schmidt and Frota,1986)を学習者に与える
⇒これらの役割のうち(1)(3)(6)(7):習得に直接ではなく、間接的に働きかける。
これらは、相互行為が習得に与える影響に関連する。
(7)では、Schmidt and Frota(1986)の後にSwain(1985)によってアウトプットのこの機能を'noticing-the-gap'と述べられた。'noticing-the-gap'はあいまいな表現だが、Ellisは、「学習者がただL2できちんと言えないことに気づくだけでなく、加えてそれに対して何らかの策を講じることができること」といった意味での'noticing-the gap'がより重要だと述べている。
⇒(4)(5):学習者が既に知っていることを実践する機会を与え、談話と言語知識を自動化するという議論…既に習得されたことを操作する必要もある。
・言語習得の2つの段階、分析(analysis)と操作(control)(Bialystok 1982,1990)
分析:言語知識が分化・構造化・意識化され、時間をかけて分析されていくこと
操作:知識項目の選択と、一部のタスクにおける産出での知識項目の調整
・このBialystokのモデルでは、産出は習得のうち操作の側面に貢献することができる。
・また、AndersonのAdaptive Control of Thought Modelを例とする能力学習モデル(Skill-learning models)によれば、理解と産出は別々の能力からなっており、スピーキングの自動化を強化するためには産出が必要だとわかる。
・ 言語活動の自動化に必要な実践とは…'real operating conditions'(Johnson 1988)
⇒(2):産出は理解とは違った形で統語的処理に関わるという議論
・ 中間言語の発達に産出は貢献するのか?
⇒Swainのアウトプット仮説によれば、学習者は産出によって統語的処理に関わるようになり、それが習得を促進する。(インプットの理解には意味的処理が使われ、言語の形式に注意する必要はあまりないが、産出には統語的処理が必要)
・Skehanは、Swainのアウトプット仮説に基づき、産出は形式への注意が必要となるが場合によるとした。流暢さ・正確さ・複雑さのうち、学習者またはタスクが正確さ・複雑さを強調する場合、統語的処理が要求される。
・ Swain, Skehan→Pushed Outputが習得を促進する。しかし、どうやって産出が習得につながるのかについては十分な説明はされておらず、ここまででは産出には限定的な役割しか与えられていないといえる。
・ 学習者が、あらかじめ集めたチャンクをばらばらにしたり、元に戻したりすることを産出を行うことなしにできるとは考えにくい⇒産出は、学習者のdual systemを繋げる機能を構成しているのではないか。
コメント
本文でTask-Based研究には認知的な視点が欠かせないということが言われていたが、symbolist・connectionist両方の立場を包含した新たな言語習得モデルに注目が集まっている点も興味深い。
アウトプットを扱うタスクを扱う研究者や教師にとっては、それが習得に役立っているかどうかの説明が欲しいところだが、実際に言語を使用することが言語活動の自動化につながるという議論はとても示唆的である。Ellisは最後に、産出の新たな役割(dual-systemを繋げる機能)に言及している。この点についても、より深い研究を期待したい。 (伊藤・平井)
ページトップに戻る
2008/09/26
Chapter 5, Task-based Language Learning and Teaching, pp. 124-139 (山下)
■Task performance and production: a review of the research
→ここでは、タスクデザインやタスク材料が生成に及ぼす影響を知るために、どのようにSLA研究者がさまざまな理論的見地を引き出してきたかをみていく。
■Measuring language production
言語の生成(特にoral production)の計測方法が問題視されている。主なものとしては、評価基盤となる分析単位である。(例:節の複雑さ等)こうした単位が異なると、研究間での比較も難しくなる。問題克服のため、Foster,Tonkyn,and Wigglesworth(2000)はanalysis of speech unit (AS-unit)を提案した。
AS-unitは、独立節か下位の節単位のどちらか、もしくは両者と関連した下位節を一緒にしたものからなる、1人の話し手の発話である。
研究者は学習者の生成を測るためにさまざまな具体的測定法を用いてきた。多くの場合、測定法は理論に基づくというより、直感的に選択、もしくはデータに志向したものであった。
例外として、Skehan(1996a)では、fluency, accuracy, complexityに区別している。Table 4.1では様々な研究で用いられた各々の具体的指標が示されている。これら3つの観点は、Skehan and Foster(1997)において、学習者の生成を実際に別々の要因として測ることのできる観点だと示されている。
■The effects of task design variables
記述タスクに用いる枠組みを使うにあたり、タスクデザインの変量が①タスクが供給するインプットのタイプ、②タスクの状況、③タスクのアウトカム、を含むということを見ることができる。タスク要因の調査で主要な問題は、1つの要因が他要因と相互に関係することである。つまり、観察された影響の要因がどちらなのか不明瞭だということになってしまう。
Input variables
具体的なデザインの変量(contextual support, 操作された要因の数、トピック)について
1. Contextual support
話し手が、絵や地図等を見ながらコミュニケーションできる状況(here-and-now)ではfluencyが促進され、そうでない状況(there-and-then)では、complexityとaccuracyが促進される傾向にある。
2. Number of elements in a task
タスク上に存在する数々の要素がタスクの難易度を決める。
3. Topic
トピックによる発話への影響も見られる。(topic familiarity)
Task conditions
1. Shared vs. split information
shared information task: 学習者の発話量を促進
split information task: 情報の意味に関する会話を促進
2. Task demands
発話は、タスク実行の数に影響されることを提案 →Robinson(2001)
①地図にルートが示されているもの
②地図にルートが示されていないもの
⇒ fluencyという点で①の協力者が優れていた。
watch-and-tell vs. watch-then-tell →Skehan and Foster(1999)
⇒ complexityの点でwatch-then-tellが優れていた。
・タスクに2つ以上の要求のあるものは、1つだけのものに比べ、結果が悪い。
Task outcomes
1. Closed versus open tasks
closed task: problem-solvoing task
open task: role-play task, authentic interaction task (Ask what their partner
had done yesterday.)
closedでは、自発的な発話、幅広い言語機能(意味交渉に関連した談話管理機能)の使用
openでは、質疑応答の談話構造、accuracy, complexityがみられた。
コメント
スピーキング能力を測る3つの観点としてaccuracy, fluency, complexityがあげられており、多くの研究でこれらが用いられているものの、それぞれの観点を測定する方法が異なるため、安易に研究間での比較ができないという感想を持った。またタスクの中で行われる課題について、学習者の行為が2つ以上になってしまうタスクがあり、特に熟達度の低い学習者にとっては、それにより発話が妨げられてしまうことが言われている。この点で、やはりタスクは学習者のレベルを十分に考慮したうえで、使用する必要性があると感じた。
(山下・平井)
ページトップに戻る
2008/10/10
Chapter 4, pp. 124-139
■Design focused tasks:focused taskのデザインで設定する主要な3つの方法について
(1)Structure-based production tasks
・Loschky and Bley-Vroman (1993):structure-based communication tasksについて議論。目標言語の素性を組み込むために製作されたタスクを3つの方法で区別(①タスクの自然さ、②タスクの有用性、③目標素性のタスクの本質)。またstructure-based taskがどんな習得の側面に影響しやすいか、についても言及。
・Tuz (1993):instructionの一部としてのタスク使用(修飾的な形容詞[ex. Two small round white buttons ]の練習タスク)。結果、6人中1人の生徒が形容詞の順序に関するタスクを達成した。
・Sterlacci (1996):modal verbsの生成的使用を引き出そうとデザインされたタスクが、実際にそれを引き出しているか調査。結果として、タスクは目標構造を引き出し、学習者に意図的にそれを使わせることはなかった(→situational grammar exerciseではない)。
・Mackey (1999):質問形式を引き出すタスクの使用に関して調査。タスクが母語話者との会話の場合、特定の質問形式を生成するのは困難だったが、繰り返すことにより、より目標に近い理解可能な質問形式になった。この点に関して、学習者はどの形式が成功に近いか理解し、タスクの達成に必要な情報を引き出すようになるということが言われている。
・structure-based production taskの妥当性についてわかったこと
①具体的な文法構造の使用をうまく目標に入れるタスクをデザインすることが可能なこと
②ある素性は、ほかのものよりも引き出すのが用意であること(様式、質問形式>複数の形容詞を含んだ名詞句)
③個々の学習者のバリエーション(学習者によって目標の構造を使ったり使わなかったり。)
④structure-based taskで、学習者はタスクを、学習ではなく、コミュニケーションの機会として認識していること(→付随的学習が可能)
・学習者が実際に目標構造をstructure-based taskの結果として学ぶことを調査した研究は数少ない。
・a rather different kind of structure-based production task
Wajnryb (1990)→ Dictoloss:学習者に、短いテキストを2回聞いた後、再構築させる手続き。テキストは特定の文法事項に焦点を当てているもので、focused taskに位置づけられる。
・気付きと目標形式の生成の促進に、どの程度dictogloss taskが効果的か。
→学習者は、テキスト再構築のために必要な言語を注意深く考えさせられるので、dictogloss taskは学習者の注意を形式に向けうると期待されている。
・Izumi and Bigelow (2000):dictoglossに類似したタスクを実施
・dictoglossは、学習者に言語形式(目標の形式とは限らないが)について話をさせる有効な手段である。
(2)Comprehension tasks:学習者に口頭または書かれたインプットにある具体的な素性を処理させるタスク。習得はインプット処理の結果として生じるという仮説に基づく。
・Input enrichment
・Input enrichmentは、目標の素性が与えられたインプット内に①頻繁で、②顕著だという方法でタスクをデザインすることに関係している。
・多くの調査研究がInput enrichmentの気付きと言語習得への効果を調査
・Trahey and White (1993):インプットがフランス語話者の英語学習者に、英語が副詞の位置を、主語―動詞間、動詞―直接目的語間に許容することを学ばせるのに十分かどうか調査
→これらの研究は、目標構造が目立たせてあるenriched inputでも、目立たせていないものも、習得を支える結果を示した(J. White, 1998)
・Input processing
・Input processing instructionはVanPatten (1996)により作られた用語。その目標は、学習者がタスクの理解に用い、学習者自身の持つストラテジーよりも良い、形式と意味のつながりを持たせる処理ストラテジーに変えること。
・3つの重要な構成要素:①形式と意味の説明、②処理ストラテジーについての情報、③structured-input活動(目標素性を処理する機会)
→重要なのは授業のstructured inputの段階(focused taskの使用に関係)
・Input processing instructionは研究者から多くの注目を集めてきた。
・VanPatten and Cadierno (1993):解釈のタスクに関するInput processingは、統制され、situationalなgrammar exerciseを含むproduction-based inputよりも効果的だ。
・この研究から、Input processing instructionのメリットが、解釈タスクの実施によるものか、もしくは処理ストラテジーに関する明示的な説明から得られたものなのかを決定するのは不可能である。
・VanPatten and Oikennon (1996):解釈タスクで与えられたstructured inputが学習においてInput processing instructionの効果に最も貢献すると提案。
・解釈タスクの習得の利点についての疑問点
① 学習を測るのに使われたテストが別々の項目(discrete-item)である点
② 多くの最近の研究では、解釈タスクのinstructionがより効果的であることが証明できていない点
⇒結論:解釈タスクを含むInput processing instructionは、discrete-itemのテストにより計測されることで学習における利点が現れる。
・これらの研究の最後の問題点→structured inputの活動が「タスク」であったかどうか、常に明らかなわけではない。(この本でいう「タスク」だったか。)
・Allen (2000):用いられている活動が、タスクに不可欠な2つの基準を満たしていない。
① 意味に主な焦点を当てていない。
② 現実世界にありうる言語処理になっていない。(authenticity)
③ 活動がうまく達成されたかどうかを測る、明示的に定義された非言語的なアウトカムがない。
⇒この活動はタスクというよりもエクササイズに近いもので、近年成されたinput-processingの研究は、structured input taskというよりむしろ、structured input exerciseについての効果を説明している。
(3)Consciousness-raising tasks
Consciousness-raising(C-R) tasksは今まで見てきたfocused taskと2つの方法で異なる。
①構造に基づく生成のタスク、enriched input、解釈タスクは暗示的学習が意図されているが、C-Rタスクは明示的学習を意図している。(理解の段階で「気づき」を生じさせる)
②今までのタスクは一般的な性質の内容を構築していたが、C-Rタスクは言語自体が内容になっている。
・C-Rタスク使用の根本的理由は、暗示的知識のまとめ役として、明示的知識の仮説的役割や、より深い処理を含む場合、学習はより重要であるという心理的研究の主張を部分的に描いている。
・Ellis (1991):C-Rタスクの主な特徴について
・C-Rタスクの例:Activity 2 of Figure 1.3, page 18
・多くの研究で、C-RタスクがL2の明示的知識を発達させるのに効果的かどうか調査されてきた。
・明らかに多くのものが、学習者のC-Rタスクの行い方に依存している。(特に学習者が達成した目標の形式への気づきのレベル)
・C-Rタスクは目標素性の理解を向上させるという結果が示されている。
(学習者にコミュニケーションの中で素性を使うという能力を習得させることにより、処理を支援する)
・C-Rタスクの価値は、それが明示的知識の発達、そして気付きの促進に効果的であるかどうかだけでなく、また学習者のコミュニケーションの機会が効果的かどうかという点にもある。
・C-Rタスクは、focus on formの達成と同時に、コミュニケーション機会の提供という点でも効果的な手段であるとように思われる。
■Implementing focused tasks
・言語焦点の達成における困難さは方法論的に克服されうるのかどうかについて議論。
□Implicit methodological techniques
・暗示的方法は、意味中心タスクを持つ方法で、学習者の目標素性の使用についてのフィードバックの提供を含んでいる。
・Nobuyoshi and Ellis (1993):明確化要求を伴う口頭でのnarrative taskにおける過去形の使用で、教師が生徒のエラーに反応するという処方。
・新たな言語知識の習得が考慮されるに当たっては、recastがより見込みのある技法。(recastは習得を援助するという強い理論的分野がある。)
・今までの習得におけるrecastの効果についての研究から一定の結果は得られていない。
・recast研究の有益さ:
①学習者が目標素性のエラーを含む発話によりタスクを行うとき、特定の言語焦点を達成できるということを証明できる点
②この焦点が、コミュニカティブに達成される点(behavior > structural practice)
③意味の交渉という状況において、暗示的なfocus on formは習得を支援する点
□Explicit methodological techniques
・学習者が、タスク実行中に目標構造に関する明示的な情報を与えられた場合、focusがタスクに加えられる。
・明示的なフィードバックは学習者に新しい形式と意味のつながりを持たせる重要な役割を果たす可能性がある。
・Samuda (2001):形式への明示的な注意は、タスクが意図した言語焦点を達成しているということを確証するのを助ける可能性がある。
→問題点:形式への明示的な注意が、タスクパフォーマンスのコミュニケーションの流れからどの程度逸らしてしまうか。
■Conclusion
・この章では、言語習得の認知理論(学習者がコミュニケーションを試みている間の、具体的な言語形式への意識的な注意をむけさせることの必要性を提案)と様々な方法によるfocused taskのデザインを調査した。(structure-based production tasks, comprehension tasks, C-R tasks)
・学習者に素性を処理させるには、注意深いデザインと、暗示的・明示的技法を含む計画的な実施が理想とされる(Samuda, 2001)
考察:
言語教育現場において授業を実施する教員は、授業計画の段階で、目標の言語形式をどのように学習者に提示し、どのように触れさせるかという点においても考慮が必要であることに気づくことができた。またこのような研究結果から、教育現場での効果的な授業デザイン・タスクデザインのあり方についても明確になってくるので、教育的意義としても有意義な研究分野であるように思う。
(山下)
ページトップに戻る
2008/10/31
Chapter 5 Focused tasks and SLA, pp. 141-151 (伊藤)
Focused tasks: 談話のうち特定の様式を要求するよう意図されている。
・ Unfocused tasks同様、タスクの基準を満たしていることが必要。特に伝達内容。
・ Focused tasksとsituational grammar exercise(場面ごとの文法練習)を区別する必要がある。Focused tasksでは対象とする特定の言語的特徴が事前に告げられておらず、注意の喚起は偶然起こるものである。一方、場面ごとの文法練習では、特定の言語的特徴が事前に知らされているため、形式への注意は意図的である。(例:Figure 5.1)
本章では、産出に関わるfocused tasksを見ていく。まずfocused tasksの心理言語学的な論理的根拠を検討し、タスクのデザインを通してどのように焦点化がなされるかを検討し、そしてタスクを実行する上で言語の焦点化をもたらすことができるいくつかの方法を紹介する。
このようなタスクは、研究者にとって学習者がある特定の特徴を習得したかどうかの測定手法となる。また教師にとっても、特定の言語要素を伝達的に、「現実の使用状況」(Johnson 1988)のもとで教える手法となる。
The psycholinguistic rationale for focused tasks(心理学的な論理的根拠)
Skill-building theories and automatic processing(技能構築理論と自動化処理)
認知心理学における自動化処理とは:記憶における特定のノード(nodes)が、適切なインプットが存在するたびに活性化することを含む。同じインプットに対して同じ活性化のパターンが何度も繰り返されることで生じる。(McLaughlin and Heredia 1996:214)
■自動化処理と操作された処理(controlled processing)
自動化処理:簡単で速い、処理容量をそれほど必要としない→形式だけでなく内容に注意を向けることができるなど、より高次の能力を使うことができるようになる。
しかし、自動化処理を抑制する・変えることは難しい。
操作された処理:簡単に構築され、柔軟であるが、処理容量をたくさん使う→形式に関して操作された処理を使うと、内容に注意を向けることが難しくなる。
■再構築(restructuring):自動化処理は、言語処理をただ強化したり早くしたりするだけでなく、知識を新しい形式に再構成する、再構築を含む。
■宣言的知識(declarative knowledge)と手続き的知識(procedural knowledge)
技能の発達は、宣言的知識が手続き的知識となる過程(知識の編集・手続き化の2つの段階)を含む。
では、自動化処理(=手続き的知識)はどのように発達させられるのか?
→自動化処理は操作された処理から発達したものである。Anderson(1993,2000)によれば、技能の発達は宣言的知識(言語に関する事実)から始まり、手続き的知識(目標に似たコミュニケーション行動)に終わる。(※但し、全ての知識が初めから宣言的であるとは限らず、また、手続き的知識の発達によって必ずしも宣言的知識が失われるとも限らない。)
以上から、学習者は、初めに宣言的知識を教えられることが手助けとなると考えられる。Johnson(1996)は、言語のある特定の一点について「説明」することが効果的なスターティング・ポイントとなるだろうとしている。しかし、指導においては明示的に説明するより、むしろ「ヒント」を与えることが宣言的知識を手続き的知識とするのに効果的だとしている。
■宣言的知識を手続き的知識にするための練習(practice)
宣言的知識を手続き的知識にするためには、その実践において注意が必要となくなるまで技能を何度も何度も反復練習する必要がある。
言語学習において練習とは、以前は特定の目標を産出することを何度も行う過程のことを指していたが、近年では「構造」より「行動」における練習の重要性が認識されるべきであるとされる(DeKeyser,1998)。行動を変える、すなわち自動化処理を発達させるためには、実際の行動そのものの練習=コミュニケーションを行うことが必要である。
⇒Focused tasksにおけるコミュニケーション練習によって、宣言的知識として存在していた言語構造を手続き的知識に変えることが期待される。
■学習過程でのフィードバックの重要性(Johnson 1988, 1996)
指導順序は学習(learn)→遂行(perform)→学習、のほうが、伝統的な学習→遂行よりも効果的である。そして学習者は、遂行の過程で間違いの訂正のフィードバックを受ける機会を与えられるべきである。このフィードバックとは、正しい形式のモデルとなる外部からのもの(ex.教師など)であると最も良い。
・ここで考えられる教授方法はタスクに基づくものであり、特にFocused tasksである。ただし学習者が最初に練習すべき形式を伝えられてしまうと、タスクは場面ごとの文法練習となってしまい、「行動」より「構造」を練習するようになってしまうという危険がある。
Theories of implicit learning(暗示的学習の諸理論)
暗示的知識がどのように習得されるのか、またその過程で明示的知識が果たす役割について見ていく。
■暗示的学習(implicit learning)
複雑で刺激的な環境の根底にある構造についての知識の習得のことで、自然に、単純に、意識的な操作のない過程を経て習得されるものである。
⇒暗示的学習とは①無意識的に起こり②自動的である という2つの基本的な特徴を持つ。
・暗示的学習は連合的学習(associative learning):インプットに規則の暗示的な抽象概念があるというよりは、非常に複雑なネットワークの発達が時間を経て確立されることによって規則的な行動が生じると考えられる。(N. Ellis 1994:1)
⇒この視点から考えると、暗示的学習は言語表象におけるコネクショニスト・モデルを必然的に伴うものである。
L1習得は始めから暗示的学習でなされているという一般的な見解があるが、L2に関してはinterface position とstrong/weak non-interface positionに分かれる。
□(第4章より)明示的知識は暗示的知識に変化しないという説(non-interface)(Krashen,1981, Zobl,1995, Hulstijn,2002)/接点(interface)があるとする強力な説(Sharwood Smith,1981, DeKeyser,1998)/明示的知識が暗示的知識に変わるというよりも、明示的知識が暗示的知識の発達を促進させるという説(weak-interface)(Ellis,1994)
⇒暗示的学習と技能構築の理論との間にある違いとは、明示的知識がどのような役割を果たすかと言う点にある。
技能構築の理論:明示的知識は、コミュニケーション練習を通して、暗示的知識にやがて変わるものとみなす。(interface)
暗示的学習:学習者が明示的知識と暗示的知識を習得する過程は、それぞれ本来的に異なったものとみなす。(non-interface)
・ Ellis(1993 and 1994)は、SchmidtのNoticing Hypothesisに基づき、明示的知識は暗示的学習を①気付きの過程(=noticing the whole) ②noticing-the-gapの2つの側面から促進するとするweak-interfaceのモデルを提示している。このモデルでは、暗示的学習とは(1)インテイク(形式が短期記憶に取り込まれる過程)と (2)暗示的知識の学習(形式が長期記憶に取り込まれる過程)の2つの段階を含む過程として特徴付けられる(Figure 5.3)。
・ また、N.Ellisもこれに近いことを述べている。両者とも、暗示的学習は明示的知識に依存しているわけではなく、むしろ明示的知識を含む過程は二次的なもので、暗示的学習を補完するものだとしている。
⇒コミュニカティヴ・ランゲージ・ティーチングのような、真正なコミュニケーション活動を作り出せるような環境づくりの必要性。
・この理論を基として言語カリキュラムとして考えられるのは、個々の構成要素があるもの、(タスクに基づいた指導を通して)暗示的知識を発達させることに主眼を置いたもの、目標言語における主要な側面についての認識を発達させることに主眼を置いたもの、がある。
※言語そのものをタスクの内容にすることで、明示的な知識を発達させる可能性がある。⇒章後半
まとめ
ここまで、異なる二つの認知的な学習の立場について説明してきた。
①言語学習を技能学習として見る(練習を通じて自動化処理に変える)立場
1. 言語の宣言的知識を教える必要性
2. コミュニカティブな練習がされる必要性
3. フィードバックの必要性
・Focused tasksは、特定の言語形式に焦点を当てたコミュニカティブな練習を提供する役割を担うことが出来る。
②学習が暗示的な過程であり、明示的な知識によって促進されるとする立場
1. コミュニケーションを通じて暗示的に学習する機会が与えられる必要性
2. コミュニケーションを行う際に形式に注意を向ける重要性
3. 形式への注意を促進させるために明示的知識を個々に教える必要性
・Unfocused tasksの使用が最も適当と考えられるものの、特定の言語形式を暗示的に学習するためのコミュニケーションを行うといった点では、focused tasksも有用と考えられる。
コメント
Focused tasks とSituational grammar exerciseとを区別することが重要であると何度も強調されている。形式への注意が意図的であるか、偶然的であるかは見落としてしまわないよう注意が必要である。
Focused Tasksの有用性を考えるとき、暗示的学習が学習に効果的であるかどうかが大きく関わってくるが、その実態(=interfaceの有無)には諸説あり、いまだに明らかになっていない。なお、暗示的学習のinterface/non-interface positionに関しては、Ellisの記述でもinterface がstrong/weakである場合とnon-interfaceがstrong/weakである場合がある。
(伊藤・平井)
ページトップに戻る
2008/11/14
Chapter 5, pp. 151-173
■Design focused tasks:focused taskのデザインで設定する主要な3つの方法について
(1)Structure-based production tasks
・Loschky and Bley-Vroman (1993):structure-based communication tasksについて議論。目標言語の素性を組み込むために製作されたタスクを3つの方法で区別(①タスクの自然さ、②タスクの有用性、③目標素性のタスクの本質)。またstructure-based taskがどんな習得の側面に影響しやすいか、についても言及。
・Tuz (1993):instructionの一部としてのタスク使用(修飾的な形容詞[ex. Two small round white buttons ]の練習タスク)。結果、6人中1人の生徒が形容詞の順序に関するタスクを達成した。
・Sterlacci (1996):modal verbsの生成的使用を引き出そうとデザインされたタスクが、実際にそれを引き出しているか調査。結果として、タスクは目標構造を引き出し、学習者に意図的にそれを使わせることはなかった(→situational grammar exerciseではない)。
・Mackey (1999):質問形式を引き出すタスクの使用に関して調査。タスクが母語話者との会話の場合、特定の質問形式を生成するのは困難だったが、繰り返すことにより、より目標に近い理解可能な質問形式になった。この点に関して、学習者はどの形式が成功に近いか理解し、タスクの達成に必要な情報を引き出すようになるということが言われている。
・structure-based production taskの妥当性についてわかったこと
①具体的な文法構造の使用をうまく目標に入れるタスクをデザインすることが可能なこと
②ある素性は、ほかのものよりも引き出すのが用意であること(様式、質問形式>複数の形容詞を含んだ名詞句)
③個々の学習者のバリエーション(学習者によって目標の構造を使ったり使わなかったり。)
④structure-based taskで、学習者はタスクを、学習ではなく、コミュニケーションの機会として認識していること(→付随的学習が可能)
・学習者が実際に目標構造をstructure-based taskの結果として学ぶことを調査した研究は数少ない。
・a rather different kind of structure-based production task
Wajnryb (1990)→ Dictoloss:学習者に、短いテキストを2回聞いた後、再構築させる手続き。テキストは特定の文法事項に焦点を当てているもので、focused taskに位置づけられる。
・気付きと目標形式の生成の促進に、どの程度dictogloss taskが効果的か。
→学習者は、テキスト再構築のために必要な言語を注意深く考えさせられるので、dictogloss taskは学習者の注意を形式に向けうると期待されている。
・Izumi and Bigelow (2000):dictoglossに類似したタスクを実施
・dictoglossは、学習者に言語形式(目標の形式とは限らないが)について話をさせる有効な手段である。
(2)Comprehension tasks:学習者に口頭または書かれたインプットにある具体的な素性を処理させるタスク。習得はインプット処理の結果として生じるという仮説に基づく。
・Input enrichment
・Input enrichmentは、目標の素性が与えられたインプット内に①頻繁で、②顕著だという方法でタスクをデザインすることに関係している。
・多くの調査研究がInput enrichmentの気付きと言語習得への効果を調査
・Trahey and White (1993):インプットがフランス語話者の英語学習者に、英語が副詞の位置を、主語―動詞間、動詞―直接目的語間に許容することを学ばせるのに十分かどうか調査
→これらの研究は、目標構造が目立たせてあるenriched inputでも、目立たせていないものも、習得を支える結果を示した(J. White, 1998)
・Input processing
・Input processing instructionはVanPatten (1996)により作られた用語。その目標は、学習者がタスクの理解に用い、学習者自身の持つストラテジーよりも良い、形式と意味のつながりを持たせる処理ストラテジーに変えること。
・3つの重要な構成要素:①形式と意味の説明、②処理ストラテジーについての情報、③structured-input活動(目標素性を処理する機会)
→重要なのは授業のstructured inputの段階(focused taskの使用に関係)
・Input processing instructionは研究者から多くの注目を集めてきた。
・VanPatten and Cadierno (1993):解釈のタスクに関するInput processingは、統制され、situationalなgrammar exerciseを含むproduction-based inputよりも効果的だ。
・この研究から、Input processing instructionのメリットが、解釈タスクの実施によるものか、もしくは処理ストラテジーに関する明示的な説明から得られたものなのかを決定するのは不可能である。
・VanPatten and Oikennon (1996):解釈タスクで与えられたstructured inputが学習においてInput processing instructionの効果に最も貢献すると提案。
・解釈タスクの習得の利点についての疑問点
① 学習を測るのに使われたテストが別々の項目(discrete-item)である点
② 多くの最近の研究では、解釈タスクのinstructionがより効果的であることが証明できていない点
⇒結論:解釈タスクを含むInput processing instructionは、discrete-itemのテストにより計測されることで学習における利点が現れる。
・これらの研究の最後の問題点→structured inputの活動が「タスク」であったかどうか、常に明らかなわけではない。(この本でいう「タスク」だったか。)
・Allen (2000):用いられている活動が、タスクに不可欠な2つの基準を満たしていない。
① 意味に主な焦点を当てていない。
② 現実世界にありうる言語処理になっていない。(authenticity)
③ 活動がうまく達成されたかどうかを測る、明示的に定義された非言語的なアウトカムがない。
⇒この活動はタスクというよりもエクササイズに近いもので、近年成されたinput-processingの研究は、structured input taskというよりむしろ、structured input exerciseについての効果を説明している。
(3)Consciousness-raising tasks
Consciousness-raising(C-R) tasksは今まで見てきたfocused taskと2つの方法で異なる。
①構造に基づく生成のタスク、enriched input、解釈タスクは暗示的学習が意図されているが、C-Rタスクは明示的学習を意図している。(理解の段階で「気づき」を生じさせる)
②今までのタスクは一般的な性質の内容を構築していたが、C-Rタスクは言語自体が内容になっている。
・C-Rタスク使用の根本的理由は、暗示的知識のまとめ役として、明示的知識の仮説的役割や、より深い処理を含む場合、学習はより重要であるという心理的研究の主張を部分的に描いている。
・Ellis (1991):C-Rタスクの主な特徴について
・C-Rタスクの例:Activity 2 of Figure 1.3, page 18
・多くの研究で、C-RタスクがL2の明示的知識を発達させるのに効果的かどうか調査されてきた。
・明らかに多くのものが、学習者のC-Rタスクの行い方に依存している。(特に学習者が達成した目標の形式への気づきのレベル)
・C-Rタスクは目標素性の理解を向上させるという結果が示されている。
(学習者にコミュニケーションの中で素性を使うという能力を習得させることにより、処理を支援する)
・C-Rタスクの価値は、それが明示的知識の発達、そして気付きの促進に効果的であるかどうかだけでなく、また学習者のコミュニケーションの機会が効果的かどうかという点にもある。
・C-Rタスクは、focus on formの達成と同時に、コミュニケーション機会の提供という点でも効果的な手段であるとように思われる。
■Implementing focused tasks
・言語焦点の達成における困難さは方法論的に克服されうるのかどうかについて議論。
□Implicit methodological techniques
・暗示的方法は、意味中心タスクを持つ方法で、学習者の目標素性の使用についてのフィードバックの提供を含んでいる。
・Nobuyoshi and Ellis (1993):明確化要求を伴う口頭でのnarrative taskにおける過去形の使用で、教師が生徒のエラーに反応するという処方。
・新たな言語知識の習得が考慮されるに当たっては、recastがより見込みのある技法。(recastは習得を援助するという強い理論的分野がある。)
・今までの習得におけるrecastの効果についての研究から一定の結果は得られていない。
・recast研究の有益さ:
①学習者が目標素性のエラーを含む発話によりタスクを行うとき、特定の言語焦点を達成できるということを証明できる点
②この焦点が、コミュニカティブに達成される点(behavior > structural practice)
③意味の交渉という状況において、暗示的なfocus on formは習得を支援する点
□Explicit methodological techniques
・学習者が、タスク実行中に目標構造に関する明示的な情報を与えられた場合、focusがタスクに加えられる。
・明示的なフィードバックは学習者に新しい形式と意味のつながりを持たせる重要な役割を果たす可能性がある。
・Samuda (2001):形式への明示的な注意は、タスクが意図した言語焦点を達成しているということを確証するのを助ける可能性がある。
→問題点:形式への明示的な注意が、タスクパフォーマンスのコミュニケーションの流れからどの程度逸らしてしまうか。
■Conclusion
・この章では、言語習得の認知理論(学習者がコミュニケーションを試みている間の、具体的な言語形式への意識的な注意をむけさせることの必要性を提案)と様々な方法によるfocused taskのデザインを調査した。(structure-based production tasks, comprehension tasks, C-R tasks)
・学習者に素性を処理させるには、注意深いデザインと、暗示的・明示的技法を含む計画的な実施が理想とされる(Samuda, 2001)
考察:
言語教育現場において授業を実施する教員は、授業計画の段階で、目標の言語形式をどのように学習者に提示し、どのように触れさせるかという点においても考慮が必要であることに気づくことができた。またこのような研究結果から、教育現場での効果的な授業デザイン・タスクデザインのあり方についても明確になってくるので、教育的意義としても有意義な研究分野であるように思う。
(山下)
ページトップに戻る
2008/11/21
Chapter 6 Sociocultural SLA and Tasks, pp 175-185.
これまで見てきた様々なSLA理論は、「人の心は言語的インプットを処理した結果生まれ、アウトプットを算出するためにアクセスされるような知識を含むようなブラックボックスである」といった考えに基づいている。
本章では、SLAにおいてこれとは異なるもうひとつのパラダイムを構築する、社会文化的な心の理論(SCT : sociocultural theory of mind)を見ていく。そして、Task-basedの研究にどのような貢献が可能かを見ていく。
■ Mediated learning
・ 社会文化的理論における中心的で特徴的な概念は、より高度な形式の脳内活動は媒介されている(mediated)点である(Lantolf, 2000a)。この理論は、媒介された心がどのように社会的活動において発達するのかを説明しようと試みている。
・ 媒介(mediation)は3つの方法で起こりうる(Vygotsky, 1978)
①物質的な道具を通して、②他人との相互交渉を通じて、③記号(言語など)を通して。
・ 第二言語学習における媒介とは(Lantolf, 2000a):①社会的な相互交渉における他人による媒介、②私的な会話(private speech)による媒介、③タスクや技術などの人工物による媒介。
・ 社会文化的理論を主張する研究者たちは、発達とは、知識を持つことではなく社会的活動に参加することだと述べている⇒習得(acquisition)よりも参加(participation)。
⇒この立場からだと、L2の「使用」と「知識」の違いが曖昧。
・したがって、SCTに基づいた研究ではpre-test, post-testの使用は避けられてきた。
■ Verbal interaction and learning
・ 媒介の第一の役割とは言語的相互交渉である。そのため、SCTは学習を対話的なものとみなす。
・ Artigal (1992)は、LADが学習者の頭の中ではなく、相互交渉の中にあるものだと述べている。⇒L2習得は純粋に個別的なものではなく、他人との間で共有されるもの。
・ 言語的相互交渉は一人でも複数人でも可能で、両方が学習の媒介となり得るが、複数人での相互行為が中心的であると見られる。複数人での談話から、学習者が補助なしで何ができ、何ができないかを発見することができる。
・ 話者間の活動と脳内活動の間には近い関係がある(前者が後者を先行する)。Vygotsky (1981) によれば、子どもの発達から見ると、最初は社会的な次元において発達が見られ、次に心理的な次元でみられる。最初は対人間で現れ、次に子どもの中で現れるのである。
・ 言語的相互交渉の主な役割には、子どもが他人による規制から自己規制へ進行することがある。
・ 以上を言語学習にあてはめると、学習者はまず新しい言語形式・機能を他人との相互交渉で表し、そしてその後に、自分一人で使えるようになるために内部化する。またコミュニケーションを要求される場面(communicatively demanding situation)では、新しい形式を使うことがうまくできずに、バックスライディングが起こることが多い。
・ タスクは学習者に、学習のための機会を提供することができる:①他人と協力して新しい言語形式を使うため、②次に、比較的難しくないタスクにおいて、内部化した構造をより独立して使用するため、そして③最後にその構造をより認知的に複雑なタスクにおいて使用するため。
⇒学習は、学習者が何らかの目標を達成するために実際に新しい技能を使用するときに起こる。インプットにある未知の言語形式を理解するだけではなく、実際に産出することが望まれる。
・ このような視点から、タスクは共同的な作業を構築するための道具と考えられるが、ただしそれが誰によって使用されるものであるかを考慮しなくてはならない。
■ Private speech
・ Ohta (2001b:16)の定義によれば、private speech(独り言)とは「聞き手に向けられていない音声化された発話」である。口まね (imitation)、他人に向けられた質問を自分が答える場合、など。
・ 幼い子どもは他人がまわりにいても独り言を口にすることが多いが、これは活動のための脳内機能を制御するために必要と考えられる。
・ 大人の独り言の場合も、「難しいタスクに直面した場合、内部の順序を外部化することで自身を制御できる(Foley, 1991: 63)」。
・ 聞き手ではなく話し手自身に向けられているため、社会的スピーチとは異なるものによって制御される。L2学習者の独り言においては:①自分自身に向けた発話ではL1を使う可能性があり、また②L2を使ったとしても、目標である形式はたとえ内部化されていても使わない可能性がある。したがって、「逸脱(deviance)」の概念は容易に独り言に適用することはできない。
・ タスクのパフォーマンスが社会的か、個人的かを区別する必要がある。
■ The zone of proximal development
・ 個人の発達のうち、実際的(actual)/潜在的(potential)レベルの間にある違いを説明するために、Vygotsky (1978) は隣接面発達の領域(The zone of proximal development : ZPD)のたとえを用いた。
実際的レベル:個人が既に見に付けた技能
潜在的レベル:個人が他人に(もしくは何らかの媒介によって)補助された場合に行うことができる技能
学習された技能は、また次の新しい技能の習得が可能となるような新たな領域を作り出す元となる。
・ 効果的なTask-based Learningのためには、学習者がZPDを動的に構築するようなタスクである必要がある。この点を見るとZPDはKrashenのi+1の考えに近いが、Dunn and Lantolf (1998)は、Krashenのi+1は言語の特徴を対象としているのに対し、ZPDは学習に関する個人に適応されるものだとする異論を唱えている。Lantolf (personal correspondence)は、習得順序は個人間の差に依存すると論じている。
・ ZPDはSCTの重要な構成概念であり、学習に関わる重要な現象をいくつも説明できる。
①外部の補助があるにも関わらず、学習者が失敗することがあるのはなぜか→必要なZDPを構築できていないから。
②一人ではできなくとも、補助があればできる構造があるのはなぜか→構造を内部化できていなくても、ZPDを構築することは出来ているから。
③学習者はどうやって新たな構造を内部化するのか→必要なZPDを構築したところに、外部の媒介を経て、構造を割り当てるから。
・ タスク研究への示唆:学習のための状況を作り出すのはタスクそのものではなく、学習者がどうやってタスクに取り組むか(活動)であるということ。タスクは、適切なZPDが作られるためにはどこに補助が必要なのかを見極めるために、学習者によって使用される道具にすぎない。
■ Scaffolding, collaborative dialogue, and instructional conversations
・ SCTでは、新しい技能の発達のうち社会的な側面はscaffoldingの概念として扱われる。scaffoldingとは、話者が一人では行うことの出来ない機能を行うために、もう一人の話者が補助する談話プロセスのことである。
Wood, Bruner, and Ross (1976) によるscaffoldingの特徴の定義:
① タスクに興味をひかせる
② タスクを単純化する
③ 目標に向かって続けさせる
④ 必要とされる特徴や、産出されているものと理想的な解答の間の不一致を示す
⑤ 問題解決までのフラストレーションを抑える
⑥ 理想となるパフォーマンスをしてみせる
・ このように、scaffoldingはタスクの認知的要求と学習者の情緒的な状態の両方に関わる。この点においてscaffoldingは、相互交渉仮説(言語学習のうち認知的側面しか扱わない)よりさらに多くを包含するといえる。
・ scaffoldingの様々な特徴→例:Ellis (1985)(pg.181後半)
・ 学習者が熟練した教師と共にタスクを行う場合、学習の機会は最大限になる。
・ 学習者の2人ともが1人の場合はタスクを達成できなくても、2人で協力することで達成できる可能性があるといった明らかな証拠がある。
・ scaffoldingは、談話においてより一般的な特徴の一つとして捉えられる。van Lier (1992)はこれを偶発性(contingency)と呼んだが、これは談話内での一貫性を生むために一つの発話が他の発話とつながることを指す。van Lierによれば、偶発性は発話への動機付けが話し相手にとって明らかであり、加えてそれが期待された通りに機能する場合に達成される。「偶発性は社会的なプロセスが認知的なプロセスに移行するための必要な材料」として見られる。
・ scaffoldingは習熟度の低い学習者について、社会的な相互行為を通した学習が起こる手段となる。
・ 最近の研究では、scaffoldingではなくcollaborative dialogue, instructional conversationの用語が好まれる傾向にある。
collaborative dialogue:話者が問題解決や知識の構築に関わっている談話(Swain, 2000: 102)
instructional conversation:教師主導で教育課程上の目標に向けられた、教育的な相互交渉(Tharp and Gallimore, 1988)
・ タスクでscaffolding, collaborative dialogue, instructional conversationが起こると、学習者がL2知識を拡大する機会は増えると考えられる。しかし、このような機会はタスクそのものではなく、タスクがどのように行われるかで作られることは明らかである。
■ Activity theory
・ Lantolf (200b: 8)は、activity theoryを「Vygotskyの当初の提議を、人間の本質や修正を元に統一させたもの」と述べている。
・ 学習者は動機(motive)を持っているが、個人が持つそれぞれの動機によって同じタスクでも異なるように行われる。
・ Activity theoryは3つの認知の側面を区別する:動機(なぜ行われたのか)・目標(何が行われたのか)・実施(operation:どうやって行われたのか)(Lantolf and Appel, 1994a: 21-2)
・ 異なる人々が異なる動機でタスクを行うため、その活動(activity)もそれぞれ異なるものになり得る。
・ そのため、タスクを行いその相互交渉を理解する際には、協力者がタスクを行うに至ったその動機を把握しておく必要がある。
■ Summary and final comment
・ SCTはタスクを研究するための手段としては不完全である。未解決の問題には以下のようなものが挙げられる。
・学習者は、共同的な活動を通じて達成する新しい言語形式をどうやって一人で内部化し、達成できるようになるのか?
・全ての形式が内部化されるのかそれとも一部の形式か、そして一部の場合はその原因はなにか?
・偶発性は、変化(tranformation)を起こすためにはなぜ重要なのか?
・変化が起こったことはどうやって証明されるのか?
・言語習得に関わるところでは隣接面発達の領域はどう働くのか?
このような限界はあるものの、SCTはSLAにおける今までの心理言語学的な不均衡を、タスクの社会的・文化的な側面を強調することで是正したという点で重要である。
コメント
ここではこれまでと異なり、タスクが持ち得る社会的・文化的な意味合いについて論じられている。見落としがちではあるが、タスクを使用する際にはこれらの要素も併せて考慮する必要があるだろう。Scaffolding(collaborative dialogue, instructional conversation)がタスクの一要素として論じられていることは興味深く、タスクの中でどのようにscaffoldingが行われているかが研究される必要があるだろう。
(伊藤・平井)
ページトップに戻る
2008/12/05
Chapter 6 Sociocultural SLA and Tasks, pp. 185-202.
<Task-based research based on a sociocultural theory of the mind>
Vygotsky的考え方では、言語学習にはdialogic talkを介するものと、monologic talkを介するものがある。ここではnon-reciprocal tasksとreciprocal tasksの両方を扱うが、キーとなるのは、SCTの見地から学習者がどのようにactivityを構築するかということと、task(またはactivity)が学習を引き起こす媒体としてどのように働くか、ということの2点である。後者については、collaborative activity・metatalk・private speechの役割について研究で明らかになっていることを述べる。
1. Constructing an activity out of a task
■同じタスク(task)でも、学習者や時が変われば異なる活動(activity)が行われる。これは個々の学習者が様々な動機(motives)や目標(goals)を持ってタスクに臨み、またそれらは変化しうるものだからである。
1.1 Task vs. activity
■Coughlan and Duff (1994)は、カンボジアとハンガリーの学習者に異なる条件でpicture description taskを行わせ、それぞれが異なるactivityをしたことを観察した。これを踏まえ、picture description taskは「自然なコミュニカティブ活動(natural communicative activity)」ではないとし、taskは不変のものでなく、それによって生み出されるactivityはいつも独特であるとしている。
■同様に、学習者が持つ動機が違ったり、目標について異なる解釈をするために、taskにおいて様々なactivityが行われることが多くの研究で明らかになっている(e.g. Platt & Brooks 1994; Foster 1998; Wang 1996; Roebuck 2000)。
■これらの研究結果はDonato(2000)の、taskは一般化できるものでもなければ、学習者をある特定の方法で活動するように操作できるものでもない、という主張を支持している。
■よってtaskは、学習者たちが持つ動機や目標にそって、彼らにより「組み立てられる(constructed)」ものであると言える。このような概念はintersubjectivity(学習者間主観性?)と呼ばれる。
1.2 Orientation
■orientationとは、学習者のtaskに対する見方や目標の特徴や、taskを達成するために用いる操作(operations)のことを指す。これは学習者がそのtaskを行ったことがあるかなどの経験に影響される。
■Brooks(1990)のスペイン語学習者を対象とした実験では、学習者はcue cardsを用いたtaskでコミュニケーションすることではなく、形容詞を正しく用いることを目標としていた。これは普段の授業が言語形式に焦点を置いたものであったからであると考えられ、学習者のtaskへの反応の仕方はclassroom settingにもよることを表している。
■Platt & Brooks(1994)やBrooks & Donato(1994)は、学習者のmetatalk(taskの行い方について学習者どうしで話し合うこと)がtaskへの取り組みに違いを生むことを明らかにした。
■Appel & Lantolf(1994)の実験では、taskそれ自体の性質も影響を及ぼすことが、2種類のテクスト(expository vs. narrative)を用いたtext-recall tasksで明らかになった。
1.3 Intersubjectivity
■学習者はintersubjectivityを構築することで、taskに対する共通の動機と目標を学習者間で共有する。
■DiCamilla & Anton(1997)は、repetitionがインプットを増やしたり理解可能なものにするだけでなく、intersubjectivityの構築に寄与することを明らかにした。
1.4 Goal-directedness and L2 acquisition
■Chapter3で出てきたEllis & He(1999)の実験では、ペアで目標項目について話し合った学習者のほうが、premodified inputを与えられた学習を凌いだ。これは学習者がtaskをcollaborative problem-solving activityであると認識して協力したからだと考えられ、taskから生じるactivityはそこで学ばれるものについて影響を与えることを示唆している。
■学習者の動機や目標は学ばれる内容に重要な影響を及ぼすが、学習と直接(directly)結びついているのではなく、非直接的に(indirectly)に結びついている。つまり、taskを楽しいものにしたり、創造的にすることで生まれる動機や目標によりoperationsが左右されるのは、偶然によるものであるということである。
2. Tasks as instruments of cognitive change
■SCTの考えでは、task駆動型のactivityにおける学習者の認知的な発達は、obejct-regulation→other-regulateion→self-regulationという順に進むが、以下の条件を伴う。(1)学習者どうしでscaffoldingがある、(2)metatalkにより言語形式に対する学習者の意識が高くなっている、(3)思考を整理するために学習者がprivate speechを行っている。
2.1 Scaffolding and collaborative dialogue
■Aljaafreh & Lantolf(1994) やNassaji & Swain(2000)により、regulatory scaleを用いて、学習者の熟達度(or ZPD)にあわせ、段階的(explicit→implicit)なfeedback/scaffoldingを与えることが有効であることがわかった。
■しかしscaffoldingのレベルを量るには相当の技量が必要で、Lantolf & Aljaafreh(1995)やSchulte(1998)の実験では、学習者が適切なレベルのscaffoldingを与えられなかったために学習が十分に行われなかったことがわかった。
■教師-学習者のinteractionによりscaffoldingを調整することはライティングを通して行うことも可能である。Nassaji & Cumming(2000)では、教師が学習者の10ヶ月間のjournal writingに対してrequesting・evaluating・predicting・giving directionsなどのフィードバックを行った。学習者の熟達度が上がるにつれ、フィードバックの特徴もYes/Noで答えられる易しい質問から、"why"や"how do you"などのより要求度の高いものへと変化し、その量も減少していった。
■scaffoldingは学習者間でも行われ、metatalkにおけるrepetitionもその1つである。role-playなどでの学習者のexpert/noviceの役割は流動的で、学習者が相互作用するなかで変化しうる。
■Donato(1994)やdictogloss taskを行ったSwain(1994)、またmetacognitive strategy traingingに焦点をあてたHolunga(1995)、L2日本語学習者を対象としたOhta(2001)の実験のいずれでも、学習者のcollaborative scaffoldingがあった場合に言語学習が最も促進されたことを報告している。
■一方、学習者間のscaffoldingはacademic languageの発達には効果的でない(Platt & Troudi 1997)や、学習者間でフィードバックをさせる場合も、学習者が録音したり書いたものに教師がフィードバックを与え、介入する必要がある(Swain & Lapkin 1998)、などの意見もある。
2.2 Metatalk
■taskを行うために学習者が用いるmetatalkでは、学習者が言語形式について話し合うlanguage- related episodes(LREs)が生ずる。このプロセスは学習者が新しい言語形式を明示的知識としてinternalization(内在化?)するのを助ける。
■Swain & Lapkin(2001)では、対話をしながら英文を修正していくreformulation taskを学習者に行わせた。この結果、学習者が行った修正のうち78%は正しいもので、修正のお手本とは異なる表現も正しく多く産出できたことがわかった。
2.3 Private speech
■private speechは次の3つがあり、熟達度が上がるにつれprivate speechには頼らなくなる。
・object-regulated :taskを達成するストラテジーとしてのもの
・other-regulated :他者または自分に質問する形をとるもの
・self-regulated :自分が問題を理解したことや困難の原因を知らせるもの
■private speechが多く産出される場合として、taskの実施方法の認知負荷が高い、現実的な場面設定である、ことがわかっている。
■private speechが言語習得を促進するかどうかということについては確たる証拠がない(cf. Lantolf 1997; Ohta 2001)。
■private speechの研究はその実施方法に決まった定義がないので、言語使用のコーパスを見た場合に、何がprivate speechを構築しているのか決定することが困難である。
3. Summary and conclusion
本章の概要は省略し、ここで述べられている問題点等をまとめる。
■SLAにおけるSCTの研究が成熟していないために、学習者がtaskに参加すること(participation)することにのみ焦点を当て、どのように言語を内在化(internalize)させるかという点を見逃しがちである。社会文化的なSLAは、学習者のZPDを明らかにする方法をきちんと定義することで利益が得られる。
■認知的な機能は時間をかけて研究されるべきなのに縦断的な研究が少ない。
■taskはactivityの本質を決める装置であり、学習者が「練習するコミュニティー」として重要な位置を占めるものであるという認識が大事。
■taskについてのcomputational(?)な見方とsocioculturalな見方の折り合いをつけるためには、1) 2つのアプローチを統合する、2) 理論の多元性を認め、それぞれの見方を生かす、の2つの方法がある。
■taskはplanされたものとimproviseされた(即興的に作られた)ものとのバランスが重要である。SCT的視野を持つことの利点は、taskで行われるactivityがplanしたものと違った場合でも、それが計画の貧弱さや教え方の悪さから生ずるものでなく、個々の学習者の持つ異なる動機や目標により生じたものであると理解できるということである。
カンボジア:研究者宅・普段のミーティングの一環として・1時間
→ダイアログ風、相互の活発なやりとり、2人の役割が入り混じる。
ハンガリー:学校で・1回限りのミーティングとして・20分
→被験者の解釈にばらつきが生まれ、活動の目標が様々に。
■Platt and Brooks (1994)によれば、role-play taskは学習者により異なる解釈がされる。
■Foster(1998)は、taskにおいて学習者がどのようなactivityを行うか決定する際の、彼らの動機(motives)や目標(goals)の重要性について調べた。4つのtaskを行わせたが、学習者はtaskを楽しむよう動機づけられたことで、negotiated input/outputがあまり生みだされなかったことがわかった。
■Wang(1996)でも
■Roebuck(2000)
Scaffolding(explicit/implicit)
■Aljaafreh & Lantolf(1994)は、regulatory scaleを用いて、学習者の書いたエッセイにチューターが与えたフィードバックがどれくらいimplicit/explicitであるか調べた。その結果、学習者の力が伸びるにつれフィードバックがimplicitになっていくことがわかった。
■Nassaji & Swain(2000)では、regulatory scaleをもとに調整されたフィードバックを与えられた学習者と、ランダムのフィードバック(random feedback)を与えられた学習者の冠詞の習得の度合を比較した。その結果、後者はあまり効果がなく、学習者のZPDをもとに調整されたフィードバックは段階的に与えることで効果があることがわかった。
Collaborative Scaffolding
■Donato(1994)は大学生のフランス語学習者のグループを対象に、動詞の習得におけるcollective scaffoldingの効果を検証、taskの前にはどの学習者も知らなかった動詞の正しい形式を、構築することができるようになった。
■Swain(2000)では、1)metacognitive strategy + communicative practice、2) metacognitive strategy + verbalize the strategies + communicative practice、3)communicative practice onlyの3グループで動詞の正しい形の習得効果への影響を調べた結果、2)で最も効果が高かったことがわかった。
■Ohta(2001)では、縦断的な観察を行い、L2として日本語を学ぶ学習者が、互いにscaffoldしあって個々の力を超える発話をしたことを報告している。
Private Speech
■oral narrative tasksは様々な方法で行われるが、複数の絵を1つずつ見せられたほうが、複数の絵を同時に見せて発話を求めるよりも認知的なストレス(cognitive stress)が多く、private speechを増加させる。同様の理由でnarrative textよりもexpository textのほうが多くのprivate speechを生む。
■simulation gamesでも、想像的な場面設定よりも現実的な場面設定のほうがprivate talkを多く生む。
<議論内容>
学習者を助けるscaffoldingが何かについての質問が出た。有名な言葉だが、具体的にどのような形となって指導もしくは学習過程に現れるかは意外と知られていない。Ellisの今回読んだセクションではscaffoldingが教師-学習者間、生徒-生徒間の両方で可能であることが述べられており、奥が深そうな用語である。
(平井、大木)
ページトップに戻る
2008/12/19
Chapter 7 - Designing Task-Based Language Courses, pp. 205-xx.
0. Introduction
■言語カリキュラムには「何を教えるか(design)」「どう教えるか(methodology)」の両面があり、この章では「design」について扱う。
■designとmethodologyは相互に関連があるが、潜在的には常に区別できるものである。
<Design> <Methodology>
structural syllabus PPP
consciousness-raising task
■タスクを中心とした教授法では焦点が「outcomes of instruction(=指導の結果得られる言語知識)」ではなく「processes
of learning(=学習するために学習者は何をすべきか)」にあるので、この2つの区別(design-methodology)とは無関係のようだが、カリキュラムを組み立てるにあたり、「どのようなタスクを入れるか(content)」と「どのようにそのタスクが用いられるか(methodology)」はともに重要である。
1. A framework for task-based course design
■タスク中心のシラバスを計画するにあたり考えるべきことを表にまとめた。
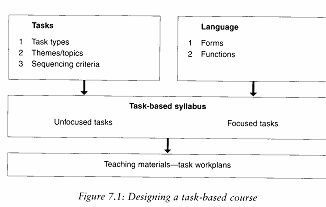
2. The rationale for task-based courses
■このセクションでは、タスク中心の教授法を支持する研究者や教育者の根拠や、それに対する重要な反応について触れる。
■構造的(structural)シラバスから、概念・機能的(notional/functional)シラバスへの移行があったが、本質的にはどちらも言語項目に焦点を置いたものであった。
■それまでの教授法の失敗から、部分的に言語的シラバスへの再評価が起こり、学習者が文法を習得する際にまず従うとされる「built-in syllabus」への関心が高まった。
■学習者がどのような言語項目を習得するかを特定するのは不可能であるとし、学習させる言語項目をあらかじめ選択することはせずに、コミュニケーション全体をまとまりとして指導の内容を特定する必要があるとの意見が出てきた。Prabhu(1987) のprocedural syllabusは、「コミュニケーションのために」教えるのではなく、「コミュニケーションを通して」教えることを説いたものである。
■Prabhuに対し、Longはコミュニケーションのなかで意図的に学習者を形式へ注目させる(focus on form)必要を説き、pedagogic tasksと、学習者のニーズ分析を原点としたtarget tasksとを区別した。
■以上から、タスク中心のシラバスは、1)指導がL2習得の認知プロセスと矛盾しないことを前提とする、2)妥当な努力目標(reasonable challenge)を掲げたうえでの学習者の参加が大切である、3)学習者のニーズを定め、特定の目標をもったコースをデザインするという目的にタスクはかなう、ということが言える。
■このようなタスク中心の指導法は多くの課題をはらんでおり、学習者が教えられた文法構造を習得しないという理由で言語シラバスを行わないのは正当ではないと言う者もいる。しかし、形式に焦点を置いたタスクは正確な言語使用を促進するという証拠もあり、言語シラバスの失敗はその内容(design)ではなくその実行の仕方(methodology)にある。
■また、文法および社会言語的能力の習得におけるタスクの有効性に関しては懐疑的な見方もあるが、タスクのなかで意味のやりとりを行うことで形式への注意が喚起され、習得を促進する、という実験的証拠も挙がってきている。
■タスクを中心とするシラバスを支持する人々の主張は、(1)言語シラバスは習得を効果的に促進しない、(2)タスクを中心としたシラバスは言語習得過程について明らかになっていることと一致する、の2点である。
■タスク中心のシラバスのデザインを考えるにあたり、次の3点について検討する。
(1)どのようにタスクを分類するか(classifying tasks)
(2)タスクのテーマ内容はどのようであるべきか(the thematic content of tasks)
(3)明示的な評価観点と一致するようにタスクをどう配列するか(sequencing tasks)
3. Classifying tasks
■同じタスクが見方により違う呼ばれ方をされるように、その分類は様々である。このセクションでは、チェックリストを用いて、タスクを分類する次の4つのアプローチについて言及する。
(1)pedagogic (2)rhetorical
(3)cognitive (4)psycholinguistic
3.1 A pedagogic classification
■Willis(1996)はテクストブックによく見られるタスクの種類を分析、以下のようにまとめた。
1. Listing:リストを作るもの
2. Ordering & Sorting:項目を並べ替えたり、順番に並べる、分類するもの
3. Comparing:情報の相違点や類似点を見つけるもの
4. Problem-solving:パズルや論理的問題などの知的活動を伴うもの
5. Sharing personal experiences:自身について自由に語ったり、経験を共有するようなもの
6. Creative tasks:上位の活動を含む数段階からなり、リサーチなどを必要とするもの
■Willisは各タスクにおける詳細な実施方法やフォローアップ・タスクなどを紹介している。
3.2 A rhetorical classification
■このアプローチでは構造や言語特性にもとづいた「対話領域(discourse domains)(i.e. narrative, instructions, description, reports, etc)」を区別することでしばしば分類される。この分類はよくアカデミックな目標を持った言語コースの根底をなすが、たいていは事前の訓練を前提とした言語シラバスであり、タスクはそれをサポートするという位置づけでしかない。
■一方、Swales(1990)により定義された「ジャンル(genres)(i.e. recipes, political speeches, job application letters, good/bad news letters, medical consultations, etc)」はコミュニケーションの目的を参加者が共有していることを考慮にいれた分類であり、Swalesはgenre-based taskには、社会文化的状況を必要とする真のコミュニケーションの目的(authentic communicative purpose)を組み込むことが必要と主張している。
3.3 A cognitive classification
■Prabhu(1987)では認知活動の種類にもとづいて3つのタイプに分けている。
1. Information-gap activity:
人から人、formからform、場所から場所へ与えられた情報が移る。
2. Reasoning-gap activity:
information-gapを超えて、与えられた情報から新しい情報を派生させる。これは推論・演繹・ 実用的理由付けを用いて行う。
3. Opinion-gap activity:
与えられた状況に対し、個人的な好みや感情、態度を明らかにする。
■Prabhuは2→1→3の順に生徒同士のやりとりを教師が促進しやすいとしている。
3.4 A psycholinguistic classification
■ここでは3章のInteraction Hypothesisで紹介されたPica et al.(1993)の分類方法を紹介する。「心理言語的」という理由は、相互作用のなかで学習者がインプットを理解する、フィードバックを得る、自身のアウトプットを修正する、といった知的活動に基づいているからである。
1. Interactant relationship:
タスク目標を達成するために、誰が交換すべき情報を保有し、要求し、供給するかone-way とtwo-wayとを区別する。
2. Interaction requirement:
学習者の相互作用における情報の要求と供給が義務的であるか、選択的であるか。
3. Goal orientation:
学習者に1つの答えに賛同するよう要求するか、それとも賛同しないことを許すか。収束的 (convergence)なタスクのほうが、拡散的(divergence)なタスクよりもやりとりを促す。
4. Outcome options:
タスクの成果がclosedであるか、openであるか。closedのほうがやりとりを促す。(上の3と の違いは何か?)
■下の表はこれら4つのカテゴリーをもとにタスクの種類をわけたものである。ここでJigsawが最も心理言語的に効力があり、opinion exchangeが最も効力がない。
|
Task Type
|
Interactantrelationship
|
Interactionrequirement
|
Goal orientation
|
Outcomeoptions
|
|
jigsaw
|
two-way
|
required
|
convergent
|
closed
|
|
information gap
|
one-way or two-way
|
required
|
convergent
|
closed
|
|
problem solving
|
one-way or two-way
|
optional
|
convergent
|
closed
|
|
decision making
|
one-way or two-way
|
optional
|
convergent
|
open
|
|
opinion exchange
|
one-way or two-way
|
optional
|
divergent
|
open
|
■このPica et al.の分類方法の問題点は学習者の双方向のやりとり(two-way interaction)があれば習得に必要な条件が満たされるとしている点である。しかしSkehan(1998)は学習者のアウトプットの特徴(fluency, complexity, accuracy)に焦点を当てた異なる分類方法を提示している。よって、心理言語の異なる理論が一貫して支持しうるタスクの分類法は、現時点でまだ確立していないと言える。
3.5 A general framework
■これまで述べられた4つの観点でのタスクの分類やタスクタイプをふまえて、1章のTable 1.1を拡大したのがTable 7.2である。Table 7.3はそれをもとにspot-the-difference taskについてその特徴を記述したものである(テクストブック参照)。
4. The thematic content of tasks
■テーマの選択の際に重要なのは、タスクを中心としたコースが言語の「一般的な熟達度」と「特別な使用」のどちらを目指すのかということである。前者の場合ガイドラインとなるのは、(1)トピックの親密度、(2)直感的な興味、(3)トピックの関連性である。Estaire & Zanon(1994)はこれに関連して「theme generator」というものを提案している。
■Prabhu(1987)で紹介されているCommunicational Teaching Projectで開発されたシラバスでは、学校生活(aspects of school)や社会生活(social life)、社会的人工物(social artifacts)に直接関わるようなテーマを設定している。
■特別な目的をもったコース(specific-purpose course)では、Long(1985)が言及しているtarget tasks(=学習者が携わる実世界の活動。ある職業で行われる仕事内容を設定するなど)が有効である。気をつけるべきは、仕事内容を色々な職業へ応用できるように一般化した形で行うことである。
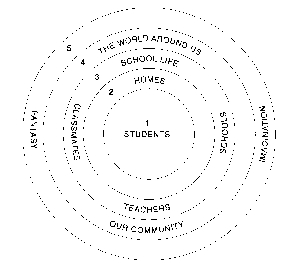
<議論内容>
■ information-gap activityの「形式から形式へ」「場所から場所へ」というのが実際にどういう活動形態をとるのか見てみないとわかりづらかった。
■ 用語に関しても、convergence/closedとdivergence/openの違いが明確にされていなかったが、closedは解が明確に定められている解答形式、openは解が1つに定まっていない記述形式であり、2つの用語は表現形式での違いに使用される。一方、convergence
は収束という意味から話している相手に心理的に収束し何らかの結論に到達させる課題形式で、反対に
divergenceは、拡散という意味から 相手から心理的に離れるということで結論に到達させる必要がない課題形式という意味で使用されているようである。 (平井、大木)
2009/1/16
Chapter 6 Sociocultural SLA and Tasks
Incorporating a focus on form into a task-based syllabus
Focus on formをタスクに組み込むには二つの方法がある。
1. ある特定のものに注目させるようにデザインされたタスク( focused tasks )を用いる。このようなタスクは、シラバスのレベルにおける組み込みに関して積極的な取り組みであると言える。
2. 言語的に中心化されていないタスクの中に、Focus on formを組み込む。事前または事後(誤りの直後またはタスク終了後)に生徒に形式への注意を促す。
ここでは(1)について扱う。(2)については⇒Chapter 8参照。
中心化されたタスクには、中心化された事項を伝えられない限り、学習者が中心化された文法事項を避けてタスクを行ってしまうという問題点がある。しかし、中心化された事項を伝えてしまうとタスクではなく練習になってしまう。
タスクを基盤としたシラバスにおいてこれを克服するためにはinterpretation tasksを使用することが推奨される。これを通して、情報を理解する上で生徒が目標となる構造を避けることができないようインプットの「種まき」を行うことができる。また、注意を喚起するようなタスク(consciousness-raising tasks)を使うことも1つの方法で、タスクの内容が文法特徴になる。
この項では中心化されたタスクのシラバスの言語内容をどのように配列するかを考え、次にコミュニカティブなシラバスに形式を組み込むための二つの提案を分析する。
Selecting and sequencing linguistic content
Focus-on formsのアプローチ、また中心化されたタスクのシラバスは、学習者が習得できる範囲、すなわち中間言語の発達と一致している必要がある。しかし教えられるシラバスに現れる「形式」は実際に内在化される「形式」とは直接的な関連はなく、よって言語形式には心理的に直接対応するものがない。
この問題には、タスク基盤のシラバスにFocus on formを組み込む際の2つの目標である、明示的・暗示的なL2知識の発達を区別することで対処することができる。特にシラバスのデザインが難しいのは目標が暗示的知識である場合で、明示的知識の場合はより扱いやすくなると言える。
Specifying the linguistic content for developing implicit knowledge
上に述べたような理由から、言語構造を段階別にリスト化してもあまり実用的ではない。したがって、ターゲットとなる構造の暗示的知識を発達させる目的で中心化されたタスクのシラバスを作成することは不適切であると言える。
暗示的知識を発達させるための方略としては、特定の特徴ではなく特徴のかたまり(cluster)を目標とすることがある(Skehan, 1998a: 130)。Skehanによれば、学習者の内的処理要因が「強すぎる」ことで、外的に習得内容を決定することが不可能となっている。しかし教師は中間言語の発達を見失わないことが求められ、そのために個々のタスクでの構造を特定することが提案されているが、Skehanはこの特定方法については言及していない。
タスクの習得目標としての構造の識別は、特定の構造の識別と同様にlearnabilityの問題に直面する。しかし、段階別の項目リストが個別またはかたまりとして組み入れられることができなくとも、項目のチェックリストを使用することが適している可能性がある。このチェックリストを使用して、教師は生徒の習得の度合いを見ることができる。これはFocus-on-formの研究で使用されてきた形式である。
・ Williams and Evans (1998: 140)の研究にみられるように、生徒が頻繁に間違えるものをチェックリストに含めることで、チェックリストとしての言語シラバスは補助的な教授の役割(remedial teaching)を果たすことが出来る。
チェックリストの内容を決定する方法としては、学習者が日常的によく間違いを犯す項目を基盤とする方法がある(⇒エラー分析の手法)。または、学習者にとっての困難を引き起こす傾向のある項目を含むという方法を使うことも出来る。このような言語項目を選ぶには以下の基準(Harley, 1994)が参考になる。但し、学習者にとって実際に起こっている問題をこれらが含んでいるかどうかを選ぶことも必要である。
(1) 学習者のL1とは異なるために知覚することが難しい
(2) インプット内において変則的または低頻度であるために突出していない
(3) コミュニケーションにおいて冗長である
(4) 学習者がその解釈を誤ったり、分析を誤ったりする可能性が高い
また、チェックリストの項目に順序をつけることは無意味
⇒項目によっては扱われる必要のないものもあり、また、その順序は“いつ、それらが問題として見つかるのか”に基づくことになるため。
暗示的知識が関わっている場合は、タスクに組み込まれる可能性があるものとして言語内容を特定することは出来るが、あらかじめどの形式がいつ注意を向けられるべきなのかは決定することが出来ない。項目のチェックリストを作ることと、いつ特定の項目に注意を向けるべきなのかを決定するための手順だけが可能である。
Specifying the linguistic content for developing explicit knowledge
暗示的知識を発達させるためのタスク⇒structure-based production tasks, interpretation tasks
明示的知識を発達させるためのタスク⇒consciousness-raising (CR) Tasks
・ CRタスクの言語内容を選択する上では、暗示的知識の場合と同様の考慮が必要である。しかし、明示的知識の場合は単なるチェックリストだけではなく段階別のシラバスを使うことが望ましい。
・ 暗示的知識のように習得が難しいものは、説明されるとわかる場合がある(例:三人称のs)⇒明示的知識として習得できるため、配列の問題は暗示的知識の場合には除外されるが、明示的知識の場合は他より理解しやすいものがあるため、配列が可能である。
Table7.6は文法構造としての明示的知識の難易度を決定する基準(一部)を示しているが、これらは構造的シラバスにおいて使われてきたものと一致する。このような基準を使用して、明示的知識を教えるための文法項目の段階的なリストを作成することができる。
・ CRタスクに基づくようなシラバスの内容は言語的内容から始まるが、タスクそのものは一般的なタスクの定義に従う必要があり、タスクの種類やその配列を考慮した上でデザインを行わなければならない。⇒タスクの分類や配列(Table 7.2, 7.4)
・ すべてにおいてCRタスクを使うことは可能だが、推奨されない。言語的に中心化されていないタスクを主としたシラバスの中にCRタスクを組み入れるほうがよいと考えられる。
Two approaches for incorporating a focus on form
タスクを基盤としたコース内にfocus on formを組み入れるための2つの提案を検討する。1つ目は学校の場におけるESL学習者への内容中心教授法(タスクを基盤としたアプローチの一種)から生まれたものだが、他の教育的な場においてもおそらく適切である。2つ目は学習単位シラバス(modular syllabus)を含み、全ての授業場面において幅広く適用可能である。
An integrated approach
内容中心教授法のコースでは、学習者は主題に関する内容を学習する場合に最も学習することが出来るという仮定を前提としている。しかしこれらのようなコースでは、文法・社会言語能力共に高いレベルには至らない。このことが、内容中心教授法においてfocus on formをどのように組み入れることができるかを考えるきっかけとなった。
・Genesse(1994: 49)によれば、一部の統合的な第二言語の教室においては、活動は内容に関するもので、言語それ自体についてではない。したがってコースのデザインは、学習者にとって重要かつ興味深い、また親しみが持てると同時に新しい要素を含むことで知能的発達に貢献できるような活動を選ぶことから始まる。
・ しかし、このような活動では言語形式にも注意が必要である。Met (1994: 163)によれば、教師がESLの目標と両立できるような内容を学校のカリキュラムから選ぶことで、それをコミュニカティヴかつ認知的な意味で言語を発達させること、また内容に関して熟達することを促進することが可能となる。
したがって、生徒が学習すべき言語形式と学校のカリキュラムに基づく内容を併せ持つような言語シラバスを作成する必要がある。これは特定の内容(文脈)の中で表れる言語形式を分析することで可能(Snow, Met, Genesse, 1989)。但しこれは、内容に拘束力のある言語(content-obligatory language)、また内容と両立可能な言語(content-compatible language)とは区別されるべきである。前者は特定の内容を学習するために必要とされる言語、後者は特定の内容の文脈内では教えられるものの内容の熟達のためには必要とされない言語である。
□ 例:トピックがgravityの場合
content-obligatory language:’to pull’, ‘to force’, アポストロフィの使用(‘the earth’s gravity)など
content-compatible language:’mass’, ‘when’節(‘when we throw a ball up into the air…)など
Snowらの提案によれば、与えられた内容の中でcontent-obligatory itemsが最初に特定され、次にcontent-compatible itemsが次の3箇所(source)から導き出される:①そのような項目をチェックリストとする第二言語または外国語のカリキュラム、②学習者の言語的な需要の評価、③内容カリキュラムに期待された言語的要求。これらの項目は内容中心教授法に組み込まれることが可能である。⇒Snowらによって、このアプローチがL2学習者の教室などで使用され得ることが説明されている。
しかしこのように形式と内容を統合しようとする試みも、Learnabilityの問題に直面してしまう。次項ではこの問題を回避するアプローチが紹介される。
A modular approach
Ellis(2002)で提案されたmodular approach では、内容と形式を統合させるための試みはなされず、シラバスは2つの別々のモジュール:コミュニカティヴ・モジュールと記号ベースのモジュールから成るものとしてみなされる。
・ コミュニカティヴ・モジュール:シラバスの主要な部分を占める。前述の基準によって選ばれた、言語的に中心化されていないタスクで構成される。生徒は規則正しいこのモジュールの中で、メッセージ中心の活動を通して流暢性、正確性、複雑性を発達させる機会を得る。中心化されていないタスクを行う場合、学習者は自然に形式に注目することができるため、もちろんタスクには形式も必要とされる。ただ、タスクデザインの時点では学習者が注意を向けるべき形式は予め決められていないということである。
・ 記号ベースのモジュール:シラバスの二次的な構成要素である。学習者にとって潜在的に学習が難しい言語特徴のチェックリストを含むが、これは「補助的な」目的でこのような自然に習得しにくい特徴を習得できるよう助けるものである。記号ベースのモジュールではfocus-on-formsの方法に従って教えることが可能(例:present-practice-produce)だが、中心化されたタスクで教えられることも可能である(structure-based production tasks, interpretation tasks, consciousness-raising tasks)。
シラバスを構成するこれら2つのモジュールの間につながりを持たせる必要はなく、教師は記号ベースのモジュールの中でいつタスクを用いるのかを自ら決めることになる。
このようなモジュラー・シラバスでは、2つの構成要素の段階を考慮しなくてはならない。
⇒例:Figure7.3が1つの可能性。学習者の注意をコミュニカティヴなものから形式へと移していく方式である。従来の言語カリキュラムで形式を教えた後にコミュニケーションの機会が与えられていたこととは逆である。
■まとめ
Task-basedのシラバスに、形式への注意を取り入れる際
・ 学習者の暗示的知識を発達させる目的である場合⇒問題はあるが、潜在的に問題のあるチェックリストを使用したアプローチは可能である。
・ 学習者の明示的知識を発達させる目的である場合⇒言語シラバスはかんたんに構築されることができる。
このようなシラバスは、①特定の形式に注意を向け、また②コミュニケーションの機会を与えるというconsciousness-raising tasksの内容に沿っている。
形式への注意を含む2つのシラバス・デザイン
・ integrated syllabus(Snow, Met, Genesse, 1989):カリキュラム内でのcontent-obligatory languageとcontent-compatible languageの特定をすることで内容と形式が統合されている。形式と内容を共に教えることが重要であるという考え方が反映されている。<欠点>シラバスの作成者にとっては技術的負担があり、また学習者にとってその内容・形式間の関連が役立つという保証も無い。
・ modular approach:言語的に中心化されていないタスクと中心化されたタスクの、関連を持たない構成要素を含み、また同時にL2習得の処理過程と両立可能である。このアプローチはPrahbuが提案したようなtask-based syllabusに首位権を渡すものだが同時に、学習者が形式への注意を必要とする段階に到達する頃に、形式に重点を置いた活動を行う機会を提供する。
Designing Tasks
シラバスは、タスクが教室で実際どのように使用されるかの詳細な計画を提供する。ここでは、Task-based coursesの準備(⇒Figure7.1)の最終段階であるタスクの実行計画(task workplans)を検討する。
Workplansが何を含み、作成者はどのようにこれを構築するのかという問題に答えるためには、1つにPractical guidesという情報源がある。
・ Practical guides:Estaire and Zanón (1994)によればこれは2つの総合的な段階からなり、それぞれがいくつもの段階を含む。
段階1は「総合的な言明(general statement)」を含み、単元が何を達成するよう意図されたものかを規定する。この総合的な言明とは(1)単元において、テーマや利害関係を持つ範囲を決定する、(2)単元の最後に最後のタスクが行われるように計画する、(3)単元の目的を決める、という順序で段階を踏む。
段階2は「詳細」を含み、単元がどのように行われるのかを規定する。段階1に続いて、(4)最後のタスクを行う上で必要な内容(主題および言語)を特定する、(5)学習者が最後のタスクを行えるよう「可能にするタスク(enabling tasks)」を計画し、配列する、(6)単元を評価するための手順を計画する、の3段階がある。
Lee (2000)はタスクを構築するただ1つの方法はないとしながらも、プロセスを導き出す4つの基準を提案している:(1)必要な情報のアウトカムを特定する、(2)トピックをサブトピックに分解する、(3)具体的なタスクを作成し配列する、(4)言語的サポートを組み入れる。
・ Task-basedの材料は実際どのような手順を踏んで準備されるのか?⇒Johnson (2000)の研究によれば、タスクをデザインする経験の浅い者は、タスクの枠組みからデザインを始めるのに対し、経験の豊富なものはタスクのジャンルからデザインを始め、機能には比較的注意をあまり向けていなかった。また、個々の間でスキーマにも違いがあった。「言語志向」のアプローチを行う作成者と、「タスク志向」のアプローチを行う作成者がいた。
経験の豊富な作成者に見られた発見的教授法の特徴:
・デザインの特性に合ったタスクを自分のレパートリーから探す
・推定されたタスクのアウトプットをまねる
・タスクの1側面において真正性のバランスをとる(例:場面と相互交渉)
しかし、これらはEstaire and Zanón (1994), Lee (2000)とは完全には一致していない。例えば、これらの著者が内容の主題をスタート地点と位置づけたのに対しJohnson (2000)の研究ではタスクのジャンルという結果が出た。
Conclusion
本章では、task-basedのコースをデザインする詳細な方法を説明することが目的ではなく、むしろそのようなコースの準備を行ううえで考慮されるべき以下のような問題を探究することである。
1.応用言語学者、教育学者たちはTask-basedのコースにどのような原理的説明を行ってきたのか?
2.そのようなコースではどのようなタスクが含まれ得るか、またタスクの種類の選択にはどのような要因が考慮されるべきか?
3.Task-basedのコースで、内容の主題はどのようにして選ばれるべきか?
4.タスクはどのようにして配列されるか?
5.Task-basedのコースには、Focus on formはどのように組み込むことができるか?
6.経験の豊富な教師は、Task-basedの教材の発展にはどのようにして取り掛かるのか?
これらは全て複雑な問題で、明確で議論のないような答えは見つかっていない。しかしこの状況は昔と変わっていない(さらに伝統的なシラバスについてもこの問題は未解明)。ただ研究とは明らかな答えを見つけるためのものではなく、教育学的に試すことの可能な選択肢を特定するものであるので、この意味では研究はコースのデザインに貢献し得る。
タスクはコースデザインにおいて強力な構成要素であり、「試験的なストラテジー」を教える場で実行する主要な役割を果たしている(Stern, 1990)。本章ではTask-basedのコースで考慮されるべき要素の一部、また試みることが可能な数々の選択肢を特定することを試みた。
(研究会でのコメント)
■ 現在は形式⇒コミュニカティヴへと移行するパターンが主流だが、modular approachのような方法は、L1が日本語である場合は取り入れることは難しいのではないか。
■ modular approachの2つの種類については、コミュニカティヴな要素と記号の要素の割合(どちらが多いか)によって、どちらかが決まることが多い。
(平井・伊藤)
ページトップに戻る
2009/1/30
2009/2/6
Chapter 8 The methodology of task-based teaching
The post-task phase (p. 258~)
post-taskの段階における3つの目標:
(1)タスクのパフォーマンスの繰り返し (repeat performance)
(2)タスクの遂行の振り返りを促す (reflecting on the task)
(3)形式への注意を促す (focusing on forms)
(1)Repeat performance
タスクの繰り返しは、流暢さや複雑さを高める。
繰り返しには、同じ条件下で繰り返す場合と異なる条件下で繰り返す場合がある。
Skehan and Foster (1997):学習者に2回目のタスクを発表するように指示する場合はduring-task optionになり、2回目のタスクまで発表の指示をしない場合は、post-task optionになる。
(2)Reflecting on the task
振り返りは、筆記・口頭によって可能であり、学習者のタスクの成果、言語のどのような側面に注目したか、どのようにコミュニケーション内の問題を解決したかなどについて報告することが考えられる。
学習者がタスク自体を評価することも可能であり、教師はそれを参考にその後どのようなタスクを用いるか検討できる。
(3)Focusing on forms
形式への注目は、タスクのどの段階においても生じることができる。
どのような形式に注目させるか?→学習者がパフォーマンス中に間違える形式。
目標形式をどのように扱うのか?→多くの方法がある。
1.Review of learner errors
・教師が目につく誤りを発見し、例と一緒に提示し、学習者に訂正させる。
・Lynch (2001): ‘proof listening’で学習者にタスクを何度も聞かせ、コメント、修正をする。
2.Consciousness-raising tasks
・follow-up taskとして学習者に明示的に特定の形式に注目させることもできる。
3.Production-practice activities
・例)repetition, substitution, gapped sentences, jumbled sentences, transformation frills, dialogues
・production-practiceの効果には疑問も上がっているが、学習者がまだコントロールできない使い始めの表現の自動化を促すと考えられる。
4.Noticing activities
・Fotos (1994):目標項目を強化したディクテーションにおいて学習者の注意が高まった。
・Lynch (2001):学習者に自分のタスクの書き起しをさせ、訂正、修正させる。教師がさらに訂正し、学習者のオリジナルと比較させる。
Using the framework for designing a lesson (p. 262~)
‘pre-task’, ‘task’, ‘post-task’ は授業を何とするかにより捉え方が変わる。
教師は、基本のレッスン形態をまず考える必要があり、少なくともduring-taskの段階、その後さらにpre-task, post-taskについてプランする。→基本の枠組みを作成した後に詳細を決定する。
① Participatory structure
participatory structure 教師と生徒がタスク・パフォーマンスに対する貢献をどのように整理するかについての手順。(例:個人作業、集団作業) 教室の中でインタラクションがどのくらい生じるかに影響するという点で重要。
task-based teachingではメインのタスクはペアまたは小グループで行うという前提。(インタラクションが前提としてある)⇔ しかし全てのタスクがインタラクティブなわけではなく、また相互的なタスクはクラス全体で実施することも可能である。(p. 263, Table 8.5参照)
② Individual students work with tasks
Communicational Teaching Project:生徒が各自タスクを行う。他の生徒や教師と相談しても良いが、それはオプショナルである。→ 生徒の性格や学習スタイルに応じたタスクへのアプローチが可能になる。
自立的、自律的学習を促すことが出来る。
個人でタスクに取り組むことが「良い学習者」の特性であり、またモチベーションも高める。ただし個人学習だからといってインタラクティブでなくなる必要はない。また、private speechも自分とのインタラクションであると捉えることもできる。
個人でタスクに取り組む方がエラーを生じるコストが小さくなる。
strategic planningは通常生徒が個人で取り組む。Foster and Skehan (1999) によると、個人プランは複雑さ、流暢さ、正確さを高めるのに効果的であった。
個人学習の欠点としては、個人の能力を超えたパフォーマンスが不可能であることが挙げられる。→ タスクを学習者に適切なレベルに設定することが重要である。
また学習者がタスクを遂行するストラテジーを持ち合わせないことも考えられる。その際はpre-taskの活動が効果的である。
③ Working on tasks in pairs and groups
利点:学習者の発話量↑、発話の多様性↑、指導のindividualization↑、不安↓、モチベーション↑、楽しみ↑、自立性↑、社会性↑、他者と取り組む力↑、学習↑。
欠点:ペアワーク(コミュニカティブな活動)が嫌いな学習者もいる。グループ/ペア・ワークは満足できる成果をもたらさないことがある。口頭の談話はすぐに消えていき、テキストが残らないため改善するのが難しい。グループワークは学習者に「良いモデル」を提示しにくい。生徒同士のインタラクションは、L2をピジン化し、化石化する可能性がある。グループワークの方が不安を高める場合もある。生徒同士の活動内で「気づき」は生じるのかという疑問がある。
Williams (2000):初・中級学習者はコミュニカティブ・タスク内では、教師が見ているとき意外、形式にあまり注意を向けないのに対し、上級学習者は形式により注意を向けることが出来る。実際に学習者が注目する形式は語彙的なものが多く、文法的・音韻的な問題への注意は低い。⇔ しかしpre-taskにおいて形式により注意を向け、筆記による産出の場合はグループワークでも形式への注意を高める可能性がある。
その他にも教室内の配置や、グループワークがうるさくなりがちである、学習者の参加の不平等性、L1の過剰使用などのリスクがある。
協力(協同)学習 (Cooperative learning):ただ生徒をグループにまとめるだけでは不十分であり、インタラクションの質を高め、お互いに助け合い効率よくタスクを進められるようにすることが重要である。Storch (2001)によると、生徒は常に協同的に取り組むわけではないが、そのように取り組むとパフォーマンスが向上する。(協力的インタラクションの特徴はp. 269を参照)→生徒の協力的態度が不可欠
Wells (1999): “progressive discourse”に必要なこと→共通理解への取り組み、より質問や命題を明らかに出来るようにする、有効な命題を拡大する、談話を進めるための批判的意見を許容する、知識を高めるために協力的に取り組む。
共通理解に向けて効率的に進めることは学習者の言語をminimalにし、公立的な会話が談話の大勢を占めるようになることは問題とも考えられる。タスク・デザインの問題ともいえる。
書き言葉の方が向上させる対象に焦点を当てられるという点で、話し言葉よりより容易に共通理解に達することが出来る。
学習者がどのくらい効果的な協力が出来るかは、タスク特性に左右される。
グループ/ペア・ワークにおいて教師が気をつけるべき点:
(1) Students’ orientation to the task:タスクが意味のある活動であることを示す
(2) Individual accountability (個人の説明責任):例えばタスクにおける各メンバーの役割を明確にする。
(3) Group composition:グループサイズと構成が重要。4人グループが良い?レベルなどは混合が良い?
(4) Distribution of information:一方通行のinformation gapタスクにおいて、生徒の熟達レベルが異なるときは、熟達レベルが低い生徒が情報を交換する役割の方が協力が生まれやすい。
(5) Physical arrangement of students:話しやすい、アイコンタクトをとりやすい、静かに話せる、コンパクトなスペースに納まる座席の配置が望ましい。
(6) Collaborative skills:効率よく協力できるようなストラテジーの指導。モニタリングも重要。
(7) Group permanence and cohesion:協同学習ではグループの機能や協力体制について考えることが必要であり、プラスの相互関係を気づくことが重要である。
(8) Teacher’s role:協力の手本、パフォーマンスの観察、問題が生じている際の介入、タスクの参加者。
④ Working on tasks in a whole-class context
教室全体の活動では不可欠な教師の役割 → (a) インタラクションがない場合は、タスクのためのインプットを中心的参加者として提供する (teacher talk)、(b) 相互的な活動内では、生徒がタスクに取り組めるような ‘instructional conversation’ を与える役割がある。
またpeer teachingという方法もある。
(1) Teacher talk
teacher talk:学習者のL2レベルに応じて、理解可能なインプットを用いて話すこと。(音韻的、語彙的、文法的、談話的な調整を含む)
teacher talkは前もってプランすることが難しく、臨機応変にしなければならない。
教師のteacher talkの能力にも個人差がある。またL2に自信のない教師はスクリプトに頼りがちで有り、teacher talkをうまくすることに問題がある。ネイティブ・スピーカーの教師は、語彙を広げすぎて学習者の習得にマイナスになることもある。
teacher talkについてのけんきゅうは少なく、教師がどのようにして熟練した実践者になれるかどうかに関する情報は少ない。teacher talkが身につけられるスキルかどうかもまだ明らかではない。
(2) Instructional conversation
instructional conversation:学習者自身では遂行できないことにおいて教師がガイドする対話的活動。
理想のinstructional conversationは意味中心で会話を促進し、かつ言語学習を促すようなタスクによって実現される。
教師中心の ‘triadic dialogue’ (3者の会話)は避けられるべきという意見もあるが、教師の質問によりnegotiationの機会が与えられることも有り、閉じたinformation questionよりも良いという意見もある。
IRF (initiate-respond-follow-up)のやり取りも重要。これが学習者の発話を目標に基づいて評価するとき談話は教育的であり、学習者の発話を前の発話につなげるようなものであれば会話的 (conversational)である。
会話の特徴:(a) 会話を誘導する責任の共有、(b) 教師から引き出されるわけではないコメントを生徒から引き出す機会を作る、(c) 明確なテーマ、(d) 教室の質問に対する生徒の応えに応答できる発話の使用。
指導の目標:(a) タスクの成果を達成する、(b) 効果的な言語使用、(c) 言語学習。
(3) Peer teaching
タスクを遂行するために生徒が教師の役割を果たす。
利点:(a) 通常の教師の役割を体験する機会を提供(残りのクラスをガイドする)→広範な言語機能を用いることでnegotiation of meaningが生じる。(b) 他の生徒が話しやすくなる。(c) 生徒の会話量が増える。
不利点:参加しない生徒がいる。
peer teachingはより高い熟達レベルで効果的と考えられる。
Conclusion (p. 275~)
教師はtask-based teachingにおいて、デザインやparticipatory structureが重要であることを認識する必要がある。
task-based lessonにおける原則(p. 276, Table 8.8を基に作成したリスト):
(1) タスク困難度を適切なレベルに設定する(pre-task活動を入れたりすることも含める)。
(2) task-based lessonの明確な目標を設定する。
(3) 生徒がタスク遂行に対する適切な姿勢を持てるようにする(なぜこのタスクをやるのかが生徒にとって明確になる必要がある)。その点ではpost-taskな役割を果たす。
(4) task-based lessonにおいて生徒が積極的に役割を果たせるようにする。コミュニケーションにおける問題が生じたときに意味交渉をすることが重要。
(5) 生徒がリスクを冒すことを促す。中間言語を ‘stretch’ 出来るようにし、 ‘pushed output’ を促す。
(6) タスクに取り組んでいるとき名意味中心の活動である。言語を目的ではなく道具として扱う。
(7) focus on formの機会を与える。形式へ注意を向けることは必ずしも(6)と反しない。
(8) 学習者自身が自分のパフォーマンスや進度を評価できるようにする。
ページトップに戻る
2009/2/20
Chapter 9 Task-based assessment (pp. 279-303)
Introduction
・ 本章では、L2学習者のcommunicative abilityを測定するためにタスクがどのように使用されているかを考える。
・ 本章における評価タスクの定義:意味に中心が置かれ、何らかの目標に向けられた言語使用の場面において、学習者のコミュニカティヴ・パフォーマンスを引き出し評価する装置
・ 言語テストでのタスクの重要性の認識…タスクが一見してL2習得を促進すると思われることから、テストの分野においても、学習者がL2でコミュニケーションを行う際の処理容量について測定を評価するためのタスクが注目されてきた。
・ McNamara (1996):Task-basedのperformance testsは特定のL2学習者にとって選択の過程を発達させる必要がある、またChapters 7&8に出てきたような言語教授における発達と合わせる必要がある⇒このために生まれたものである
・ Brindley (1994):’task-centred assessment’の利点
・教師/学習者がツールとしての言語を中心におく(i.e. washback effect)
・学習プロセス内に、より評価を取り入れやすい
・学習者に有益な(経過、達成においての)診断フィードバック
・専門家でなくても、評価の内容がわかりやすい
・ Task-based testingは、test performanceとcriterion performanceの間の相関を高くする(評価の妥当性・信頼性を確かなものにする)ための方法とみられている
Language assessment paradigms 3つの主な言語評価のパラダイム
(1) the psychometric tradition (言語テストにおける、心理測定学的な伝統)
(2) integrative language tests(統合的言語テスト)
(3) communicative language testing(コミュニカティヴな言語テスト)
・ これらはBaker (1989)に従って総合的な枠組みに組み入れられている:system-referenced / performance-referenced, direct / indirect
(1) The psychometric tradition
・心理学のテストで使われた方法(多項選択式など閉じた形式)で、客観的とされた。テストの点は統計にかけられる⇒信頼性・妥当性を構築するためのitem and factor analysis(因子分析)
・ 言語は、下位要素(音韻、語彙、文法など)の知識を、リスニング・スピーキング・ライティング・リーディングの4技能に関連付けられてテストされる。TOEFLが一例
・ この伝統への批判のまとめ(Gipps, 1994: 14)
・実際に達成されるものより、相対的な位置づけが強調される
・簡単に量的にできる技能や知識が優先的に扱われる
・認知の協同的形式より個々のパフォーマンスが教育的な進捗を示すものだとする前提
・教育的進捗は科学的に測定するものであるとする概念
⇒psychometric traditionは、信頼性や、様々な言語使用の文脈での一般化可能性(generalizability)を強調し、妥当性を過剰に構築するものである。
※但し、このような見方は必ずしも常に正当とはされていない。根強い伝統であることを見失ってはいけない。
(2)Integrative language tests
・psychometricと同様、客観性と信頼性を優先させ、これを統計的手法を用いて確かなものとする。しかしpsychometricと異なり、その内容は多次元的というよりは一元的な言語の見方をする特徴がある。
・ Oller (1979)は、言語の習熟度は別々の要素から成っているのではなく単一的であるとした。⇒文法・語彙という別々のテストの結果が高い相関を示し、同一の因子を測っていると考えられた。
Ollerはこの因子を、言語的な、またそれ以外の文脈を使用して言語要素を処理する能力’pragmatic expectancy grammar’とし、この因子を目標とするためには学習者の単一の言語分野を全体的な、real-timeの言語活動によって刺激することが必要だとした。⇒cloze tests、ディクテーション
言語能力が一元的だとすれば、統合的テストでのパフォーマンスに基づいて実世界でのパフォーマンスを推定すればよい。(統合的テストをパフォーマンス・テストと見ることができる)
問題点:①概念的問題…学習者の学習システム(’expectancy grammar’)と文脈上での使用(’pragmatic’)の間の関係がはっきりせず、’pragmatic expectancy grammar’全体の内容がない。②実験的問題:Ollerが使用した因子分析が決定的でなく、さらには間違っているとも言われる(Huges and Porter, 1983)。また他にも、Ollerの研究にはオーラル・テストがなかったことによって多元的な結果が除外されたのではないかとも言われる。
・ integrative language testingによってcloze testsの研究が発展し、また全体的なテスト手法が強調されることで後のパフォーマンス・テスト研究の原型となった。
(3)Communicative language testing
・ Morrow (1979)はpsychometric traditionにおいて重要視されていた信頼性を、表面的妥当性において必要な従属物であると位置づけた。このような考え方から生まれたテスト…The Communicative use of English as a Foreign Language test (CUEFL) :言語的知識や言語技能よりも、総合的なタスクの達成で評価される。このようなコミュニカティヴなテストは、スピーキング評価を含むという点で前述の2つのパラダイムと異なる。
・ UKにおける初期のcommunicative language testingの動き…信頼性に言及することにも、体系的な研究を行うことにも失敗していた。またテストの表面妥当性、内容妥当性については明らかにしたが、構成概念妥当性についての考慮はなかった。
・ 以上の脱落部分について:Weir (1988)は、構成概念、内容、表面の妥当性と波及効果としてのテストの価値、またそれらの統計的属性と予想的価値を強調し、教育目的の英語テストでこれが達成できるとした。
・ Bachman (1990)は、言語知識のモジュラー・モデルに基づいたテストを提案した。モデルは構成知識(文法、逐語的知識)と実践的知識(機能的、社会言語学的知識)の2つのカテゴリーから成る。これらが実際のパフォーマンスに統合される上でのstrategic competenceもモデルに含まれた。またBachmanは信頼性にも注目し、communicative testの手法において表れたエラー(一般化可能性理論において、測定上の説明できない分散)をpsychometricな手法によって減少させられることを示した。このようなBachmanの研究はTask-based testingにおいて大きな影響を与えている。
・ コミュニカティヴ・テストとは、Fulcher (2000)によれば①performanceを含む(⇒test performance とcriterion performanceが出来る限り同じであるべき)②現実場面における能力で評価されるべきだという意味でauthenticである(⇒受験者がタスクのコミュニカティヴな目標を認識する必要がある)③real-life outcomesに基づいて評価される(⇒テストにおいて、受験者が満足のいくoutcomeを達成する形でタスクを実行することが目標であるべき)
・ 以上のように、communicative language testing はTBAの形式をとっている。真正性と表面妥当性という点で現実世界におけるタスクを優先している。しかし上記の3つの定義には問題がある。(例:テストでのタスクが、現実世界におけるタスクと一致することは考えにくい⇒内容妥当性は達成可能か?)
A general framework 上述のテストを分類する枠組み
・Baker (1999)によれば、system-referenced testsとperformance-referenced testsとを区別することが可能。
system-referenced tests:言語知識を体系として評価を行う。特定の文脈上のものではなく総合的な評価で、構造指向的。⇒psychometric, integrative
performance-referenced tests:特定の文脈における言語使用について評価。内容指向的。
※ communicative language test…どちらにもなり得るが、両方でなくてはならないという考えもある(McNamara, 1996)
・ 直接テストと間接テストの区別(test performanceとcriterion performanceの関係)
直接:目標となるパフォーマンスを直接取り入れる。文脈に沿った言語使用を引き出すのが目的。直接テストによる習熟度の評価は、パフォーマンス自体に必須ではないが、外部の評価などを通してパフォーマンスから得られなければならない。
間接:より文脈化されておらず、人工的。目標となるパフォーマンスを分析し、その構成要素や特徴を測定できるようにする。テストそのものから特定の言語尺度を使用して習熟度を測定する(cloze testなど)。
但し、全てのテストは何らかの形で間接的であり、目標となるものと測定するものが完全に合致することはない(実際の使用を観察する形でない限りは)。
⇒4つの評価方法(Table 9.1参照)
・ 直接的なsystem-referenced:自由作文のような伝統的な言語テスト、また情報交換を含むようなコミュニカティヴなタスクに基づいたテスト。Task-basedである。
・ 間接的なsystem-referenced: psychometric, integrativeのテスト
・ 直接的なperformance-referenced:Task-basedで、実際のコミュニケーションを評価するか現実世界でのシミュレーションのような形をとる。特定の目的があるような言語能力を評価するために使用される。
・ 間接的なperformance-referenced:分析的なデザインのため、特定の技能のパフォーマンス、また実際の使用に関連した特定の機能や方略を取り出す。IELTSのような学術的な言語能力テストはこの方法で評価される。
Defining ‘task-based assessment’
・ 直接的なperformance-referencedは含まれ、間接的なperformance-referencedは除外される(タスクを行うための特定の能力は測定されるが、デザインの中にタスクは含まれない)。直接的なsystem-referencedも含まれる(オーラル・インタビューやinformation gap taskがタスクとして扱われるため)
⇒TBAは、現実世界で使われる行動か、その中で行われる言語処理を含む全体的なタスクを使用する評価といえる(直接的)。
・ しかし、Baker (1989)の言うように、4つの評価方法の違いは連続的であり、どれがTask-basedなのかは必ずしも簡単にわかるとは言えない。究極的には、評価方法自体が直接的か間接的かが重要である。
(研究会でのコメント)
・ 間接的なperformance-referenced:IELTSが例として挙げられているため、述べられている「特定の機能や方略」としてはプレゼンのようなものが考えられるのではないか。(伊藤)
ページトップに戻る
2009/3/16
Chapter 9 Task-based assessment (pp. 286-303)
The components of a task-based test
Task-basedのテストは(1)タスク、(2)実施の手順、(3)パフォーマンスの測定 から成る。
Task design
タスクの選択には①構造中心的(construct-centred)アプローチと②作業見本(work-sample)アプローチがある。
① 構造中心的アプローチ…言語使用の理論を基盤とする。直接的なsystem-referenced testsに基づいたTBAに対応
② 作業見本アプローチ…現実においてどのようなタスクが求められるかを、目標言語の場面を分析して決定する。直接的なperformance-referenced testsに基づいたTBAに対応
⇒しかし、両方のTBAはいずれも両方のアプローチを必要とすることが理想的である。
Task-design in direct system-referenced tests
ここでは、直接的なsystem-referenced testsの根拠をなすいくつかの構造のうち、2つについて述べる:①コニュニカティヴ・オーラル・テストの根底となっている「言語習熟度」観/②Skehanのタスク研究の基盤となっている言語能力の二重理論
①「言語習熟度」観
・ Chalhoub-Deville (2001)によれば、オーラル・テストはTask-basedの指導と同じ言語使用観・言語習得観に基づいている。彼女によれば、学習者中心の性質を反映していること(画一性や慣習を指向するのではなく、個別の表現を促す)、意味のある場面という文脈に基づいていること、そして現実で使用されるような真正性を持っていること、の3つがこのようなテストで使用されるタスクの主な特徴である。そしてこの3つの特徴を持つタスクは、「受験者から豊かな言語サンプルを取り出す」ことができる。
・ Chalhoub-Devilleは、The Oral Proficiency Interview (OPI), the Simulated Oral Proficiency Interview, the Contextualized Speaking Assessmentの3つのテストの全てについて、多かれ少なかれ上記の特徴を明示していると述べている。⇒しかし、この主張には疑いの余地がある
② 言語能力の二重理論
・ Skehan (1998:164)は、「テストは、言語運用の性質とそれがどう言語能力に基づいているのかを機能的に明示しなければならない」としており、そのためには心理言語学的な理論を形成することが必要となる。そこでSkehanはWiddowson (1989)に従い、言語知識の貯蔵と言語運用に関連する概念であるanalysabilityとaccesibilityとを区別するモデルが最も有効であるとした。
・ Skehan (2001)は、言語運用に割り当てられた得点に影響を与える5つの特徴を特定し(Chapter 4)、それらが複雑性、正確性、流暢性に与える影響を示した(Table 9.2)このようなメタ分析によれば、タスクが不変のものではなく、よって異なるタスクから導き出された結果が違う場合、それが能力の違いによるものなのかタスクの違いによるものかは明らかではない。
・ 直接的なsystem-referenced testsでのタスク使用には3つのことが暗示される
(1) 異なる種類として存在するテストの場合、タスクのデザインが全て同じである必要がある。
(2) あるタスクでの言語運用は必ずしも別の種類のタスクでの言語運用と一致しないため、文脈を離れて一般化する際には注意が必要である。
(3) テストが受験者の「総合的な言語能力」を測定する場合、言語運用の異なる側面をそれぞれ主に扱うタスクを含むと良い。
・ 但しSkehanは、教室等で行われた研究を基としている。テストの場面では結果が出ていないという研究もあり(Wigglesworth, 1997a; 2001; Iwashita, Elder and McNamara, 2001)、教室の場面とテスト場面で同じ結果が出るとは必ずしも言えない。
Task design in direct performance-referenced tests
・ 直接的なperformance-referencedではタスクの目的は異なる。総合的な言語習熟度ではなく、特定の、現実的な行動を測定するために使用される。⇒作業見本アプローチ
Target language use (TLU)の場面や文脈をテストのタスクに含むことで、特定の学業、専門、職業などに関する個人の能力を推測する。
・ しかしBachman and Palmer (1996)やDouglas (2000)の述べるように、TLUの文脈を含むだけでなくその相互作用的な特徴も含まなくてはならない。
・ Douglasは、テストのタスクの真正性(TLUタスクとテストのタスクの間の等価性)を確かなものとするため、Bachman and Palmer (1996)の枠組みを使用した。枠組みでは以下の特徴が特定される。
1. Rubric(指示)
タスクの目的、応答手順、タスクの構造、その形式、達成するまでの時間、採用された評価基準、をさす。TLUの場面では、参加者の背景知識としてあるため暗示的である場合が多いが、テストでは明示するべきである(Douglas)。
2. Input
言語使用者が処理・応答する、特定の目的である題材をさす。テストのタスクでは、文脈の主要な特徴を確立する。Douglasによればインプットには2つの側面:刺激とインプット情報がある。刺激とは特定の目的を持った場面を作り出す働きをするもので、インプット情報はタスクを行ううえで処理しなければならない視覚、聴覚、物理的な対象である。
3. The expected response(予想された反応)
Rubric, inputの2つによって、テスト作成者が受験者から引き出したい反応のための準備がされる。受験者が言語の特性、そして特定の目的を持つ背景知識を見せることが期待される。
4. The interaction between input and response
Bachman and Palmer (1996):インプットと反応との間の相互交渉における3つの側面
・ インプットが受験者の反応として表れることで、がタスクは多かれ少なかれ反応を示す(reactive)ものである。よって、タスクは相互的(reciprocal)または非相互的である。
・ またタスクの作用域(scope)は狭く(インプットと期待される反応とが最小)も、広く(インプットと期待される反応が広範)もなり得る。
・タスクは直接的な反応、もしくは間接的な反応を要求する。
5. Assessment
タスクのパフォーマンスを評価する基準。Douglasは、indigenous assessment criteria(固有評価基準)、つまりTLUタスクの参加者がパフォーマンスに対して使用する基準の必要性を強調している。この基準が、評価しようとする言語能力の構造の定義となる。
このような枠組みでは、適切な「内部文脈(internal context)(Selinker and Douglas, 1985では’discourse domain’)」が受験者の中で活性化されることが必要だと強調されている。しかし、Douglasの言うようにこれを「科学的」に試みることはできず、「LSP(Language for Special Purposes)テスト」の手法を用いる必要がある。⇒これが伴うものは厳密には特定されていない
Integrating the two approaches to task design
ここまで見てきた異なる2つのアプローチを統合する試み
・ 心理学的アプローチにおいては:パフォーマンスに影響するデザインや暗示的な特徴のみに焦点が当てられており、タスクの内容は一切考慮されていない。適切な談話領域が活性化されるためには内容への配慮が必要である。system-referenced testは本来、学習者の総合的な習熟度を測るものであるため、特定のTLUタスクをテスト・タスクと同様なものとみなすことは出来ないが、総合的な目的を持つ学習者のために’stereotypical tests’(道を聞く、家族についての情報を交換する)を同様とみなすことはできる。
・ LSPテストに使われているニーズの分析によるアプローチ:タスクが心理言語学的側面、そしてそれがどのようにパフォーマンスに影響するのかという視点が欠落している。Skehan(1998a)の述べるように、言語の貯蔵される方法がどのようにパフォーマンスに影響するのかが枠組みの中に包含されていない。ただし、LSPテストに含む文脈を特定すれば、Table9.2のような側面について考慮することも可能となる。
上記のように、2つのテストは統合することができる。Norris, Brown, and Hudson (2000)は、13の様々な領域を含むタスク例を作り上げている。以下は3例。
1. クレジットカードの評価(預金の特典を比較する)
⇒複雑さ6:code complexity, cognitive complexity, communicative demandのうち全ての領域で認知的に難しい
2. 友人たちの好みを聞いた上でピザを注文する
⇒複雑さ2:一領域にとどまっており、簡単
3. チェックを使って適切な金額を払う
⇒複雑さ4:三領域のうち二つにわたっており、中程度の難しさ
しかし、以上の難易度とタスクの成功率の間に関係はみられなかった。ただ、Norrisらの研究は心理言語学的の伝統と、直接テストのニーズの分析の伝統を組み合わせる必要性を表している点で重要である。
Implementation procedures
教室でタスクを実行する手順はパフォーマンスに強い影響を与えることがわかっているが、テストのタスクではこの点が無視されてきた。ここでは、注目されてきた2つのテスト手順について考える。
Planning time
計画所要時間は、言語教授の場合は流暢性、複雑性、時に正確性を高める。これがテストの場合は、「最高のパフォーマンス」が求められるため、計画所要時間によってパフォーマンスが向上する場合には、これがタスクの重要な実行手順だとすることができる。
・ Wiggleworth(1997b)の研究:テスト場面で、タスクをplanned/unplannedで行ったグループ間で、外部からの分析的評価からは有意差(流暢性、文法、intelligibility)はみられなかったが、談話の分析から、複雑性・流暢性・正確性において一部の協力者には有意差がみられた。⇒一部のタスク、また学習者に関しては向上するが、外部評価からは明らかでない。
・ Wigglesworth(2001)の研究:タスクにおける計画は、参加者にとってなじみのあるタスクや構造的・非構造的タスクの両方で有害な影響をもたらすという結果。⇒談話の分析による測定ではなく、外部評価を使用したためかと考えられる。
・ Iwashita, Elder, and McNamara (2001)の研究:談話の分析、外部評価の両方において有意差が認められなかった。
⇒更なる研究が必要。計画所要時間がタスクのパフォーマンスに与える影響に関しては、外部評価による測定の信頼性に問題があると考えられる。しかしテスト場面では、談話の分析による評価は実用的でない。
Interlocutor
variability theory(変動性理論)やSLA研究によれば、話し相手はL2学習者の産出に主要な影響を与える。テストの場面ではどうか。
・ 社会文化的理論によれば、社会的な相互交渉は評価タスクのパフォーマンスに影響する。
・ Brown and Hill (1998):受験者とその対話者の相互交渉では、後者の方向付けが必須である。なお、interlocutorでも’facilitators’(参加者に合わせる)と’gatekeepers’(参加者に合わせない)とは区別されるが、この異なる役割は参加者のパフォーマンスの評価方法に影響を与えた。
・ Wigglesworth (2001):対話者が母語話者か、馴染みのない非母語話者かで、交渉を要する役割分担タスクのパフォーマンスに影響があった(非母語話者の場合の方が簡単であるという結果)。
・ Fulcher (1996a):Berkoff (1985)の、タスクをグループで行うことは「よそよそしい試験官」と「緊張した受験者」との間の「人工的な会話」が持つ問題を乗り越えることができる、という主張を検証した。グループで行われたタスクの方が参加者は自信を持つことが出来、最も緊張せず、また楽しかったという報告が得られた。また統計による分析によれば、グループで行われたタスクがもっとも簡単だった。
・ O’Loughlin (2001):話し相手の性別⇒受けた評価、質的な側面共に有意差はなかった
⇒どのような側面が実行手順に影響を与えるのかについての更なる研究が必要。特に、外部からの評価がどのように実行手順から影響を受けているのかという点、時間のプレッシャーがどのようにテストのパフォーマンスに影響するのかという点について。
・ Yuan and Ellis (2003):学習者がオンライン・プラニングを行った際、産出がより正確だった。⇒テスト場面での検証が必要。
Measuring performance in task-based tests
タスクそのものは受験者のパフォーマンスを引き出すだけで、言語能力を測定しないため、「パフォーマンスを評価」することが必要となる。主な方法は次の3つ。また、誰が評価するのか(第三者、受験者本人など)という問題もある。
1.タスクのアウトカムの直接的評価
2.談話の分析評価
3.外部評価
Direct assessment of task outcomes
・ 正解か不正解かがわかっているようなClosed tasksはアウトカムに基づいて直接的評価が可能(→Figure 9.1)だが、Open tasksではできない。
・ 直接的評価の利点:客観的に評価が可能(評価者による評価はない)、簡単かつ早い
・ 直接的評価の欠点:試験官が受験者を一人ひとり見ていなければならないことが多く、比較的運営が難しい。⇒書くタスクではこの問題は解消される。
また大きな問題としては、非言語能力によってタスクを達成している可能性がある。
⇒直接的評価の欠点というよりは、作業見本アプローチの直接的performance-referenced テストの欠点である。直接的なsystem-referencedの方法ではこの問題は回避できる。
Discourse analytic methods
タスクのパフォーマンスで出現した特定の言語特徴を勘定するもの。受験者の言語能力(流暢性、複雑性、正確性など)、社会言語能力(要求方略の使用など)、談話能力(連結符号の適切な使用など)、方略的能力(意味交渉に使われる方略など)を中心とすることができる。
・ 多かれ少なかれ客観的な評価の手法と言える。直接パフォーマンスを評価している側面もあるが、実際のコミュニケーション行動について行う判断からは遠い(例:流暢/正確/複雑かどうかでコミュニケーションの効果を判断することはない)
・ Task-based研究で広く使われてきた手法ではあるが、パフォーマンスを書き出す必要があるためテストでは実用的とはいえない。主に外部評価との比較に使用されてきた。
External ratings
前述の2つと異なり、評価者の主観に基づく。信頼性を確かにするための努力がなされてきた。
・ 尺度を使った外部評価はsystem-referenced, performance-referencedの両テストにおいて最も一般的。尺度は、(1)competency(何が測定されるのか)(2)パフォーマンスのレベル(しばしば帯域と呼ばれる)、の2つを特定する。また別の外部評価ではチェックリストを用いて能力を評価するものもあり、有益な診断的情報となる。
・ Task-basedのテストでは目標となる能力は、タスクを達成するための行動的意味合い(⇒Table9.3)か、もしくは言語的意味合いで表現される。Table 9.3のようなタスクでは、タスクそれぞれに個別の評価項目を設けなくてはならないという問題があるがこの場合、行動的・言語的両方の要素を統合した尺度を作成することも可能である。
・ 測定される能力が言語的である場合、パフォーマンスのどの言語の側面が測定されるべきか:総合的/分析的(4技能など)の2種類。OPIのようなテストでは両方が含まれる。分析的な方法を選ぶ場合は、理論的根拠に基づいて測定する側面を選ぶべきである(Skehan, 1998)。多くのテスト作成者は、機能的な条件で能力を選ぶことが多い(例:古いELTSテスト)。
・ 能力の段階・チェックリストはどのように決定・定義されるのか、そして基準となる段階は何に基づいているのか?
⇒McNamara(1996):(1)理論主導アプローチ…基準に基づき、行動をチェックするようなものではdescriptors(Table9.4参照)は文脈主導型となり、あるいは提示された言語能力に応じて段階が決定されるような、概念から派生するものとなる。この場合最高段階は「母語話者レベル」となるが、これは実証されたものではない。
(2)実験的にdescriptorsを作り上げるアプローチ…テストの様々な項目と全般的能力を関連させ、そこから発達尺度を推測する’content-referencing’という手法を使う(例:North, 1996)。もしくは、談話分析の見識から実験的に尺度を発展させることも出来る(例:Fulcher, 1996b)。
・テストで基準を作成するのはさらに問題が多く、管理者によって人為的に、はっきりとした根拠なく決められる場合が多い(大学入学の基準など)。
評価尺度は適用されなければならないが、そのようなタスクを行うためには評価者が不可欠である。(⇒後半、TBAの問題点の項)
Self-assessment
談話分析による評価以外の直接的評価・タスク・パフォーマンスの評価は、自己評価が可能である。
・ 自己評価の利点:時間を消費しない、外部評価と比べて費用がかからない、自分の学習をコントロールするという教育的目的がある場合にそれを満たすことが出来る、学習者に内省・目標を定めることを促すことが出来る。
・ 自己評価の問題点:妥当性・信頼性→自分自身のパフォーマンスを適切に評価することは可能か?
Bachman(1990: 148):自己評価の形式が自己評価に影響を与えた。習熟度に関しては、抽象的な言語能力を問うよりも、実際的な必要性や場面について問われたものの方が指標となった。また、言語をどれくらい使えるかよりも、言語のどの側面が難しいかを問われた方が効果的な回答が得られた。
Sasaki (2000):日本語の自己評価点と客観的な評価の点数との間には関連はなく、「異なる心理特性」を表しているとした。Sasakiは、これは評価方法が特定の技能を測るものというよりは包括的なものだったためではないかとしてBachmanの主張を支持している。
信頼性は、自己評価では一般的に高いが、再テストの際の信頼性は疑わしい。
全体的には、自己評価は根拠がしっかりしており信頼できるものであると言える。
まとめ
受験者の能力を評価するためのタスク・パフォーマンスの測定は、TBAの重要な要素である。ただ根拠がしっかりしていて信頼性がある測定を行えるだけでなく、実用的でコストのかかりすぎない手法が求められる。
(研究会でのコメント)
・ タスクはただ作られるだけでなく、それによって引き出されたアウトカムをどうやって評価するかを視野に入れてデザインする必要があることがわかる。
・ 外部評価の項目で、テストにおける評価基準作成は人為的で根拠のある場合が多いとの指摘があった。限界はあるものの、できるだけ明確な根拠に基づくよう努力されるべきである。 (伊藤)
ページトップに戻る
2009/4/9
Chapter 10: Evaluating task-based pedagogy (pp. 319-328)
1. Introduction
■言語学習において学習者は意味の生産(making meaning)を行わなければならず、その意味生産のプロセスにおいて学習者は言語形式に注意を払い、気づく必要がある。タスクはこれらの条件に適う言語習得装置であると言えるが、多くの場合タスクはPPPなどの言語形式に焦点を当てた従来の教授法の最終ステップとして位置づけられており、コースの中心を成してはいない。
■上記の原因を探るため、本章では以下の3つのことを行う。
・innovationistの視点に立ち、タスクを中心とした教授法の実用性を探る
・タスクを中心とした教授法の実証的評価(empirical evaluations)が不足していることについて議
論する
・タスクを中心とした教授法に対する数多くの理論的批判をまとめ、教育的視点から返答する
2. An innovationist perspective
■タスクを中心とした教授法は「革新(innovation)」であると捉えることができ、教育に対する既存の価値観を揺るがし、慣れた教え方に取って替わる「脅威(threat)」となることもある。この脅威に教師がどう対処するかには、次の4つの要素が関わる。
(1) 革新の社会文化的コンテクスト:生徒-教師の関係がタスクに向いている文化か、など
(2) 個々の教師の人格と技術:L2のoral proficiencyなど
(3) 実施の方法:革新自体の性質とは直接関連しないので扱わない
(4) 計画自体の特性:タスクを中心とした教授法を採用できるか吟味するのに有効。本章のメイン。
■(4)はp.322のTable 10.1に要約されている。いくつかを取り上げてみる。
Complexity:どれくらい理解しやすい革新内容であるか
(例:focused tasksとcontextualized language exercisesを区別できるか)
Explicitness:革新に対する理論的根拠がどれくらい明確で説得力があるか、複数の理論を含むか
Originality:教材を自作しなければいけないか、すでに出版されているものがあるか
■タスクを中心としたコースを始めるのと、タスクを実験的に行うのでは、前者のほうがチャレンジングであり問題を引き起こすことも懸念されるので、2つは区別する必要がある。この区別は本書を通して言及しているtask-basedとtask-supportedの区別と一致する。innovationistの考え方ではtask-supportedのほうが導入しやすいとされるが、task-basedよりも理論的に優れるということを意味するのではない。
3. The empirical evaluation of task-based teaching
タスクを中心とした教授法の実証的評価には、次の2種類がある。
☑ミクロ的評価(micro-evaluation): 評価対象が1つのタスク
☑マクロ的評価(macro-evaluation): 評価対象がタスクを中心としたコース全体
3.1 The micro-evaluations of tasks
■タスクのミクロ的評価には2つの目的がある。1つは、特定の学習者グループにとってタスクが有効なのかということを調べること。もう1つは、タスクの欠点を見つけ改善する方法を見つけること、である。
■ミクロ的評価の観点は3つある。
①student-based evaluation: 生徒のタスクに対する姿勢や意見を明らかにする
②response-based evaluation: 期待していた結果をタスクが生んだかを、プロセスと産出の両面 から評価する
③learning-based evaluation: 指導の前後で、言語習得が成されたかを明らかにする。1回の指 導では見極めが難しい(unfocused taskの場合は特に)。
■Hoogwerf(1995)は、日本人留学生に対して行った8ヶ月間のCRタスク(目標言語項目は主語-動詞の一致で、writing形式のもの)の効果を検証。期待していたプロセスは、生徒が主語に線を引き、それに合う動詞の形を供給すること。期待していた結果は、生徒がタスクに熱心に取り組むことであった。下の表は評価の結果を日本語で簡単にまとめたものである。
Types of evaluation Main results
Student-based 生徒のジャーナルでは、タスクに前向きに取り組んでいたことがわかる。
Response-based 多くの生徒が主語に線を引き、正しい動詞形を答えることができた。
Learning-based 全体的には、指導前後での伸びは見られなかったが、上位群は顕著な伸びを示した。
Table 10.2: Results of a micro-evaluation of a task (p. 325)
■このようなミクロ的評価の利点は2つ。1つは、タスクの長所や短所など、デザインについての有益な情報が得られることである。もう1つは、教師自身の教室で行ったときに、アクションリサーチの有効な手段となる、という点である。
3.2 Macro-evaluations of task-based courses
■マクロ的評価はプログラム評価(programme evaluation)とも考えられ、ミクロ的評価とは対照的に、多くの文献を見つけることができる。以下ではその例として、Prabhu(1987)のCommunicational Teaching Project(以下CTP)を異なる方法で評価したBeretta & Davies (1985)とBeretta (1990)を紹介しつつ、マクロ的評価の実施上の問題点についても言及する。
①Beretta & Davies (1985):
CTPの効果について、実験群と統制群の学習結果を比較することで評価した。このとき評価の偏りを防ぐために、両群に行った学習形態(実験群:タスク中心、統制群:言語構造中心)に合わせたテスト形式(タスク中心のテスト、言語構造テスト)と、中間的な形式のテスト(文脈化された文法テスト、ディクテーション、聴解・読解テスト)を採用した。その結果、実験群がタスク中心のテストと中間的な形式のテストの両方で統制群の成績を上回り、タスクを中心としたCTPは言語形式に焦点を当てた従来の教授法よりも優れていると結論づけた。
②Beretta(1990a):
BerettaはCTPの評価を教師に注目して行った。15人の教師のコメントをもとに、プロジェクトの実施の度合いを次の3つのレベルにわけた。
Level 1 orientation:タスクを中心とした教授法の理解が不十分で、実施できなかった
↓
Level 2 routine:プロジェクトの理論的根拠を理解しており、効果的に実施できた
↓
Level 3 renewal:鑑識眼をもってプロジェクトの長所と短所を見極めることができた
40%の教師はLevel 1に、47%はLevel 2に、13%はLevel 3に位置づけられた。しかし、常勤教師と非常勤教師を区別して評価を行うと、75%の常勤教師はLevel 1であるとわかり、このプロジェクトの導入が難しいことが明らかになった。
■このようなプログラム評価は複雑で、学習結果に基づいた評価を行った場合、有意差が出づらいという問題がある。理由は以下の3つ。
理由1:どういうテストが両群にとって公平なものか決定しづらい
理由2:グループを均質にするための統制がとりづらい
理由3:方法論(method)を比較する時に、外部的描写(external descriptions)に基づいて行うと比
べづらい
■プログラム評価をする者は、理論と実践のどちらを優先すべきかで迷いやすい。とはいえ、タスクを中心としたプログラムの評価の必要性は高まっているので、プログラムの目的にかなった評価方法をするためにも、評価法の更なる開発が待たれるところである。
(研究会でのコメント)
ミクロ的評価の3つの観点のうち、response-based evaluationとlearning-based evaluationの違いは何かについて質問があった。タスクを用いた言語学習には、目標言語形式を使ってタスク自体を達成する、タスクにより言語形式を内在化する、という2つの目標がある。前者の観点は1つめの目標が、後者の観点は2つめの目標が達成されているかどうかを評価するものである、と今野さんより助言を頂いた。 (大木)
ページトップに戻る
2009/4/9
Chapter 10後半(pp. 328-338)
Theoretical objection to task-based teaching (pp. 328-336)
The restricted nature of task-based communication (pp. 328-331)
■ task-based teaching(タスク中心教授法)が言語の使用を制限した結果,学習者が言語学習の成功に欠かせない重要な経験をし損ねている。
■ Jakobson (1960)が示す言語機能
(1) referential function:ほとんどのタスクがこれに当てはまる。
(2) emotive function:role-play task(役割演技タスク)が当てはまる。
(3) connative function:opinion-gap task(情報格差タスク)が当てはまる。
(4) phatic function:ある程度,すべてのタスクがこれにも当てはまる。
(5) metalingual function:consciousness-raising task(意識高揚タスク)が当てはまる。
(6) poetic function:完全に欠けている部分。学習者がタスクを行う時,言語そのものに注意を払って言語を操作しようとはしない。 language play (Cook, 1997, p. 227)
■ Cook (2000)は言葉による遊びとタスク中心教授法を反映した近年の教育学的強調との違いを概観した。
■ Cookはまた,タスクが引き出すコミュニケーションはもともと限られていると要点を示した。その制限には2点あり,(a)人々がauthenticallyに言語を使用するのを反映していない(つまり,日常の言語使用は言葉遊びであふれている),(b)人々のやる気をなくさせるものである,ということである。
■ Cook (2000)は言葉遊びを教室に導入する教育的提案をしている(例:pattern drills)。しかし,言葉遊びにある動機とpattern drillsは全く違うものであり,異なる活動でもあるということから,この提案は説得力のないものである。
The cultural relativity of task-based teaching (pp. 331-333)
■ 2番目の批判は実際,linguistic imperalism(言語帝国主義)(例:Phillipson, 1992)や言語教育への批判的アプローチ(例:Pennycook, 1994)の理由から,社会的政治的なものである。この観点から,タスク中心教授法はアングロ・アメリカ的産物である。
■ critical pedagogy(批判的教育)は,その基礎をなす社会政治的なメッセージを解き明かすために,言語教育への特定なアプローチの分析を必要としている。Pennycook (1994)が指摘するように,言語教授法にはそのアプローチに埋め込まれた談話を教えることが含まれている。
■ つまり,Pennycookは指導実践の隠れた社会政治的メッセージの検証を推進し,学習者が新植民地主義イデオロギーの受身的消費者にならないように‘counter discourses’の確立を主張した。
■ タスク中心教授法には,隠れた社会政治的メッセージがある。
■ さらに,タスク中心教授法によって求められる教室実践は文化的重みがあると考えられる。コミュニケーション教授法の一形式としてのタスク中心教授法は,特定の文化的文脈を含んでおり,それには学習が協同的・経験的活動として見なされない文化的文脈との対立が存在する。
■ “第2言語”指導で適切であることは,“外国語”指導では適切ではないかもしれないと考えられる。
(1) 授業時数の制限のため,タスク中心教授法は外国語学習では実用的ではない。
(2) タスク中心教授法は,第2言語における口頭表現力が不安定な非母語話者によって行われるのに困難をきたす。
■ タスク中心教授法に対する批判的な見方が,重要な疑問を引き出している。
■ 学習者からの批判的反応を引き出すタスクが必要である。このことは,言語特徴だけでなく,特定の言語形式の選択が社会政治的意味を符号化する方法に焦点を当てたconsciousness-raising tasks(意識高揚タスク)を構築することで可能である。
■ 批判的教育が挙げた批判は,タスク中心教授法の拒絶ではなく,むしろその限界(と危険)の暗示と考えられる。
Teaching languages as communication (pp. 333-336)
■ タスクはコミュニケーションを指導するのではなく,学習者をコミュニケーションへ参加させることをねらいとしている。
■ 「タスクは,習得を促進するコミュニケーション言語活動という結果になるのか?」という質問に対し,前章で導き出された答えは‘Yes’である。しかし,それには代替案がある。
■ 学習者には方略的能力が必要とされるが,中間言語を“拡張する”機会をなくすかもしれない。Breen (2001, p. 128)から,タスクが到達されるようにデザインされたコミュニケーションを促進するという保障はないと言える。
■ また,充分にsituational authenticity(状況的真正性)やinteractional authenticity(相互交流的真正性)を到達可能であるかどうかも問われる。
■ 教室内で自然なコミュニケーションを再現することをやめるべきである。その代わり,教室内文脈は一種の‘instructional discourse’ (Seedhouse, 1996)を構成することを認識し,このような文脈が習得にどのように働くのかを理解すべきである。
■ 教室内の参加者はタスクを行う際にコミュニケーション・ゲームをしているが,完全に教師や生徒の役割を捨てていない。つまり,タスクは達成すべきこと=“真の”コミュニケーション行動という結果にならないと考える理由が充分ある。
■ コミュニケーションを疑似体験できないならば,わざわざやろうとすべきことであるか。Widdowson (2001, p. 18)は,ある特定の特徴を持つ言語の側面,つまり言語能力の指導に焦点を当てたほうがよいと提案した。
■ タスクを通してコミュニケーションを疑似体験することができないことをやるよりは(teaching language as communication),コミュニケーションのための言語能力を指導すべき(teaching linguistic competence for communication)である。
■ タスクによって学習者を教室外のコミュニケーションで起こるcognitive process(認知的プロセス)に引き込ませることが,主要な議論となっている。
■ タスク中心コミュニケーションが“自然で”,“真正性があり”,“会話的な”ものであることを明示する必要はない。しかし,前章で示したとおり,この主張には基本原理が成り立っていない。タスク中心の相互交流は,習得が起きる中で認知的プロセスを促進しているので,複雑で多様なものでありうる。
Conclusion (pp. 336-337)
■ 指導の現場でタスク中心教授法を改編して実施されていることは少なく,また今のところ,タスク中心のコースが実際に行われているのが少ない。
(1) 応用言語学の考えでは,タスク中心教授法が言語使用の種類において制限されている。
(2) タスク中心教授法が,文化的文脈に沿っていないアングロ・アメリカ的な発明品であると考えられる。
(3) タスクが教室内の“自然なコミュニケーション”という結果ではないので,(2)のような考えは弁明できないものであると見なされる。
(4) タスク中心教授法が実行するには難しい,急進的な革新であると考えられる。
■ task-supported teaching(タスク支援型指導法)が多くの教師にとって指導方法の一部であると考えられる一方,タスク中心教授法はそうではない。
■ 本章では,Communicational Teaching Projectの流れに沿って,異なる文脈内でタスク中心のコースを実践することや,注意深く実験的な評価を出すことによって,タスク中心教授法が理論から実践へ移行する方法を提案した。
■ 局所的・大局的評価が,タスクによる指導法を普及させる主要な役割を果たすと考えられる。
■ また教員養成においては,タスク中心教授法の原理・指導法の導入を含めた。これはタスク中心教授法とタスク支援型指導法との違いに気づかせることができるし,タスク中心教授法の方法論に焦点を当てることができる。
(研究会でのコメント)
■task-based teachingの批判とは,Angro-Americanなものの考え・見方をそっくりそのまま別の論理をもつもの(例:アジア諸国の英語教育)に当てはめていくことは危険である。(=task-based teachingに対するEllisの一種の批判?)
■「タスクは,習得を促進するコミュニケーション言語活動という結果になるのか?」という質問への答えは必ずしも‘Yes’であるとは限らない。なぜなら,タスクそのものが習得に役に立つとは限らないからである。
■ タスクを通しての疑似体験よりは,コミュニケーションのための言語能力を指導することのほうが,学習者にとっては効果的であるのかもしれない。また,タスクによって学習者を教室外のコミュニケーションで起こるcognitive
process(認知的プロセス)に引き込ませるほうが,重要となってくると考えられる。 (柴原)
ページトップに戻る

ページトップに戻る
ご意見やコメントがあればこちらまでお寄せください。