






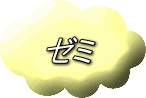
| �p�ꋳ��]���_ |
|||||||||
| 2012�N�x�i2012.4���`�j���j�S���@�p�ꋳ��_�̎��ƂŔ��\���ꂽ���W�������ڂ��Ă��܂��B |
|||||||||
�P�w�� ��5��7�� �S���FS.H. �����Ƃŋc�_���ꂽ���e�́u?�@�@�@�v�Ƃ��ĒNjL���܂����B 1.1 ���Ƃ́H�K���Ƃ́H n ��ꌾ��
(first language: L1) O �l�����܂�čŏ��ɐڂ��錾��B���(mother
tongue)�B���R�Ƀ}�X�^�[����B n ���
(second language: L2) O ��ꌾ��̌�ɐڂ��錾�ꂷ�ׂāB�ӎ����Ċw�K����B n ���ƊO����
(foreign language: FL) �̎g������ O �@�@�@�@�@�@�@ �O����Ƃ��Ẳp��
(English as a foreign language: EFL) O �{���ł́u���v�͂��L���Ӗ��łƂ炦���u�O����v�Ƌ�ʂ��Ă��Ȃ��B n �K��
(acquisition) �Ɗw�K (learning)
�̈Ⴂ O �u�K���v�͓��Ɉӎ����Ȃ��Ă����R�Ɏ�ɓ���閳�ӎ��ȃv���Z�X�B O �u�w�K�v�͈ꐶ�����ӎ��I�ɕ����邱�ƁB �@�@�@�@�@��Krashen
(1982) �͂��̓��S���قȂ���̂ł���A�w�K�ɂ���ē���ꂽ����m���͏K�����ꂽ�m���ɕω����邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����C���^�[�t�F�C�X�̗�����Ƃ����B 1. 2 �ߔN��SLA���������̗��R n ����܂ł̊O���ꋳ�炪�\���Ȑ��ʂ������Ă��Ȃ�����B�p�ĕ��w��p��w����������Ƃ��Ă�����������ʓI�ł������B n �S������w��F�m����w�Ȃǂ̗אډȊw�̔��B�ɂ��A�l�̔F�m�E�w�K�V�X�e���ɂ��Ă̌������i�W��������B O ����܂ŁA���K���⏈���̌����͋���̕��@�_�J���̂��߂̃n�E�c�[�ɂ�����镪�삾�Ƃ݂Ȃ���Ă����B O �������������N���A���ɂ�����S������w�I�Ȍ�����F�m�Ȋw�I�Ȍ���(��ꌾ��̌����ł͊��Ɏ��g�܂�Ă������ꏈ���V�X�e���Ɋւ�����̂Ȃ�)������I�ɐi��ł����B 1. 3 SLA�����̎�ށF�������،^�Ɖ����T���^ n �������،^�̌��� O ��ʂɎ��،���
(empirical studies) �Ə̂���A�����I���� (experimental
study) �E�ʓI���� (quantitative
study) �ƌĂԂ��Ƃ�����B�S���w�ɂ����č̗p����Ă�����@���قڂ��̂܂ܓ��P�����A������p�����Ȋw�I�Ȍ������@�B O �������،^�̌����̂��߂̃X�e�b�v �@ ��s�����̒��� �A �����ړI
(research objectives) �̐ݒ� �B ���T�[�`�N�G�X�`����
(research questions) �̐ݒ� ?���T�[�`�N�G�X�`������Yes / No�œ�������^�╶�ł�What���^�⎌�Ŏn�܂���̂ł��悢�B �C ��������
(research hypotheses) �̗� ?research hypothesis�̈Ⴂ (1) �`���̈Ⴂ�́A�O�҂��^�╶�̌`�Ō�҂̋^�╶�ł͂Ȃ��`�B (2) ������x�u�����Ȃ�̂ł͂Ȃ����v�ƌ��ʂ��\���ł���悤�Ȏ���research hypotheses�Œ��A�͂�����Ɖ��������Ă��Ȃ��ꍇ��research questions�𗧂Ă�B�]���āA�ǂ��炩�Е������悢(����������Ă��錤��������)�B �D �ǂ�Ȍ������@�ŇA�`�B�𗧏��邩�̌��� �E �����̎Q����
(participants) �̌��� ?participants�́u�Q���ҁv�������́u���͎ҁv�ƋL�q���A�u�팱�ҁv�Ƃ����\���͔�����ׂ��ł���B �F �����f��
(materials) �̌��� �G �葱��
(design) �E�菇 (procedure)
�̌��� �H �������ʂɑ��镪�͕��@
(analysis) �̌��� �I ����
(result) �E�l�@ (discussion)
�E���_ (conclusion)
�̓W�]�Ɋւ���l�@ n �����T���^�̌��� O �ʓI�����ɑ��āA���I����
(qualitative study) �ƌĂ��B O �����T���^�̌����ɂȂ�P�[�X (a)�@��s�������S�����邢�͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��B �@�@�@�@�@�@?���̏ꍇ�A��s�����Ȃ��̉������،^�����ɂ��ł���B (b)�@�����𗧂Ă邾���̍����Ɍ����邽�߉��������藧���Ȃ� (c)�@���������{���Ă��K�����������̏ؖ��ɂȂ�Ȃ��B (d)�@�팱�Ґ�������I�ɕs�����Ă��邽�߁A���v����ɂ������Ȃ��B (e)�@�f�[�^�����v����\�ȃ^�C�v�̃f�[�^�ł͂Ȃ��B �@�@��(d)(e)�̏ꍇ�ł��m���p�����g���b�N�����p����Ό���\�ȏꍇ������B O ���̌^�̌����ŗp�������@�͓��L�E�|�[�g�t�H���I�E�C���^�r���[�E���b�v���g�R���@�Ȃǂ�����A�ω��̃v���Z�X���ώ@�ł���B 1. 4 �{���̎�|�ƑΏۂƂ��錤���̃^�C�v n ���̖{���ΏۂƂ���̂́A�������،^�̃^�C�v�B �y�Q�l�����z �����m�F�E�y�c�S��E�����m�E��іΑ�. (2009). �w�p�ꋳ��p�ꎫ�T�x. �����F��C�ُ��X. �y�{���Ǝ��Ƃ̊��z�z ���̖{�ł́A���ƊO����̋�ʂm�ɂ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��������AESL����EFL���ł͉p��̊w�K�������@�Â���C���v�b�g�ʂȂLjقȂ�_������������A�����������w�K���̈Ⴂ���������ʂɔ��f�����\�������邾�낤�B���������āA�_����ǂލۂɂ͎����Q���҂̒u���ꂽ�w�K���ɂ����ڂ��A���ꂪ���{�lEFL�w�K�҂ɂ��K�p�ł��錤���ł��邩�ǂ����������ׂ��ꍇ������̂��낤�Ɗ������B �@�܂����ƂŁA�u�����̊S�̂��鎖���������Ȃ����Ă���搶���̃z�[���y�[�W���Q�Ƃ���v�A�u���m�_���ׂ͍����L�q����Ă���A�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�v�A�u���،����̌^�͂قƂ�nj��܂��Ă���̂Œm���Ă���Ɠǂ݂₷���v�ȂǁA�_���̒T������ǂݕ��Ɋւ��ėL�v�ȃA�h�o�C�X�������������̂ŁA���ꂩ���s������ǂݍ���Ō����ۑ���i��A�������ʔ����ėL�v���Ɗ������錤�����ł���悤�ɂ������B�@���͘_�����������Ƃ��Љ�v���Ɍ��т��Ǝv���̂ŁA���̐ӔC���ʂ�����悤�M�S�Ɍ������Ă��������B
Step2�@��s�����������ɓǂ�Ńe�[�}��ݒ肷�邩 ��2-1�����͂ǂ̂悤�ɂ��ďW�߂�H �ȉ��̂R��ނ̓ǎ҂�z�肷�� (A)���K�����ǂ̂悤�Ȃ��̂ŁA��̓I�ɂǂ̂悤�ȃe�[�}�Ō����ł���̂��킩��Ȃ� (B)���������ςȌ����e�[�}�͌��肵�Ă��邪�A��s�������ʂ��킩��Ȃ� (C)��s�������킩�������A���̒��œ��ɊS�̂�����،�����֘A�̂�����،���������ɒT������ 2 �ǎ�(A) �E���K���Ɋւ������发�A�T������ǂ� �E���K���̒��g�ɗ����������I�������� �@�����Z�\���i���X�j���O�A���[�f�B���O�A�X�s�[�L���O�A���C�e�B���O�j �@�@�����e�� ���Օ��@�x�[�X�̑��K������ �@�@�@�@�N���X���[�������K������ �@�@�@�@CALL(computer assisted language learning) �E��w�}���فA��������}���فA�n��̌����̐}���فAamazon.co.jp�Aamazon.com�ȂǂŌ��� 2 �ǎ�(B) �E����܂ł̌������ʂ����r���[�_��(review article)��ǂ� �@�������e�[�}���i�荞�� �E���G���ɂ͂Q�ʂ�̘_�������� ���V���ȃI���W�i���Ȏ��f�[�^���f�ځE�E�E���،����_�� ����s�����ɂǂ̂悤�Ȃ��̂�����A�ǂ̂悤�Ȍo�܂��o�āA�����_�łǂ��܂ł̂��Ƃ��킩���Ă� �@�邩���ڂ����ՂÂ����_���E�E�E���r���[�_��(review article) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�[�x�C�_��(survey paper) �Ea review�`�Aa survey�`�Ȃǂ̌��ƂƂ��Ɍ����e�[�}���o�����郌�r���[�_����T���o�� �@�����S������w�̈� The
Oxford Handbook of Psycholingustics.(Oxford University Press) �����K���̈� Doughty, C.J.and Long. M.H.(eds) The Handbook of Second Language Acquisition(Wiley-Blackwell) Ritchie, B.W The New Handbook of Second Language Acquisition �@�@�����[�f�B���O�̈� �@�@�@Israel,
S.E.,and Duffy,G.G.,(eds) �@�@�@Handbook of Research on Reading Comprehension �@�@����v�ȊC�O�̑��K���W�̎G�� �@�@�������f�[�^�x�[�X �@�@�@LLBA(Linguistics & Language Behavior
Abstracts) �������{���A�L���_�E�����[�h 2 �ǎ�(C) �E�ŋ߂̎��،��ؘ_����T�� �E�����O�̎G���A�����O�̍u���E���\ �ELLBA�Ȃǂ̃f�[�^�x�[�X�A�G���̊������̌f�ژ_�� �@�w��̃v���V�[�f�B���O�X(proceedings)�A�w����ǂ���w���A �u���҂̃z�[���y�[�W���疳���_�E�����[�h �@�@ �E�u����͂��I�v�Ǝv���_���̌������@�̈ꕔ�A���Ȃ�̕�����͕킷��i�ǎ�����j �@�@�@�@�����n�߂Ę_���������ꍇ�ɂ͗L�v �@�@�@�@�@�������ړI�A�����A�������@�Ȃǂ������ł��A�팱�ҁi�Q���ҁj���S���Ⴆ�Εʂ̌����ɂȂ� �E���،��ؘ_���ɕK�v���`���E�̍���A�p��\�����Q�l�ɂ��邱�Ƃ��ł��� �@������̕\�����g�p����͓̂���i���ށj�@ ��2-2�����͂ǂ̂悤�ɂ��ēǂށH 2 �ǎ�(A)�F����E����� �E���̓_���l�����ēǂ� �@�@���҂��͂�����(preface)��A��(introduction)��ǂ�ŏ����̖ړI�𗝉����� �@�A�ڎ�(table of contents)���݂āA�S�̂̍\����c������ �@�B������邢�͊e�͂�ǂނ����悻���ڕW�������������� �@�C�ڍׂɓǂ������ƁA�Ƃ��ǂ݂�����������ʂ��� �@�D�ڍׂɓǂޕ����ł́A�p�\�R�����g������������ �E����E�T�����Ƃ��Ă����ꂽ���� �@Grabe,
W.and Stoller,F(2001) Teaching and
Researching Reading.Edinburgh Gate : Pearson Education. 2 �ǎ�(B)�F���r���[�_�� �E��s������،����ɂ��Ă̘_�]�A���e������ �E�������ʂ̌���(state of the art)������ �E���̓_���l�����ēǂ� �@�@�ǎ�(A)��5�_�Ɠ��� �@�A�ł��邾���ŐV�̃��r���[�_���i���s��5�N�ȓ��j �@�B�ᔻ�I�ɓǂ� �E�����ꂽ���r���[�_�� �@�@�@�@Clahsen,H.and
Felser,C(2006)Grammatical Processing in Language Learners.Applied �@�@�@�@Psycholinguistics 27 : 3-42 2 �ǎ�(C)�F���،��ؘ_�� �E�_�����e���v��f�[�^�x�[�X���쐬���� �@�����������g�ň��p���₷���v��t�H�[�}�b�g������i���p�̌��x5�s���x�j �@�@���ǂ�ȖړI�������āA�ǂ̂悤�Ȏ�����������A�ǂ̂悤�Ȍ��_������ꂽ�����Ȍ��ɂ܂Ƃ߂� �@�@���������g�̃R�����g���L�^���� �@�@��Word�Ȃǂ̃��[�v���\�t�g�ŁA�P�_���P�t�@�C���ɂ��APDF�t�@�C���ɕϊ����Ă��� �E���ؘ_�����`���i�t�H�[�}�b�g�j�A�\��(organization)��O���ɂ��� �E��ʓI�ȍ\�� �@(1)�T�v(abstract) ���_���S�̂̎�|�A200�`300����x (2)�����̔w�i(background) �@ ����s�������ʂ����������Y�����̈ʒu�Â������
(3)�����̖ړI(purpose) �@�@ �������ۑ�(research question)�₻��ɑ�������(hypotheses)���܂� (4)�������@(method and procedure) �@�@�@��(a)�팱��(subjects)�A�Q����(participants) (b)�h���ޗ�(materials) (c)�����f�U�C��(experimental
design) �]���ϐ�(dependent variable)�A�Ɨ��ϐ�(independent variable) (d)�葱��(procedure) (e)�f�[�^�̕��͕��@(data analysis) (5)����(results) �@�@�����ϒl(mean)���W����(standard
deviation:SD)�Ȃǂ̐��l�A�\(table)���O���t(figure)�A �@�@�@t-����(t-test)�A���U����(analysis of variance:ANOVA)�A���d��r(multiple
comparison)�Ȃǂ̓� �@�@�@�v���茋�� (6)�l�@(discussion) �@�@���u���ʁv�Ŏ����ꂽ���l���牽�������邩 (7)���_(conclusion) �@�@���u�l�@�v���炢���Ȃ錋�_�������邩 (8)����̓W�](further study) �@�@�����_�̐����ƁA�����̗��ӓ_ (9)���p�����ꗗ(references) (10)�t�^(appendix) �@�@ �E�_���T���v�� �@ Webb,S.(2008)Receptive and
Productive Vocabulary Sizes of L2 learners. SSLA 30:79-95 ��2-3�����e�[�}�̐ݒ���@�́H 2 ����e�X�g�����Ă���ׂ����� (a)�Ó���(validity)�E�E�E��������Ӗ��E���l�����邩 (b)�M����(reliability)�E�E�E�q�ϓI�Ȏ��f�[�^�������邩 (c)���s�\��(practicability)�E�E�E�f�[�^���W�����ۂɉ\�� 2 �����e�[�}���_�E���T�C�Y���� 2 ���s�\�����T�[�`�v�������l���� 2 �������T�[�`�v�����̏����i�����̐����q��@�́E���X�؉Ñ����j �@����Ă���{�l���u�ʔ����v�u�L�Ӌ`���v�Ǝv���� �A������ʂ��ĐV�����Z�p�◝�_���w�ׂ� �B�C����̌��������̊�b�ɂȂ� �C�����̏A�E�ɂȂ��� �D���p��̉��l������ �E�w��I�ɉ��l�������i����̔��W�ɍv������j �F���ʂ��w�����G���Ŕ��\�ł��� �G�ǂ�Ȍ��ʂ��o�Ă��A���l������ �H���L�̋@�ނ�\�Z�Ə���̊��ԓ��Ő��s�\�ł��� �@ ���܂Ƃ߁E���z �@�E�@�_���̌`���⌋�ʂ̕��͂̂�������g�ɂ��Ȃ���A�Ǝv���Ă������A��������܂���Ȃ��ƁA�u��s�����̒T�����v�u�_�����e�̗v��f�[�^�x�[�X�̍����v�u����̓I�ȃe�[�}�̌������v�Ȃǂ𗝉��� �@�@�邱�Ƃ��ł����B �E ���̏͂��܂Ƃ߂Ă݂āA�_���쐬�ւ̔��R�Ƃ����s�������Ȃ茸�����悤�ȋC������B�����A�_�������� �@���Ƃւ̊y���݂��o�Ă����̂ŁA���̏͂��n�ǂ��A���M�������Ď�肩���肽���B �E ���T�[�`�v�����̍쐬�⌋�ʂ̕��͂ɂ͓��v�I�ȏ����Z�\���[���ւ���Ă���Ǝv���̂ŁA���Ƃł����H �I�Ɋw�сA�_���ɐ����������B
�����ƌ�̎��g�� 2 p.32�`�̋L�q�ɏK���A�_���̃R�����g�t���L�^�p�v��������Ă݂܂����B O �������@ �ga survey of English leaning at
elementary school in Japan�h�@ O �_�� Daniela Nikolova (2008) English-teaching in elementary schools in
Japan : a review of a current government survey. Asian EFL Journal Vol.10.
Issue1. Article12 O �v�� (a)�����̖ړI �@�@�@���{�̂���܂ł̉p�ꋳ��̗��j���ӂ�Ԃ�A�ŐV�̒����ƎЉ��Ɋ�Â��������w�Z�ɂ���p�ꋳ�� �@�@�ɔᔻ�I�Ȏ�����^����B�܂��A���w�Z�p�ꊈ���̖��_���\�Ȍ���������A���{�I�ȉp�ꋳ��ے��̉�������������B (b)�������@ �@�@���{�̉p�ꋳ��̗��j����l���� �@�A�������w�Z�̉p�ꊈ���͂��� �@�B����̉ۑ�Ɖ\�Ȏ��g�݂��l���� (c)���_ �@�@1853�N�̊J�����A2�ʂ�̉p��w�K���@���������B1�߂́A�u���m�Ȕ����v�Ɓu�Ӗ��v���d������� �@�@�@�A2�߂́A�u�Ӗ��v�݂̂��d��������@���������A��҂̊w�K�ҕ�������x�����������B1921�N��
Harold E. Palmer���AOral and Direct method��������A�펞���G���̌��t�Ƃ������Ƃō̗p��Ȃ������B1970�N��ɂ́A�u���H�I�A�v���[�`�v�Ɓu���_�I�w�K�v�̋c�_���������B1990�N��ɓ���A ���ۉ��̗����Communicative
Approach ��Communicative Language Teaching�ɕω����n�߁A�܂��A�����w�Z�ō̗p���ꂽ�B2002�N�ɂ́A�u�p��b�v��u���ۗ����v�̎��Ƃ��A�������w�Z�ɂ��Љ�ꂽ�B�܂��A���N�u�Q�P���I�헪�\�z�v�ɂ��p�ꋳ��̎��̌��オ�����A����܂ł̐������Ȃ����������@ (reading, writing���S)�͔p�~����A���̋Z�\
(listening, speaking) �̔䗦�����ߑg�D���ꂽ�B �@�A�������� �@�@�u�p��b�⍑�ۗ����̎��Ƃ��s���Ă��邩�v��37.7�����s���Ă���A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N�P��37.3���A���P��34.3���@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�����̗̂\�Z���̗��R�őS���I�ɂ�������� �@�@�u�p��b�⍑�ۗ����̎��ƂɊւ��閞���x�v�������F����71.5���A����14.3�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w���S�C�F�����ɐϋɓI90.3���A���ɓI5.9�� �@�@�u�p�ꂪ�D���ȗ��R�i�U�N���j�v���̂�Q�[�����ł��邩��74���A�p�ꂪ�ǂ߂邩��44.6���A �O���l�̐搶�Ƙb���邩��40.6�� �@�@�@�@�u�p�ꂪ�����ȗ��R�i�U�N���j�v�����ɓǂ߂Ȃ�����46.8���A �p��̎��Ԃ𑼋��Ȃ̔��W�w�K�ɓ��Ă������悢����43.3���A �F������O���l�ƓK�ɏ��ɘb���Ȃ�����37.1�� �@�@�@�@�u�������p��̊w�K�����������i�U�N���j�v���w�K������64.7���A�w�K�������Ȃ�22.5�� �@�@�@�@�u�������p��̊w�K�����������R�i�U�N���j�v���p��̓ǂݕ����w�т�������62.7���A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���l�Ɖp��Řb����������51.2���A�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�����Ɖp��Řb����������49�� �@�@�@�@�u���w�Z�p�ꊈ���̂˂炢�́A�q�ǂ��������p��ւ̒�R�������������̂ɂȂ��Ă��邩�v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s6�N���̕ی�ҁt�����Ȃ��Ă���77.7���A�قڂ����Ȃ��Ă���16.9�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���t�t�@�@�@�@�@�����Ȃ��Ă���67.1���A�قڂ����Ȃ��Ă���27.4�� �@�@�@�@�u���w�Z�p�ꊈ���̂˂炢�́A�q�ǂ��������O���l�ƃR�~���j�P�[�V���������ł̐ϋɓI�ȑԓx��ӗ~��{�����̂ɂȂ��Ă��邩�v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s6�N���̕ی�ҁt�����Ȃ��Ă���50.9���A�قڂ����Ȃ��Ă���35�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���t�t�@�@�@�@�@�����Ȃ��Ă���57.7���A�قڂ����Ȃ��Ă���34.7�� �@�@�@�B�����Ȋw�Ȃ́A���`�ȂǃA�W�A�̍��X���Q�l�ɁAnative ��non-native���t�̘A�g���������ׂ��� �@�@�@�@����B�܂��A����̐����l���Ɠ��{�̓`���̎Љ�I�����̗������A������e�ɑg�ݍ��ނׂ��ł���B�O �@�@�@�@����̓��������݁A�ٕ����ւ̏_��ȑԓx����ނɂ́A���ɏ��w�Z��U�w�N�Ƃ����N��K���Ă���B �@�@�@�@�E�p�ꊈ���̎�����S���I�ɓ��ꂷ�邱�� �@�@�@�@�E�������y���݂Ȃ���w�K�ł���悤�ȋ��ȏ������� �@�@�@�@�@�����ȏ��Ƃ��Ă̌��ʂ��������蒲�����Ă���Areading��writing�ɂ��Ă��������Ƃ�����ɓ���Ă��� �@�@�@�@�E�p���O���l�ƃR�~���j�P�[�V�������邱�ƂɑO�����ȎႢ�������w���S�C�ɂ��Ă� �@�@�@�@�E�p��w�K�̊��𐮂��A���t��ی�҂̊肢�����݂Ȃ���Areading��writing�̏����I�ȓ��e���� �@�@�@�@�@�����Ƃ��l���Ă����B �@�@�@�@���w�Z�̉p�ꊈ���́A�Љ�I�ȗ����A���t�x���A����ے��̈����Ȃǂ܂��܂��c�_���c���Ă���B���t �@�@�@�@���O�������������A�������O������w�肷���ł̌��ݓI�ȑԓx��{�����߂ɁA�������ӌ����� �@�@�@�@�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B (d)�R�����g �@�E���݁A�T�P�P�ʎ��ԂŁA���ȂƂ��Ă͈����Ă��Ȃ��O���ꊈ���ł͂��邪�A���{�̉p�ꋳ��̗��j�A �@�@�w�Z�̌���A�����A���t�A�ی�҂̊���A�p�ꋳ��̗��_�A�ߗ����̉p�ꋳ��̌���ȂǁA�l�X�ȋc �@�@�_���o�Č����̂��̂ƂȂ����A�d�݂̂���J���L�������ł���B �@�E�w�K�w��������ł́A�u�������Ɓv�u�ǂނ��Ɓv�͌����Ƃ��Ĉ���Ȃ��Ƃ���Ă���B�w���҂Ƃ��āA�� �@�@�w�Z�̒P�Ȃ�O�|���łȂ��ɂ��Ă��A�u�������Ɓv�u�ǂނ��Ɓv�����炩�̌`�Ŏ�����Ă��悢�̂ł� �@�@�Ȃ����Ƃ����l�����������B�O���ꊈ�������{�����O�ɁA���łɂ��̋c�_���Ȃ���Ă������Ƃ�m��A �@�@����̊O���ꊈ���̓W�J���C�ɂȂ�Ƃ���ł���B �@�@�E���U�ɂ킽���ĉp��ɐe���݁A�����̂������ʂŊ��p���Ă������߂ɂ́A�w�K�̏����Ɂu�p�ꂪ�����v�ȏɂ��Ă��܂����Ƃ��ł������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł���B����̋��t�Ƃ��Ă���������ԋC������ł���A���w�Z�A�����w�Z�ւƂȂ��Ă��ɂ�����ӔC��������Ƃ���ł���B�M�҂��q�ׂ�A�u�w�K�҂̂��߂ɂȂ錵�����ԓx�A�w�K���e�v�Ƃ������̂�����ɋ�̓I�ɒ��ׂĂ��������B �S���FA.S. �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Step 3 ���T�[�`�v�����������ɍ쐬���邩 (2) �����ۑ� �E�����ۑ� (research questions)�c�������@�A���Ɏ����̃f�U�C������W�f�[�^��O���ɒu���A��̓I�ɋL�q���A������́B �E���������c�����ۑ�̈��ɑ��āA�����̔w�i�ŋL�q�������e������̗\����t�^������́B ��1) �p���f�B�O�}�e�B�N�E�V���^�O�}�e�B�N��b�����N���� �@��b���f�e�X�g�̉ɂ����āA�V���^�O�}�e�B�N�Ȕ��f�ۑ�ƃp���f�B�O�}�e�B�N�Ȕ��f�ۑ�ł́A�ǂ���̂ق����듚��(number of error responses)���������B �A��b���f�e�X�g�ł̉��Ԃɂ����āA���f�ۑ�̂ǂ���̂ق��������̏ꍇ�̔�������(reaction time)���Z�����B �������ۑ�́A5w1h�`�ł͂Ȃ��Ayes/no�ɊҌ��ł��鏑�����̕����ǂ��B ��2)���ǂ��p�P��̋����I�w�K�ɗ^������� �@�p�������ǂ���g���[�j���O�ƁA�ٓǂ���g���[�j���O�ł́A�ǂ���̂ق����p�����̐V�o�P��̒蒅�����������B �A�ĔF�^�̒P��e�X�g�����{�����ꍇ�A���ǂƖٓǂ̃g���[�j���O�ł͂ǂ���̂ق����V�o�P��̒蒅�����������B �B�Đ��^�̒P��e�X�g�����{�����ꍇ�A���ǂƖٓǂ̃g���[�j���O�ł͂ǂ���̂ق����V�o�P��̒蒅�����������B (2) ���� �����c���ɐݒ肵�������ۑ�ɑ�������J�n���_�ł̗\����^������́B�������A��s�����̃��r���[���ʂ��玩�R�ɓ����Ȃ����́A�S���L�q���Ă��Ȃ�����ȗ\���́~�B ��1) �@��b���f�e�X�g�̐��тɂ����ẮA�V���^�O�}�e�B�N�Ȕ��f�ۑ�̂ق����A�p���f�B�O�}�e�B�N�Ȕ��f�ۑ�����듚�������Ȃ��B �A��b���f�e�X�g�ւ̉��Ԃɂ����ẮA�V���^�O�}�e�B�N�Ȕ��f�ۑ�̂ق����A�p���f�B�O�}�e�B�N�Ȕ��f�ۑ���������̏ꍇ�̔������Ԃ��Z���B �����x�[�X(paper-based)�Ŏ��{���ꂽ��s���� (Shimamoto, 2005)��� ��2) �@�S�̂Ƃ��ẮA���ǂ̕����ٓǂ����A�����I�Ȍ�b�K���������₷���B �A�Đ��^�̕��ł́A���ǂ̕����ٓǂ����蒅�����������A�ĔF�^�̃e�X�g�ł͗��g���[�j���O�Ԃ̒蒅���̍��͌����Ȃ��B �� �������� (��c, 2006: ��c, 2007)��蓱�����B 3.4 �������@�͂ǂ�����? (1) �팱��(�Q����) �ߔN�́A�Q����
[participants]�Ƃ������������蒅���Ă���B ���K�v�ȏ�� �@�ǂ̂悤�Ȕ팱�҂� �A�Q���l���͉��l�� �B���̃��x��(TOEIC�̃X�R�A�Ȃ�) �C�j���̓��� �D�C�O���w�̗L�� �E�N��\�� (2) �����ޗ� �����ɂ����Ĕ팱�҂ɒ��錾��h���̂��ƁB ��)�p���f�B�O�}�e�B�N�E�V���^�O�}�e�B�N��b�����N���� �E�^�[�Q�b�g�� (target words)30��A��s�h���Ƃ��ăv���C���� (prime words) �Q��� �@�^�[�Q�b�g��ƃp���f�B�O�}�e�B�N�ȊW�ɂ��邩�Ȃ����̔��f���邽�߂̃v���C���� �A�^�[�Q�b�g��ƃV���^�O�}�e�B�N�ȊW�ɂ��邩�Ȃ����̔��f���邽�߂̃v���C���� (3) �����f�U�C���Ǝ葱�� �E�]���ϐ��ƓƗ��ϐ����L�q���Ă��镔���������f�U�C�� ���]���ϐ� ����1�F�p���f�B�O�}�e�B�N�E�V���^�O�}�e�B�N�Ȍ�b���f�̐��� (�듚��) ����2�F��b���f�̔������� (�~���b�Fmsec.) ���Ɨ��ϐ� ���f�ۑ�̎�� ���P�v���i�Q�����j�̔팱�ғ��iwithin-subject�j�����v�� ���ׂĂ̔팱�҂������̐f�f���s���Ƃ����悤�Ȏ����������Œ肷��ƁA�w�K�� �� (learning effect)�Ƃ����銵��̌��ۂ������邽�߁A����������������� �ւ���Ƃ������삪�K�v�B (4) �f�[�^�̕��͕��@ (data analysis) �����Ŏ��W�����f�[�^�ɑ��A�ǂ̂悤�ɏW�v���A���v������s�����Ƃ������ʂ����q�ׂ镔���B ��) ���ϒl���o���A�L�q���v���Z�o����B ���ϒl�̍����L�ӂł��邩���肵�A�Ή������t-��������{����B (5) �����\�� (schedule) ���̌�̗\����܂��ɋL���A�����܂łɎ��{���邩���l���Ă����B �@�����ޗ��̏��� �A�팱�� (�Q����)�̊m�� �B�f�[�^�̎��W �C�f�[�^�̏W�v�E���v���� �D�w��\�̗\�� �E�_�����M�̗\�� (6) �Q�l�����ꗗ (references) �c�����̔w�i�̉ӏ��Ŏ��グ�������ŁA��ɓ���E�T�����A���r���[�_���A���،����_���Ȃǂ��ΏۂɂȂ�B�C���^�[�l�b�g�ŏ��̌����E���W�������ہAweb�T�C�g�̃A�h���X���f�ځB ��APA (American Psychological Association)���s�̃X�^�C���}�j���A�� (APA manual)�ɏ]���̂���ʓI�B ���T�[�`�v�����{���ɋL�q�o���Ȃ����������h���Ȃǂ�����ꍇ�A�t�^ (appendix)���g���ďڍׂɋL�q����Ɨǂ��B ���R�����g �����ۑ�̏������ɂ��āA���̖{�ł�yes, no�ɊҌ��ł���悤�ȏ�������E�߂�Ƃ������B�������A���ۂɎ�u�ґS�������ꂼ�꒲�ׂĂ݂�ƁAyes,
no�ɂ͊Ҍ��ł��Ȃ��悤�ȏ����������Ă���_���⌤�������X����B���������Œ��ׂ����̂��ɂ���ď������͕ς���Ă���̂œ��R���Ǝv�����A�_����ǂޓǎ҂̎��_�ɗ��ĂAyes, no�œ�������悤�Ȍ����ۑ�̂ق����A�[�I�ɂ킩��₷���Ƃ����悤�ȗ��_������Ǝv����B �Q���҂ɂ��ẮAparticipants�Ə������Asubjects�Ə������ŁA������_���⌤���ɂ���ĈقȂ��Ă������Ƃ��킩�����B�܂��AAPA 6th Edition�ł��eparticipants�f�Ƃ��ċK�肵�Ă���(APA 6th Edition, pp.17-18)�B�C�m�_���ȂǁA�����Ř_�������M����ۂ́Aparticipants�œ��ꂵ���ق����ǂ����낤�B �������Ă�A�_�����M�̍ہA�f�[�^�͂��邱�Ƃ͂������d�v�����A��L�ŏq�ׂ��悤�Ȍ����̒��ƂȂ��Ă��镔������������ƍ\�z���邱�Ƃ��d�v���Ǝv���B 5��21�� �S���FR.F. Step 4 �S������w�ISLA�����f�[�^�ɂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂����邩�@(pp.65-81) 4.1 �������f�[�^ n �������͐������A�܂��͌듚��(���_�|������)�̃f�[�^�ɂ��邱�Ƃ��ł���B�p�����g���b�N�ȓ��v������{���\�B u �u�p�����g���b�N����v�F���v�w�ŗp�����錟��̂����A�ΏۂȂ��W�c�̕��z�ɂ��āA�p�����[�^�[��݂��čs���錟��B��W�c�������z���Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ���Bex) t����A���U���́A�s�A�\���̑��W���Ȃ� (1) �N���[�Y�e�X�g�f�[�^(closed test data)/ �N���[�Y�@ n �p������@�B�I��n�Ԗږ��ɒP����폜���Ă����A�e�u�����N�𐄑�������A��[�e�X�g�B n ��c(1985) �E�N���[�Y�e�X�g�̍ۂɁA���[�f�B���O�ɂ�����f�B�R�[�X���x���̏��(�p���S�̂̈Ӗ����e)�̕K�v�������Bsequential cloze(�ʏ�̃N���[�Y�e�X�g)��scrambled cloze(�t���p���P�ʂł��ɂ��A�A�g�����_���ɕ��ׂ��e�X�g)���r�B(p66,67�̗�Q��) �E�̓_�@�F����@(���e�L�X�g���̒P��Ɠ���łȂ���Ȃ�Ȃ�) �K��@�i��������Ӗ��E���@�I�ɉ\�ȉł���ΐ����j �E���v�I����F�Ɨ��ϐ�=�N���[�Y�e�X�g�̎�ށE�̓_�@ �@�@�@�@�@�@�@2�v��(2 sequential cloze/scrambled cloze�E2 ����@/�K��@)�̕��U���� �@a(1)�@����@�ō̓_����ƁAsequential cloze��scrambled cloze�Ԃ̕��ϒl�͗L�Ӎ����Ȃ� �@�@(2)�@�K��@�ō̓_����ƁAsequential cloze�̂ق����Ascrambled cloze�����L�ӂɐ����������� n ��c(1990) �E�_�����ƕ��ꕶ�Ŕ�r����ƁA����@�E�K��@�̍̓_�@��sequential cloze��scrambled cloze���������B�N���[�Y�e�X�g�̃e�L�X�g�^�C�v���A�_�����E���ꂩ�Ƃ����u�`���X�L�[�}�v���e������Ƃ����l�@�B �E�_�����ł́A�ǂݎ�́A���e�ɂ��Ă̒m��(�u���e�X�L�[�}�v)�̗L�����e������B (2) �L����f�[�^ (memory span data) n �L����f�[�^�F�Z���L���A���[�L���O�������͈̔͂𑪒肵���f�[�^ �E����^�p�̍ہA�������m�o�E�������A�L������v���Z�X�����s���Ă���B�����E�ێ�����e�ʂł��郏�[�L���O�������ɂ͌l��������B ���[�L���O�������̌l���𑪒肷����@�Ƃ��A���[�f�B���O�X�p���e�X�g�A���X�j���O�X�p���e�X�g������B n ��c(1994) �E�p�������Ɠlj��̕ێ��E�Đ����r �p���i�v26���E�Œ���30���߁j�����o�ƒ��o���A�p���M�L(�p�����̂���)�ƈӖ��M�L(�a��)�̕M�L�Đ��������B �������M�L�Đ����ꂽ�Œ��̃Z���e���X���̉��ߐ����Z�o�������ʁA���o�����o���p���M�L�E�Ӗ��M�L�Ƃ��ɏ������B a���{�l�p��w�K�҂̓��X�j���O�������[�f�B���O�̂ق����A�L���E�Đ������ӁB 4.2�@�v���g�R���f�[�^ �v���g�R���e�[�^�́A�p�����g���b�N�ȓ��v�ł͂Ȃ��A���I�f�[�^�̈�B (1) ���b�v���g�R��(think aloud protocols) n �u���b�v���g�R���v�Ƃ́A�S���w�̓��ϖ@�����ƂɁA�F�m�V�X�e���𐔗ʉ����Ȃ���i�Ŋώ@���鎎�݂Ƃ��āA�팱�҂ɒ��ژb��������@ n �Q���҂����g�̔F�m�v���Z�X����ς��A��������B��������ӎ��I�ȑ��삪�K�v�ȉۑ肪�K���Ă��āA�ӎ����������I�ɐ��s�ł���ۑ�͓K���Ȃ��B n Yoshida(1997) �Erational cloze(�쐬�҂̊�����ƂɃe�X�g�����) �e�X�g�ɉ���ۂ̃X�g���e�W�[(����)�ɂ��Ĕ��b�v���g�R���@��p���Č��B(p.74,75�Q��) �E���b�v���g�R���f�[�^����A���ǁA���@�m���A�����A���ȃ��j�^�[�ȂǗl�X�ȃX�g���e�W�[�𗘗p�������Ƃ����������B �E���b�v���g�R���f�[�^�͎��g�̔F�m�ߒ����O�҂Ƀ��j�^�[���Ă��炤�g���[�j���O�Ƃ��Ă��L���B (2) �M�L�v���g�R�� n �u�M�L�v���g�R���v�Ƃ́A���[�f�B���O(���X�j���O)�̌��ꗝ����ʓI�ɑ��肷���i�ŁA���[�f�B���O��A�����E�L�����Ă�����e���ł��邾���M�L�E�Đ����Ă��炤�^�X�N�B�ʏ�͕��ōs���B u �����ƕێ��̃g���[�h�I�t�F���[�L���O�������ɂ͗e�ʐ���������A���̐������ŏ����������u�����v�Ɓu�ێ��v�Ɋ��蓖�ĂȂ���Ȃ�Ȃ����߁A�u�����v�Ɓu�ێ��v�̓g���[�h�I�t�̊W�ɂ���B a�����M�L�Đ��ł��邱�Ƃ͏�������̉~�����������A�lj�͂������w�W�ƂȂ�B �M�L�Đ� n ���{�@�F��莞�Ԃɉp���p�b�Z�[�W��ǂ݁A���̌�\���Ȏ��Ԃ̒��ʼnp���̓��e����{��Ŋo���Ă��邾���M�L���� n ���ӓ_�F1. �M�L���A�p���͎Q�Ƃ��Ȃ��@2. ���e�̗v��ł͂Ȃ����ߓ��e�ɂ��������Ƃ�]���ł����ׂĕM�L���� 3. ���̌`�ŕM�L���� n ���č̓_ �E���O�ɉp�����A����܂��͐߂ɂ��A�C�f�A���j�b�g�ɕ�������B(p.78, 79�Q��) �E�M�����ێ��̂��߂ɁA�Q���ȏ�̍̓_�҂��̓_���A�̓_�̑��ւ��Ƃ邱�Ƃ��K�v�B �E�����F�Ó��������� �@�ǂݎ肪�p����V���łǂ̂悤�ɕ\�ۂ��Ă��邩����ł���B �@�@�@�@�A�I����ł͏o��҂��Ӑ}�����ӏ��̗���x�݂̂�����ł��邪�A�M�L�v���g�R���ł͎҂̓ǂ݂̎��Ԃ�c���ł���B �@�@�@�@a�Ó��������� �E�Z���F�M�������Ⴂ�\�� �@ �҂̍Đ����ʂ݂̂�����ΏۂɂȂ�B �A �A�C�f�A���j�b�g�ւ̕��������܂��ł����A�q�ϓI�K�����`���ł��Ȃ��ꍇ������B �B �����̍̓_�ҊԂňقȂ錋�ʂɂȂ�\��������B �Q�l���� �����m�F, ��. (1999). �w�p�ꋳ��p�ꎫ�T�x.����:��C�ُ��X. �K��S�i (��). (2009).�w�p�ꃊ�[�f�B���O�̉Ȋw?�u�ǂ߂�����v�̓�������x.�����F������. �S���FY.Y. Step 5�@�������{�ƃf�[�^�W�v���ǂ̂悤�ɂ��čs�����@(pp.152-168) �S������w�I�Ȏ��ؓISLA�����ň����������ǂ̂悤�Ɏ��{���邩�A�܂������Ƀf�[�^���W���A�W�v���邩�̕��@�_����5�͂ŏq�ׂ��Ă���B 5.1�@�팱�҂������ɏW�߂邩 �����e�[�}�����܂�A�����̖ړI�E���@�����܂�A������@�܂Ō��܂������̒i�K�ŁA�팱��(subjects)�E�Q����(participants)���ǂ̂悤�ɒT�������A�W�߂邩��������K�v������B �E�f�[�^���W�̂��߁A���ł����Ƃ͒S�����Ă��邱�Ƃ����������B �����k�Ɏ������͎҂ɂȂ��Ă��炤���Ƃ��ł���B �������Ώۂ����i�p��j�̊w�K�E����̏ꍇ�A���ۂɋ��ڂ������Ă�����������e�[�}�ɂ��Ė��ӎ���ώ@�Ⴊ�{����B �������͎҂̕�W�ɂ� �E�f���𗘗p�����L�� �E�g�ѓd�b�̗��p �E�`���V ���𗘗p���A�ȉ��̓_�ɒ��ӂ��č��m����� 1.
�����҂������Ȃ闧��ŁA�ǂ̂悤�ȖړI�̎������ǂ��������@�ň˗����Ă���̂����m�ɂ��邱�ƁB���̍ہA��w�@�̌����Ȃɏ������Ă���Ƃ��ɂ́A�����Ȗ��A���������A�w�����������L�q���Ă����������悢�B 2.
���E�ǂ��łǂ̂悤�Ȍ`�Ŏ��{����̂��A�\�ȓ����E�ꏊ�E���@��������Ɠ`���A�������邱�ƁB 3.
�f�[�^���W���̈��S��̖�肪�S���Ȃ����ƁA�܂��������͎҂̏����Ȃ�(informed consent)�邱�ƁB�����̂��܂��܂ȃP�[�X��z�肷��ƁA�ł���Ώ���̃t�H�[��������A���������|�̏��������Ă��炤���Ƃ��]�܂����B���̎��A�������ʂ\����ۂɂ́A�l���͌��J���Ȃ����Ƃ��m�F���Ă����K�v������B (pp.
154-155�Ɏ���) �E�`���V�ɂ�QR�R�[�h������Ȃǂ��Ď����҂ɃR���^�N�g�����₷���悤�S�|����B �܂��A���U�̍ۂɂ͖��m�Ȏ�|���q�ׂ�K�v������B �E�����ɂ͎��ԓI�]�T������l��I�Ԃׂ��B �����x�݂ɋ�����2�C3�l�ŐH�����Ă���w���ɂ��˗����Ă��f����\�����Ⴂ�B �E��������A���̏�ł����ɃA�|�C���g���������ǂ��B �E���،����ł͎������͎҂��Œ��30�����x�K�v�B �E���Ƀp�����g���b�N����(e.g. t-����EANOVA)���g���ꍇ30�����ڈ��ɂȂ�B �E�����Q���҂��ǂ����Ă��W�܂�Ȃ��ꍇ�i�������͎҂�����E�R�X�g��������Ȃǁj�A�m���p�����g���b�N�@��p���邩�A���������Ă͂܂�ꍇ�݂̂��̂܂܃p�����g���b�N������s���B �m���p�����g���b�N����𗘗p����ꍇ �E���Ԋu���ۏ���Ȃ������ړx�f�[�^����W�c�̐��K��������ł��Ȃ��P�[�X�ɗ��p�B �������A���̃P�[�X�ł��p�����g���b�N����Ɠ��l�A��W�c����̃����_���ȕW�{�̒��o���O���ƂȂ�B �J�C��挟��AU-����A�X�s�A�}���̏��ʑ����Ȃǂ���\�� ���Ԋu�����ۏ����P�[�X�ȂǁA�p�����g���b�N���肪�g����ׂ��P�[�X�Ńm���p�����s���ƁA���v��̌�肪���������\��������̂Œ��ӂ��K�v�B �Q�l *�R�����S���t�\�X�~���m�t�����V���s���\�E�B���N����Ȃǂ̐��K�������p���ĕW�{�����K���z���邩�m�F�����Ƃ��K�v�ƂȂ�ꍇ������B **�����̐��K������́A�u�ϐ��͐��K���z�ɏ]���v�Ƃ����A���������ݒ肳���̂�p> .05�ɓ��Ă͂܂�ꍇ�A�A��������ۗ����A���K���z�ł��邱�Ƃ����肷��B �q�X�g�O�����ȂǁA���o�I�Ȋm�F���s���K�v������B �p�����g���b�N����𗘗p����ꍇ �Ԋu�ړx�f�[�^�̑O��i���K���̏����Ȃǁj�����炩�ɂȂ��Ă���A a)
����ג��o b)
��W�c�̕��z�����K���z���Ă��邱�� c)
��W�c�̕��U�������� �ꍇ�A�������͎҂̐l���������ł����Ă����p�\�ł���B �E�������͎҂̐���1�A2���Ƃ��������̏ꍇ�A���ጤ���i�P�[�X�X�^�f�B�j�Ƃ��Č������s���B 5.2�@�������{��̗��ӓ_ �E�������{�̍ۂ́A���߂̏�����S�|����iPC�̋N����\�t�g�̗����グ���j�B �E�������͎҂ɂ͉ۑ�ɏW�����Ă��炤���Ƃ��K�v�ȃP�[�X�A�����f�[�^�����W����ꍇ���Â��ȏꏊ���m������i�������c���j�E �E�A���P�[�g���̏ꍇ�͋i���X���ō\��Ȃ��B �E�������͎҂�2�l�����Ŏ������s���ꍇ�ɂ́A�ْ���^���Ȃ����߂ɁA���͋C�Â������K�v�B �EPC���g���Ď������s���ꍇ�́A�����������Ȃ����߂�PC��ʏ�Ő������s���A�T���v�����Ŏ����̗v�̂�����ł��炤���Ƃ��K�v�B �E�T�v���̐����̍ۂɂ́A�u�������͎҂̗���v�ɂȂ��Ē��J���Ȍ���PC��ʏ�ʼn������ׂ��ł���B �E�P�̐�����ʂɑ����̉���i���j���l�ߍ��݂����Ȃ��悤�A�t�H���g�T�C�Y��16pt�ȏ�ɂ���ׂ��ł���B ��P159�Ɏ������͎҂�1��1�̑Ζʌ`���Ŏ��������{�����ۂ̃T���v���w������CALL�����ň�Ď������s�����ۂ̎w�������Ꭶ����Ă���B �E�������͎җp�̎w�����̍쐬�́A�������͎҂̗����ɂȂ��āA�ǂ̂悤�ȏ����ǂ̂悤�ɓ`���邩���ӂ��B 5.3�@�f�[�^�W�v�̎��� �ESPSS�Ȃǂ̓��v�\�t�g�ɍŏ�����f�[�^����ꂸ�A�ŏ���excel�Ƀf�[�^���͂��邱�Ƃ𐄏��B �E����Ƀe�X�g�̖��ԍ��ȂǁA�c�s�Ɏ������͎Җ���ԍ������L������B �EExcel�ō쐬�����f�[�^��SPSS�Ȃǂɓǂݍ��܂��A�������瓝�v���s���B �uL2���L�V�R���ɂ�����V���^�O�}�e�B�N����уp���O�}�e�B�N�l�b�g���[�N�̌����v�ɂ�����f�[�^�������@�ɂ�����f�[�^�W�v�̎���(p. 161-167) �E�������Ɣ������Ԃ̃f�[�^�����W�B �ECALL�����ɂ����Ď��������{�B �E�������͎�1�l1�l�����ꂼ��̃y�[�X�Ŏw������ǂ݁A����ɂ��������ĒP��̃l�b�g���[�N�Ɋւ���e�X�g���s�����B �E�������͎҂��Ƃ�excel�e�L�X�g�t�@�C���������I����A�����I�ɕ\�������悤�ɐݒ肳��A�������͎҂̎����Ǝ��{�����ƂƂ��ɁAp. 163�̂悤�ȃf�[�^���\�������B �E���̎����ł̓e�X�g���ڈȊO�ɁA�����v�̂̐����𐳂������삵�����m�F���邽�߂ɁA������ʂ̃y�[�W��������鎞�Ԃ���msec.�ł��������ɂ��Ă��f�[�^�o�͂��Ă���B �E���K���̌��ʂ��ǂ��ł������������H�����������ɑg�ݍ��݁A����ɑ��Ẵt�B�[�h�o�b�N��^���Ă���B �E�t�B�[�h�o�b�N��^���邱�Ƃ́A�������͎҂̎����v�̂ւ̐����������𗠕t����_�ŏd�v�ł���B �Ep.165�A�}43�̂悤�ɋs���������ʂɑ}������邱�Ƃ��܂܂���B �E�I���W�i���f�[�^�t�@�C���ɂ͌����ɕs�v�ȃf�[�^�������܂����Ă���̂ŁA�s�v�ȃf�[�^�s�͍폜����B �E���̍ہAexcel��Ń\�[�g���s�����Ƃŗe�Ղɍs�����Ƃ��ł���B �E�s�v�ȏ��̍폜���ς�A�������͎҂��ƂɊe���ڂ̏W�v�ie.g. �듚���┽�����ԁj��S�������͎҂̃f�[�^�ɑ��čs���B�i�Q�Ɓ@p.167�j �E�������͎҂̖��O�i��������ID�j���c�̍s�ɁA�f�[�^�̎�ނ����̗�ɖ��L����B���̍ہA�����̏���1��ځA1�s�ڂɒ���悤�ɂ���B �E�������Ăł���excel�t�@�C����ۑ����ASPSS�֓ǂݍ��܂���ƁA1�s�ځA1��ڂ̍��ڂ����v����̂��߂̕ϐ��Ƃ��ĕ\�������悤�ɂȂ�B �⑫ �f�[�^���W�̍ۂɂ́A�M�����̖�肪������̂́A�C���^�[�l�b�g�����p�������@������B �Esurvey monkey�@(http://jp.surveymonkey.com/) �ȒP�Ȏ��⎆�������쐬�A���W����ɂ͗L�p�B�������A�팱�҂ɂ͌��ǂ��肢���邩�A�����̃z�[���y�[�W��u���O�Afacebook�Ȃǂ𗘗p���č��m����K�v�����邽�߁A�팱�҂��{���Ƀ^�[�Q�b�g�ɓ��Ă͂܂�̂��A�Ƃ�������肪����B �EAmazon mechanical turk�ihttps://www.mturk.com/mturk/welcome�j �@Amazon.com�̉^�c����T�C�g�B�K�v�ȏ���o�^������A�팱�҂Ɏ��⎆�ɓ����Ă��炤���Ƃ��ł���B���̏ꍇ�A�A�}�]���M�t�g�J�[�h���ӗ�Ƃ��Ĕ팱�҂ɔz�邱�Ƃ��ł���̂ŁA�팱�ҏW�߂ɂ͎g���₷���B �S���FH.W. STEP 6 �@�w��\���ǂ̂悤�ɂ��čs���� �� 6.1�@���ʂ��猋�_�E�l�@�������ɓ����� ��ʓI�ȃA�h�o�C�X�͓�����A�Q�l��Ƃ��Ė�c�́uL2���L�V�R���ɂ�����V���^�O�}�e�B�N����уp���f�B�O�}�e�B�N�l�b�g���[�N�̌���[1]�v�̌��ʂƌ�����������B �����F�@�듚���ɂ��āB�V���^�O�}�e�B�N���f�̂ق����p���f�B�O�}�e�B�N�Ȕ��f������������A���v�I�ɗL�ӂȍ��͂Ȃ��B�A�������Ԃɂ��āB�V���^�O�}�e�B�N�Ȕ��f�̓p���f�B�O�}�e�B�N�Ȕ��f�����������Ԃ��x���A���v�I�L�ӁB ���_�F�u���{�l�p��w�K�ҁi��w���j�ɂƂ��āA�P��̃R���P�[�V�����Ɋւ���m���́A��ƌꂪ�Ӗ��I�Ɏ��Ă��邩�Ƃ����p���f�B�O�}�e�B�N�Ȓm�������s�\���ł��̌������x���v �l�@�F�u�P��ƒP�ꂪ�ދ`��W�ɂ��邩�ۂ��́A���ꂼ��̌�̈Ӗ��i�a��j���킩��A�����悻�̔��f�͂ł��邪�A����̒P��ƒP�ꂪ�R���P�[�V�����̊W�ɂ��邩�ǂ����͒P��̈Ӗ��i��j���o���Ă��Ă���ɗ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����������A���ǁE�����Ȃǂ̕��@�ő�ʂ̌���C���v�b�g����������E��������̌���ʂ��āA�����������m���͐g�ɕt���̂ł͂Ȃ����B�v hw: ���ʁE���_�E�l�@�ɑΉ�����p��́A���ꂼ�� results/outcomes�Aconclusion�A analysis�H�H�H ���ʂ͎������̌��ʂŐ��ʂ�L���ȂǁA���_�͎������ʂ̉��߂�������RQ�ɑ��铚���H�H�H�A�l�@�͔��W�I�ȉ��߁H�H��L�́u����������v�ȉ��͎����Ƃ͖��W�B �� 6.2 ���\�w��E�������I�� ���낢��ȃ��x���̊w��⌤�������B���ۊw���č��≢�B���̊w��A�����̑S�����A�n����i�x�����j�A�w�����special Interest group �iSIG�j�ȂǁB �w��F�����\�̓��e�̂��̂���� ������F�w��̂悤�Ȑ����Ȃ��ŁA�݂��̕��̂��߂̏W�܂� hw: �ߋ��Ɍ�����Ŕ��\�������̂Ɠ���̌����i���Ƃ��Γ���̃^�C�g���j��ʂ̊w��Ŕ��\���邱�Ƃ͉\���H�H�H�@����w��Ŕ��\���������Ɠ���A�����A���邢�͗ގ����Ă��錤����ʂ̊w��Ŕ��\���邱�Ƃ͉\���H�H�H ���L�w��̏ڍׁi����\�����݁A���̊J�Î����Ȃǁj�͂��ꂼ��̃E�F�u�y�[�W���Q�Ƃ��邱�ƁB �i�P�j�O���ꋳ��W �������� �E�S���p�ꋳ��w��iThe Japan Society of English Language Education: JASELE�j �E��w�p�ꋳ��w��iJapan Association of College English Teachers; JACET�j �E�O���ꋳ�烁�f�B�A�w��iJapan Association for Language Education and Technology: LET�j �E�S����w����w��iThe Japan Association for Language Teaching: JALT�j �E���{�ꋳ��w��iThe Society for Teaching Japanese as a foreign language�j ���C�O�� �EAILA�iAssociation Internationale de
Linguistique Applique�j �ETESOL�iTeachers of English to the Speakers of
Other Languages�j �i�Q�j���K���W �������� �E����Ȋw��iJapan Society for Language Sciences: JSLS�j �E���{���K���w��iThe Japan Second Language Association: JSLA�j �E���Ƃ̉Ȋw��iJapan Society for Speech Sciences: JSSS�j ���C�O�� �EAAAL�iAmerican Association for Applied
Linguistics�j �ESLRF�iSecond Language Research Forum�j �EAMLaP�iArchitecture and Mechanism for Language Acquisition
and Processing�j �EIRA�iInternational Reading Association�j �i�R�j����w�E�����w�E�S���w�W�Ȃ� �E���{�p��w�� �E���{����w�� �E���{�����w�� �E���{�����w�� �E���ꏈ���w�� �E���{�S���w�� �E���{�F�m�S���w�� �E���{�F�m�Ȋw�� �E���{�����]�@�\��Q�w�� �� 6.3 ���\�v���|�[�U�������� �w��Ŕ��\����ɂ́A�܂����\�v���|�[�U���iproposal�j�������Ĕ��\�\�����݂�����B�����̊w��ł̓v���|�[�U���̐R��������B �Q�Ɨ�� pp.181-184 �Epaper submission�F�������\�Aposter
submission�F�|�X�^�[ �E���\���W����̈�igeneral
research area of presentation�j��Fb. cognitive
processes and effects, g. Linguistic
analyses �E���\�v��isummary�j �E���\�T�v�iabstract�j hw�F�ƐтƂ��Ă͌������\���|�X�^�[�@�H�H�H ���̌�A���or ���ۂ̘A�������B �\�����݂̎����ƕ��@�A���̎����Ɣ��\���@�A�w��ւ̓��e�̎����ƕ��@�Ȃǂ����O�Ƀ`�F�b�N���邱�ƁB �� 6.4�@�w��\�i�������\�j�̃m�E�n�E ��������┭�\�w��ɂ���Ă����\�̕��@�͈قȂ�B �����]�@�\��Q�w��Ȃǂł́A���\�҂̓X���C�h�Z�b�g��p�ӂ��āA���W�҂����삷��B�p�ĕ��w��p��w�̊w��ł͔��\�҂͔z�z�����i�n���h�A�E�g�j��z�z����B���K�������̊w��ł̓p���[�|�C���g�ipower point: PPT�j�Ɣz�z�������g���B �i�P�jPPT�̏��� �e�X���C�h�̃t�H���g�T�C�Y�͑傫���Ƃ�i�Œ�20 point�ȏ�j�B�P�̃X���C�h�ɉ��ł�����ł��l�ߍ��݂����Ȃ��悤���ʂɒ��ӂ���B�}�\�A�C���X�g�A�ʐ^�Ȃǂ̍H�v������B�s�v�ȃA�j���[�V��������ʉ��͂Ȃ��Ă悢�B �i�Q�j�z�z�����̍쐬 PPT�`���ň������ꍇ�́A�u����Ώہv�́u�X���C�h�v�̂܂܂Ńv�����^�́u�v���p�e�B�i�v�����^�ݒ�j�v�P�y�[�W�ɉ����������Ƃ������C�A�E�g��ݒ肷��Ɩ��ʂȗ]�����Ȃ������̍쐬���ł���B �i�R�j���\���e�̗L�� ��c�́A���O�̃��n�[�T���i���K�j�͏\���ɍs�����A�ǂݏグ�p�̌��e�͗p�ӂ��Ă��Ȃ��B�ǂݏグ�p�̌��e��p�ӂ���ƁA�Ђ����特�ǂɏW�����Ă��܂����Ƃ����肤�邽�߁B [1] syntagmatic links: ��b�̃l�b�g���[�N�ɂ����āA���̌�Ƃ��̌�͂�������Ɏg���邪�A����ʂ̌�Ƃ���ʂ̌�͂�������Ɏg���Ȃ��Ƃ��������̊W���w���B�R���P�[�V�����B �@paradigmatic inks: �ދ`��E���ӌ�E�֘A����ʁE���ʔ��e�Ȃǂ̊W���w���B |
|||||||||