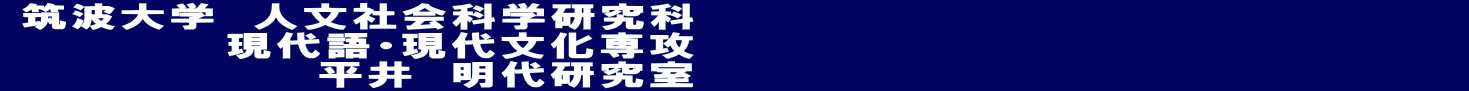
|
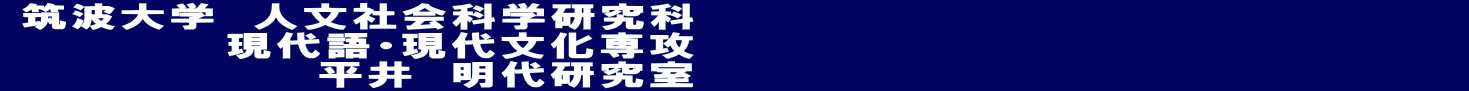
|
| 2017年度 異文化言語教育評価論 |
第5章 質的研究の進め方(p89-p109)
浦野他. (2016). 『はじめての英語教育研究 ? 押さえておきたいコツとポイント』 東京, 日本: 研究社.
1. どのようなときに質的研究を選択するのか
■質的研究の背景:現実世界の定義や理解の仕方は各人で異なっており、様々な解釈や視点が存在しうるという考えがある
→そのため、データ収集、分析、解釈の視点も様々
■質的研究を選択する5つの目的
・文脈を考慮しながら複雑な現象を深く捉える
・文脈を考慮しながら研究参加者の変容を捉える
・研究参加者の視点から経験の意味や認識を深く捉える
・先行研究での対象外の現象を文脈の中で明らかにする
・量的・質的データを組み合わせ研究の信憑性を高める
1.1文脈を考慮しながら複雑な現象を深く捉える
■目的:自然な環境においてデータを収集し分析する事で、出来るだけ細部を切り落すことなく複雑な現象を捉える
■研究事例1(p.90-p.91.参照)
→学習者の外的要因や内的要因を切り離すことなく描写し、学習スタイルやストラテジーと学習者の外的・内的要因との複雑な関係性を捉えている(l.7-l.12)
1.2文脈を考慮しながら研究参加者の変容を捉える
■目的:一定期間データを収集し、その期間にどのように研究参加者が変容していったのかを捉える
■研究事例2(p.91.参照)
→自然な環境において、個人を取り巻く文脈を切り落すことなく、変容の過程を捉えている(l.3-l.10)
1.3研究参加者の視点から経験の意味や認識を深く捉える
■目的:既存の理論や研究者が前もって規定した枠に囚われることなく、研究参加者の視点からその経験の意味や認識を深く捉える
■研究事例3(p.92.参照)
→インタビュー(質的データ)を収集し分析する事で、研究参加者の言葉に基づいて、経験の意味や認識を深く捉える(l.4-l.9)
1.4先行研究での対象外の現象を文脈の中で明らかにする
■目的:先行研究では明らかにされていない現象を、文脈の中で明らかにする
■研究事例4 (p.92-p.93.参照)
→質問用紙や実験結果に基づく先行研究では明確でなかった現象を明らかにしている(l.4-l.9)
1.5量的・質的データを組み合わせ研究の信憑性を高める
■目的:量的、質的データを組み合わせ、それぞれの利点を生かしつつ、データと研究者の解釈の間に齟齬がないように研究の信憑性(credibility)を高める
■研究事例5 (p.93-p.94.参照)
→量的データを主とし、質的データを補完的に用いている。結果として、データの解釈の信憑性を高めると同時に、調査項目が決められている質問紙調査では明らかに出来なかった新しい側面を見つけている(l.5-l.14)
■混合研究法における質的データの扱い
・量的データを主とし、質的データを補完的役割で用いる場合
→質的データの結果は量的データの解釈を強化する
・量的、質的データを同じくらいの重要度で用いる場合
→量的データと質的データの結果を統合して結果の解釈をする
2.どのように研究参加者を選択するのか
■合目的的抽出:研究目的に合わせて研究参加者の選択を行う(punch,2009)
→これは全ての質的研究に共通している
■研究事例6(p.94.参照)
→目的にしている研究参加者だけではなく、他の立場の研究参加者も対象にすることで様々な視点から分析することが出来ている(l.3-l.8)
■研究事例7(p.95.参照)
→研究参加者を最初から定めずに、質問紙でデータ収集を行い、分析を行った後、その結果に基づき新たなデータを収集するために、研究参加者を選択している(l.4-l.9)
■便宜的抽出:研究者がアクセスできる範囲内の研究参加者を選択する事
3.アプローチ、データ収集法、データ分析法の違いは何か
■アプローチ:事例研究、ナラティブ研究、エスノグラフィー、GATなど
→質的研究を遂行する際の考え方
■データ収集法:観察、質問紙、インタビュー
■データ分析法:会話分析、談話分析、テーマ分析(質的内容分析)
⇒上記3つ(アプローチ、データ収集法、データ分析法)のレベルを区別し、各々をきちんと記述していく事で、研究の位置づけが明確となる
4.どのようなアプローチがあるのか
■英語教育でよく用いられる5つのアプローチ 表5.1参照(p.97)
・事例研究
・ナラティブ研究
・エスノグラフィー
・GAT
・質的記述的研究
4.1事例研究
■目的:現実世界において一定の文脈に基づいて限定された研究対象(事例)を深く理解する事 (p.98 図5.2.参照)
■英語教育における具体的事例
→個人の学習者、教師、授業、プログラムの複数の学習者
■TESOL
Quarterlyの質的研究のガイドライン(Chapelle&Duff,2003)
(1)研究の前提とされている考え方
→データの解釈の仕方には複数の見方があり、研究者、事例(研究参加者)、その他の人々の視点を認識し、解釈的で帰納的な研究の形として経験の詳細や意味の記述を探求する
(2)データ収集法(p.99 研究事例8 参照)
→一般的に、インタビューや観察(自然な環境で得られるもの)など複数のデータ収集法を用いてデータを集める
(3)データ分析法
〇テーマを見出す
→音声や動画記録などのデータ(一次データ)収集後に、テキスト化されたデータ(二次データ)にコーディングをして、重要な点や構造を明らかにする
〇テーマ内の項目の種類を数量化したり、マトリックスや表を使ったりして集約する
4.2ナラティブ研究
■ナラティブ:人々の経験を反映した語りの事
→ナラティブには、語るという行為と語られた結果としての物語という2つの意味合いが含まれている(フリック,2001)
■意義:個人の経験を生き生きと描写し、研究参加者の経験の意味を研究参加者自身の視点から捉える
■データの種類:インタビューなどで得られる話し言葉のナラティブと、学習雑誌などで得られる書き言葉のナラティブ
■研究事例9(p.101 表5.3.参照)
→ナラティブフレームを用いて書き言葉によるナラティブのデータ収集を行っている(l.3-l.8)
■ナラティブ探求の前提
ナラティブには語り手としての研究参加者、物語が起こった時、物語が位置する物理的環境または場所の3つの要素があり、それらが文脈を構成して、その文脈が意味を理解する手助けとなる(Barkhuizen,2008)
■データ分析
〇データの中にある要素から一貫性のある新しい記述を見出す
→ナラティブ分析に標準化された手順はないため
4.3エスノグラフィー
■意義:ある状況を共有する特定の集団の人々の文化を理解する
■データ収集法:観察(フィーノルド・ノーツ、ビデオ、写真など記録されたもの)やインタビュー
→また、学習者の振り返りの記録、授業で使われたハンドアウトなど様々なデータ収集法が用いられ、異なる方法で収集したデータを組み合わせるのが一般的
■データ分析法
○テーマを見出す(p.104.研究事例10.
l.11-l.16)
○談話分析により発話の特徴を見出す
■留意点
○どの学問分野の枠組みに依拠しているか明確にする
○多様な分析法がある
4.4GAT
■意義:研究参加者のプロセスや状況を理解する
■データ収集法:インタビューや観察
■研究事例11(p.106)
→2年間に渡り、データ収集と分析のサイクルを4回繰り返し、その結果明らかになったコアカテゴリーを作成している(p.106.研究事例11 参照)
■データ分析法
→新しい概念が見出されなくなるまで、データ収集と分析を継続的かつ循環的に行う
⇒したがって、多くの研究参加者が必要とされる
■留意点
○哲学的前提の異なる6種類の版がある(木下,2014)
○英語教育では分析法として用いられることが多い
→分析の技法だけにとらわれた場合、GATと質的分析法との区別が不明確となり、分析も不安定になると木下は指摘している
4.5質的記述的研究
■意義:出来事を日常の言葉で記述して、その出来事について、研究参加者が捉えた意味を正確に説明する(Sandelowski,2000)
→研究者の介入や要因の統制などは行わず、現象の率直な記述が求められる場合に適している
■データ収集法:質問紙、インタビュー、観察
■データ分析法:テーマ分析(質的内容分析)
■研究事例12(p.108)
→振り返り日記を書く事の利点(l.4-l.7)と課題(l.7-l.10)のそれぞれをテーマ毎に整理し、教員の実際の発言の例を示しながら記述されている
■留意点
〇データから離れすぎたり、入り込んだりしない
〇データの概念的解釈や高度に抽象的な解釈を必要としない
〇具体的な研究のプロセスを書く