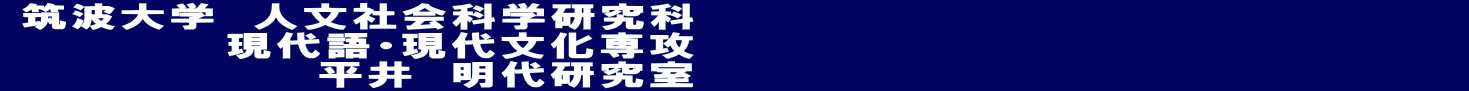
|
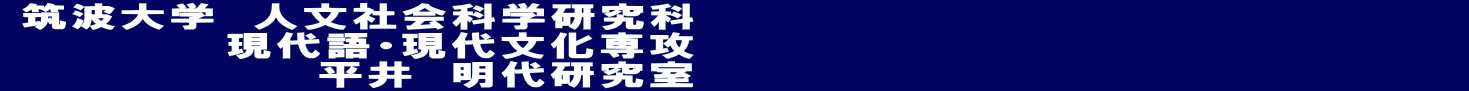
|
| 2017年度 異文化言語教育評価論 |
第 2 章 研究テーマの決め方(pp.15‐31)
浦野研他(2016).『はじめての英語教育研究―押さえておきたいコツとポイント』.研究社.
1 研究を行う目的は何か
◎研究のプロセス(p.16 図 2.1 参照) ・興味・関心のあるテーマについて幅広く読む、聞く →そのテーマを理解するための概念的枠組みとしての知識を増やす(第 3 章を参照) ・知識を増やすだけでは研究は形にならない→先行研究に基づいて研究課題を絞り込む ・研究課題に対して適切なデータを計画的に収集、分析する(第 4 章以降を参照) ◎本章:研究のプロセスのスタート地点である研究テーマについて考える
1.1 研究を行う目的 ◎研究を行う目的とその整理 ・研究の目的=何を問題にして、何を明らかにしようとしているのか ◎基本的な目的の整理(川﨑, 2010, pp.15-17) (1)概念の整理・検討:それまでの研究で用いられてきた概念、理論、方法論などを議論の対象とし、 その意味や問題点を明らかにする (2)新事実の提示:発見された史料、資料を通じて新しい事実を報告する (3)仮説の検証:あらかじめ設定した理論的な予測や仮説が特定のデータによって支持されるかどうか示す (4)事象の理解・仮説の生成:研究対象の観察・記述を通じてそれまでになかった理解や仮説を導き出す ・cf.第 1 章表 1.1(p.8)研究の種類:文献研究と実証研究
1.2 研究に関する知識 (1)信念としての知識:主張する人が真実であると思っているだけで実証的に検証されていないもの (2)権威としての知識:著名な研究者が言っているからという理由で真実とみなされるもの→検証すべき仮説 (3)先験的知識:経験によらず、論理的な推論や先行研究の知見から得られるもの (4)実証的知識:現象の観察、調査、実験の結果から結論を引き出すことで得られるもの ・cf.第 1 章第 2 節 社会的な営みとしての研究 ・研究では、先験的知識の蓄積をどう踏まえ、どういう研究課題を立て、どのように実証的知識を得るかが重要
2
2 どのように研究テーマを決めるのか
2.1 自分の興味がどこにあるか探る ①学習、指導経験や専門的に学んでいることから、もっと詳しく知りたいこと、解決してみたい問題を挙げる →自身の経験を他の人に話す、他の人の意見を聞いて自分の考えとの異同を整理する ②自分の興味に関係のある書籍や雑誌を、理論研究と実証研究に分けて集める →授業や研究会、学会で得られる資料・論集も活用 ③分野全体や特定のトピックについてのハンドブック=「手引き」 →他の分野(教育学、心理学、社会学、言語学など)の文献・発表にもいろいろ当たって関心を広げる
2.2 研究テーマ選択の決定要素について考える ◎研究テーマを選択する際の 3 つの要素 ・「やりたいこと」:研究する人自身の興味・関心 ・「やるべきこと」:その時代の教育実践あるいは理論構築において、今求められているテーマ ・「やれること」:あいまいではなく具体的に研究を進めることができそうなテーマ →この 3 要素が重なり合うテーマを見つけるべし!(p.21 図 2.2 参照)
2.3 理想・現状・課題を押さえる ◎何から手をつければよいか?研究の方向性を見失った時には? →「現状→課題→解決策」の 3 段論法(p.22 図 2.3) ①その研究の「理想」状態をイメージする一方で、「現状」を知る ②理想と現状とのギャップ=解決すべき「課題」 ③その課題の何に着目するか、なぜそこに着目するのかを考え、説明できるように研究テーマを深める
2.4 研究対象となる構成要素を押さえる ◎研究テーマを絞れない、深められない場合は?→自分の研究対象の構成要素について考える (例)テーマ「中学校での英語のコミュニケーション活動」 ①活動のタイプを考える:ドリル、エクササイズ、コミュニケーション活動、タスク ・「生徒が活動で英語を話せない」という課題における「活動」とは? ②中学校という対象は、どのようにコミュニケーション活動に影響を与えているか ・教材、教具、教師、教科書、クラスサイズ、授業時間、人間関係など ・生徒の習熟度によって、言語材料や題材、認知処理過程は異なる
3
3 よい研究テーマを考える視点は何か
◎研究テーマ=対象とする領域、取り上げる現象、それに対するアプローチと研究のデザイン ◎よい研究テーマとは?(伊丹, 2001, p.107) ・たんに論文が仕上がるためというよりは、考え続けるべきテーマ ・10 年やれるくらいの大きな視野あるいは深さのあるテーマ
3.1 研究のタイトルから考える ◎自分の研究テーマがよいものであるか?→研究のタイトルを見る (例)「高等学校での英語の物語創作タスクの活用」(p.25 図 2.4 参照) ・教師、学習者両方にとって重要課題であり、3 要素(2.2 参照)を満たすテーマ ・物語創作タスクがライティング能力の向上に効果があると示し、論文として完成 →それだけでは「よい研究テーマ」とはみなされない ◎個別研究により追究したかったこと (a)高等学校段階の学習者の英語ライティング能力の成長過程 (b)高等学校の英語教育カリキュラムに組み込むための諸条件 ◎研究テーマはタイトルに端的に示される ・「高校生の英語ライティング能力の成長過程:物語創作タスクの活用を通じて」→明確で「よい研究テーマ」 ・研究のアプローチと研究のデザイン(第 4 章以降を参照)をタイトルに端的に示す→完成度の高い研究 ◎広い(一般的な)視点 (a):「第二言語学習者のライティング能力(産出能力)の発達」 (b):「外国語環境の学校での英語教育のカリキュラム編成原理・方法」
3.2 先行研究から研究テーマを考える ◎研究テーマに基づいて行う先行研究の検討 (1)選定したテーマが、英語教育研究ではどのような切り口で扱われているのかを把握する (2)これまでの研究で何が調査されてきたか、これまでに何が判明しているのか、何がわかっていないのかを検討する (3)これまでの研究の問題点(理論的欠陥、方法論的問題など)を検討する ・まだ判明していないことを発見→それを調査することが研究課題 ・先行研究に問題が見つかる→それを修正することが研究目的 ◎序論の役割(Bitchener, 2010, pp.34-35) (1)関心のある問題、論点、疑問を提示する (2)問題の背景や文脈を提示し、先行研究から得られる考えを概観する (3)既存の知識において不明である点を提示する (4)どのようにその不明な点を明らかにするかを説明する (5)どのように調査を進めていくかを概観する (6)本研究がどのように当該分野に貢献するかを説明する (7)本論の内容と構成を概観する
4
◎(1)から(7)をしっかり述べる理想的なルート (a)「最短」で研究テーマを絞り込む(例:Urano, 2005) ・多くの説明を重ねなくても(1)から(6)がしっかり述べられていれば、論文はわかりやすくなる (b)研究テーマが「全体図」の中でどういう意味を持っているかを示す(例:Shintani, Li, & Ellis, 2013) ・その分野の知見の俯瞰的整理→研究テーマと「全体図」 ・系統的レビュー→そのテーマの重要性を明確にする
4 研究テーマを決めるコツは何か
◎テーマを決めること迷ったときは?→助言を与えてくれる先輩や指導教員がいるのが望ましい ◎いないときには? ・研究の蓄積が多いテーマを選ぶのがよい(伊丹,2001; 川﨑,2010) →研究の「型」や方法論が学べる、先行研究で集められたデータや事実を利用できる ・先行研究の限界や抱える問題を正確に把握するアプローチ (a)批判的レビュー・アプローチ:演繹主義的 (1)文献で重要だとみなされているが、誰も体系的な検証をしていない仮説を選ぶ (2)文献で当然視されているが、信憑性がないと内心思っている仮説を選ぶ (3)文献に見られる論争に参加して、その解決に貢献する (4)文献で当然視されているが明示化されていない前提を明確にする、その前提の正しさを判定する (5)文献で見逃されてきた盲点を選び、検討する (6)別の分野から理論を借りてきて、自分の研究分野内の問題を解明していく
(b)事例中心アプローチ:帰納主義的 (7)現実と理論予測との間のギャップに注目し、異例を見つけ、それを緻密に分析する (8)検証したい仮説が支持される確率が最も高い事例を選び、本当に支持されるかどうか調べる (9)検証したい仮説が支持される確率が最も低い事例を選ぶ (10)事例と事例との間のギャップに注目し、なぜギャップが生じるか、先行研究で解答が示されているかを調べる