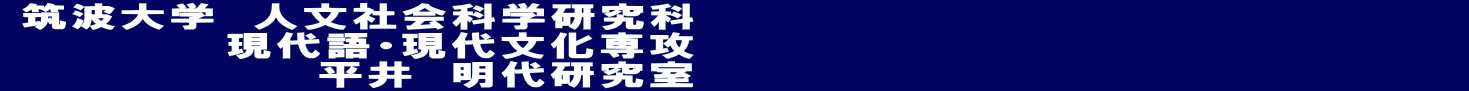
|
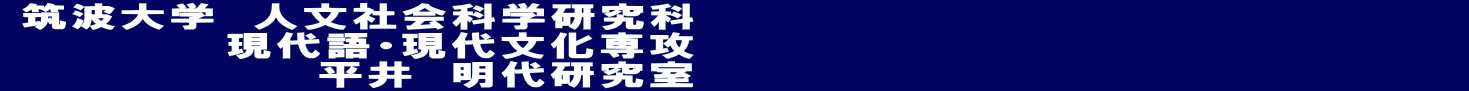
|
| 2017�N�x�@�@�ٕ������ꋳ��]���_ |
��1�́@�����Ƃ͉����H
�Y�쑼. (2016). �w�͂��߂Ẳp�ꋳ�猤�� ? �������Ă��������R�c�ƃ|�C���g�x
(pp. 1?13). ����, ���{: ������.
�����\�҂����ɏd�v�Ɗ������������{�[���h�̂ɂ��܂����B (���������C�����܂��c�c)
�P�@�����Ƃ͉����H
���{���̖ړI�F���� (research) �̐i�ߕ��ɂ��āA��ԑ�Ŋ�{�I�ȂƂ���𗝉����Ă��炤�B
�������Ƃ́A�ȉ���3�̗v�f���琬�藧�B1�ł������Ă���A�����Ƃ͌ĂׂȂ��B
(1) �����ۑ� (research questions: RQs)
(2) �f�[�^ (data)
(3) �f�[�^�̕��́E���� (analysis and interpretation)
�ȏ��3�̗v�f�́A���ꂼ���
(�����̕��@�_) ������A�݂�Ȃ��������@�_�ɑ����Č������s�����Ƃ����
�Q�@�Ȃ���������̂��H
2.1 �������s�����R���l����
���E�ƕʂ́u�������s�����R�v
�@��w�̋����F�Ɩ��̈�Ƃ��āi���i�R���̍ۂɌ����Ɛт��]�������j
�A��w(�@)���F�w�ʂ̎擾�v���������߁A������(����)�E�ւ̏A�E�̂���
�B�p�ꋳ�t�F�m�I�D��S�������� (��w�����A�@���ɂ����Ă͂܂�)�A���Ɖ��P�A���H��̖��̉����̂���
�@��F�u1�g��2�g�œ������������Ă���̂ɁA1�g�̒�������̐��т�2�g���F�����Ȃ��̂͂Ȃ��H���ׂ悤�I�v
2.1.1 ���H�Ƃ��Ă̌����Ɗw�p�I�Ȍ���
���u���H�Ƃ��Ă̌����v (practitioner research): �l�̊S����o�����A�l�ɊҌ�����錤�� (�B�̗�)
�E�����ҁF���H�҂Ɠ���l��
�E�ړI�F���t�������̐��k�����ɂ��ė�����[�߂���A���H��̖������������肷�邱��
���u�w�p�I�Ȍ����v ([scientific/academic] research):�@�l����Ȃ��A����S�̂̌���E���W�Ɋ�^���錤��
�E�ړI�F��葽���̋����ł��K�p�ł���悤�Ȓm���ݏo���A�p�ꋳ��(����)�S�̂����悭���邱��
2.1.2 ���H�Ƃ��Ă̌����Ɗw�p�I�Ȍ����̋��ʓ_�A����_
�����ʓ_
�E�����ۑ���i�荞��Őݒ肷��K�v������B
�E�f�[�^�̎����d�v (�����A�����ۑ�ƏƂ炵���킹�Ăł���������m�ɋL�q����ƍ����Ȃ�)
������_
�E�f�[�^�̕��́E���߁F���H�������҂̃N���X�̊w�K�җ���
�� �w�p�����̒��̊w�K�҂ɓ��Ă͂܂�X������ʉ�
���{���ł́A�w�p�I�Ȍ����̕��@�_�ɏd����u���ĉ������B
�@�@���H�Ƃ��Ă̌����ɂ��Ă͋g�c�� (2009) ���Q�l�ɁB
2.2 �w�p�I�Ȍ�����S�̂̔��W�E����ɖ𗧂Ă�
�������Ƃ́A�����ȒT���̐ςݏd���ł���A���̍v�����W��邱�Ƃŕ���̑S�̑������炩�ɂȂ��Ă����B
���w�p�I�Ȍ�����S�̂̔��W�E����ɖ𗧂Ă邽�߂ɂ́A�����̌����Ƃ���܂ł̌����Ƃ̂Ȃ���������ׂ��B
�@�������̌������p�ꋳ�猤���̒��́u�����ډ��Ԓn�v�ɏœ_�ĂĂ���̂�����邱�ƂŔF�m���Ă��炦��B
2.3 �����̌����Ƒ��̌����Ƃ̂Ȃ��������
���������s���ۂ̎菇
�@��܂��Ȍ����e�[�}�����߂��B
�A�e�[�}�Ɋւ��邱��܂ł̌��� (=��s����; previous studies) ���O��I�Ɍ������� (=����̒n�}���)�B
�B�����e�[�}�����œ_������A��̓I�������\�Ȍ����ۑ�ƂȂ��B
�������̌��������̌����ƊW�Â��Ȃ�����`�������Ƃ��A���̌����̈ʒu�Â��𗝉������|����ɂȂ�B
���p�ꋳ��(����)�ň�ʓI�Ɏg���Ă��錾�t�Ő������邱�ƂŁA���̕���̑����̐l�ɗ������₷���Ȃ�B
�@���p�ꋳ��̎��H�Ɨ��_ (theory) �����I�Ɍ��コ���邽�߂ɂ́A�I�m�Ȍ��t�Ŏ��H�Ɨ��_����邱�Ƃ��K�v
�R�@�ǂ̂悤�Ȏ�ނ̌���������̂�
3.1 �����̑�܂��ȕ��� (�\1.1�Q��, p. 008)
�������̎��
�E���������F�����̎�����o�����̋L�^�A���Y�e�[�}�̐�s���������W�E�������A��������ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����_�Â����邩������������A����̉ۑ�����������肷�錤���i��F���j�����A���ފJ�������j
�E���،����F��s�����Ŗ��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��ۑ�ɂ��āA�����Ҏ��炪�V���Ƀf�[�^�����W������A�����̃f�[�^�𗘗p�����肷�邱�Ƃɂ���ė��_�̐����E���ւƌ����������B���I�������ʓI�����ɕ�������B
3.2 ���،����̎��
(1) �T���^�̌���
����s�����̏���ł͖��m�ȕ��������\���ł����A�肳����Ńf�[�^�̎��W�ƕ��́E���߂����錤��
�E�ړI�F�ώ@�╷�����ȂǂŁA�ו��Ɏ���܂łł��邾���ڂ������J�Ƀf�[�^�����W���A���炩�̕����������o���B
(2) ���،^�̌���
����܂��Ȍ����e�[�}�����߂遨��s�����̎��W�ƕ��͂��s�����������ꂽ�����\�Ȍ����ۑ��ݒ肷�錤��
�E�ړI�F�u�`�Ƃ������_�Ɋ�Â��Ɓc�Ɨ\�z�����v�Ƃ������� (hypothesis) �𗧂āA���ꂪ�����������������B
4 �ǂ̂悤�ȃv���Z�X�Ō������s���悢�̂� (�\1.2�Q��, p. 012)
(1) �����e�[�}�����߂�F�����̋����E�S�̂��镪��������\�����l�̂��錤���e�[�}���i�荞�ށB
(2) ��s������T��F��s���������ƂɌ����c�����A��s�����Ɛ������̂��錤���ۑ���T��B
(3) �����ۑ���i��F�����ړI�m�ɂ��A�����ۑ�����肵�A���̉����̂��߂��K�ȃf�[�^�̃^�C�v��I�ԁB
(4) �f�[�^�����W����F�f�[�^�̓����𗝉����A�ǂ̂悤�ȃf�[�^�����W���Ċώ@�E�����E�������s�����f�U�C������B
(5) �f�[�^�͂���F���I�E�ʓI�A�v���[�`��p���āA�ώ@�E�����E�����Ŏ��W�����f�[�^���K�ȕ��@�ŕ�������B
(6) ���ʂ\����F�������ʂ��K��������₷���܂Ƃ��A�����̉��l�������B