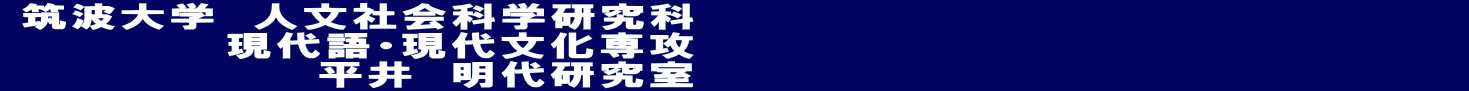
|
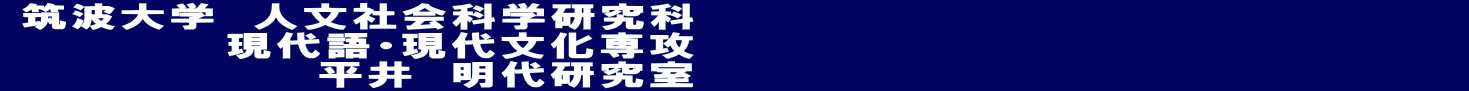
|
| 2017�N�x�@�@�ٕ������ꋳ��]���_ |
�T.�@�����̂܂Ƃ�
1.
Introduction
�E �����̎w���@���r���邽�߁A�ʂ̋��͎҂�ΏۂɎ������錤���ɂ����āA�����҂́u�w���@�v�i�Ɨ��ϐ��j�����͎҂́u�p��n�B�x�v�i�]���ϐ��j�ɗ^����e���ׂ悤�Ƃ���B���́u�w���@�v�̂悤�ɁA�f�U�C���ɑg�ݍ��܂ꂽ�v����A�f�[�^���W�̉ߒ��Ŕ�r�ł���v���ɂ����ʂ��A�Œ���� (fixed effect) �Ƃ����B
����A���͎Ҍl�l�̉��炩�̍��ɂ���Đ�������ʂ��A�����_������ (random effect) �Ƃ����B
�E �������ʃ��f��
(mixed effects model) �Ƃ́A�����̌Œ���ʂƃ����_�����ʂ̗������l���ɓ���铝�v��@�ł���B
�E �{�͂ł͗�Ƃ���longitudinal
study (�����Ԃ̋��͎҂̕ω�����̃e�X�g�ɂ���Ē������錤��) ��z�肵�A�������ʃ��f���ɂ�镪�͂̕��@�������B���ɁA�������ʃ��f����L2��longitudinal study�ɂƂ��ėL�p�ȓ����������A���L���g���Ă���ANOVA��t����ɐV���������@�ɂ��Ȃ肤��B
2.
Mixed Effects Models
2.1 �������ʃ��f���ōl�������v�����m�̊W
�E �O�q����Longitudinal
study�Ȃǂł́A�������͎҂ɓ���������J��Ԃ��A�w���@�ƃe�X�g�����̌��ݍ�p�ׂ邱�ƂŁA���͎҂̏n�B�x�̐L�т��r����B���������ꍇ�A�J��Ԃ���ANOVA���p������B
�E �������A�����̃N���X��w�Z����f�[�^���W�߂�悤�ȏꍇ�A�Ⴆ�N���X�ɂ���Ď��͍�������Ȃǂ̏��N���肤��B���������ꍇ�A��r����Q�ǂ������Ɨ���������Ƃ͂������A���m�ɓ��v�I���͂��s�����߂ɂ́A��W�c�̊W�����l�����邱�Ƃ����߂���B
�E �������ʃ��f���ł́A�v�����m�̊W��\�����p��Ƃ��āAnested�Acrossed�Ƃ����ꂪ����B
�E 2�̃N���X���琶�k�������ɎQ������Ƃ��A���k�ɂ��N���X���قȂ邽�߁A�N���X�v���͌l���v���ɑg�ݓ����ꂽ�Anested�ȊW�ł���B���̂悤��nested random effect���܂߂ĕ��͂��邱�Ƃɂ��A���͎҂̌l���ƁA�O���[�s���O���@�Ƃ����������_���v�����ɍl�����邱�Ƃ��ł���B
�E ����A2�̃N���X���琶�k�������ɎQ�����A�����̃N���X��L1�����{��A������̐��k������Ƃ��A�N���X�ɂ��L1���قȂ�킯�ł͂Ȃ����߁A�N���X�v����L1�v����crossed�ȊW�Ƃ�����B
�E �������ʃ��f���ł́A���̂悤�ȗv�����m�̊W (nested / crossed) �𗼕��܂߂āA���͂��邱�Ƃ��ł���B
2.2 �������ʃ��f���ōl������鍀�ڂɂ�鍷
�E ���͎҂��L����W�c�̂����̈ꕔ�̃T���v���ł���̂Ɠ��l�A����ɗp����}�e���A���Ȃǂ̍��ڂ��L����W�c�̈ꕔ�ł���B����āA���ʂ𑼂̏W�c�Ɉ�ʉ�����ɂ́A���͎҂����łȂ��A���ڂɂ�鍷�������_���v���Ƃ��čl�����ׂ��ł��� (Clark, 1973)�B
�E �]���ł͂��̖��̉�����Ƃ��āAANOVA�ɂ�����F1��F2��2�̕��͂��s�����@���������B��̓I�ɂ́AF1���͂ł͊e���͎҂̕��ς�SD�AF2���͂ł͊e���ڂ̕��ς�SD������Ă����B
�E �������A���̕��@�ł́A�����̃����_���v�����ɍl�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�܂��A����̕��͂ł͐M�����������A�����̕��͂ł͒Ⴂ�悤�ȏꍇ�ɁA���ʂ̉��߂�����ɂȂ�B
�E ���̂悤�ȏꍇ�A�������ʃ��f����1�x�̕��͂ŗ����̃����_���v�����ɍl���ł��邽�߁A�ʁX��F1���́AF2���͂��s�������ǂ����@�ł���Ƃ����� (Baayen, Davidson & Bates, 2008; Locker,
Hoffman, & Bovaird, 2007)�B
2.3 �������ʃ��f���̗��_
�E �������ʃ��f���̗��_�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@ ���̉�A���͂Ɠ��l�A�A���I�ȕϐ�
(e.g., ����) �̉e���ׂA�A���I�ȋ��ϗ� (e.g., �N��A���̌��ꑪ��ɂ�����p�t�H�[�}���X�A�F�m�\��) ���l�����邱�Ƃ��ł���B
�A �f�[�^�Ƀ����_���Ɍ��������邱�Ƃ�O��Ƃ��邽�߁A�����l�Ɋ挒�Ȑ��������� (Quene & van den Burgh, 2008; Gelman
& Hill, 2006, Chapter 25)�B
�B �����U���⋅�ʐ��̉��肪��������Ȃ��Ă��A�挒�ł��� (Quene & van den Burgh, 2008)�B
e ANOVA���l�A���K���z�͖�������Ă���K�v�����邪�A���̎�ނ̕��z�ł��A�K�������f���ł���Ύg�����Ƃ��ł���B
e �Ⴆ�Alogit
distribution����ʉ��������ʃ��f���ł���Abinary�ȃ^�X�N�̉��]���ϐ��Ƃ������͂��\�B
�� �]����ANOVA�At����ł͐��������]���ϐ��Ƃ��邱�Ƃ������������A0 < ������ < 1�ł��邽�߁A�������͖{���A�A���ϐ��ł͂Ȃ� (Jaeger, 2008)�B
�C unbalanced design�ɂ����Ďg���镪�͂ł��邽�߁A�����f�U�C�������łȂ��A�R�[�p�X���͂⑽�l�ȕ���ł�longitudinal data�̕��͂ł��g�p�ł���
(e.g., Boyle & Willms, 2001; Collins, 2006; Goldstein, 1995; Raudenbush,
2001; Singer, 1998)�B
3. Practical Example
3.1 ���z�����f�[�^�̏Љ�
�E Meunier and Littre (2013)
�ɂ��A���z��longitudinal study����ՂƂ��ĕ��͂����B
�E ���̌����ł́A156���̋��͎҂�Ώۂ�2�N�Ԃɂ킽��w�K�҂̎����̊w�K���� (5��) �ɂ�����A2�̋��͎Ҋԗv���̎w���@ (���͎Ҋԗv��) �̌��ʂ������Ă���B
�E �����ϐ��Ƃ��Č��ʑ���ɂ��u�n�B�x�v�A�����ϐ��Ƃ��āu�w���@�v�u�e�X�g�����v�̂ق��A���ʂ�N��AL1��p�ꌗ�o���N�����f�[�^�Ƃ��ėp�ӂ��Ă���B
�E ���̃f�[�^�͖{���̃E�F�u�T�C�g (http://oak.ucc.nau.edu/ldp3/AQMSLR.html) �ɂ���i���������A���݂̓A�N�Z�X�ł��Ȃ��͗l)�B
�E �������ʃ��f����SPSS��SAS�ł����͉\�B
3.2 ���͎菇
�E ���͑Ώۂ̃f�[�^�͌��܂����`���ŕ��ׂĂ����Ȃ��ƁA�v���O�����œǂݎ�邱�Ƃ��ł����A���͂ł��Ȃ��BR�̍������ʃ��f��(lmer��) ��p����ۂɂ́A�S�Ă̕ϐ��E�v�����c�ɕ��ׂ�K�v������ (Linck
& Cunnings, 2015)�B
�E nested�ȗv�����m�̓��x�����O�ɒ��ӂ���B�Ⴆ�A1�g��2�g�̐��k�������ہA1�g�̐��k��26�Ԗڂ܂Ő�������ɂ́A2�g�̐��k��1�Ԗڂ��琔����̂ł͂Ȃ��A27�Ԗڂ���p�����ă��x�����O����K�v������B
(1)
�f�[�^�̕ϊ�
�E ���͌��ݍ�p������A���ɓ��邽�߁A�A���ϐ��͒��S������ (�e�ϑ��l? ����)�B����ɂ��v�����m�̑��d��������h�����ʂ����� (Jaeger,
2010)�B
�E 2�������琬��J�e�S���ϐ��́A�������ł͂Ȃ�������0.5��?0.5�Ŏ����B����ɂ��R�̌v�Z�����������I�ɕς��(contrast coding system)�B������v�����m�̑��d��������h�����ʂ�����(Chen, Ender, Mitchell,
& Wells, 2003, Chapter 5)�B
|
[R�R�}���h] �E �A���ϐ��̒��S���F �t�@�C����$�V�ϐ���= �t�@�C����$�ϐ���? mean(�t�@�C����$�ϐ���, na.ru = TRUE) �E 2�����J�e�S���ϐ��̕ϊ��F �t�@�C����$�V�ϐ���=
ifelse(�t�@�C����$�ϐ���== �g�������h, ?0.5, 0.5) |
(2)
�p�b�P�[�W�̃_�E�����[�h
�E �������ʃ��f���Ŏg���ׂ���lme4�p�b�P�[�W (Bates, Maechler, Bolker, & Walker,
2013)�B���̋L���̎��_�ł�version 1.1?7�ƂȂ��Ă���B
�E ���ɂ�Car�p�b�P�[�W (Fox & Weisberg, 2011) ��psych�p�b�P�[�W(Revelle, 2014) ���L�p�ł���B
|
[R�R�}���h] �E �p�b�P�[�W�����Finstall.packages("�p�b�P�[�W��", dependencies = TRUE) |
(3)
�̗p���铝�v���f���̑�g (�����N��) �̌���
�E�q�X�g�O������Q-Q�v���b�g��p���ăf�[�^�̕��z���m�F����BQ-Q�v���b�g�ł́A���K���z���Ă���v���b�g��������ɂȂ�B
�E ���������K���z���Ă��Ȃ���Εϐ���ϊ�����B
|
[R�R�}���h] �E �q�X�g�O�����Fhist(�t�@�C����$�ϐ���) �E ���KQ-Q�v���b�g�Fqqnorm(�t�@�C����$�ϐ���) �E �ϐ��ϊ�(���W�b�g) �F�t�@�C����$�V�ϐ���= logit(�t�@�C����$�ϐ���) |
�E �����Q-Q�v���b�g�ɂ��`�F�b�N�̌��ʁA���܂萳�K���z�炵���Ȃ��`�ł������B���̂悤�ɒl�����͈� (0�_�`100�_) �Ɍ�����e�X�g�X�R�A�������ꍇ�́A�����悤�ɗL���͈͓��̕��z���������W�b�g���ɂ��ϊ����o����B
(4)
���f���̍쐬
�E lmer����p����f�������B
�E summary����p����ƁA��������f���Ɋւ��铝�v�ʂ�������������B
�E �gREML criterion at
convergence�h�Ə�����Ă���l�́u��E�x�v�������B����͎��ۂ̊ϑ��l����������f���ɂ��\���l����ǂꂾ������Ă��邩�Ƃ����l�ŁA�����������ǂ��B
�E �gScaled residuals�h�Ə�����Ă���l�́A�u�ϑ��l�Ɨ\���l�̍��v�̍ő�l�A�ŏ��l�A�����l�Ȃǂ�^���Ă���B������������A�����̒l���Ώ̓I�ȕ����ǂ��B
|
[R�R�}���h] �E ���f���쐬�F ���f����= lmer(�����ϐ���~ �����ϐ�+ (�����_���v��),
data = �t�@�C����) �� �����ϐ��̕����́A�Œ�v���̎���ʂƌ��ݍ�p���l���ɓ���邩�ۂ��̎w��B �u�v��A+�v��B�v�E�E�E�v��A��B�̎���� �u�v��A:�v��B�v�E�E�E�v��A��B�̌��ݍ�p �u�v��A*�v��B*�v��C�v�E�E�E�v��A��B��C�ɂ�����ʂƌ��ݍ�p�S�� �� �����_���v���̕������A�ǂ̎���ʂƌ��ݍ�p���l�����邩�����A���������Ⴄ�B �u(1|�v��X)�v�E�E�E�����_���v��X�ɂ������ �u(1+�v��A|�v��X)�v�E�E�E�����_���v��X�ɂ�����ʂƁA�v��A�Ƃ̌��ݍ�p �� �v�����m��nested��crossed���͎������肵�Ă����̂ŁA�R�}���h�͕ς��Ȃ��B ��Fmodel.1 = lmer(prof ~ course*time +
(1|student) + (1|class), data = scores) �E ��������f���ɂ�铝�v�ʂ������Ɗm�F�F summary(���f����) |
(5)
���f���̔�r
�E �e�v���̎���ʁA���ݍ�p�����f���ɓ���邩�ۂ��ɂ���āA�l�����郂�f���͕����o��B�����̔�r���ɗp��������1�Ɂu�ޓx�䌟��v������B���f�����m�̈�E�x�̍����v�Z���A���̍����L�ӂ����Z�o����B
|
[R�R�}���h] �E ���f����r�Fanova(���f����, ���f����, refit = FALSE) �� ���f����3�ȏ��r���邱�Ƃ��\�B �� ��r���郂�f���̑���_�������_���v���ł���ꍇ��REML (�����t���Ŗޖ@) �ɂ���r���ǂ��A����_���Œ�v���ł���ꍇ�͂����łȂ��ʏ�̍Ŗސ��肪�ǂ�(Pinheiro
& Bates, 2000)�B��҂̏ꍇ�͏�L���hrefit=FALSE�h���O���B |
�E �����_���v���Ƃ̌��ݍ�p�����邩�ۂ��́A���܂��c�_����Ă���B
�E ���f�������P (e.g., �ޓx���L�ӂɌ���) �����ꍇ�ɂ͓����ׂ��Ƃ�����������邪�A�������̏ꍇ�A���͂Ɏg���Œ�v���Ƃ̌��ݍ�p�́A���͎Ҋԗv���ȊO�S�ē����̂���ʓI�ł���B
�E �����������v�� (�N��Ȃ�) �ƃ����_���v���̌��ݍ�p�́A�l���ɓ���ĕ��G�������炩�ɑ����悤�ł���Ζ������čl�����Ȃ��Ă��ǂ��B
(6)
�e�Œ�v���̌��ʂ��L�ӂ��ǂ������Y�o����
�E Summary���ɂ��t�l�͏o�邪�A�Œ�v���̎��R�x�͒�܂�Ȃ����߁Ap�l�̎Z�o�ɂ��Ă͂��܂����_���o�Ă��Ȃ�(Baayen et al., 2008;
Bates, 2006)�B