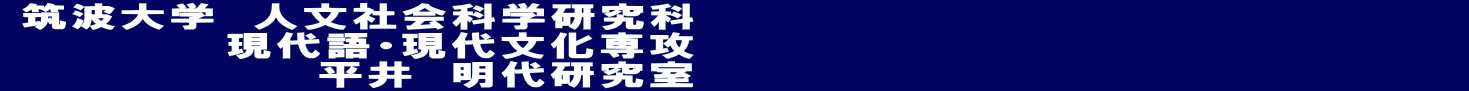
|
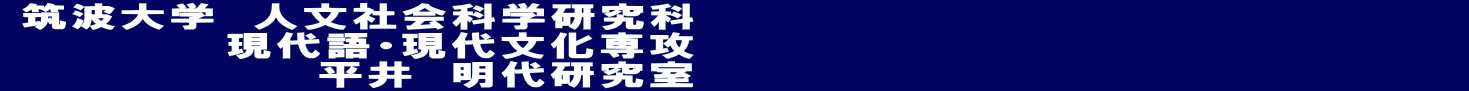
|
| 2017�N�x�@�@�ٕ������ꋳ��]���_ |
He, L., & Shi, L. (2012). Topical knowledge and ESL writing. Language
Testing, 29(3), 443-464.
1.
�v��
�@�{������ESL (N = 50) ��ΏۂɁAEnglish Language Proficiency Index (LPI) �̃��C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�ɂ�����g�s�b�N�Ɋւ���m�� (topical knowledge)�̌��ʂ��ΏۂƂ����B�Q���҂͏����A�����A�㋉�̂悤�ɏn�B�x�ʂɕ������A2�̈قȂ� (general and specific topic)�g�s�b�N�Ɋւ���G�b�Z�C (�������Ԃ���) ���������B���͂̌��ʁAgeneral topic�ɂ��ď������ꍇ�A���ׂĂ̎Q���҂̃��C�e�B���O�p�t�H�[�}���X���L�ӂɌ��シ�邱�Ƃ����������BSpecific topic�́A�P�̕]���ϓ_�ł�����e�ɂ����ĒႢ���_�ɂȂ����B����́A�l�� (ideas) �̎��Ɣ��B�̒Ⴓ��Î��I�ȗ�����(position taking)�A�ア���_�ɂ����̂ł���B�܂��w���́Aspecific topic task�ɂ�����\���⌾��̎g�p�Ɋւ��Ă��Ⴂ���_�ł������B�����́A�������ƈ�ѐ��̒Ⴓ�A���ʂ̒Z���A����I���A�A�J�f�~�b�N�p����g�p����p�x�����Ȃ����߂ł���ƍl������B�C���^�r���[ (�x��)�ɂ��ƁA�Q���҂�specific topic�̃G�b�Z�C�������ꍇ�A����specific topic�Ɋւ���m�����K�v�ƂȂ邽�߁A���͂��Y�o���邱�Ƃ�����Ȃ����Ƃ������Ƃł������B�{�����́AESL �̃��C�e�B���O�e�X�g�ɑ��ēK�ȎY�o�B�����邱�Ƃւ̏d�v���Ɋ�^������̂ł���B
2.
�����ړI
�@
general
knowledge / specific knowledge�����߂���ꍇ�AESL�w�K�҂͑S�̓I�ȓ��_�Ɨv�f���_�Ƃ����_�ŁA�ǂ̂悤�ɈقȂ�̂�
�A
2�̎Y�o�́AESL�w�K�҂̃��C�e�B���O�ɂ�����e�A�\���A����̂悤�ȃe�L�X�g�I�����ɈقȂ������ʂ�����̂�
�B
�Q���҂́Ageneral knowledge / specific knowledge�����߂��鎞�A�ǂ̂悤�Ƀ��C�e�B���O�p�t�H�[�}���X��m�o����̂�
3.
���@
3.1.
���C�e�B���O�v�����v�g
���g�s�b�N�̑I���́A3�̏n�B�x�̊w����Ώۂɗ\�������Ƃ��čs��ꂽ�B�ȉ��������Ŏg�p���ꂽ�g�s�b�N�ł���B�g�s�b�NA��general topic�A�g�s�b�NB��specific topic�ł���B
3.2.
�Q����
���Q���҂�ESL�N���X�ɍݐЂ��Ă���50���B�w�������́A�v���C�X�����g�e�X�g�ł��ꂼ��̏n�B�x(�����A�����A�㋉)�ɍ����N���X�ւƔz�����ꂽ�B
3.3.
���͂Ɋւ���X�R�A�����O
���w���̃G�b�Z�C�́A3�̊ϓ_ (���e�A�\���A����)�ɑ��� 6�|�C���g�̕��͓I�]����p�����B���̕��@�́ALPI�̑S�̓I���͂ɗp�����郋�[�u���b�N���牞�p�������̂ł��� (Appendix �Q��)�B
���]���҂�2���ōs���A�]���҃g���[�j���O�����{�����B�����ł́A�]���ɑ��ċ��ʂ̌��������Ă�悤�ɂȂ邱�Ƃ��ړI�ł������B
���܂��A�����]���҂�T���j�b�g�Ƃ��ׂĂ̌�� (����I�A��b�I�A�X�y�����O�A�C���@)����肷��悤���߂�ꂽ (accuracy)�B�����āA���ꂼ��̃G�b�Z�C�̑��ꐔ (length)�ƃA�J�f�~�b�N�Ŏg�p�����P�ꂪ�ǂ̒��x�p�����Ă��邩���v�Z�����B
���Ō�ɁA ����3�̎w�W��6�|�C���g�̃X�P�[���ɕϊ������B
3.4.
���C�e�B���O�X�R�A�̓��v�I����
���X�̃��C�e�B���O�ɂ�����S�̓I�ȓ��_�́A3�̊ϓ_�̕��ςƂ��Čv�Z����Ă���B�S�̓I�ȓ��_�Ɗϓ_���Ƃ̓_���͂��ꂼ��Ɨ������ϐ��Ƃ��Ĉ����Ă���B
��t������g�p���A2�̎Y�o�ɂ�����S�̓I�ȓ��_�̈Ⴂ�����ꂼ��̏n�B�x�Ŕ�r�����B
���n�B�x�ƃ��C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�ɂ�����2�̎Y�o�ɂ��������ʂƌ��ݍ�p����肷�邽�߂ɁA3�~2�̕��U���͂��g�p�����B���d���͂ɂ̓e���[�L�[���p����ꂽ�B
������̉ߌ�̗��́A3�̓_���ɑ��ă{���t�F���[�j�̒����ɂ���Ē������ꂽ�B
3.5.
�C���^�r���[
�����C�e�B���O���_�Ɋ�Â��ʓI����������������邽�߂ɁA�x���e�X�g�Ƃ��ď��\�����C���^�r���[ (30��) �����{�����B����́A2�̎Y�o�Ɋւ��Ăǂ̂悤�Ɋ������̂�������̂��ړI�ł���B
���n�B�x���ƂɎQ���� (�v5��)���{�����e�B�A�őI�ꂽ�B
���������x���ł�2�� (Ben and Bill)�A�������x���ł�1�� (Ida)�A�㋉���x���ł�2�� (Allen and Alex)������̃C���^�r���[�����BBen�ABill�AAllen�AAlex�́A��ꌾ��Ƃ��Ē������b�������AIda�͊؍����痈�Ă����B
4.
����
�����C�e�B���O�̑S�̓I���_�́A3�̏n�B�x�ɓn����general topic�̕���specific topic�������т��ǂ������B
��3�̊ϓ_�����Ă��A3�̏n�B�x�ɓn����general topic�̕���specific topic�������т��ǂ������B
���܂��{�����ł́A����n�B�x�̓G�b�Z�C���C�e�B���O�ɂ�����p�t�H�[�}���X�����߂��v�ȗv���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ������ꂽ�B
������̓C���^�r���[������m�F���邱�Ƃ��ł���B�Q���҂�specific topic�̃G�b�Z�C�������ꍇ�A����specific topic�Ɋւ���m�����K�v�ƂȂ邽�߁A���͂��Y�o���邱�Ƃ�����Ȃ����Ƃ������Ƃ������B
�����̂悤�Ȃ��Ƃ���A�e�X�g�쐬�҂͏�����̒m���ɉe������悤�ȕ����I�܂��͐����I�o�b�N�O���E���h�ɑ��ĕq���ɂȂ�K�v������B
5.
�l�@
�@�{�����Ŗ��炩�ɂȂ������Ƃ́A���C�e�B���O�̃p�t�H�[�}���X�͂��̃g�s�b�N�Ɋւ���m�������ɉe���͂����Ƃ������Ƃł���B����́A�C���^�r���[����5���̌���f�[�^������ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B�ȉ��ł́A�w�K�҂����g�s�b�N�Ɋւ���m�����傫���e�����镪��ł��낤�e�X�e�B���O�ʂƎw���ʂ�2�̊ϓ_����l�@����B
�@�e�X�e�B���O�Ɋւ��ẮA�{���ł����p����Ă���Carlson and Bridgeman (1986) �������悤�ɁA�u�g�s�b�N�ɂ����e�́A�l�I�Ȃ������͕����I�Ȍo���ɕ���̂ł͂Ȃ��A�ł����������łȂ���Ȃ�Ȃ� (p. 139)�B�v���Ƃ������ɂ����Ă��l�����ׂ��_�ł��낤�B���̂��Ƃ���A���C�e�B���O�\�͂𑪒肷��ꍇ�A�n�B�x�̗v�������ł͂Ȃ��w�K�҂����g�s�b�N�Ɋւ���m�����l���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�e�X�g���g�p���ă��C�e�B���O�𑪒肵�悤�Ƃ���̂ł���A���C�e�B���O�\�͂Ƃ͂ǂ̂悤�ȍ\���T�O��L���Ă���̂����I�Ɏ����A���m�ȑ�����s���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ炢�ł��낤�B
�@���ɁA�w���ʂɊւ���l�@������B�G�b�Z�C���܂ރ��C�e�B���O���w������ہA�n�B�x�������w�K�҂����n�B�x���Ⴂ�w�K�҂Ƀg�s�b�N�Ɋւ���m���������悤�Ƃ��邪�A�����Ƃ������Ȃ����Ƃ��{�����Ŏ�����Ă���B����̎����ł́A����n�B�x�����C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�ɗ^����e���͏������Ƃ������Ƃ����v�I�����ŏq�ׂ��Ă����B���������C�e�B���O�ɂ����Ă͌���n�B�x�͏d�v�ł���Ƃ����F���͈����x�^���Ă���ł��낤�B�Ƃ������Ƃ́A�n�B�x�������w�K�҂ɂ͂��g�s�b�N�Ɋւ���m�����d�v�ł��邱�Ƃ������悤�B�����̂悤�ɓ��萫�̍����g�s�b�N���������Ƃ͏��Ȃ��Ƃ͎v���邪�A������x���萫�������g�s�b�N�ɂ��ď����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�́A�n�B�x��킸�g�s�b�N�Ɋւ���m����^���邱�Ƃ��d�v�ł���B
Appendix
Tang, C., & Liu, Y. T. (2018). Effects of indirect
coded corrective feedback with and without short affective teacher comments on
L2 writing performance, learner uptake and motivation. Assessing
Writing, 35, 26-40.
1. �v��
�@���������t�B�[�h�o�b�N (CF) �̗��_�͂���܂ł̌����Ŗ��炩�ɂ��ꂫ���B�������A�ԐړICF�ɂ����邳��Ȃ錤���A�܂�ǂ�������ɂȂ邽�߂ɐ��k���܂����@�Ƃ��Ă̋��t�̃R�����g�̖����ȂǏ������t�ɂ������t�B�[�h�o�b�N�̉\���Ɋւ��钲���͈ˑR�Ƃ��ĕs�����Ă���B�{�����ł́A�R�[�h�t���ԐړI�t�B�[�h�o�b�N (ICCF) �ƒZ��affective comment���AICCF�݂̂���L2�w�K�҂̃��C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�A�A�b�v�e�C�N�A���`�x�[�V������ ���コ���邩�ǂ����������BL2�w�K�� (N = 56 ) �́A��L�̃t�B�[�h�o�b�N����肻����3�̃^�X�N�������������B���͂̌��ʁA�S�̓I�ȃ��C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�ɗL�ӂȌ��オ�����A������t�B�[�h�o�b�N�̎�ނɊւ�炸�w�K�҂ɃA�b�v�e�C�N�ɂ��L�ӂȌ��オ����ꂽ�B���̂��Ƃ���AICCF��affective comment��lj����Ă�L2�w�K�҂̃��C�e�B���O��L�ӂɑ��i���邱�Ƃ͒Ⴂ�Ƃ������Ƃ������ꂽ�B�������Ȃ���A�Q���҂̎��⎆�f�[�^�̌��ʁAaffective comment��lj��������ƂŊw�K�҂Ƀ|�W�e�B�u�ȃ}�C���h�Z�b�g�̌`���𑣐i���邱�Ƃ��ł������Ƃ������ꂽ�B����I�����Ƃ��āAICCF��affective comment�͑���I�ȊW�ł���Ƃ������Ƃ�������ł��낤�B
2. �����ړI
�@
CF��ICCF�����̏ꍇ�AICCF�͊w�K�҂̃��C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�A�A�b�v�e�C�N�A���`�x�[�V�����𑣐i���邱�Ƃ͂ł���̂�
�A
ICCF��affective comment��lj������ꍇ�AICCF�͊w�K�҂̃��C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�A�A�b�v�e�C�N�A���`�x�[�V�����𑣐i���邱�Ƃ͂ł���̂�
�B
ICCF�����̏ꍇ��affective comment �t��ICCF�̏ꍇ�����C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�A�A�b�v�e�C�N�A���`�x�[�V�����Ŕ�r����ƁA���ꂼ��ǂ̂悤�ȈႢ������̂�
3. ���@
3.1. �Q����
��56���̒�����b�҂��{�����ɎQ�������B�p��̏n�B�x��CEFR A2 ���x���ł������B
���܂��A�Q���҂͓�����L2���C�e�B���O�X�L���������Ă����B
���Q���҂́A(1) ��r�Q�Ƃ���ICCF ������^����Q (n = 28)�A (2) �����Q�Ƃ���ICCF��affective comment��lj�����Q (n = 28)�ɕ�����ꂽ�B
3.2. �f�U�C���Ɠ���
���O���[�v�̈Ⴂ�Ɋւ�炸�A�Q���҂�3�̃^�X�N (3�̊G�����Ƃɕ�����쐬) �Ǝ��⎆���P���s�����B
���w�K�҂́A�ŏ��̃��C�e�B���O�^�X�N��70-100�����x�ŏ����悤���߂�ꂽ�B
�����C�e�B���O��Brown (2007)�ɂ���č쐬���ꂽ���[�u���b�N���p�����A2���̕]���҂ɂ���ĕ]�����ꂽ�B�ϓ_�́A(1) �X�y�����O�⌾�t�����A(2) ���@�A(3) ���e�A(4) �\���ł���A100�_���_�ɐݒ肳��Ă���B
���_�������ŏ��̃h���t�g���w�K�҂ɖ߂�����ɁA�����҂͏��������^�X�N (second writing task) ��^���A�w�K�҂ɏC���������B
���w�K�҂ɂ�ICCF��^���Ă���̂ŁA�����҂͂���ɑΉ�����R�[�h�\��^�����B�ϓ_�́ABrown (2007)�Ɠ���4�̊ϓ_�ł���B
���w�K�҂̃A�b�v�e�C�N�𑪒肷�邽�߂ɁA3�ڂ̃��C�e�B���O�ۑ肪�w�K�҂ɗ^����ꂽ�B
������܂ōs���Ă����h���t�g��3�ڂ̃h���t�g���r���A3�ڂ̃h���t�g�Ō���ꂽ�����Ȃ����́A�A�b�v�e�C�N�̏؋��Ƃ��Ă��邱�Ƃ��ł���ł��낤�B
���Ō�ɁA�S�Ă̊w�K�҂̓��b�J�[�g�X�P�[�������̎��⎆�ɉ����B
���w�K�҂̃��`�x�[�V�����ɑ���S�̓I�ȕω������邱�Ƃ��ł��郊�b�J�[�g�X�P�[�����̎��⎆�ɉ����A�m�肽�����Ƃ��s���|�C���g�m�邱�Ƃ��ł���open-ended �̎��⎆�������Ď��{�����B
3.3. �菇
3.4. ����
��ICCF ������^����Q (n = 28)�Ǝ����Q�Ƃ���ICCF��affective comment��lj�����Q (n = 28)��Ώۂɂ��A�ȉ��̑g�ݍ��킹�Ń��C�e�B���O�̓��_��t����ŕ��͂����B
�@
�P�ڂ̃h���t�g�̓��_ (�����Qvs �����Q)
�A
2�ڂ̃h���t�g�̓��_ (�����Qvs �����Q)
�B
3�ڂ̃h���t�g�̓��_ (�����Qvs ��r�Q)
�C
�P�ڂ̃h���t�g�̓��_��2�ڂ̃h���t�g�̓��_ (�����Q)
�D
�P�ڂ̃h���t�g�̓��_��3�ڂ̃h���t�g�̓��_ (�����Q)
�E
�P�ڂ̃h���t�g�̓��_��2�ڂ̃h���t�g�̓��_ (�����Q)
�F
�P�ڂ̃h���t�g�̓��_��3�ڂ̃h���t�g�̓��_ (�����Q)
4. ����
��ICCF�݂̂̏ꍇ�A�w�K�҂̃��C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�ƃA�b�v�e�C�N�ɑ��Č��ʓI�ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B
���{�����Ŗ��炩�ƂȂ������Ƃ̒��ŏd�v�Ȃ��Ƃ́Aaffective comment�t��ICCF��ICCF�݂̂̏ꍇ�Ɣ�ׂ�ƁA���C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�Ɋւ��Ă͓����̌��ʂ��F�߂�ꂽ���A���⎆�̌��ʂ���affective comment�t��ICCF�͊w�K�҂��܂����ʂ�����Ƃ������Ƃ��킩�������Ƃł���B
���w�K�҂��AL2�̏n�B�x�̉e����ICCF�ƃR�����g�𗝉��ł��Ȃ��ꍇ�A���t�̓R�����g��L1�Ŏ������Ƃ��l���������ǂ��ł��낤�B
���܂��Aaffective comment�t��ICCF��^���邱�ƂŊw�K�҂̃��`�x�[�V�������㏸���AICCF�����[���l���邱�Ƃ��������ꂽ�B�܂�A���҂͑��ݓI�ȊW�ł��邱�Ƃ�������ł��낤�B
5. �l�@
�@�{�����́A�R�[�h�t���ԐړI�t�B�[�h�o�b�N (ICCF) �ƒZ��affective comment���AICCF�݂̂���L2�w�K�҂̃��C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�A�A�b�v�e�C�N�A���`�x�[�V���������コ���邩�ǂ����������B���͂̌��ʁAaffective comment�t��ICCF�́A���C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�����コ����_�ł�ICCF�݂̂ƕς��Ȃ����A�w�K�҂̃��`�x�[�V���������コ������ʂ����邱�Ƃ��������ꂽ�B���`�x�[�V�������オ�邱�ƂŁAICCF�����[���l���邱�ƂɂȂ���A���ʓI�Ɍ���K���ɗǂ��e����^����ƍl�����B
�@�������Ȃ���A�{�����̉ۑ�Ƃ��Ă�������̂͋@�ւ̒Z���ł���B����͒Z���Ԃ̒����ł��������߁A�����I�Ȓ������K�v�ł���B�����I�Ɍ��āA���C�e�B���O�p�t�H�[�}���X�͂ǂ̂悤�ɕω�����̂��A�܂��A���`�x�[�V�����͂ǂ̂悤�ɕω�����̂�����肵�Ȃ���Aaffective comment �t��ICCF�̉e�����ǂ����̂Ȃ̂��ǂ����Ɋւ��錋�_�͏o���Ȃ��ł��낤�B
�@�����āAaffective comment �t��ICCF�̉e���Ɍ��_���o�����߂ɂ́AICCF�ȊO�̗v�����l������K�v������B�Ⴆ�A�^�X�N�̃^�C�v�ɂ����affective comment �t��ICCF�̌��ʂ����E�����\��������B����̎����ł́A3�̊G�����Ƃɕ���������Ƃ����`���ł������B�^�X�N�`�������R�p�앶�̏ꍇ�ł͂ǂ̂悤�Ȍ��ʂɂȂ�̂�������K�v������ł��낤�B�^�X�N�`���ɕt�����āA�g�s�b�N�Ɋւ���m���̉e�����ӂ݂�K�v������B�܂��A���`�x�[�V�����Ɋւ��Ă͕����I�w�i���傫�ȗv���ɂȂ邱�Ƃ��l�����邽�߁A���Ղɓ��{�l�Ɉ�ʉ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B